|
�܂荞�݃`���V�@�`�@����ȈՉ�� for SS�� ���[���h�A�h�o���X�h��헪�@�`
�iAmazon.com�j
�@�����ł͊e����̊ȈՉ�����s���Ă���B
�@�������A���S�҂ł��Ȃ��߁A�������������Ă��炦��悤�A�o���邾���ȒP�ɁA�Ȍ��ɂ܂Ƃ߂�����ł���B
�@�A�t�B���G�C�g�����˂ċL�����N�����Ă��邪�A�������������Ƃ͓��ɋC�ɂ����A�e�X�̕���ɋ����������Ă��炦��K�����B
�@���ڂɂ���Ă�SS�ł̎��������Ă���̂ɁAMD�łɏ����������e�̋L�q�����邩���m��Ȃ��B
�@�o���邾���ԈႦ�Ȃ��悤�ɏ����Ă������ł͂��邪�A�����ԈႦ���ӏ�������Δ]���ŕϊ����ēǂ�ł������������B
�@���㕺���@�q���@�Q�[���\�t�g�E�U���{�E�����@DVD�E�u���[���C
|
|
 |
��PSW222�@�iSd.Kfz.222�@���b�ԁj
�@�O�����221���̋����Ƃ��ĊJ������A���������ɂđ��S�ʂɓn��g�p���ꂽ20mm�@�֖C����4�֑��b�Ԃł���B
�@�O������221���Ɏ��Ă��邪�A����Ɣ�ו����A���b�͋�������Ă���A�����I�ɂ͏�ʔłƍl���Ă��ǂ����낤�B�i�����������������e�����A�����w�������Ȃ��Ă���B�j
�@�ו���ǂ����Ă݂�Ɖ��Ǔ_�͑���ɂ킽����A�g������͕��}�ł������悤���A���A���n�Ȃ�Ύ���80km������@���������A�A�t���J����Ȃǂł͍D�]�ł������B
�@���ʁA�C�����A���H�̑���������������ł͒������@���͂̒ቺ�������A���̂悤�Ȑ���ł̓n�[�t�g���b�N�^�C�v�A���փ^�C�v�̑��b�ԂɌ�サ�Ă���B
�@���Y���̂͑�풆���ɏI��������A�{�Ԃ��������ꂽ�����ɂ���ẮA���ǁA�C�����{����ĉ^�p���ꑱ���A�I��܂ŔC�����p�������B
�@�Q�[�����ł͂قڏ������琶�Y���\�ŁA�I�[�\�h�b�N�X�ȑ��b�ԂƂ��ĉ^�p���\�ł���B
�@��ɘR�ꂸ�A�ړ��͂��傫���A�퓬�͂��Ⴂ�A�R�X�g�������A���G�͈͂��L���Ƃ����A�T�^�I�ȑ��b�Ԃł���A�Њd�Ɏg������x�̑�Η͂������Ă���B
�@�i�����PSW231�ŁA��Η͂��Ȃ��Ȃ����ɍ��G��1�L����i���G4��5�j�A����Ɏ�̑��b�A�b�v�ƂȂ�B
�@�M�҂́A���b�ԁ���Q���C�ɂ������s���G����C���Ŏg���̂Ăƍl���Ă��邪�A�厖�ɉ^�p���Ă���v���[���[�͐i�����ɑ�Η͂��A�����\�͂���I�Ԏ��ɂȂ邾�낤�B
|
|
��PSW231�@�iSd.Kfz.231 8-rad�@���b�ԁj
�@�l�֒�@�Ԃ��y���b�Ԃł��������Ƃ���A����ɑ��Ȃ��d���b�ԂƂ��ĊJ�����ꂽ�ԗ��ŁA�Z�ցA���^�������`�����̂ō��݂��Ă��鎖���班�X��₱�����Ԃł�����B
�@�����̒�@�Ԃ͈�ʓI�ȃg���b�N��W�[�v�Ȃǂ̃V���[�V���Q�l�ɗp���ĊJ�������ԗ��������������A�{�Ԃł͔��ւƂ����`�炻��ɓ��Ă͂܂炸����Ȍ`�p����ꂽ�B
�@���ɑS�Ă̎ԗւ�����\�ƌ����_�͔��ɍ��x�ȋZ�p�ŁA����ɑO���A�㕔�ɂ��ꂼ��^�]�Ȃ��݂����Ă������Ƃ���ɂ߂č����@�����Ər�q����ɂ������Ă���B
�@�����͌y�퓬�ԗ��Ƃ��Ă͈�ʓI��20mm�@�֖C���̗p����Ă���A��@�ԂƂ��Ă͕W���I�Ȏd�l�ł��邪�A�O�q�̋@�����E�r�q������{�ԂƂ̑����͗ǂ������悤�ł���B
�@�Z�^�����H���j���ɗ��_����_�ł������̂ɑ��A�{�Ԃ͈��H�ɂ��������肵�����\���ł������߁A��ɉ^�p�����̉��ǂ��Ȃ������킢�������B
�@���_�Ƃ��Ă͍������\�邽�߂ɋ@�B�I�ɕ��G���������ƁA����ɂ���č��R�X�g���������Ƃ��������A�u�ʂ�莿�v���d������h�C�c�鍑�R�炵���ԗ��ƌ�����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�Q�[���ł͏��Ղ���PSW222����̐i���A�������͎��@�����ɂ�鑦���Y�œ��肪�\�ŁA�ǂ����������W���I�ň����Ȓ�@���j�b�g�ł���B�i���^���o��j
�@���G�͈͍͂L���@���͂��\���Ŏg������͗ǂ����APSW222�������\�ł������̂ɑ��A�{�Ԃł͑�Η͂������Ȃ��Ă��܂��_���ɂ����B
�@�i�����PSW234�n�ƂȂ邪�A���b�Ԏ��̂���قǑ�ɉ^�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��Ȃ����߁A���Q���C�ɂ����ϋɓI�ɍ��G�͈͂��L�߂Ă��������Ƃ���ł���B
|
 |
��PSW234�@�iSd.Kfz.234�@���b�ԁ@��234/2��������̃v�[�}�j
�@���H�ɋ����A�^�p���̍�������PSW231�i8�֑��b�ԁj�̌�p�Ƃ��ĊJ������A��b�\�͂̍���������ǂɂ���đ����̕����o���G�[�V�������o�ꂵ���d���b�Ԃł���B
�@PSW231�͉^�p���̍����ԗ��ł��������A�R�X�g�̊���ɑ��b�������ł���ア�Ƃ�����_������Ă������߁A�{�Ԃł͂��̓_���ŏ�����O���ɒu����ĊJ�����Ȃ��ꂽ�B
�@������PSW231�ׂ̍������ȓ_�𑽂����P�����j��������A�܂��A�����ɂ��Ă��Ջ@���ςɉΗ͎x�����o����悤�A20mm�@�֖C�𓋍ڂ����ԗ��A��ԖC�𓋍ڂ����ԗ�������B
�@�o���G�[�V�����Ƃ��Ă�50mm��ԖC�^�C�v�A20mm�@�֖C�^�C�v�A�͂Ă͎ԑ̂Ɍ�����ʒ��C�g75mm��ԖC�Ȃǂ����݂��A��������܂��Ȃǔ��ɖL���Ȃ��̂ł������B
�@�ǂ̌^�������đ����Ƃ͌����Ȃ����Y�䐔�ł��������APSW231�ȏ�̑��j���ɑ��b�ԂƂ͎v���Ȃ��Η͂�^����ꂽ�{�Ԃ͏I��܂Œ����ɔC�������Ȃ��Ă���B
�@�����A�q�g���[�̍l���ɂ���Đ��܂ꂽ75mm���g�C�𓋍ڂ����^�ł͂������ɖ����������A�퓬�p���́A�h��͂̒ቺ�������ŁA�ǂ��炩�ƌ����Αΐ�ԖC�ɋ߂����̂������B
�@�Q�[���ł͒��Ղɍ����|���邠���肩�猻��n�߁A20mm�@�֖C�^�C�v��50mm�C�^�C�v�������͓���e/�֒e�C�^�C�v��75mm�C�^�C�v�Ǝ������o�߂��邲�Ƃɐi�����Ă����B
�@�i������PSW231�������X�����Y�ł��鎞�������Ղ���Ɣ�r�I������A�퓬����C���ł�������������ɑ��Q���C�ɂ����g���Ă悢���낤�B�i��Ă�Ȃ�b�͕ʁj
�@�i���̓}�C�i�[�`�F���W��F�ŁA�ŏI�^��75mm�C�^�C�v�͉Η͔��Q�����e����2�ƔC���p���͂Ɏx��o�邽�߁A50mm�C�^�C�v��PSW234/2�����C���ɂ���̂��x�X�g���B
|
 |
��II������@�i�y��ԁj
�@��̑��Ŕs�k���A����J�����֎~����Ă����h�C�c�鍑�́A�����ɔ_�Ɨp�g���N�^�[�Ƃ��Đ�Ԃ̌����J�������Ă����B
�@�{�Ԃ͂��̉ߒ��ŌP���p�E�m�E�n�E�~�ϗp�ɊJ�����ꂽ��ԌQ�̂�����1�ł���B
�@�{���͌����E�P���p�ɗp������v��ł��������A��͐�Ԃ̊J���x�����炭���͕s���̂��ߎb��I�ɐ퓬�ɗp�����邱�ƂƂȂ�A�����Ŏv��ʔėp���������B
�@���̐킢�ŗǍD�ȋ@���́A��평���̐�͂Ƃ��Ă͏\���ȉΗ͂��F�߂��A���i�グ���ꐳ����������邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�@��평���̊ԁA���炭�͎�͐�Ԃɂ����������Ȃ���������������A�����ł̔\�͕s�����w�E����n�߂�ƁA���X�ɒ�@�Ȃǐ퓬�ȊO�̔C���ւƓ]�����ꂽ�B
�@�܂��A�{�ԑ̂͐������̕���ɓ]�p����A�ڗ��������̂ł̓}�[�_�[�ΐ�ԖC�����C�A���F�X�y�����C�Ȃǂ�����B
�@�Q�[���ł̖{�Ԃ͑��b�ԂƓ������ړ��́A���G�͈͂ɗD����@�p��ԂƂ��Ĉ�����B
�@�퓬�\�͂͒Ⴂ���̂̑��b�Ԃ��͂��d���A�R�X�g�������ړ��͈͂��L�����߁A��y�ȃ��[�_�[�Ƃ��Ċ����҂ł��邾�낤�B
�@�i����͖{�Ԃ̃}�C�i�[�`�F���W�ʼn��ǐ�������A���̓_�ł͖ʔ��݂����邪�A�萔��������قǂ̕���ł͂Ȃ����߁A��͂��@�p�Ɗ�������ق����ǂ��B
|
 |
��38t������@�i38�it�j��ԁFPzKw38t�FLT-38�@�y��ԁj
�@���X�̓`�F�R�X���o�L�A�ŊJ������Ă������̂����A���Y�̐^�������������������I�ȕ����ɂ��h�C�c�鍑�R�ɐڎ�����A���R�ɂ���Đ��Y�E�^�p���ꂽ��Ԃł���B
�@��평���̌y��ԂƂ��Ă͔��ɂ悭�l����ꂽ�v������Ă���A�������III����ԂɕC�G����قǂ̐��\�������Ă��������琶�Y���ꂽ�����������ɕ����z�����ꂽ�B
�@�O�C��35t�����l�A�����I�ɗD��Ă������\�ł��������A�B�ꑕ�b�̕n�コ������������Ƃ��ċ�����Ă������߁A����͌�ɑ��b���̕ύX�E�lj����b�ȂǂɌ��т��Ă���B
�@�����͎���ɉ��������̂ŁA��C37mm�C�A���C7.92mm�@�e�����ڂ���A�o�ꎞ�Ƃ��Ă͏\���ȉΗ͂������Ă������A��C�̐��蓮�ł��������ߋ@�q���ɂ͂����B
�@�����̎ԗ��͐��\�̍��������평���ɏd����͕��݂̊�������������A�\�r�G�g�킪�n�܂鍠�ɂ͌y��Ԃ̐��ނƋ��ɑO�����珙�X�ɑނ��Ă������B
�@�O�����牓�̂�����͌x���C���ȂǂɊ��蓖�Ă�ꂽ���A�ꕔ�̎ԑ̂͒��C�g�𓋍ڂ����ΐ�Ԏ����C�A�A���@�e�𓋍ڂ������ԂȂǂ֗��p����Ă���B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��琶�Y���\�ŁAA�^�AE�^���o�ꂷ�邪�A��������y��ԂƂ��Ă̕]���͔����Ȃ��̂ł���A�O���ϋɓ������鉿�l�͂قƂ�ǖ����B
�@�����A�ԑ̎��͉̂��l������A���ɍ��t�@�C���ł͔�r�I���Ղ���}�[�_�[III�i���ł��鎖�͑傫���A���̓_�ł͗L�p���B�i����A�|�S�ł̓o�ꎞ���͔����ł���B�j
�@��C���ł̊���ɂ͂��܂���҂ł��Ȃ����A���ǂ̑f�ނƂ��Ă͖ʔ������߁A���Ղ�2�A3���j�b�g�����Ă���Ɓu����ȕ���ɂ��Ȃ�̂��v�Ɩ{��̑�햡�𖡂킦�邩������Ȃ��B
|

coffee break |
|
�`���b�Ԃƌy��ԁ`
�@���b�ԂƂ͕����ǂ��葕�b���{�����ԗ��ł���A�y��ԂƂ͕��ޓI�ɂ͐�Ԃɑ������̂̌������퓬���l�����������Ȑ�ԂƂ͈���������ŏ��^�E�y�ʂȎԗ��̎��ł���B
�@����ɂ����Čy��Ԃ͎�͐�Ԃ̍��x�Ȕ��B�ɂ���đ��݈Ӌ`���قƂ�ǖ����Ȃ��Ă��܂������߁A����ȃP�[�X�������ĂقƂ�Ǎ̗p����Ȃ��Ȃ��Ă������A���b�Ԃ͂������őe���A�\�������A��q�ȂǂɗL���Ȏԗ��Ƃ��č��ł��R���E���Ԃ̑o���ɂ����ĕ��L���g���Ă���B����E���ł͂�����̎ԗ������L������ɓ�������A�O���ɂ����Ă͒�@�A�Η͎x���A����ł͎����ێ��A�����{�g�D�̎����Ȃǂɐϋɉ^�p���ꂽ�B�����A���B���ʂł͐�Ԃ̔��B�������������������피�����肩��y��Ԃ��ϋɓI�Ȑ퓬�ɎQ�����鎖�͏��X�Ɍ����Ă������B
�@�{��ɂ����鑕�b�ԁA�y��Ԃ͈��������G�͈͂��L���������ɒ�@�p�̃��j�b�g�Ƃ��đ��݂���B��{�I�ɕ����E���b���n��Ő퓬�͋��ł�����̂́A�ԗ��ɂ���Ă͂�����x�̉Η͂������̂�����B�\�͂��悭����������Ŋ��S�ɍ��G�C���ɓO���邩�A�ꍇ�ɂ���Ă͉Η͎x�����S�����A���̕ӂ���l�����ĉ^�p���Ă��������B�܂��A��Η͂����ԗ��͓G��R�̈ړ���W�Q���錡�����j�b�g�Ƃ��Ă��z�u�ꏊ�ɋC���������B
|
 |
��III������@�i����ԁj
�@�h�C�c�鍑��ԕ����̎�͂ƂȂ�ׂ��AIV����ԂƋ��ɊJ�����ꂽ��Ԃł���B
�@�{�Ԃ͓������ɕ��s�J���̍s���Ă���IV����ԂƋ��ɉ^�p�����v��ł��������A���Y�͒x��ɒx��A�Ε��J��O�ォ��悤�₭�{���Y�ƂȂ�A���̐��𑝂₵�Ă������B
�@��C�͏���37mm�A�����`���50mm�ƌv��ǂ���g�����ꂽ���AM4�V���[�}����T-34�Ȃǂ̑�����ԂƑΛ�����ɂ͏�ɉΗ͕s���ŁA�V�^��Ԃ̓o��Ƌ��Ɉ����ނ����B
�@�^�����\�����͔�r�I�ǍD�ł��������߁A�ԑ̂𗬗p���A�Ή����ː�ԁA�ˌ��C�Ȃǂ֓]�p���ꂽ���A��͐�ԂƂ��Ă͕�����Ȃ������ł������悤�Ɏv����B
�@���̂܂܂ł�75mm�C���𓋍ڂł��Ȃ��ԑ̂̂��߁A�d���Ȃ��Ƃ����Ύd���Ȃ��̂����A���܂�̒Z�����ɓ�����ւ����Ȃ��B
�@�Q�[���ł̖{�Ԃ���r�I�j���ǂ���̈����ŁA�i���ł̓}�C�i�[�`�F���W���J��ւ����A�ŏI�I�ɂ͑���̕���ւƓ]�p���邩�A�ޖ��������߂ƂȂ�B
�@�U�����x����r�I�������߁A���Ղ���III���ˌ��CG�^�AIV��F�^�̓o��܂ł͌��ł��g��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���K��ԂƂ��Ă͂��̌�̊���͂قƂ�NJ��҂ł��Ȃ��B
�@����^���ڂ����50mm�CL60�������Ă��Ă��V���[�}���n�ɂ͂��s���AT-34/85�Ɏ����Ă͐搧�͉��Ƃ����邪�قڕԂ蓢���ƁA�͂����茾���ΐi��Ŏg�������b�g�͂Ȃ��B
�@���܂�W�Ȃ����A�M�҂́u��Ԃ�III����Ԃ̂ݐ��Y�\�v�Ƃ�������ŃL�����y�[�����N���A�܂Ńv���C�������Ƃ����邪�A���ɂ���ǂ������������ł��o���Ă���B
�@���̎��A���߂�75mm���C�g�̂��肪���݂������ł��A��������̖����ȁA���ʂȉ^�p�ɂ��čl�������ς�����B
|
 |
��IV������@�i����ԁj
�@���X��III����Ԃ�⏕��������Ƃ��Đv���ꂽ��Ԃł��邪�AIII����Ԃ̔\�͓I���E���������Ă��܂������Ƃ����͐�Ԃ̍��ɒ������̂��{�Ԃł���B
�@�����͕⏕�I�ȉΗ͎x���Ƃ��Ă̐���������75mm�Z�C�g���̗p���Ă������A�O�q�̂Ƃ���III����Ԃ̔\�͂����E�ɒB�����75mm���C�g�����悤�ɂȂ����B
�@���C�g�C�𓋍ڂ��Ă���̊���͖ڂ��݂͂���̂�����A��������������k�A�t���J�̕����ʼn^�p���ꂽIV����Ԃ̓}�[�NIV�X�y�V�����Ƃ��ĘA���R�ɋ����ꂽ�قǂł���B
�@�{�Ԃ̎ԑ̂͗D�G�Ȑv�ł���A�^�p���ꂽ���Ԃ��������Ƃ���A��C�⎩���C�A�ΐ�ԖC�A�ق��l�X�ȕ���֓]�p����Ă���B
�@�������Ɏ�����͐�Ԃɂ͗����̂́A�����O�̐��Y���ƃR�X�g�A�����₷���A�������ȂǗD�ꂽ�_�͐������A������̎�͐�ԂƂ��Ċ����B
�@���Y���̖�肩���햖���܂ʼn��ǂ͑����A���Y�����������A���̍��ɂ̓p���^�[��e�B�[�K�[�ɑ傫������肵�A�\�͕s���͖��炩�ł��������I��܂Ő킢�������B
�@�Q�[���ł͒��Ղ̎�͐�Ԃ�1�ɂȂ�͂��Ȃ̂����A�߂������Ƃɂ�����Ƀp���^�[����������邽�߁A����ł��鎞���͔��ɒZ���B
�@���Ղ܂ł͒Z�C�g�C�ł��邱�Ƃ���Η͕s���ɔY�܂���邪�A���C�g�C�iF2�^�ȍ~�j���̗p�����Ƒ啝�Ɏg�����肪�ǂ��Ȃ�A���_�͂�����ɉ��P�����B
�@�i����̓}�C�i�[�`�F���W�������A�����ăe�B�[�K�[�iF2�^�̓e�B�[�K�[�iP�j���}�E�X�ւ��j�A���ǐ�̓t�������A���[�x�����[�Q���Ȃǐi���E���ǂɂ͋ɂ߂ėD��Ă���B
|
 |
���p���^�[�@�iV����ԁ@����ԁj
�@3���A4����Ԃ������Ă��Ă��͂Ȃ��Ȃ��|�����Ƃ̂ł��Ȃ������\�r�G�g��T-34����Ԃ́A�h�C�c�鍑�ɂƂ��đ傫�ȋ��ЂƂȂ�������B
�@����ɑ��h�C�c�鍑�̏o�����������A����܂ł̐퓬�o���܂���������T-34����Ԃ�O�ꂵ�Č������A�����đ����̋Z�p�𓊓������V�^��Ԃ̊J���ł������B
�@���̐��ʂ��{�Ԃł���A����܂ł̃h�C�c�鍑�R��Ԃƈ�����ɂ₩�ȃJ�[�u�A�X�����ԑ̂͂s-34�̓����ɋ߂����̂ł���B
�@�茘���v�ƌ����ɂ͂�≓���A��r�I�V�����Z�p��������������Ă���A���ꂪ�����ŏ����^�ł͑����̎ԑ̂Ŗ�肪�������A�ғ����͂��܂�ǂ��Ȃ������B
�@�������A�������}���ꂽ����������A�����Ɖ��ǂ͓����ɐi�߂��A���Ԃ��|����������̉��ǂ��{���ꎟ��Ɏ�����͐�ԂƂ��Ăӂ��킵���\�͂����Ɏ���B
�@�����e�i���X���@�͔��ɓ�����̂ł������炵���A���A�b�l�����{�Ԃ��^�p�����t�����X�R�ł͉^�p���@�̓���ɋ����A�{�i�I�ȉ^�p��������߂��悤�ł���B
�@�Q�[�����ł͒��Ղ��z�����������D�^�������Y��������A�����Ă����ɉ��ǁE�����Y�łf�^�ւ̐�ւ����s����B
�@���C�g�C�̓e�B�[�K�[I�̎�C�����Α��b�Η͂������A�U�����x��22�Ƒ�������Ԃ̏�������A��e�o�n�f�����h��͂��D�G�ƁA���ɗ�����ԂƂȂ��Ă���B
�@�i���E���ǐ�����[�N�g�p���^�[�A�e�B�[�K�[II�AE-50�Ƌ��͂Ȃ��̂�������Ă���A�{�Ԃ����Y�\�ɂȂ����Ȃ�ΑS�Ă̐�Ԃ�{�Ԃ�ւ��Ă��ǂ����炢�ł���B
|
|
��E-50�@�i����ԁj
�@���X�̐�Ԃݏo�����h�C�c�鍑�ł́A������Ԃ����ő̐��\�̗D�ꂽ��Ԃ������ʂƂȂ������A���ʁA��ނ̑������琮���E���Y�����̒ቺ�����ɂȂ�������B
�@���̏����P���邽�߁A���i�̋��ʉ��E��ԋ敪�̈�V��}��E�v�悪��������A�{�Ԃ����̌v��ɑ���J���E���Y���\�肳��Ă����B
�@���łɗɂȂ����ł̊J�����̂����A�������R�����ƂȂ��Ă����h�C�c�鍑�ł͎v���悤�ɊJ���͐i�܂��A���ǂ͊������Ȃ������B
�@����ɂ��Ǝ�C��75mm�A88mm�Ȃǂƌ����Ă͂邪�A�����܂ł��v��ߒ��E�v�ߒ��̘b�̏�A���܂�ɂ��m�E���m�ȋL�^�����Ȃ����ߒ肩�ł͂Ȃ��B�i���R�A���̂��j
�@�Q�[���ł͏I�Ղɍ����|����p���^�[����i�����\�ƂȂ�B
�@��C�ɂ�88mmL71�����ڂ���Ă���A�ړ��͂�7�A���b��JS��ԕ��݂Ƃ����ɂ߂č����퓬�\�͂ŁA����ԃN���X�̐�ԂȂ�Ζ��Ȃ�����I�ɍU�����\���B
�@�i�����͐��\�̍����p���^�[�ŁA�i������܂ł̌o���l�҂����y�A�i����͈ړ��́E���x�͗�������̂́A����ɑ��b�E�Η͂̏オ��E-75�ƁA��������C���`�L���������\�ł���B
�@���[�g�ɂ���Ă͓o�ꂵ�Ȃ����A�h�C�c�鍑��I��ł���Ȃ�A����A�{�Ԃő��ԌR�c������Ă݂Ăق����B
|
|
���}�[�_�[II�@�i�}���_�[II�@�쒀��ԁF�ΐ�Ԏ����C�j
�@�\�r�G�g�평������D�ꂽ�\�r�G�g�R��Ԃ̋����ɔY�܂���Ă����h�C�c�鍑�R�ł́A���ɔ\�͕s���̎ԑ̂Ȃǂ�]�p���A�ΐ�Ԏԗ��Y���鎖�����肵���B
�@�ԑ̂ɂ͎������炨����Ƃɋ߂���ԂƂȂ��Ă���II����ԁiF�^�j���̗p����A��C�ɂ�75mm���C�g�C���̗p����Ă���B�i�����^��D/E�ԑ̂��b�l76.2mm�C�𓋍ځj
�@�{�Ԃ͎ԗ��s���E�Η͕s���Ɋׂ��Ă����h�C�c�鍑�R�̊�@�I�Ȏ������x���Ă���A�\�r�G�g�풆���ɂ����闤�R��傫���x�����Ă���B
�@�܂��A���R����Ԃɔ�ׁA��r�I�������ڂ��ꂽ76.2/75mm�C�͓������̓G����Ԃ����j�ł���\�͂�L���Ă���A���j�\�͂Ɍ����Ă݂�Δ\�͂͋ɂ߂č��������B
�@�������A���̕��A���b�A�퓬���͂��Ȃ�ȑf�ȍ��ƂȂ��Ă���A��e�����ꍇ�̐������͒������Ⴍ�A�������퓬�ɑς�������̂ł͂Ȃ������B
�@�Q�[�����ł͒��Ղɍ����|���邠����ɉ��ւ���A���ǁiII����Ԃ��FL�^�͏����j�������͑����Y�Ƃ����`�Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��o����B�i�����t�@�C���ł͎�����o��j
�@�Η͂�IV�����H�^�����̋��͂Ȃ��̂ł͂�����̂́A�e���A�h��͂ɓ����A�|�S�̐����ł͒��C�gIV����ԓ��Ɠo�ꎞ�����قړ����Ƃ��������ɂȂ��Ă���
�@�ꉞ�A�}�[�_�[III�ɐi���͏o������̂́A�{�Ԃ��g�����炢�Ȃ�A���̐�Ԃ��^�p����ق����ǂ����낤�B
|
 |
���}�[�_�[III�@�i�}���_�[III�@�쒀��ԁF�ΐ�Ԏ����C�j
�@�J���Ɏ������o�܂̓}�[�_�[II�Ɠ����ł���A�����═���������悤�Ȃ��̂ł��������A������͋����������i��ł��܂���38t����Ԃ̎ԑ̂�p���č���Ă���B
�@�����̓}�[�_�[II���l�A�����^�ł̓\�r�G�g�R�����b�l����76.2mm�C���A��Ƀh�C�c�鍑�R�W����75mm�C���̗p���Ă���A�����I�Ƀ}�[�_�[II�Ɠ����ƌ����Ă悢�B
�@�ꓖ����I�ȕ���ł��鎖�͒N�̖ڂɂ����m�ŁA�c�Ȍ`��Ŗh�䐫�͒Ⴍ�A���������]���ɂ����v�ł��������A���ʁA�Η͂͋��͂œ��R�̑���͂ƂȂ����B
�@�����̌��s��Ԃł�����III���EIV����Ԃł͌��j�̓������T-34����ɂ��Η͂͏\���ŁA�q�g���[���{�Ԃ̌��Y�����w�������قǂł�����������L�p�ł����������f����B
�@���Y�ׁ͍X�Ƒ��������ԑ̂̋K�́A�v�v�z���璷���g����悤�ȕ���ł͖����������߁A�v�̂悭����ꂽ�쒀��ԃw�b�c�@�[�̊����Ƌ��ɐ��Y�͑ł���ꂽ�B
�@�{�Ԃ���͉��ǂɂ���āu�M�d�Ȏ�����]�����g���s�����ƌ����h�C�c�鍑�R�Ȃ�ł͂̎v�z�v�����Ď��A����38t��ԂƋ��ɉ��ǁE���p������ǂ�Ɩʔ�����������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͒��C�g�C�����͂̂��镺��ł��邪�A�����̖C��������ԂƓo�ꎞ�����قڏd�Ȃ��Ă��邽�߂ɗD�ʐ��͒Ⴍ�A�s���ȕ���ƂȂ��Ă���B
�@�D���͉̂Η݂͂̂ƌ������[���A����Ɍ�ɑ����Y���\�A�Ɛ����ȂƂ���i��Ŏg���悤�ȉ��l�͖����B�i�����t�@�C���ł͏��Ղ���38t����Ԃ̉��ǂœ���j
�@�ꉞ�A�w�b�c�@�[�ȂǓ����ԑ̂�����ɉ��ǂł��邪�A�i���E���ǂɌb�܂�Ă���Ƃ͌����Ȃ����߁A��ǂ��l�����ď����𓊓�������x�ɂ����g���Ȃ����낤�B
|
 |
��III����ԁ@�ˌ��C�@�i�쒀��ԁF�ˌ��C�j
�@�����̉Η͎x�����s�����ߊJ�����ꂽ��Ԃł���A�h���^���܂ސ��Y���̓h�C�c�鍑�ōł������B�i�����A����ŕ���̐������Ⴄ���߁A��T�Ɉ�܂Ƃ߂ɂ͂ł��Ȃ����B�j
�@�����ɂ͂����܂ŕ����̉Η͎x���ɓO���Ă������A���̌����A��Ԑ�̑����ɔ����A����ɂ͒��C�g��C�ւƊ�������A�쒀��ԂƂ��Ă̐����������Ȃ����B
�@�{�Ԃ͑S���C���ł͂Ȃ����߁A�������@����ɂ͌����Ȃ���Ԃł��邪�A�����̑����Ȃ��Ă��������ł̓o��̂��߁A���̓_�͂��܂���ł͂Ȃ������悤�ł���B
�@75mm���C�g���̗p���ꂽG�^�ł́A�\���ȉΉA�������ꂽ���b�������AT-34�̋��Ђ��瑽���̕��m��ی삵���B
�@�Q�[�����Ń��C���ƂȂ�̂�G�^�ŁAIII�����J�^���i�����\�ł���A���@�����ɂ�萶�Y���\�ƂȂ�B
�@G�^�͈ړ��͂�4�Ɨ}�����Ă��邪�A75mm���C�g�̉��ւƓ����ɐi�����\�ƂȂ邽�߁A���̎����ɑ������ł���Ȃ�ΉΗ͖͂����B
�@�o�꒼��̓R�X�g�������퓬�͂������Ƃ��������炯�ł͂��邪�A�����ɒ��C�gIV����ԁA�p���^�[�A�e�B�[�K�[����������邽�߁A���܂芈��̋@��͂Ȃ����낤�B
|
 |
��IV���쒀��ԁi/70�j�@�i�쒀��ԁF�ˌ��C�j
�@��͂Ƃ��ċɂ߂ėD�ꂽ����ł�����III����ԓˌ��C�̌�C�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���A�]���I�ɂ͂������ŁA���܂�ڗ����Ȃ������ԗ��ł���B
�@�{�Ԃ͎ԑ̂ɗ]�T�̂���IV����Ԃ�p�������III����ԓˌ��C�̗ǂ��_��g�ݍ��݁A�啝�Ȑ퓬�͌����ڎw�������̂��������A���������ł̃o�����X�͗ǂ��Ȃ������B
�@��C�͓����p���^�[�����̂��̂��g����\��ł��������A�p���^�[�Ƃ̗D��x�̈Ⴂ�������^�܂ŕW���I��75mm�C���g����ȂǁA���̈��������s���Ȃ��̂�����B
�@III����ԓˌ��C�Y���Ă����A���P�b�g�Ђ̍H�ꂪ��������A���̐��Y���ꎞ�~�܂������ɂ͖{�������ꂽ���������������A�H�ꕜ���͐v���ɍs��ꂻ����Ȃ�Ȃ������B
�@���Y�䐔�͑����Ƃ͌������A2,000��O��̐������֑��荞�܂ꂽ�ƌ����Ă��邪�A���̐��̏��Ȃ���III����Ԍn�ɔ��IV����Ԍn�̐��Y���̈������e�������̂��낤�B
�@�q�g���[���{�Ԃ��C�ɓ����Ă����Ƃ����b�����邪�A�p���^�[�Ɣ���Ă���������Y���E�@���͂Ȃǂ��l����Ɛ��������ԗ��Ƃ͌������A�O����ȊJ��������Ă���Ɛɂ��܂��B
�@�Q�[���ł͒��Ղ��߂�������IV����Ԍ���^����̉��ǁA�ꕔ�}�b�v�ł̑����Y�Ŏ�ɓ���A�܂�75mmL46�C�^���A����75mmL70�C�^�������ĉ��ǁE���������B
�@����^�������Ă��Ă��p���^�[�ƌ������Ƃ���ŋ��͂ȑ����\�͖͂������̂́A�Η͂͂����͐�Ԃ������ȓ_�͗��_���B�i�����̏��Ȃ��X�^���_�[�h�}�b�v���ł͗L���j
�@��ԌQ�̗D�G�ȃh�C�c�鍑�R�ł͕K�{�Ƃ͌����Ȃ��n���Ȑ�Ԃ����A��苭�͂ȃ��[�N�g�p���^�[�ɐi���ł��铙�ʔ����_������A���1�A2���������Ă��ǂ���������Ȃ��B
|
 |
���w�b�c�@�[�@�i�쒀��ԁF�ˌ��C�j
�@�A���R�̔�����Q�ɂ��쒀��Ԃ̐��Y���C�����r�₦�Ă��܂����h�C�c�鍑�R�́A�ȑO���v�]�̏o�Ă����ԍ��̒Ⴂ�쒀��Ԃ̌��ƍ��킹�A�V�^�쒀��Ԃ��J�������B
�@���ꂪ�{�Ԃł���A���^����ԍ��AIV����ԂƓ������C�g�𓋍ڂ��Ă���ƌ��������������Ă���B
�@���Y�͑�^�{�݂������Ȃ�BMM�Ђōs���Ă���A���^�E��^��ԗp���i�̐������s���Ȃ����t���Ȃ����38(t)��Ԃ̎ԑ̂���肭���ǂ��A�R���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă���B
�@�����̐�Ԃ��痬�p���ꂽ���i�E�Z�p�������A�ɂ߂ĒZ�����ԂŊ������ꂽ�{�Ԃł͂��邪�A��o�����X�̈����������ڗ����A�@�����A���Z���Ȃǂ͗ǂ��Ȃ������B
�@�ǂ��炩�ƌ����@�������������ΐ�ԖC�Ƃ��������������A�^�p�ɂ͓�������͂��������A��͒ቺ�ɂ��s�������Η͂�₤���߁A�O���ɔz�����ꕱ�����Ă���B
�@�Q�[���ł͒��Ղ��o�ꂷ����̂́A�قڒP������ł��邱�ƂƁA���h�C�c�鍑�R��Ԃ̗D�G�ȓ_���ڗ����A�ǂ����Ă�����Ō����Ă��܂����݂ł͂���B
�@�P�̂Ƃ��Ă̐��\�͒Ⴍ�Ȃ��A�J�뒆��ԂƂ��Ĉ����Ȃ�ΗD�G�ȕ��ނɓ���̂����A�L�����y�[���ł͑O�q�̂Ƃ��葶�݁E�^�p���l�͒Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B
�@���쒀��ԂƂ̐i�����C���̈Ⴂ����i���E���ǂ��s���ȓ_�������A�i��ʼn^�p����قǂ̕���ł��Ȃ����A�R�X�g���������߁A�V���O���}�b�v�ł͗L����������Ȃ��B
|
|
�����[�N�g�p���^�[�@�i�쒀��ԃp���^�[�@�쒀��ԁF�ˌ��C�j
�@�{�Ԃ̓p���^�[�̎ԑ̂𗘗p���A�ԑ̂��g���A�e�B�[�K�[II�Ɠ����a��88mm�C�𓋍ڂ����쒀��Ԃł���B�i�ˌ��C�Ƃ��Ă��j
�@���b�͌��̃p���^�[�ɏ����������{���������ł͂��邪�A�ǍD�Ȕ�e�o�n���Ă��邽�߁A�v���������ł��ꋭ���悤���B
�@���͂Ȏ�C�A���ǂ��ꂽ���b�͊m���ɐ퓬�\�͂����߂����A����łقڂ��̂܂ܗ��p���ꂽ�@�B�n�ɑ傫�ȕ��S�������A�@�B�����͍����k�܂����悤�ł���B
�@�{�Ԃ́A�{���A�ΐ�ԕ����ɔz������镺��ł��邪�A���̐퓬�\�͂̍�������z���v���������A�ꕔ�ʏ�̐�ԕ����ɂ܂Ŕz������Ă����B
�@���̂��Ƃ���l����ƁA����������ƁA�{�Ԃ̓h�C�c�鍑�ň�Ԑ퓬�\�͂̍�����ԂȂ̂�������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͎��@�����Ńp���^�[G�AE-50����i���E���ǂ��\�ƂȂ�B�iE-50����ł͎キ�Ȃ邱�Ƃɒ��ӁA���ɂ������������P�[�X�͊������A�C������ׂ��ł���j
�@�Η͂͐\�����Ȃ��A���x��24�Ƒ��̐�Ԃ���͐搧�����A���ړ��͂�6�A�������p���^�[���d���Ƃ������Ɛs���߂ł���B
�@����������Ј��̏o���Ȃ�MG�AE-50�������o�Ă���A�i���悪���[�N�g�e�B�[�K�[�Ɍ����Ă��܂����߁A��ʔz���͂����߂ł��Ȃ����A���̐��\�͔��ɖ��͓I���B
�@�p���^�[�̊���i�M�ғI�ɂ�2�`3���j�b�g�j�̓��[�N�g�p���^�[�ɂ��Ă��悢���낤�Ǝv���B
|
 |
�����[�N�g�e�B�[�K�[�@�i�쒀��ԁF�ˌ��C�j
�@�őO���ł̑�Η͎x���ƁA�����i����������j�G��Ԍ��j���o����퓬�ԗ����K�v�ł���Ƃ����v�]����n����グ���A���̗v�]�ǂ��萶�܂ꂽ�̂��{�Ԃł���B
�@�{�Ԃ́A�e�B�[�K�[II���x�[�X�ԑ̂Ƃ��A��C��128mm�C�𓋍ځA���b�ɂ����Ă͍Ō�����250mm�ƌ����O�㖢���̉ΉE���b�����B
�@�܂��A�����ɂ̓|���V�F���G���W�����̗p����Ă������A�����̗�ɘR�ꂸ���̃G���W��������ƂȂ�A��Ɋ����E���ǂ���Ă���B
�@�X�y�b�N�I�ɂ́A���Ȃ�̋����ł����Ă��قڑS�Ă̘A���R��Ԃ̑��b���ђʉ\�A��e�����\���ɂ߂č����A���㗝�_�ł̓h�C�c�鍑�R�ɗL�]�Ȃ��̂������B
�@���ۂɂ̓G���W����������d�ʂ��痈��쓮�n�̖�肪�R�ς݂ł���A�n����ԕ��̏��Ȃ��Ȃ��Ă��������ɔ��Ԃ������A���ǂ͂قƂ�NJ���̏�͖����B
�@�����ɂ̓p���c�@�[�t�@�E�X�g��p�������R��˂ɂ�錂�j��A���\�I�D�ʂ������Ă��A�����J�R�����j�ł��Ȃ����̃G�s�\�[�h������A�S�ʂɓn���ĕs�^�Ȑ�Ԃł������B
�@�Q�[�����ł͏I�ՂɃ��[�N�g�p���^�[�A�܂��̓e�B�[�K�[II����i���E���ǂ��\���B
�@�퓬�ɂ͗L��]��قǂ̔\�͂������Ă���̂����A�@������ړ���3�Ɠݑ��ŁA�قږh�q�v���A�������͒x��Ă���x���v���Ƃ������^�p�@���K���Ă���B
�@�i��������͎���x����������̂́i�������24��22�j�A�\���ɗ��x��ς{�Ԃ͐S������͂ł���A���������Ƃ�1���j�b�g�ʂ̓X�g�b�N���Ă����Ă��ǂ����낤�B
|
 |
���e�B�[�K�[�@�iVI����ԁ@�d��ԁj
�@���œo�ꂵ����Ԃ̒��ōł��L���ł���A�ł��l�C�������A�h�C�c�鍑�R��Ԃ̗D�G���𐢊E�ɒm�炵�߂��d��Ԃł���B
�@�S�ʓI�ɕێ�I�Ȑv�ł���A�X�Α��b�������������ȊO�������A�t�@�����猾�킹��ƁA���̖����Ȋ������܂��ǂ��E�E�E�̂��������B
�@�J���͔��ɕ��G�ȉߒ������ǂ��Ă���A�q�g���[�ƃ|���V�F���m�����ގ��������āA�����܂łɂ��낢��Ƃ�₱�����ł������B�i�y���������ł͂��邪�b�͊�������B�j
�@��ɂ��q�ׂ��Ƃ���X�Α��b�͍̗p����Ă��Ȃ����A�����Ƃ��Ă͋��͂ȑO�ʑ��b�����̗p����A�h�䐫�\�͋ɂ߂č����A�A���R��Ԃł͌��j�����ɓ�������B
�@�܂���C�ɂ�88mmL56���̗p����Ă���A���̑�Η͓͂������̓G��Ԃ�w�Ǒ��苎�邱�Ƃ��o���A�\�r�G�g���܂ޘA���R���m�����|�̒�ɗ��Ƃ����B
�@�������A�S�̂��悭���Ă݂�ƉΉE���b�͐\�����Ȃ����A����肪���Ɏキ�A���̏d�ʂ̂��߂Ɉړ��n�悪���������i���E���H�Ȃǁj���Ƃ������������悤�ł���B
�@�Q�[�����ł͎��@�����ɂ��IV����ԁiF�^�ȍ~�j����i�����\�ŁA�ꕔ�̃}�b�v�ł͑����Y���\���B
�@�g������̖ʂ���p���^�[�ɂ͗����̂́A�Η͂͏\���Ő��x��22�ƍ����A�i������IV��F�^����e�B�[�K�[�iP�j���}�E�X�n�Ɠ���ȕ���ɐi���ł���̂����͂�1�ł���B
�@�����Ȑi����̓e�B�[�K�[II�Ƃ���������́E�L���Ȑ�Ԃł��邽�߁A�h�C�c�鍑�^�C�v��I��ł���Ȃ�Έ�x�͎g�������B
|
 |
���e�B�[�K�[II�@�i�e�B�[�K�[B�FVI����ԁ@�d��ԁj
�@�P�[�j�q�X�e�B�[�K�[�A�L���O�^�C�K�[�A���C�����e�B�[�K�[�ȂǑ����ٖ̈������d��ԂŁA���ł̂��̉ΉA���|�I���݊����瑽���̘A���R���m�����ꂳ�����B
�@��C�ɂ͂قƂ�ǂ̘A���R��Ԃ��A�E�g�����W����_���ł����Η͂̒��C�g88mm�C���̗p����Ă���A����ɂ���ĘA���R��Ԃ�����I�ɑ��苎��З͂��ւ��Ă���B
�@�܂��A��b�I�ȕ����͕ێ�I�Ȑv�������������̂́A���������b�ɉ����X�Α��b���̗p���ꂽ���ɂ��h�䐫�\�͒������㏸���A���̖C�e�˕Ԃ��قǂł������B
�@�ΉE�h��͂Ƃ��ɋɂ߂ėD�ꂽ��Ԃł��������A�d��Ԃ̒��ł����Ȃ�d���ԗ��ł��������ߑ���肪�キ�A�����쓮���ʂɌ̏����������Ƃ��ꂪ��_�ł������B
�@�������A�{��Ԃ��o�ꂵ�������ɂ̓h�C�c�鍑�͂قڎ��ɓ����Ă���A�ǒn�I�Ȏ���퓬�������������߁A�����̈����͂��قǖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł���B
�@�U�����̉^�p�ł͋@�����̈�������]���͗ǂ��Ȃ����A�����ł͔��ɂ��܂��g���A�ǂ��炩�ƌ������͂Ȗh�q�p����Ƃ��Ă̕]���������ƌ����邾�낤�B
�@�Q�[���ł��������\�͏\���Č�����Ă���A�ΉA���x�A�h��́A�e�����������x���ł悭�܂Ƃ܂��Ă���A��_�͋@���͒��x�ƂȂ��Ă���B
�@���x�̍����ɂ���ĂقڑS�Ă̓G��Ԃ���搧������_�͗��������A�\�r�G�g�d��ԑ���ł����D�ʁA�A�����J�E�C�M���X�鍑��Ԃ�����Ȃ�ΗD�ʂƂ�����ł���B
�@�i��/���ǂŋ��_�h�q�ɍœK�ȃ��[�N�g�e�B�[�K�[��A128mm�C������E-75�ւ̐i�����\�ƂȂ邽�߁A�{�Ԃ̐��\�����\������͍D�݂Ői��������Ɩʔ������낤�B
|
|
��E-75�@�i�d��ԁj
�@E-50�̊J���o�ܓ��l�A�퓬�ԗ��̑������甭�����������E���Y�����̒ቺ�����������邽�߂ɗ\�肳��Ă����uE�v��v�Ɋ�Â����ԗ��̈�ł���B�B
�@�e���̃p�[�c�͋��ʉ�����AE�v��ɂ����鑼�ԗ����i�����������p�\�ƂȂ�\��ł��������A�p�[�c�̈ꕔ���������������_�ŏI����}���A��͂�\��݂̂ł������B
�@���̊��������ꕔ���Ƃ����̂��A�I��ԍۂ̕����s���̂����łق߂�ꂽ�悤�ȏo���ł͂Ȃ��A�i���E���\�͗\��̐��\�������Ȃ�Ⴂ���̂ł������ƌ����B
�@��C�ɂ̓e�B�[�K�[II�ɓ��ڂ���Ă���88mm�C�����ǂ������̂����ڂ����\��ł������炵���A���Ɏ��H��������Ă����Ȃ���炭�\�r�G�g�d��Ԃ����y������Η͂ł������낤�B
�@�v�掩�͔̂�r�I�L���ł͂��������A���ۂɂ͂܂������̖������ƌ����Ă悢���x���ł���A���̌v�悪�������Ă����疖���h�C�c�鍑�̒�R�͌������Ȃ��Ă�����������Ȃ��B
�@�ώG�ɂȂ��Ă��܂�����ԋ敪�̐����͔��ɗD�ꂽ�l���ł��������A�v�悵�����������������ɁA���̔����͂��܂�ɂ��x�������̂ł���B
�@�Q�[�����ł�88mm�C�łȂ�128mm�C�����ڂ���Ă���A���x��22�Ƃ������̂̉Η͂�155�Ƌɂ߂č����U���͂��ւ�B�i�e�B�[�K�[II�A���[�N�g�p���^�[�Ȃǂ͐��x24�j
�@�����O�̏d���b�ɉ����A�@���͂ɂ����Ă��ړ�5�ƗD�������[�ł͂Ȃ��g��������ǍD�����A���x22�Ƃ�����_�������߁A���ׂĂ̐�Ԃ�{�Ԃi�������邱�Ƃ͔��������B
�@�e�B�[�K�[II �AE-50�Ȃǂ���i���œ��邱�Ƃ��\�����A�ŏI�i���ԗ��ł��邽�߁A�i���͂����ŏI���ƂȂ�B
|
|
���G���t�@���g�@�i�t�F���f�B�i���g�@�d�쒀��ԁF�ˌ��C�j
�@�����̗p����Ȃ������|���V�F�e�B�[�K�[�A�ԑ�VK.4510(P)�̈����ɂ��Č����Ɍ������d�˂����ʁA�h�C�c�鍑�ł͂��Ƃ������鎩���C�Ƃ��Ă̗��p�����肵���B
�@�{�Ԃ̓G���t�@���g�i�t�F���f�B�i���g�j�ƌĂ�A���X���Ȏԑ̂ɂ͂���Ɍ������b��lj����A��C�ɂ͑���a���C�g88mm/L71���̗p����Ă���B
�@���b�͍Ō�����200mm���ق���A���̂����C�̈З͂����O��ƍU��̔\�͔͂��ɍ������̂ł������B�i�������g���ɂ����A�O�����Y���͋@�֏e����������_���������B�j
�@�{�Ԃɂ̓|���V�F���m���ւ���Ă��邽�߁A��O�Ȃ������Ƃ��Ă͊v�V�I�������d�C�n�C�u���b�h���G���W�����̗p����Ă���B
�@�ߋ��̌����E�����ł͓ݑ��̏�Ɍ̏Ⴊ�����Ƃ���Ă������A�ߔN�̌����ł͖{���̓g���u�������Ȃ������̂ł͖������낤���A�Ƃ���������������������悤�ɂȂ����B
�@���āA���̃G���W���͊���̏d��Ԃɍ̗p����Ă��邪�A�ʂ����Ă��̐��\�͂������������̂��낤���A�����͐s���Ȃ��B
�@�S�ʓI�ɂ�͂薳���������A�����Ƃ��Ă͊v�V�I�Ȑ�Ԃł͂��������A�����I�ɂ͂�͂�^�p���ɂ����Ƃ������Ƃ��낪�����ȂƂ���ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[���ł͒��Ձ`�I�Ղɂ��������鍠�Ƀ|���V�F�e�B�[�K�[�����ǂ��\�A�����ċ쒀��Ԍn�ւƐi�����q����B
�@�ΉE�h��͖͂��͓I�ł͂��邪�A�ݑ��i�ړ�3�j�A�@�֏e�������Ȃ��ȂǑ���Ԃɔ�ׂĎg������͗�邽�߁A�̗p�̉ۂ̓v���[���[���悾�낤�B
|
 |
���}�E�X�@�i�d��ԁF���d��ԁj
�@��ɂ��A�q�g���[����̋����v�]�ŊJ�����n�܂�A�i�`�X�ƗǍD�ȊW�ɂ������|���V�F�Ђ��J���𐿂������u���ۂɓ����v���x���܂Ŋ��������̂��{�Ԃł���B
�@�i�q�g���[�̗v�]���ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƁA�����_�ōō���̐�Ԃ����Ƃ������̂ł������悤�ŁA�܂��A�{�Ԃ͓������Ƃ͓����������Ƃ������x���ł͂Ȃ��B�j
�@�|���V�F���m�̓��Ӂi���ӂƌ����Ă悢�̂��E�E�E�j�Ƃ���d�C���G���W����A���܂�ɂ��d�߂���ԑ̂ȂǁA���낢��Ɩ��̑����{�Ԃł��������A�����ڂ̃C���p�N�g�͌������B
�@��C128mm�C�A���C75mm�C�{�@�e�Ƒ��Η͂͋ɂ߂č����A���b�����Ō���240mm�ƌ�������܂łɂȂ��h��͂ł��������A�������痈��d�ʑ����͖����ł��Ȃ����̂������B
�@190�g���ɋ߂����d�͑O�q�̃G���W����������A����n�鎖���o���Ȃ��A���������̏Ⴙ�������ł��邩�ǂ������������ƁA�����Ɉ��e���������炵�Ă���B
�@�q�g���[�̗v�]�ǂ���A�ō��ΉA�ō����b�A�ō��Z�p�Ő��藧��Ԃł��������A���ʓI�ɂ̓o�����X�̈������s�삾�����ƌ��_�t���ł��邾�낤�B
�@�Q�[�����ł͏I�ՂɃe�B�[�K�[�iP�j����i�����\�ƂȂ�A�|���V�F�n�d��Ԃ̍ŏI�i���̂ƂȂ��Ă���B�iIV��F2�@���@�e�B�[�K�[�iP�j�@���@�}�E�X�@�̗���j
�@�ړ��͂�3�ƌ����ݑ��ȏd��Ԃł��邪�A�����ڂ̃C���p�N�g�AJS-3���̖h��́A128mm�C�̈З́i�������e����3�����Ȃ����j�̓v���[���[�ɋ���Ȉ�ۂ��c�����낤�B
�@�|���V�F�n�d��Ԃ̕ϑԓI�ȕȁi�|�S�ł͐�ɂ��N���\�Ȃǁj�́A�ǂ��^�p���邩����Y�܂���邪�A���̕Ȃ����y���ގ����o����̂��㋉�҂Ȃ̂�������Ȃ��B
|
 |
�����F�X�y�@�i�����֒e�C�j
�@�t�����X��̎��_�Ŕ\�͕s���A���ɑ��b�ɂ����Ėh��͕s�������炩�ƂȂ���II����Ԃ̎ԑ̂𗬗p���A105mm�y��C�𓋍ڂ����̂��{�Ԃł���B
�@���ڂ���Ă����C�̓h�C�c�鍑���R�̉^�p�������C�Ɠ������̂ł͂��邪�AII����Ԃ̎ԑ̂Ƃ�قǂ摊�����悩�����̂��A���ɍ����]�������B
�@�ǂ��炩�ƌ����Ώꓖ����I�ȗ���ō��ꂽ���ł͂�����̂́A�\�z�O�̉^�p���\�A�ΉA�M�����A�R�X�g�ȂǗD�ꂽ�_�������ƂƂȂ�A����֒͞e�C�̍��ɒ������B
�@�{�Ԃ̐��\�́A�q�g���[���uII����Ԃ͑S�Ė{�Ԃɓ]�p����v�Ǝw�����o�����قǂƌ����Ă��邱�Ƃ���A�����Ƃ��Ă͋ɂ߂č����^�p���\�ł����������f����B
�@�Ȃ��A�ԑ̂�II����Ԃł͂��邪�A�����ɉ��ǂ��������Ă���A���nj�̎ԑ͎̂����I�Ƀ��F�X�y��p�̎ԑ̂ł������悤���B
�@�Q�[���ł͒��Ոȍ~���琶�Y���\�ƂȂ�iII����Ԃ̉��ǂł�������j�A�W���I��105mm����C�����̂܂����������悤�Ȑ��\�͔��Ɏg������̍������̂ł���B
�@�܂��A��ʂ̃t�������ɔ�ׂĂ�⑽�߂ɒe���𓋍ڂ��Ă���A������x�⋋��������Ă��p�����Č���x���𑱂�����ʂ͐S�����B�i�}�V���K��������j
�@�h�䐫�\�͑��������֒e�C�Ɠ����悤�ɊF���Ƃ����Ă悢���A�R�X�g�����������Y���\�ł��鎖����A��Q���Ă����܂�C�ɂ����ɍςނ��낤�B
�@�i�����150mm�C�𓋍ڂ�����ʂ̃t�������ŁA������͋��͂ȉΗ͂������Ƃ���A�i������͏o���邾�����߂ɐi�����s�������B
|
|
���O���[���@�i�O�����@�����֒e�C�F�����d�����C�j
�@�h�C�c�鍑�R�͋���������������ė��p���A��肢�g�ݍ��킹�ƍ��x�ȋZ�p�ɂ���ċ��͂ȕ���𐔑������A�o������蕺���]�点�Ȃ��悤�ɂ��Ă����B
�@�{�Ԃ����̒��̈�ł���A�ԑ̂ɂ�38t�^��ԁA�C��sIG33�d�����C���̗p���A������������ȕ���̑g�ݍ��킹�Ȃ�������ɗD�G�ȕ���Ƃ��Ċ������Ă���B
�@�Ȃ��A�O��H�^�ł�38t�^��Ԃ̎ԑ̂��قڂ��̂܂g���i�}�[�_�[�ȂǂƓ����j�A���K�^�ōœK�����ꂽ�ԗ����g���Ă������A���ۂɂ͕��s���Y���Ă����悤���B
�@�̗p����Ă���sIG33�d�����C�͂�⋌���ȖC�ł��������A���������ɔz�������C�ł͍ő勉�̂��̂ł���A150mm�ƌ������a���瓾��Η͂͋ɂ߂ċ��͂ł���B
�@�ꌩ����Ə��^�ԑ̂ɑ���a�C�Ƃ����g�ݍ��킹�͔��ɃA���o�����X�Ɏv���邪�A���ꂪ�ǂ��Ӗ��ŗ����A�q�g���[����͑������Y�w�����o��قǂ̐��\�ł������B
�@�O���ł͂��̐퓬�\�͂͋ɂ߂čD�]�Ŕ��ɏd�ꂽ���A���Y���͑����ƌ��������p���̎ԑ̂�������֓]�p����n�߂�Ɛ��Y�͏a���A�V�K���Y�͊��S�ɏI�������B
�@�Q�[���ł͍��t�@�C���Ő����lj�����Ă���A���ՑO����J���\�ɓo��A38t��Ԃ���̉��ǂŎ�ɓ���鎖���\�ł���B�i�|�S�ł͊J���\���������Ă���B�j
�@�����������d�����C�ł���_���l�����Ă�����������ɍ��킳��Ă���A�h��͂͊F���Ŏ˒���3�ƒZ�����Η͓͂��R150mm��C�����Ƃ������A���o�����X�ȕ���ł���B
�@�g��������l����ƃ��F�X�y�A�t�������̕����D�G�ł��邽�߁A���Ղłǂ����Ă���Η͂̎����֒e�C���ق����ꍇ�ȊO�͂���قǕK�v�ƂȂ���̂ł��Ȃ����낤�B
|
|
���t�������@�i�����֒e�C�j
�@���X�͈ꎞ���̂��̎����C�J���v��ł��������̂́A�\�z�O�̗ǍD�Ȏ������ʂ����ʐ��Y�Ɏ������̂��{�Ԃł���B
�@�ԑ̂ɂ�III����ԁEIV����Ԃ̂��̂����p����A���A���i�͂�����x�̋��ʉ����}���Ă���A���̏��150mm��C�����ڂ���Ă���B
�@�Ȃ��A�ȑf�����ꂽ���ʉ������͐��Y�����̌���Ƃ��������b�g�������炵�����A���ʁA��p�̎ԑ̂ł͂Ȃ����߁A�C�e�̓��ڂɂ͓�������B
�@�����C�Ƃ������Ƃő��b�������A�O���ɂ͗��ĂȂ��n���ȑ��݂ł͂��������A�I��܂Ō������̎x���C�����m���ɐ��s�����B
�@�Q�[�����ł̓��F�X�y����̐i���A150mm��C�AIV����Ԃ���̉��ǂœ��邱�Ƃ��\�ł���B
�@�C�e�����������Ď˒���1��������̂́A�h�C�c�鍑�R150mm��C�����̂܂������ɂ����悤�Ȑ��\�ŁA����x���ԗ��Ƃ��Ă͗D�ꂽ�Η͂Ƃ��ė���鑶�݂��B
�@�h��͂͊F���ɓ������A��������O���֓ˏo����悤�Ȃ��Ƃ������悤�ɋC���������B
�@�i����͖������A���l�̃R���Z�v�g�ł���ʂ̕���ւƉ��ǂ��\�ł��邽�߁A�]�T������Ύ����Ă݂�̂��ʔ������낤�B
|
 |
���f�}�[�O D7�@�i�f�}�[�N Sd.Kfz.10�@��ԗ��j
�@�ԑ̂͑��O��茤���p�Ƃ��č���Ă��������O�Ԃł���A��炩�̎���Ԃ��o�Đ������E��ʐ��Y�����ꂽ�̂�D7�^�A�{�Ԃ̎ԑ̂ł���B
�@���̎ԑ͎̂�Ɍ����p�ɊJ�����ꂽ���A��@�֖C��P�b�g�C�����ڂ����ȂǑ����̕���ւƓ]�p���ꂽ�B�i�����A���ݒm���Ă���ȊO�̎g����������Ă��邾�낤�B�j
�@��ԗ��Ƃ��Ă̖{�ԁu�f�}�[�OD7�v�́A���̔����O�Ԃ�20mm��@�֖C�𓋍ڂ������̂ŁA�@���́E��Ί���������킹��������h�C�c�鍑�R���̑�ԗ��ƌ����Ă悢�B
�@�����^�ł͖h��p�̑��b�A�Η͕s�����ڗ����A���ɖh���������Ƃ����d�l�͗]��ɂ��낤���������댯�ɎN�������߁A����͌�ɉ��ǂ���Ă���B
�@�ȈՂȑ�ԗ��ł��������^�p���͗ǍD�ł������炵���A�����ȑ��ԍ̗p����ӊO�Ƒ��I�Ղ܂Œ������Y�͑��������A���Y�����̂͏��Ȃ���ʔz���ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�@�ǂ��炩�ƌ����ǂ̍��ɂ�������u�ꓖ����I�v�ȑ�ԗ��ł͂��������A��Ί�Ƌ@���͂̑g�ݍ��킹���o���A��̑�ԗ��E��Ԃ̂�������o�����B
�@�Q�[���ł͏��Ղ�������ɑ����Y���\�ƂȂ��Ă���A�Η͂͂������̂̋@���͂����邱�Ƃ��珉���̑�Η͂Ƃ��Ă͎g������͏�X�ł���B
�@���̐�������Βn�U���ւ̓����͖��d�����A�R�X�g���}�����Ă���_�͕]���������A�{���̑�C���ł͔�Q���C�ɂ����O���ϋɓ����ł��邾�낤�B
�@�i�����Sdkfz7/1�i���@�����ɂ�葦���Y���\�j�ŁA�n���Ȃ��猘���Ȑ��\���オ�����܂�邱�Ƃ���A�����Y�E�i���̉��ւƋ��ɑ��₩�Ɉ����p�������B
|
 |
��Sdkfz7/1�@�i��ԗ��j
�@Sdkfz7�n�[�t�g���b�N��20mm4�A����@�֖C�𓋍ڂ������̂ŁA��퓬�̂ق��ɒn��ւ̋@�e�|�˂Ȃǂɂ��g�p���ꂽ�ԗ��ł���B
�@�ԑ̂͌����E�A����ړI�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ŁA88mm���˖C�̌����A�l���ړ��ȂǂɍL���g���Ă���������m���x�������A�����������f��A�Q�[���ł����Ȃ��݂��B
�@�����́i���ڔ\�́j�A�s���n�̑��j���ɗD��Ă������Ƃ��瑕�b���������̑�ԗ��ւ̓]�p�ɂ͍œK�Ȏԗ��ŁA�n���ɐ���\�͂Ȃǂ������������Ƃ�����p�������������B
�@�����ʂ�20mm�@�֖C���̗p����A�ꔭ�̉Η͂͑傫���Ƃ͌����Ȃ�������4�A���ƌ����d�l����ł��o�����e���͔��[�ł͂Ȃ��A�|�˂��鑤�ɂ͖��ȑ㕨�ł������ƌ����B
�@������ԗ��Ƃ��Ă̓o�����X���ǂ��D�ꂽ�������\�������A���ڂ���Ă����@�֖C�͒n��ւ̎ˌ����\�ł��������߁A��E�Βn�C���Ƃ��킵�Ȃ������܂�����B
�@������ɂ͍q��̐i���ɂ���Ė{�Ԃł͖��炩�ɔ\�͂��s�����鎖�ԂɊׂ������A�퓬�ԗ��̕s�����炻�̂悤�ȏ��ł��^�p���ꑱ���Ă���B
�@�Q�[���ł͏��Ձ`���Ղɂ����ăf�}�[�OD7����̐i���A���@�����ɂ���đ����Y���\�ŁA�����ȑ�ԗ��Ƃ��Ď��p���̍������݂ł���B
�@�b�����̂��ߖh�䐫�\�͂قږ����ɓ��������A����ɉ^�p�ł���N��ɂ��Ă͑�Η͂������A�ΐl�Η͂������_�͒n���Ɏg���₷���B
�@�i����38�����ԂƂȂ邪�A������͗��m�肵�Ă��邽�߁A�i�����T�����[�x�����[�Q���iIV����Ԍn�iH�^�Ȃǁj������ǁj�֏�肭�q�������Ƃ���ł���B
|
 |
��38�������@�i38(t)���ԁ@���ԁj
�@�x�d�Ȃ�헪�E��p�̎��s���琧�̎�̉��������Ă����h�C�c�鍑�R�ł́A�������ɑ傫���Ȃ��̋��ЂɑR���邽�߂̐�p�ԗ������߂��A�J�����n�܂����B
�@�ꉞ�A���[�x�����[�Q���͊������z���\��ł������̂����A�q�g���[�̉����ɂ�肱��̉��ǁE���Y���������肵�����߁A����܂ł̌q���Ƃ��ċ}篁A�{�Ԃ͊J������Ă���B
�@�ԑ̂ɂ�38(t)�y��Ԃ�p���A���20mm��@�֖C���Œ�ƌ`�Ƃ��Ă͊m���ɑ��Ԃł��������A�Η͂����b���Ⴍ�A�����I�ɂ́u�ꉞ��퓬���o����v���x���ł������B
�@�}���̒ᐫ�\�ԗ��ł͂��������A�@�������ɐ����ł���ƌ����_�͗��R�Ƃ��Ă͔��ɗL�p�Ȃ��̂ŁA�ʎY���ꂽ�ԗ��͎��X�Ƒ��b�t�c�֑����z�����Ȃ���Ă���B
�@���̐�������퓬�̌������O���֓����i��ɐ����j����鎖�������A�Q����G��R�ƌ��𑱂������A���\�I�ɑ��b�s���Ƃ������Ƃ��瑹�Q���傫���A����ꂽ�ԗ��͂��Ȃ葽���B
�@���[�x�����[�Q���Ȃǂ̖{�i�I�ȑ��Ԃ���������ƁA���p���̖�ڂ͉ʂ������Ƃ��ꐶ�Y�͒�~����A�㑱�̑��ԒB�Ə�����サ�Ă������B
�@�Q�[���ł͎j�����l�ɉΗ͕s���̖ڗ����ԂŁA���Ղ�Sdkfz7/1����̐i���A���@�����ɂ�鑦���Y�ɂ���Ď�ɓ���邱�Ƃ��o����B
�@���\�s�������m�ł��邱�Ƃ���A���ꂵ���g���Ȃ��Ȃ�ǂ����悤���Ȃ����A����ȊO�Ȃ�Ώo�������{�Ԃ̔z�����Ԃ�Z�����ASdkfz7/1���烁�[�x�����[�Q���ւƂ��܂��Ȃ������B
�@�i����̓��[�x�����[�Q���ł��邪�A���[�x�����[�Q���͌��4����ԁiH�^�j����̉��ǂŊy�ɓ����邽�߁A�킴�킴�{�Ԃ��o�R����K�v�������̂��~�����낤�B
|
|
�����[�x�����[�Q���@�i���ԁj
�@VI����Ԃ̎ԑ̂ɓ��ڂ����u�퓬���ɓW�J�����l���̑��b�ŁE�퓬���v�������I�ȑ��Ԃł���A���̌i�ς���Ƌ�^���ԁF���[�x�����[�Q���Ƃ����������B
�@37mm��C�����ڂ���i����20mm��C�����ڂ����\��ł������j�A�����������ւƂ̗v�]�����艼���Y�Ƃ����`�ŗʎY�ɓ������B
�@�퓬���ʂ͂��܂�c����Ă��Ȃ��悤�����A�����̃h�C�c�R�ł͐������X�Ɏ�������A�A���R�̋�P�A���ɏP���@�̓������ɂ͋ꂢ�o�������邱�Ƃ����������B
�@���̂��Ƃ���A�z����̐��ł͌��킪�\�z����A�����̊���������Ǝv����B
�@�{�Ԃ͐����ȑ��ԓo��܂ł̌q���Ƃ��ĉ��̗p���ꂽ�悤�Ȃ��̂ł��邪�A��p�@�̊J���̒x�ꂩ��I��܂Ŏ��͂Ƃ��ĔC����S�����A�����̕��m����P���������B
�@�Q�[���ł͎��@�����ɂ��IV����Ԍn�iH�^�Ȃǁj������ǁA�����Y���\�ł���B
�@���Ԃ͑S�ʓI�ɃR�X�g�������A�ʎY�����₷�����߁A�R�X�g�̍����q�j�b�g�𗎂Ƃ��̂ɔ��ɓK�����ݒ�ł��邱�Ƃ������B�i���̎��͊o���Ă����Ɩ��ɗ����낤�B�j
�@����āA�����Y���\�ł���A�퓬�@�A88mm��C�Ƃ̃R���r�l�[�V�����ő��Q�����ꂸ�ϋɓI�ɉ^�p���Ă��������B
�@���\�͂������ĕ��ʂƂȂ��Ă���A�ΉE���x���ɂ܂��܂��ŁA�퓬�@�┚���@�A�y�U���@������Ȃ�Ζ��Ȃ��}�����\�A���b�ԁA�������x�Ȃ�Βn�����\�ł���B
�@�{�Ԃ́A������A�L�����y�[���Ŏg����ŏ�ʂ̑��Ԃł���A�i����̃��B���x���r���h�͎�̉��Ƃ������ʂ��҂��߁A��������i�����Ȃ��悤�C���������B
|
 |
�����B���x���r���h�@�i���B���x�����B���h�@���ԁj
�@���[�x�����[�Q���͋��͂ȉΗ͂��ւ锽�ʁA�퓬���͏㕔���b�ł��J���\���ł��������ߐ퓬�̐��������܂łɊԂ������A����Ɏˌ�����ނ��o���ɂ��Ă��܂����_���������B
�@���̂��ߏ����ی삷�鑕�b�����߂�҂͔��ɑ����A�{�Ԃ͂��̗v�]��������IV����Ԃ��x�[�X�ɊJ������A�ȈՂȂ���������ی삷�鑕�b��^�����Ă���B
�@���ς�炸�I�[�v���g�b�v�ł���_�͕ς�薳���������A�قڑS���͂ɑΉ����鑕�b�͂�����x�h�䐫�\�����߂鎖�ɐ������A�Ȃ�Ƃ������ی�ł���悤�ɂȂ����B
�@�{�Ԃ͊m���ɖh��͌���ɐ����͂������퓬���ƌ����镔���͋����A���ڂ��ꂽ�@�֖C��Sdkfz7/1�Ɠ����ł��������߁A�������̂������������̂̕��������Ƃ�������B
�@���ɑS�����̃��V�v���@����ɂ̓��[�x�����[�Q���ȉ���20mm�@�֖C�ł͖��炩�ɉΗ͕s���ŁA���Ă�������������t�ł��������߁A���Y�v��͑啝�ɏk�����ꂽ�B
�@�ꕔ�͂�����x�̊�������������V�K���Y�͂قڊF���A�ԑ̂͏C���Ŗ߂��Ă���IV����Ԃ��g����L�l�ŁA�������v�f�ʂ�ɂ����Ȃ����������������镺��ł��낤�B
�@�Q�[���ł́u�����I�ȍŏI�i���v�̑��ԂŁA���[�x�����[�Q������i���œ��鎖���ł���A���A���̔\�͒l�̒Ⴓ����i���Ƃ��������މ��ƌ������ق����������B
�@�{�Ԃւ̐i�����قƂ��㩓��R�ł���A���[�x�����[�Q������͎�����̉��A�I�X�g�E�B���h�ւ͐i���\�Ɍq���肪������̂̐i���s�Ƃ����Ӗ��s���ȕ��̂ƂȂ��Ă���B
�@�������������R����h�C�c�鍑�R�̑�ԗ��E��Ԃ͎����I�Ƀ��[�x�����[�Q������Ԏg���₷���A�����Ői�����~�߂Ă����̂���Ԗ���낤�B
|
|
���I�X�g�E�B���h�@�i�I�X�g���B���g�@���ԁj
�@���B���x���r���h�Ɠ��l�Ƀ��[�x�����[�Q���̌�p�Ƃ��Čv�悳��AIV����Ԃ��x�[�X�ɊJ�����ꂽ���Ԃł���B
�@�{�Ԃ͂���܂ł̑�ԗ��E��Ԃ̔��ȓ_�𑽂����P���\�͂������ɐL�����Ԃ��������A�{���̃N�[�Q���u���b�c���Ԃ���ɍT���Ă��������琶�Y���͋ɂ߂ď��Ȃ������B
�@IV����Ԃ���b�ɂ��Ă����_�̓��B���x���r���h�Ƒ卷�Ȃ����A�@�֖C��37mm�ɋ�������A�ԑ̂����̑���a�@�֖C�ɑΉ�������ׂ������̉��ǂ�������ꂽ�B
�@�퓬���͓��R�S���͑��b�ŕی삳�ꃁ�[�x�����[�Q���̖h��͂�����A37mm�@�֖C�͒e���̌����ł�20mm�@�֖C�ɗ����̂́A�˒��E�Η͂͂����啝�ɏ����Ă����B
�@���\�I�͗ǍD�������悤�����A�ڂ������퓬�L�^�͖����ǂ̒��x�̊��������̂��͖��m�ł͖������A��������������II�^���v�悳��Ă��������狰�炭�L�p�ł������̂��낤�B
�@�����Ƃ����ɐ��\�������Ƃ���q�̐��Y�v��ɉ����A���Y�H�ꂪ�����ɘA�������ɂ��������Ƃ�����A���Y����50�ɓ͂������̐��͂��܂�ɂ����Ȃ������B
�@�Q�[���ł̓h�C�c�鍑�R�ŋ��̑��Ԃ����A�L�����y�[���ł͐��Y�E�i���s�Ɠ�̃��j�b�g�ł���A�����I�ɉ^�p�s�ł���B�i����������ƈӊO�ȕ��������̂�������Ȃ����j
�@����ăL�����y�[���ł͐i���\�ł��̐��\�����邾���ƂȂ��Ă��܂��̂����A���̐��\�̍�������^�p�ł��Ȃ��������ɐɂ��܂��B
�@�ꕔ�̃}�b�v�ł��̑��݁E���Y���m�F�ł��邪�i���̐��˓��C�Ȃǁj�A���ǁA�ʏ�̃L�����y�[���ł̓��[�x�����[�Q�����g�����ɂȂ邾�낤�B
|
 |
��88mm Flak 36�@�i�������˖C�j
�@�A�n�g�E�A�n�g�̖��ł�����݂́A���˖C�Ƃ��Ă��ΐ�ԖC�Ƃ��Ă����͂ȃh�C�c�鍑�R�̌��������˖C�ł���B
�@�����A����̗���ɉ����Ď��X�ƐV�Z�p����荞�q��@�́A���͂⋌���̑�C�ł̌��Ă͓���Ȃ����A�e���ł͐V�^��C�̔z���𑁋}�ɍs���K�v���������B
�@�h�C�c�鍑�ł�����͓��l�ŁA�����̒鍑�����ł͂�⋌����18�����˖C���^�p���Ă������A����ɃN���b�v�Ђ��A�b�v�f�[�g���s���A36�^�i�{�C�j�Ƃ��ēo�ꂷ�鎖�ɂȂ�B
�@��v�A�����R�̍��˖C��75mm�ł���̂ɑ��A88mm�Ƃ������a�͋ɂ߂č����j��͂ŁA�����O�̐��x�̍���������A��U�������łȂ��Βn�U�����g����قǂł������B
�@III���EIV����ԂȂǎ�͐�Ԃ��G��Ԃ̑��b���ђʂł��Ȃ��̂ɁA�{�C�͂�������ђʂ���Ƃ������Ƃ����X����A���̂��Ƃ�������͂ȉΗ͂ł��������Ƃ��f����B
�@�Q�[�����ł͏������琶�Y���\�ł���A��ˌ��͂������̂��ƁA���x22�Ƃ������\�����đΒn�ˌ����s�����Ƃ��\�ł���B
�@�O�q�̂Ƃ���A��͐�Ԃ�����Ȃ��������琶�Y���\�ł��邽�߁A�Η͕s���̎��ɂ͂��܂��^�p���邱�Ƃő傫�Ȑ�͂ɂȂ邾�낤�B
�@�������A�h�䐫�\�͊F���ɓ������A�O���ɏo���Ƃ�������S�łƂ������Ƃ����肤�邽�߁A�ߐM��������^�p�͋֕����B
�@�i�����88mm Flak 41�Ŏ˒��������1�L�����Ƃ��o�����A���ǂł͎������ɂ��邱�Ƃ��ł��A���p���͔��ɍ����B
|
 |
��88mm Flak 41�@�i�������˖C�j
�@��Η͂��ւ�Flak 36�ɑ���a���̃o�[�W�����A�b�v���{�������˖C�ł���A���a��L56����L74�Ƃ���ɒ����Ȃ������A36�^�ɔ�˒���30%�O��L�����Ƃɐ������Ă���B
�@���̉Η͂͂��͂⌡�����˖C�Ƃ������x���ł͂Ȃ��A���_�ɌŒ�ݒu���鍂�˖C�Ǝ����悤�ȈЗ͂ł���A120mm�O��̌Œ荂�˖C�Ɣ�ׂĂ����Ȃ����̂ł������B
�@�A�n�g�A�n�g��̒��ł��ɂ߂č������\���ւ�{�C�ł͂��邪�A�\���̊���ɂ��܂�ɂ��З͂��������A�̏Ⴊ��⑽���Ȃ��Ă��܂����_���ő�̎�_�ł���B
�@���̎�̖C�͂����炩���邪�AL56��p����������18�A36�^�����߂Ƃ��A���@�B�����̓����37�^�iL56�j�A�ʂĂ�L88��p����37/41�^�Ƃ������̂����݂���B
�@�{�C�͂��̒��ł����Ȃ�o�����X�̎�ꂽ���̂ł��������A���Y�̒x���g���u������v���悤�ȗʎY���i�܂��A���̎�Ƃ��Ă͐��Y�吔�����Ȃ������B
�@�ΐ�Ԑ�����Ȃ���悤�H�v���Ȃ���Ă���A���ہA������ł����Ă���̂����A����������Ƒΐ�Ԑ퓬���l���������̕ӂ�̐v���̏��U�����Ă����̂�������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͒��Ձ`�I�Ղɍ����|����ӂ��36�^����i���ł���悤�ɂȂ�A�ꕔ�̃}�b�v�ł͑����Y���\�ŁA���̈З́A�˒��͋���36�^������B
�@���ς�炸����ڂĕ��݂̖h��͂ɂ͕s����������̂́A�n��͋��Ђ̎˒��A�n�Βn�ł͐�ԖC�ɗ��ʉΗ͂Ɛ�͂Ƃ��Ă͐\�����̂Ȃ����\���B
�@�˒��̒������炻�̂܂܂ł��\���Ȑ�͂����A�I�Ղɂ͎��������ǂ��\�ł��邽�߁A��C�Ȃǂł��������Q���ʂ悤�C�����Ȃ��炤�܂����ǂ������Ƃ���ł���B
|
 |
��105mm��C�@�i10.5cm leFH 18�@�����֒e�C�j
�@�ČR���錾������O���疧���Ƀ��C�����^���Ō����J������A�J��O�ɐ����̗p�A�����Ĉ���I�ŃI�[�\�h�b�N�X�ȃX�^�C�����瑽���̕����ɔz�����ꂽ���C�ł���B
�@���ɂ����Ă͑����̖��C���a�����Ă��邪�A�{�C�͋@�B�I�ɕW���I�ł����������畺�ɂƂ��Ă͓���݂₷���A���\�����肵�Ă������߉��ǂ������A�I��܂ʼn^�p���ꂽ�B
�@�����^�͌����̕��@�┭�C��̔����̋z�����@�ɂ�������A���ɂ����Ă��i���r��ł��������Ƃ���A���̖ʂł͉��ǂ��ϋɓI�ɍs���Ă���B
�@�܂��A�{�C�̉��nj^�͎������֒e�C���F�X�y�ɍ̗p���ꂽ��AIII���ˌ��CStuH 42�Ȃǂɍ̗p�����ȂǁA������Ȃǂւ̓]�p���ϋɓI�ɍs���A���L���g��ꂽ�B
�@���}�ȖC�ł͂����������̕��M�����͍����A�h�C�c�鍑�R�͂������A���͊W�ɂ��鍑�ɂ��A�o�����ȂǁA�����݂̂Ȃ炸�����܂����ł��g���Ă���B
�@�֒e�C�Ƃ����n���ȑ��݂ł͂��邪�A�J�킩��I��܂Œ��������ȓ����������A�����̍U�����疖���̎琨�ɂ܂ő����̏�ʂŊ����B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��瑦���Y���\�ł��邱�Ƃ����Q���C�ɂ����g���A�ΉE�˒����ɕ��ϓI�Ȑ��\�ł��邱�Ƃ���Ȃ����������₷����C�ł���B
�@�����C�̎�_�ł���h��͂̒Ⴓ�͖{�C�ł������邽�߁A�O���t�߂֔z�u���鐫�����l�����A�o�������D�ʂȈʒu�ɓW�J���ĖC�����s�������B
�@���Ղ���150mm��C�ւ̐i�����\�ŁA���Ղɂ̓��F�X�y�ւ̉��ǂ��o���A�ėp���ɂ��D��Ă��鎖���琔��͎����Ă��Ă����͂Ȃ����낤�B�i�����F�X�y�͒��Չ߂��ɑ����Y�j
|
|
���h�C�c�鍑�R�����@�i�����j
�@�ǂ����Ă����㕺��ɂ���ڂ������Ă��܂������ȃh�C�c�鍑�R��͂ł��邪�A������͂̋K�͂������̈ꍑ�̌R�Ƃ��Ă͑�K�͂Ȃ��̂ł���A�l�X�ȓ���������B
�@���ɋ���E�P���Ɋւ��Ă͋��ɋɂ߂Ď��̍������̂ł���A�����̓��K�������Ɣ�א��i��̔\�͂������A���Ղ̏��Ȃ���풆���܂ł͔��ɍ����퓬�͂��ւ��Ă����B
�@�����i�ɂ����Ă��A�����̍\���l����������x�ɂȂ�Ɣz�������@�֏e�A����ɖ҈Ђ�U������p���c�@�[�t�@�E�X�g�i�V�����b�N�j�ȂǁA�Ɠ��̔\�́E�l��������������Ă���B
�@�܂��A���Ȃɂ���Ă͑�풆�Ɂu���e���v�Ƃ����ď̂���������Ă���A�����Ƃ�����ɂ����Đ�Ӎ��g���A���݈ȊO�̉����u���ʂȈӖ������v���������킹�Ă����悤���B
�@���ʁA���͂̊W�Ŗ��������A�@�B���̒x���A�������e�E�Z�@�֏e�����X�܂ōs���n��Ȃ��ȂǁA�h�C�c�鍑�R�̕����ɂ͏�ɐ��Y�E�����͕s�����t���܂Ƃ��Ă����B
�@�����āA���킪�i�ނɘA��Ĕ�Q���傫���Ȃ�A�A���R�Ƃ̐틵���U�甽�]���鍠�ɂ͕��m�̎��A�����i�̋����ʂ������n�߁A���X�ɂ��̔\�͂𗎂Ƃ��Ă������ƂɂȂ�E�E�E�B
�@�Q�[���ł͎�����Ɍ����������̕������o�ꂵ�A�����A�G���[�g�����A���b�G�e���A�~�����A���e���ASS���b���e���ƃo���G�[�V�����L���ł���B
�@���ł��G���[�g�����A���b���e���A�~�����ASS���b���e���̎g������͗ǍD�ŁASS���b���e���Ɏ����Ă͑S�Q�퍑�̕������ŁA�ō��̐퓬�\�͂��ւ�B
�@���Ղ���G���[�g�������~�����ւ̐i�����o���Ȃ��Ȃ�ȊO�͑傫�Ȗ��������A�������D�G�Ƃ�������{�鍑�R�����Ƃ̔�r�ł���镔���͂قƂ�ǖ����B
�@�O�q�̂Ƃ���A���Ոȍ~�͍~�����̊m�ۂ��������ƂȂ邽�߁A�~�������K�v�ł���Ȃ�A���Ղ܂łɕK�v�ȕ��𑵂��Ă��������Ƃ��낾�B
|
 |
����l���y���b���@(���b��)
�@�����̋@�B���𐄂��i�߂邽�߂ɑ���{�鍑�R���J�������ԗ��ŁA���X�͑��b�ԗ��Ƃ��Ăł͂Ȃ��e��Ȃǂ̉^���ԗ��Ƃ��Čv�悳��Ă����ԗ��ł���B
�@�J�����ɂ͗D�G�ȃC�M���X�鍑�̃r�b�J�[�X����Ԃ���{�Ƃ���A����ɃT�X�y���V�����̉��ǁA�n�ڕ��@�̕ύX�Ȃǂ��{���ꂽ���ƂŔ��ɗD�ꂽ�ԗ��Ƃ��Ċ��������B
�@�ԗ������������e�X�g���Ă݂��Ƃ���A�R���̊��҈ȏ�ɍ����@���́A�^�p�����m�F���ꂽ���߁A���̎��_�������ĉ^���ԗ��ł͂Ȃ����b�ԂƂ��ċ敪�̊i�グ���Ȃ��ꂽ�B
�@���͉^���ԗ��Ƃ͌����ǂ��A�ꉞ�͔������b���{����A�����a�@�e����������Ă������ߍŒ���̐퓬�͂͊m�ۂ���Ă���A�g������̗ǂ����瑽���̔C���ɍ̗p���ꂽ�B
�@�O���^�ł��^�p���͏\���ł��������A����^�ł͑����̉��ǁA�^�p���@���L�߂邽�߂̉��ǂ��{����A�����萫�̍����ԗ��Ƃ��Ċ����x�͏オ���Ă���B
�@�������퓬�ɂ͑ς����Ȃ��ԗ��ł��������A�y�����ƌy�ʂ��̃o�����X���ǂ����H�ɂ������������߂ɏd��A�O����ނ����ԗ����I��܂ő厖�ɉ^�p���ꂽ�B
�@�Q�[���ł͏��Ղ��瑦���Y�ł���u�ɂ߂ăR�X�g�̈�����@�ԁv�Ƃ��ēo�ꂵ�A�n��ȗ��R���҂������ɍ���Ȃ��悤���G�͈͂��L�߂Ă����d�v�Ȏԗ��ł���B
�@���b�͖����ɓ������������@�e�݂̂̂��ߐ퓬�͂͒������Ⴂ���A��@�p���j�b�g�Ƃ��Ĉړ���6�A���G�͈�4�Ƃ������\�͗��������A�R�X�g������قڎg���̂Ċ��o�Ŏg����B
�@���Ղ���㎵���y���b�ԁA����y��Ԃi���E���ǂ��\�����A����炪�����Y�ł��鎞���͑�����A���b�ԁE�y��Ԃɂ����܂Ŏ�Ԃ������邩�ǂ�������l�������B
|
 |
���㎵���y���b���@(�e�P�@���b��)
�@���{�R�������̋@�B���𑣐i���邽�߁A�J�����ꂽ���b�Ԃł���B
�@�@�B���͂��Ƃ�莩���ԉ�����x��Ă������{�R�ɂƂ��āA�M�d�ȋ@�B�������Ƃ��ďd��A�I��܂Ŏg�p���ꂽ�B
�@�O�g�͋�l���y���b�Ԃł��邪�A��l�����@�e�݂̂̕����ł������̂ɑ��A�{�Ԃ�37mm�C�𓋍ڂ��A�Η͂���������Ă���B
�@�܂��A�Ђ̔������₷�������K�\�����G���W�����f�B�[�[���G���W���ɕύX�����̂��傫�ȕύX�_�ł���B
�@���ɂ��ׂ������C�͐������s���A�����̃}���[��ł͋㎵������ԂƋ��ɑ��ʂ��グ���B
�@��햖���ł͐N�U��킪�s���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���̋@���͂����������Ƃ͂Ȃ��Ȃ������A�M�d�ȉΗ͂Ƃ��čŊ��܂ő�ɂ��ꂽ�B
�@�Q�[���ł͈ړ���7�A���G�͈�4�Ɗ��S�Ȓ�@�p���j�b�g�Ƃ��Ċ���B
�@���{�R��ԓ`���̑��b�����Ƃ����������p���ł���A��h��10�A�Βn�h��5�ƕ��������n��ȑ��b�ł���A���d�ȍs���͍T�������B�@�i�L�q�C���j
�@�ǂ��炩�Ƃ����Ζ��ɗ����Ȃ����ނ̃��j�b�g�ł͂��邪�A$250�Ƌɒ[�ɃR�X�g���������߁A���[�_�[�Ƃ��đ�ʐ��Y����̂��ʔ�����������Ȃ��B
|
 |
������y����@(�n���@�y���)
�@��C�ɂƂ͂������Ƃ������Ɏ����ԉ��E�@�B����i�߂Ă�������{�鍑�R�́A�������ʂ̏����荇���Ŏv��ʃo�����X�̕���ɒ��ʂ��Ă��܂����B
�@���́u����v�Ƃ͓����̎�͐�ԁA���㎮����Ԃ����܂�ɂ��x�����A�����ԉ��E�@�B�����������ƘA�g�E�����ł��Ȃ��Ƃ������̂ŁA�{�Ԃ͂����₤�ׂ��a�����Ă���B
�@�Z�p�͂̊W�����n�̓G���W���̎g�p�͓��R�����ŁA���㎮����ԂƓ����̃G���W�����̗p���ꂽ���A����͋@������ɂ͌y�ʉ����K�{�Ƃ��������ɈӖ����Ă����B
�@�@�����m�ۂ̂��߂̌y�ʉ��A���^���͓O�ꂳ��A��C�͏��������̂���37mm�C���A���킹�Čy���b���̗p����A�퓬�͓I�ɂ͒�ΉE��h��͂ƖJ�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B
�@�����A���ꂾ���O��I�ȋ@���͋����E�y�ʉ������ꂽ�䂦�Ɉ��H�̑����������ʂł͋@���͂ɗD��A�����m����ł͕͗s���ł��A�����Ղ��ȂǁA����̗ǂ��ʂ��������B
�@��p�Ɍb�܂ꂸ�g��������ꂽ�_�A���\���A���o�����X�ȓ_�����ʓI�ȕ]���͗ǂ��Ȃ����A�^�p���@�ɖ�肪���������ߏ�肢�^�p������Ă���Ɖ���܂��B
�@�Q�[���ł͌y��ԂƂ��ēo�ꂵ�A�R�X�g���������G�ɗD��A���Ղɋ�l���y���b�Ԃ���̐i���A���@�����ɂ�葦���Y�Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��o����B
�@�@�e�݂̂̋�l���y���b�Ԃɔ��C���������ƂŐ퓬�͂͌��サ�Ă��邪�A�Η͂͒Ⴍ���b���������߂ɐ퓬�ł͊��҂ł��Ȃ����߁A���G�C���ɐ�O������̂��ǂ����낤�B
�@�i����͋㔪���y��ԂɂȂ邪�A����{�鍑�R�̑��b�ԁE�y��Ԃ̐��\�͂قډ����ł��邽�߁A�i����������i����ɂ��u�i���v���s�����Ǝ��̂��܂�K�v������������Ȃ��B
|
 |
���㔪���y����@(�P�j�@�y���)
�@����y��Ԃ̌�p�Ƃ��ĊJ���E�^�p���ꂽ����{�鍑�R�̎ԗ��ł���A����y��Ԃ̗ǂ��������c���V���ȋZ�p�𓊓��������R�y��ԂƂ��Ă͖�S�I�Ȏԗ��ł���B
�@����̓A���o�����X�ȓ_���s�]�ł��������̂̐�ԕ��ɂƂ��Ă͊���e���ԗ��ɂȂ��Ă���A�z�����炵�炭�͐V���ȗv�]���p�Ԃ̘b�͏o�Ȃ������B
�@�R���ł����̂悤�ȏ��牽�̘b���o�Ȃ��������A����̗���Ƌ��ɂ�͂葊���̌�p�Ԃ��K�v�ł���Ƃ̐����オ��A���ɋ������5�N�̍Ό����o�ēo�ꂵ���B
�@����ɔ�ב����̐V�Z�p�E��ԗ��_����荞�܂�Ă���A�v�A�����̐ݒu���@�A���b�̎{�����A�����ȂǓ����̑���{�鍑�R�Ƃ��Ă͋ɂ߂Đ�i�I�ł������B
�@�����̗v���Ɍb�܂�u�����\�Ȃ͂��v�ł��������A��ǂ̗��痈�鍑�͒ቺ�A�y��Ԃ̗̍p�������������A��������𗘂����Ă��������琶�Y���͋ɏ����ł���B
�@�o�ꎞ�ɂ͊��Ɍy��ԂƂ����敪�ɖ��������鎞���̏�A���Y�䐔�̊W������ɕ����ԗ������Ȃ��A���ۂ̉^�p�L�^��C�ɂȂ�悤�Ȉ�b�͂قږ����ƌ����Ă������낤�B
�@�Q�[���ł͑���{�鍑�R�̍��G�p����ŏ�ʂƂ��ēo�ꂵ�A���Ոȍ~�ɋ���y��Ԃ���̐i���A�ꕔ�}�b�v�ł͑����Y�ɂĎ�ɓ���B
�@���\�I�ɂ͋���Ƒ卷�͖����A���R�̒�@�ԁE�y��Ԃ̗�ɘR�ꂸ�ᐫ�\�łقڍ��G�p�Ƃ����ʒu�t���͕ς��Ȃ����߁A�o�������퓬������ĉ^�p���ׂ��ł���B
�@�I�Ղɍ����|���邠����Ɏ������ԃ\�L�ւƉ��ǂ��\�ɂȂ邪�A������͕ʂ̕���ւƗl�ς�肵�Ă��܂����ߒ��ӂ��K�v���B
|
 |
�����㎮������@(�����)
�@����{�鍑���̍��Y�E���������ꂽ��Ԃ����A��͂蓖���̓��{�ł͓Ǝ��̊J���͓���A���ۂɂ̓C�M���X�̐�Ԃ��Q�l�ɊJ������Ă���B
�@�������Ȃ���A�����Ő�ԂY�E�J���ł���Ƃ������Ƃ͑�ϗL���Ȏ��ł���A����^���܂ߖ{�Ԃ̐����͑���{�鍑�̐�ԊJ���ɉe����^�����悤��
�@���̍��Y��ԂƂ������Ƃ�����A�����A���b�A�@�B�����͗ǂ��Ƃ͌������A�ꕔ�������Ⴄ�A�n���ɒ������Ԃ�������ȂǁA���P���ׂ��_�������A���ꂪ��̉��ǂɌq�������B
�@�܂��A���b�́A�����̓S�|�Z�p�ł͑��b�S������H�ꂪ�w�ǖ����A�����͂����ꕔ�̍H��Ő��Y����A�n�ڋZ�p���Ⴉ�������߂Ƀ��x�b�g�~�߂����p����Ă���B
�@���̂��߂ɑ\�r�G�g��ł͉Η͂�����Ȃ��ABT��Ԃ��܂Ƃ��Ɍ��j�o���Ȃ��ȂǁA�Ǝ�ȓ_��������炩�ɂȂ�A���_�����S�ɘI�o����`�ƂȂ����B
�@���\�I�ɂ͑�평���ʼn^�p��ł�����ׂ����x���ł͂��邪�A�����I�ȉΗ͕s��������Ɏ�o����A��Q���o�����퓬�ɎQ������Ƃ����ߎS�ȉ^�������ǂ����B
�@�Q�[�����ł͒���ԂƂ͖��O�����́A�����A�x�����b�ԕ��݂̈����ƂȂ��Ă���B
�@���ɗD�ꂽ�ʂ͖����A�ނ�����Ƃ��낵���Ȃ��Ƃ����A�ɂ߂Ĉ����Â炢��ԂŁA�{�ԂY���邭�炢�Ȃ�A��������C�Y��������L�Ӌ`���낤�B�i�M�҂̍l���ɂ��j
�@�������Ȃ���A�i����͑���{�鍑�B��̏d��ԁi�܂�����������\�́E�E�E�j�ƂȂ��Ă���A1�A2���j�b�g���x�X�g�b�N���Ă����Ζʔ�����������Ȃ��B
|
 |
���㎵�������/���@(�㎵������ԃ`�n/���@�����)
�@�����ł̐l�C�͍������A�X�y�b�N�͑����y��ԕ��݂ł���A���\�I�ɂ͗̒��ł����Ȃ艺�̒���Ԃł���B
�@���X�̃`�n���Z�C�g57mm�C�ł������̂ɑ��A�`�n���ɂ����Ă͒��C�g47mm�C�ւƕύX����Ă���A��炩�̉Η͋������{����Ă���B
�@�o�ꎞ�������_�Ŏ�C��47mm�C�͂��łɎ���x��ƂȂ��Ă���A��G���ł���A�����J�̒���ԃV���[�}���ɑ��ẮA��ɂ��Ȃ�̕s�����������邱�ƂɂȂ����B
�@���{�ł̕���J���͑嗤���ƂƈႢ�A���{�l�̑̊i�A�n�C�A�������̋Z�p���x���A�������̓_���l������K�v���������炵���A�{�Ԃ̊J���ɂ����Ȃ�̋�J���������悤���B
�@������x�̋K�i����͂Ƃ��Ă����悤�����A���������ł��ꕔ�̕��i�ł͕����Ђ̔����ɈႤ���i�����݂��Ă����炵���A�����e�i���X���͂��܂�悭�Ȃ������炵���B
�@�Q�[�����ł͑���{�鍑�R�̗��핺�퐫�\�A���̈������ǂ����Ă��ڗ����A�R�����Ă����퓬���e�A����v�z�̔��B�̒x�����l����Ǝd���̂Ȃ����Ƃł���Ǝv����B
�@��O�Ȃ��{�Ԃ̐��\�����Ȃ��������̂ł���A���Ոȍ~�A�����������ΐ�Ԍg�щΊ�����悤�ɂȂ�ƒ��������Q����������悤�ɂȂ�B
�@�{�Ԃ��ʔz������v���C�X�^�C���͂����߂ł��Ȃ����A��ʔz������Ȃ�ł�����葹�Q�����Ȃ��Ȃ�悤�ɐ�ǂ����ɂ߂ĉ^�p�������B
|

coffee break |
|
�`����{�鍑�̐�Ԏ���`
�@��ʓI�ɑ���{�鍑�̐퓬�ԗ��A���ɐ�Ԃ͔�͂Ŏア�Ƃ���Ă���B�������A���ۂɂ͔��㎮����Ԃ͓o�ꓖ���A�����̐�Ԃɔ�ׂĂ�����قǗ���Ԃł͂Ȃ��������A���S�ʂʼn^�p���ꂽ�㎵������ԁi/���j����͂�o�ꎞ�͂���Ȃ�̐퓬�͂������Ă����B���́A�Ȃ��킢���������Ă��i������A�J�����p�����i�܂Ȃ������̂��ł���B
�@�M�҂��l���邾���ł����R�͊������B�܂��A���O�������Ă��������R��ɋ��͂Ȑ�Ԃ͕s�v�ŁA��Ԃ����ڂ���Ă��Ȃ��������B�{���������ł��������ߐ�Ԃ����܂��R�p�@�A�R�͂̊m�ۂ��D�悳�ꂽ���A�܂��A���̂��ߌ�p��Ԃ̊J������ɂȂ��Ă������B���ɑ��������X�Ɛ�Ԃ�i�������Ă���������ɐڂ���@��قƂ�ǖ����A���ɂ��̏��ɓ����Ă����܂����̑Ή��i�����ǁj�����ő�����Ԃ�������̂�ϋɓI�ɍ�낤�Ƃ��Ȃ��������B�����ėA���D�A�`�Ȃǂ̃C���t�����\���łȂ�����������^���ɐ��������������Ȃǂł���B�ނ��Z�p�I�Ȗ������������A���̑�����������肪�Ȃ��B���ɏd�ʂ̂��鋭�͂Ȑ�Ԃ��J���ł��Ă���ʂɍ��鍑�͂͂Ȃ��������A�o���オ���������O���ɉ^�Ԏ��������̑���{�鍑�ł͓�������̂��B�Z�p�卑�̑���{�鍑�ł�����܂ł̐킢���瓾���Â���P��n���I�ȉe���͂ǂ����悤���Ȃ������ƌ�����B�܂�A�ォ�����ƌ��������K�R�I�ɂ����Ȃ����ƌ��������������̂��낤�B
�@�܂��A�l�ԓI�Ȏ��_�Ō���Ɠ����̓��{�l�̑̊i�ł͐l�͂ő���a�C�e�̑��U��d�ԑ̂̑��삪�o����Ƃ͎v�����A���͂Ȑ�Ԃ�����Ă��^�p���̓��������������Ȃ��B
|
 |
���ꎮ����ԁ@�`�w�@(�����)
�@�㎵������Ԃ͓o�ꓖ���������E�ō����x���̐�Ԃł͂��������A���ڂ��ꂽ57mm�Z�C�g�ł͐퓬�\�͂ɕs��������Ɣ��f����A�J���E���������ꂽ�̂��{�Ԃł���B
�@�{�Ԃ̎ԑ̂͒����𑽂��p�����č���Ă���A���x�b�g�~�߂𑽗p���č��ꂽ�㎵������ԂȂǂ̑��b�ɔ�ׁA������x���������h��͂��������Ă���B
�@����Ŏ�C�͂���Η͂̂��̂����߂�ꂽ���̂́A���������]���̐�ԂƋ��ʉ���ړI�Ƃ���47mm���̗p����Ă���A�Η͓I�ɂ͖w�Ǖω��������B
�@�틵�̍D�]�����o���Ȃ����Ő��Y�͑�����ꂽ���A���̖w�ǂ͖{�y����ɉ�������Ă���A�퓬�ɎQ�����邱�Ƃ͂قږ��������B
�@�Ȃ��A�{�Ԃ̐��Y�Ƌ㎵������ԉ��̐��Y�͎����I�ɂ��Ԃ��Ă���A���Y����ł͑S�̓I�Ȑ��Y���������Ȃ艺�������悤�ł���B
�@�Q�[���ł͎��@�����ɂ��i���E���Y���\�ƂȂ�B
�@�㎵������ԉ����l�A47mm�C�̉ΉE���x�͋ɂ߂ĒႭ�i���x��13�j�A���x���ɒ[�ɍ����Ȃ���ΐ搧�����͓̂�����낤�B
�@�|�S�̐����ł́A����{�鍑�R�̗��x���S�ʓI�ɗD������Ă��邽�߁A������x�͐킦�邪�A�����ȕ��퐫�\�������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�ߐM�͋֕��ł���B
�@����ԂƂ��ẴR�X�g���ɒ[�ɒႢ�̂��~�������A�i���ɂ�鋭�����l����Ȃ�ΐi���܂ŋC�����A�o������葹�Q���ŏ����ɂ����߂�悤�A�^�p�������B
|
 |
���O������ԁ@�`�k�@(�����)
�@�V�^�V���[�}���Ȃǂ̓o��ɂ��A���Ȃ�̗ɗ������ꂽ����{�鍑���R�́A�\���킦���Ԃ��K�v�ƍl���A�ɒ[�ȒZ���ԂŊJ���E���Y���s����v������ł��o�����B
�@���ʂƂ��ēo�ꂵ���̂��A��C�𗬗p���č��ꂽ75mm�C�������A�ꎮ����Ԃ̎ԑ̂ɑ��b�lj��E���ǂ��{�����{�Ԃł���B
�@�{�Ԃ̓J�^���O�X�y�b�N�͗D��Č�������̂́A75mm�C�͒����s���ł���A�����Ɉꎮ����Ԃ̎ԑ̂𗬗p�������Ŋe���ɕ��ׂ������A���x�ቺ�ȂǗl�X�ȕs�����������B
�@���x�͓������̑����d��ԕ��݂̓ݑ��ł����ă`�n�����A75mm�C�͒����s���E�C�e�̒�i�����琫�\�I�ɂ̓h�C�c�鍑��50mm�C�Ɠ����x������ȉ��̐��\�Ǝv����B
�@�d�ʂ�18t���Ă���A���̃N���X�����͈�ʗA���D�̕W���I�ȃN���[���ł݂͒�グ���o���Ȃ����߁A������Ԃł̐�Ԃ͗A���s�ƂȂ�B�i��^�A���D���j
�@�Q�[���ł̖{�Ԃ͂���܂ł̓��R��ԂƈႢ�A�ΉE���x�Ƃ��ɋ�������Ă���A�㎵������ԉ��A�������͈ꎮ����Ԃ��i���A���@�����ɂ���đ����Y���\�ł���B
�@��ɋ�������Ă���Ƃ͏��������̂́A����́u��r�I�������Ă���v���x���ł���A���x�D���̂Ȃ��ꍇ�ł͑�������Ԃɂ��Ȃ���ꍇ�������B
�@�������Ȃ���A�����x�Ȃ�Α�������ԂƂ��ӊO�ƌ��������郌�x���ł��邽�߁A�����x��Ԃő����Y���\�ł���Ȃ�ΐϋɓI�Ɏg���Ă��������B
�@�Η͂͂�����x����A�ړ��͂�5�A�Q�[���Ȃ�A�������R�\�A�i����͎l������Ԃ������C�ƁA�㔼�̊�b�I�Ȑ�ԂɂȂ邾�낤�B
|
 |
���l������ԁ@�`�g�@(�����)
�@�O������ԂƓ����E���l�̃v�����ɂĊJ�����v�悳�ꂽ��Ԃ̈�ł���A���ŋ߁i2012�N�~�G�j�A�l���̒�ɖ����Ă���̂ł͂ƌ����Ă����Ԃł���B�i���ݒ������j
�@�������Ȃ�����������ԂƂ͈Ⴂ�A������͉��Ƃ������܂ł����������̂́A�x�[�X�ƂȂ��Ԃ������������_�ŏI��ƂȂ�A�ɂ������ʎY�ɂ͎���Ȃ������B
�@����܂Ń`�n�n�ԗ�����b�Ƃ����Ԃ�������������{�鍑�Ƃ��Ă͒������ŏ�����u�ΐ�Ԑ�v���l��������Ԃł���A���̐v�v�z�͍��܂ł̂��̂������x�Ȃ��̂ł������B
�@��C�ɂ͏�������^��57mm�A�������^��75mm�̖C�����ڂ���e�X�g���s���Ă������A�틵�E�Η͂̍����Ȃǂ���������^���{�̗p����A75mm�C�̓��ڂ����肵�Ă���B
�@���Y���@������܂ł̂��̂ƈႢ�A�����̕����ɒ������̗p���ꃊ�x�b�g���r������Ă��������A�Z�p�͂̒Ⴓ����ŏI�H���̑g�ݗ��Ăł͂��Ȃ�̋�J�E�H�v���������悤���B
�@�]���̑���{�鍑��Ԃ���y���ɐi�����������ꂽ��Ԃł��������A���̒a���͂��܂�ɂ��x���A�����삯���邱�Ƃ͖��������̂ł���B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɓo�ꂵ�A�O������Ԃ���̐i���A�ꕔ�}�b�v�ł͑����Y�Ŏ�ɓ��邪�A�i�����̎O������ԂƂ̔�r�ł����\�͍��قǕς��Ȃ����߁A�����x�͕K�{�ł���B
�@����ԂƂ͌������̂́A�������̑�������ԂƂ̔�r�ł͐퓬�͂͂܂��܂����肸�A���x������Ȃ���A�����J�R�y��ԃ`���[�t�B�[����ł����낤�����x���ł���B
�@�{�Ԃ��u����{�鍑�R�̐�Ԃ͎キ�A�g����������v�Ƃ�����ɘR��Ȃ����߁A�C�����ĉ^�p���A���܂��i����̌�����ԂɂȂ��Ă��������B
|
 |
��������� �`���@�i����ԁj
�@���{�R���J�����Ă�������Ԃł���B
�@��Ԃ��̂��̂̏d�v���𗝉����Ă��Ȃ��������{�R�ł́A��ɖ����I�ȉΗ͕s���A��e���̑��Q�ɔY�܂���Ă����B
�@�����Ŗ{��Ԃ̊J�����܂ސ�Ԃ̎d�蒼�����n�܂����̂����A������n�߂��������x�������B
�@�悤�₭�J���̎n�܂����ꎮ�`�����A�ꎮ��Ԃ̈ꕔ�����ɏo�n�߂��A�������͖{�y�p�ɔz������n�߂��Ƃ���ŏI����}���Ă��܂��B�i�͖C��ԁj
�@����Ԃ͂Ƃ��Ƃ��������邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B
�@�Q�[�����ł�88mm�C�𓋍ڂ��A���{�R�ō��̉Η͂��ւ�A�����C���C���̓��{�R�ɋ@���͂�^���Ă����B
�@�������A���{�R�ō��Ƃ͂����Ǒ�������ԓ������������x�ŁA�����̏�Ԃł����̐퓬�őS�ł��邱�Ƃ������B
�@��ʔz��������ɂ́A�����̑��Q�ɂ͖ڂ��҂鈤������ƁA��ƂȂ�O���E�l������Ԃ̉^�p��_�o���ɍs���K�v�����邾�낤�B
|
 |
�������Β��@�i�����Β��J�~�@����ԁ@�����Β��̓ǂ݂́u�Ȃ����Ă��v�u�����тĂ��v�̓�ʂ�ŁA�ǂ����ł��j
�@����{�鍑�C�R�ł������C�R���l�ɗ��핔����ۗL���Ă������A�����̕������㗤���𐋍s����ꍇ�A���������ł���퓬�ԗ������݂��Ȃ������B
�@����͔z������Ă����퓬�ԗ��������������p�̂��̂ł��������߂ŁA���R�̂��ƂȂ���C�ォ��̐N�U�A�h���E����^�p���l�����Ă��Ȃ����������ł���B
�@�㗤���ɋ@���́A�܂��x���Η͕͂K�{�ƍl�����C�R�ł͗��R�ɋ��͂�v�����A����y��Ԃ��x�[�X�ɐ������p��Ԃ̋����J�����s���A���̐��ʂƂ��Ė{�Ԃ͒a�������B
�@�ԑ̎d�l�͂قڋ���y��Ԃɏ��������A�h�����H�ɉ������E���t���[�g�������\�ɂȂ�Ȃlj��ǂ͖{�i�I�ŁA�t���[�g�����ŏ㗤�セ����O���Đ�ԉ�����@�\�ɂȂ��Ă����B
�@�����ɂ��Ă͎�C37mm�ΐ�ԖC�A���C�ɋ@�e�𓋍ڂ��Ă���A����͌���^����y��ԓ����̑����ŁA�퓬�\�͍͂����Ȃ����̂̍Œ���̉Η͂�^�����Ă���B
�@�������p�̗��_�͏d���A��ɓ���ւ̐�͑����E�x���E�����A���̂��ߐϋɓ������ꂽ���A���\�̒Ⴓ�����Q���傫���A�����ł͑傫�ȏo�������^�p���s��ꂽ�B
�@�Q�[���ł͒��Ղ��������肩��o�ꂵ�A�敪�͂Ȃ�������ԁA�قړƗ��������݂Ƃ��đ����Y�ʼn^�p���鎖���\�ƂȂ��Ă���B
�@���\�͂܂��������҂ł��Ȃ����x���ʼnΗ͕s���A�h��͕s���͌����A�B��̎�蕿�ł���u���n���v�\�͂�]���ɑ����Ă��Ȃ��}�C�i�X�ʂ��ڗ��Ƃ�����ł���B
�@�ꉞ�͒���Ԃ����A�����I�Ȕ\�͂͑��b�Ԉȉ��ŗǂ��_�͂قڊF���ł��邽�߁A�{�Ԃ����邭�炢�Ȃ瓯���R�X�g�ŕ��������Y����ق����}�V��������Ȃ��B
|
 |
���������d��ԃI�C�@�i�I�C�ԁ@�d��ԁj
�@���O�ɑ������\�r�G�g�R�Ƃ̏����荇���ő�����Ԃɑ�����������{�鍑�R�́A������Ԃ̕n�コ��g�������đ̊����A���̓_���d��Ȏ�_�ƔF������Ɏ������B
�@���R�����ł͂��̖����������ׂ��A�܂��͂Ƃ�������v�ŋ���Ȑ�Ԃ����삷�ׂ��Ɣ閧�v��͗����オ��A���100�g����Ԃ����Ď��ɖ{�Ԃ��Ƃ����o�܂Ŏ��삳��Ă���B
�@���R��ԂƂ��Ă��ґ�Ɏ������g���A���������b�͍Ō�����200mm���ւ�A��������C105mm�J�m���C�A���C47mm�C�A�����ċ@�e�Ƃ����鑽�C����Ԃł������B
�@�d�ʂɂ��Ă͗l�X�Ȏ������120�g���A140�g���Ƃ��薾�m�ɂȂ��Ă��Ȃ��A�M�ғI�ɂ́u�����܂ŏd���Ƃǂ����ł������i�����s�\�I�ȈӖ��Łj�v�ȂǂƂ�Ⓤ�����Ɏv���Ă��܂��B
�@����10�l�O����悹�đ���|�S�̉Ƃ̂悤�Ȃ��̂ŁA���������ł͂��܂�̏d���ɕܑ��H���ς��ꂸ�A�ʂ����������Ƃ��Ƃ��j��Ă��܂����Ȃǂƌ������������������ł���B
�@�I��ԍہA�ǂ��ɂ����đO���֑���Ȃ������s���낵�A�������Ē������ʂ֑���ڏ��������Ƃ���ŏI����}���A���ǁA�g��ꂸ�A�g�ݗ��Ă�ꂸ�ƕs���ȍŊ����}�����B
�@�Q�[���ł͒��Ղ���I�Ղɍ����|����ӂ�ɔ��㎮����Ԃ���i�����\�ƂȂ�A���b�����Ȃ�Α����d��ԂɕC�G���鐫�\���ւ�A�����܂ő��b�����B
�@��ɓ��ꂽ����͒N�����u�O��̑���{�鍑�d��Ԃ���ɓ��ꂽ���v�Ɗ��삷��͂������A���ۂ̐��\�͂ǂ��\��������悢���̂��A�M�҂��\���ɍ���قǂł���B
�@�ŏI�i���䂦���W���������A�Α��b�Η͂̓`�n�����A�ړ��͂�3�Ǝ�ɓ��ꂽ��͎g�����ɍ��郌�x���ł���i�����̕ǂƂ��Ă�����Ȃ��j�A���S�Ɏ�̕��킾�ƌ����Ă悢���낤�B
|
 |
���ꎮ�����C�@�z�jII�@�i�ꎮ�\�W�����C�@�����C�F�쒀��ԁj
�@�ꎮ�C��ԃz�jI�i75mm�C���ڂ̎����C�j�̐�������A������a�̂��̒Nj��������ʊJ�����ꂽ�����C�ł���A���i�I�Ƀ��F�X�y�̉e�����Ă���ԗ��ł���B
�@�ԑ̂̓z�jI�Ƃقړ����ł��邪�A���b�͈ꕔ�Ȃ���Ă���ԑ͔̂�r�I�y�ʂŁA�z�jI���������a105mm�C�𓋍ڂ��Ă��@���͂͂���قǗ����鎖�͂Ȃ������B
�@�{�Ԃ�105mm�C�͑���a�̂������Ŋm���ɑ傫�ȉΗ͂������Ă������A���̖C���̂͒P�g�C�ł��邽�߂ɏ������x���A�����Z���Ƒΐ�Ԑ�ɂ͕s�����ł���B
�@�������쎩���C�̃z�jI�ł��������߁A�����Ȏԑ̂ɑ���a�C�Ƃ������тȑ����ł��o�����X�͗ǍD�ł���A�̗p���̃e�X�g�ł͖C���A���s�A�^�p���͗ǍD�ł������ƌ����B
�@�ʎY���x�ꂽ���߂Ɋ��������ԗ��͂킸���ŁA�ꕔ�͑O���֑���ꂽ���̂̓r���őD���ƌ������ꂽ��A�{�y�Ɏc�������̂͌���p�ɉ������ꂽ��Ɗ���͏��Ȃ������B
�@����{�鍑�R�Ƃ��Ă͊���Ƃ܂Ƃ��ȗ��p�E�v�z�ō��ꂽ���l����ԗ����ƕM�҂͎v�����A���Y����z���̎d���Ɍb�܂ꂸ�A�s�^�Ȏԗ��������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[���ł͋㎵������Ԍn�A�ꎮ����Ԃ���̉��ǁA���@�����ɂ�鑦���Y�Ŏ�ɓ���A�u�Ȃ����v�쒀��ԂƂ������ނɂȂ��Ă���B�i�z����̉e����������Ȃ��j
�@���قڊF���ł��������߂ɕ��ނ͊J���҂����Ȃ�������Ǝv���邪�A�Ƃ��������̃Q�[���ł͉��B�̞֒e�C�쒀��Ԃ̂悤�Ȉ����ƂȂ��Ă���A�͂����茾���Ύア�B
�@�������������Ƃ��������b�g�͂��邪�A���\���Ⴂ��ɐi���������őł��~�߂ƂȂ邽�߁A�Q�[���̃��j�b�g�Ƃ��Ă͎g���K�v�̖������ނɓ��邾�낤�B
|
 |
���������ԃ\�L�@�i���ԁj
�@�R�p�@�̔��B�ɔ����ċ�̋��Ђ�������悤�ɂȂ�������{�鍑�R�́A���O����ԗ��̌������s���Ă������Ȃ��Ȃ��ǂ����ʂɌ��т��Ȃ������B
�@�{�Ԃ͂��̌o�܂ɂ�镛�Y���̂ЂƂŁA���H�ւ̓�����O��ɊJ������Ă��������ǔ\�͕s�����琳�������ꂸ�A����ԂƂ��Ċ�������݂��Ă����ɂ����Ȃ��B
�@�ԑ̂ɂ͋㔪���y��Ԃ��̗p����A��p�r�ɍ��킹���g���E�lj����b�������{����Ă��������̎ԗ��̐��\�����\�����ɁA���̎��_�ł�△�����������̂��낤�B
�@�����͘A��20mm��@�֖C���̗p���Ă���A����͈�O�̎����ΐ�^�Z���������x�s��������Ă������Ȃ���������A�ˌ����x�����e���鎖��D�悵�����ʂł���B
�@�ˌ��Ɋւ���\�͂͂���܂ł̎����Ԃ�����������A�g��������l�����ꂽ�퓬���A�S����\�ȖC���ȂǍl�����܂ꂽ���̂��������A�ɂ��������ꂪ���ɏo�鎖�͂Ȃ������B
�@����܂ł̑����̔��ȓ_�����P����A�܂������ɑ����̋ߑ�I�ȍl�����������ꂽ�ԗ��ł��������A����{�鍑�R�ł͂���𗝑z�I�Ɏ������邾���̗͂͂Ȃ������̂��B
�@�Q�[���ł͑���{�鍑�R�B��̑��ԂƂ��ēo�ꂵ�A�I�Ղɍ����|���邠����ɋ㔪���y��Ԃ���̐i���A�ꕔ�}�b�v�ł̑����Y�Ŏ�ɓ���B
�@�n��ȓ����R���ے����镺��̈�ł���A�������\�͒Ⴍ��Η͂Ƃ��Ă͗]��ɂ�����Ȃ��ƌ��킴����A�����ȂƂ���i��Ŏg���قǂ̕���ł͂Ȃ����낤�B
�@��̕���Ƃ�����������A�����ɓ���Ă���������x�̑��ɂ͎g���邽�߁A�ŏI�I�ɉ^�p���邩�ǂ����̓v���[���[�̔��f���悩�B
|
 |
���ꎮ�C��ԁ@�z�jI�@�i�����֒e�C�j
�@�����I�ȋ@�B���̒x��͏d�v�ȉΊ�ł��錡���C�܂ŋy�сA������莋��������{�鍑�R�́A�d�Ί�̎�����������A���s���낪�J��Ԃ��ꂽ��Ɋ����ւƎ������B
�@�{�Ԃ͂��̐�삯�ł���A�㎵������Ԃ̎ԑ̂�75mm��͖�C�𓋍ڂ��A�i�O�ʂ̂ݏd�_�I�ɂ����j����{�鍑�R��ԂƂ��Ă͔�r�I�������b�����̂������ƂȂ�B
�@���Ƒ����������琳���������肳��Ă������A���Y�͂̒Ⴓ���琶�Y�͈���ɐi�܂��A��풆������悤�₭���Y���J�n���ꂽ�B�i���Y�䐔�͂�͂菭�Ȃ��j
�@�y���b�A��Η͂ɔY�܂����̂�����̑���{�鍑�R�퓬�ԗ��Ƃ��ẮA�������Ȃ��Ȃ�����������Ă���A���������ԗ��ƌ����Ă��ǂ��B
�@�{���z���ɂƂǂ܂炸�A�e���ʂւƑ��荞�܂ꂽ���A�������������������ԑ̂͏��Ȃ��A�傫�Ȑ�ʂ�������ɂ͂��܂�ɂ��������Ȃ������B
�@�Q�[���ł͌㔼�ɓo�ꂵ�A75mm��C�Ɠ����̎˒��E�Η͂������A�@���̖͂R����������C�̕⏕�A�������͎�͎����C�Ƃ��ĉ^�p���鎖�ɂȂ�B
�@�����ԐڍU���̂ł����C�ɔ�ׁA�h��͂��Ⴂ�A�e�������Ȃ��_�͑傫�ȃ}�C�i�X�v�f�����A���������O���֓��B�ł���ƌ����_�ł͖{�Ԃ̑��݈Ӌ`�͑傫���B
�@�h��͂ɖ�肪���邽�߁A����̗\�z����鋒�_�ɂ͑�����C���A�N����̗\�������n��ɂ͏����̖{�Ԃ��A�ƁA���܂��g��������̂����z���낤�B
�@�i����͎l�������C�z���ŁA75mm�����C��150mm�ւƉΗ͂��オ�邽�߁i�˒���4H�֏オ��j�A�o�ꎞ����R�c�R�c�b���A�i������͐ϋɓI�ɐi�������Ă��������B
|
 |
���l�������C�z���@�i�����֒e�C�j
�@�����Ȍ����֒e�C�����Ă��܂��C���ŁA����̗L�����p��͍����Ă�������{�鍑�R�ł́A�h�C�c�鍑�R�̕����C����{�Ƃ��ēƎ��̎����֒e�C���v�悵���B
�@�ԑ̂ɂ͋㎵������Ԃ̂��̎g���A���̂����Ɋۂ��ƌ����C�𓋍ڂ���悤�Ȍ`�ŊJ���͐i�݁A�J�������萔�����Ŏ��퓊���ƈٗ�̃X�s�[�h�Ŏ��p������Ă���B
�@�v���͏��K�͂̉��ǂ��������Ă����悤�ł��邪�A��{�I�ɑ�K�͂ȉ��ǂ͍s��ꂸ�A�h�q����Ƃ̂��ƂŖh�����������ƂȂ�A��e���\�͗ǂ��Ȃ������B
�@���ڂ��ꂽ150mm�C�̉Η͂͑傫���A�t�B���s���Ɏ����������ꂽ�ꕔ�̖{�Ԃ���r�I�����������A�����䐔�̏��Ȃ�����ŏI�I�ɗL�Ӌ`�Ȑ�Ђ�ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�@�\���I�ɑΐ�Ԑ���l������Ă����{�Ԃł͂��邪�A����𐬂����߂̐�������Ȃ���ɁA�C�����͎��͌x�����܂Ƃ��Ȏx������ꂸ�A��Ɍ������킢���������Ă����B
�@����{�鍑�R�Ƃ��Ăُ͈�ȑ���a�C�ł���A���������J���������A�܂Ƃ܂����䐔����������Ă���ΐ��ő劈��ł����ʂ��������ł��낤�ɁA���̓_���ɂ��܂��B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɂ��������邠����Ői���E���ǂ����ւ���A�ꎮ�C��ԃz�jI�^����̐i���A�O������ԃ`�k����̉��ǂœ��肪�\�ƂȂ�B�i�i���͂����ŏI���B�j
�@�˒���4�ƒZ����ɒe�������Ȃ����߁A�p�ɂȕ⋋���������鎖�ɂȂ邪�A150mm�C�̈З͂͂��܂������A�����֒e�C�Ƃ��Ă͂��Ȃ�̉Η͂��ւ�B
�@���R�ɂƂ��Ă͋߉q���A88mm��C�A������ԂɎ����܂Ƃ��Ȑ�͂ł���A��e�Ɏア��_����肭�t�H���[���ĉ^�p���Ă��������B
|
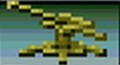 |
��75mm��C�@�i���������W����퍂�˖C�@�������˖C�j
�@����{�鍑�R�ŕW���I�Ɏg�p���ꂽ75mm���a�̑�C�ł���B
�@��{�I�Ȑv�͋��C�̏\�ꎮ�ɏK���Đv����Ă��邪�A�e���ɉ��ǂ��������A�����|�e���V������ێ����邱�ƂƂȂ����B
�@���ʁA�J�����ɂ͌����̂��Ƃ��l������Ē������y�ʉ�������Ă���A���ꂪ�����ő啝�ȑϋv�x�̒ቺ�������A�����ԁE�����̉^�p�Ŕj���E����̋��ꂪ�����������B
�@�{�C�͑����Ƃ����Ďg�p����A�e�n�̐��ŕK���Ƃ����Ă悢�قǔz���E�^�p����Ă���A���ɒፂ�x�ɑ��Ă̓G�@�ɑ��A�͋����C�𗁂т����B
�@�Q�[�����ł͑���{�鍑�ɂƂ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ�����̂ЂƂł���B
�@���ۂ͑ϋv�x�̒Ⴂ����ł��������A�h��̗͂D��������Ă���A�S�Ă̖h��͂�50�Ƃ����ٗl�Ȗh�䐫�\���ւ�B
�@�Η͓I�ɂ͂܂��܂��ŁA�Βn�U���ɂ����x�̒Ⴂ�i���x14�j�ΐ�ԖC�Ƃ��Ďg�����Ƃ��\���B
�@�i�����88mm��C�Ɗm���ɋ������s���A�Η͕s���̖����I�ȑ���{�鍑����̒��ł͋M�d�ȕ���ł���A��ɑ��߂ɃX�g�b�N�E�琬���Ă��������B
|
 |
��88mm��C�@�i��㎮���W���˖C�@�������˖C�j
�@����{�鍑�͑����m������J�킷��O�ɒ�������ł̐킢�Ńh�C�c�鍑�u�C�R�^�v��88mm��C���b�l���Ă����B
�@���̖C���e�X�g�����Ƃ�����肵�����\�E�����₷�����m�F�������߁A�܂��ꕔ���Y���ł̕��������݂��A���̕����̃e�X�g�ł��ǍD�Ȍ��ʂ�����ꂽ�����牼���������ꂽ�B
�@�����͐������̃h�C�c�鍑�N���b�v�Ђɖ��f�ŕ������s���Ă������A�O�������̐�����͌_��Ɋ�Â������C�Z���X�����x�����A�������ɓ��R�ɑg�ݍ��܂�Ă���B
�@�{�C�̓h�C�c�鍑���R�Ŏg���Ă����C�Ƃ͈قȂ������̂ŁASK C/30�Ƃ����C�R�d�l�ł��邽�߁A�������Ƃ����������{���Ƃł������ق����������B�i���ɂ����ƕt���Ȃ��B�j
�@����Č����ɂ͂�△��������������������̐ߖ�����˂Ă��Ȃ�̌y�ʂ��{���ꂽ���A����ł��������Ƃ��Ă͓����A���ǂ͍�������{�ݍ�Ƃ��قڕK�{�ł������B
�@�\���I�Ɍ����C�Ƃ͂������ꂽ�C���������A��x�W�J����ΈЗ͍͂����A�@�B�I�Ƀ����e�i���X�ɂ��L���ł��������߁A�{�i�I�ȍ��˖C�Ƃ��Ē��������B
�@�Q�[���ł�75mm��C�̐i�����瓾�鎖���o�������{�鍑�R�̎�͏d�Ί�ł���A�@���͈ȊO�̉ΉE�˒��E�h��͂̑S�ĂɗD��A���ɏd�v�Ȉʒu�ɑ����B
�@�����̉Ί�ɔ�ׂ�ΉΗ͎͂��邪�A����ɖh��͂̍����͓��ɏG�łĂ���A�{�C��v�ǁE�s�s�ȂǂɎ{�݂�����̃w�b�N�X�͓�U�s���ɋ߂���ԂƂȂ�B
�@�h�䐫�\���b�����ł��邽�߉ߐM�͋֕������A�Βn��ɖ��\�̐��\���ւ鎖����X�g�b�N�𑽂߂ɂ��A�d�v�ȋ��_�ɂ͐ϋɓI�ɍ����Đ�ǂ�D�ʂɐi�߂����B
|
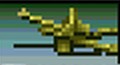 |
��75mm��C�@�i��Z����C�@�����֒e�C�j
�@�t�����X����C���Q�l�Ɍ������s���A�Z�p�W�����ĊJ�����ꂽ����{�鍑��75mm��C�ł���B
�@�O�g�̎O�����ɔ�ׁA���A���x�A������@���i�i�Ɍ��サ�A���S�ʂɂ킽��^�p���ꂽ�B
�@�{�C�̏d�ʂ͂���܂ł̖�C�����i�i�ɏd���A�ړ��ɂ͂�����x�̘J�͂��K�v�ł������悤�ł���B�i�Ƃ͌����Ă��قƂ�ǂ͎����ԉ�����Ă����悤�ł͂���B�j
�@���{�R�ł͑�����ԂɑR�ł���Ί킪���Ȃ��A��ɉΗ͕s�������ł��������A�{�C�͂��̐����Ȃ��d�Ί�̂ЂƂƂ��Ĕ��ɏd�ꂽ�B
�@�Q�[���ł̓R�X�g�͂��������A�Η͍͂T���߂ƈꌩ�Η͕s���̖�C�Ɍ����邪�A���̐^���͑ł��ꋭ���ɂ���B
�@���{�R�����C�͑S�ʓI�ɍT���߂ȉΗ͂ł��邪�A������̕�����h��͂��D������Ă���A�{�C�ɂ����Ă��e�h��͂͑�20�A�Βn�Ί�50�Ɣ��ɍ����Ȃ��Ă���B
�@����Ȑ�Ԃ�������ɂȂ�A�i�����105mm�A150mm�Ɗm���ɒi�K�I�������ł��邱�Ƃ���A75mm��C�ƃZ�b�g�ő��߂ɐ��Y���Ĉ�ĂĂ��������B
|
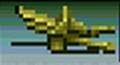 |
��105mm��C�@�i��ꎮ�\�W�֒e�C�@�����֒e�C�j
�@�����̑����i���V�s�̕��ɐ�ւ����钆�A��C�Ƃ�������ɂ����Ă������a�̕������a�̕��ɐ����コ���闬�ꂪ���܂�������B
�@������C��105mm�A122mm�Ȃ�3�P�^��̌��a�����̂���ʓI�ɂȂ�ƁA����{�鍑�R�ł����̗���ɒǐ����ׂ��A�{�C�̊J���E�z�����}�����B
�@�{�C�̓t�����X�A�V���i�C�_�[�Ђ̋��͂ɂ���ĊJ������Ă���A�����Ƃ��Ă͔ėp���̂����ʓI�E����Ȑv�ƂȂ��Ă���A���̎�����X���[�Y�ɍ̗p�ƂȂ����B
�@�ߋ��̖�C�������d�ʂ͑����Ă��܂������A�@�����ɕt���Ă͗ǂ��l���Ă܂Ƃ߂��Ă���A�^�p���̈ړ��A�����͑��̖C�����ނ���y�ł������ƌ����Ă���B
�@�����̓��N���X��C�̐��Y���ɂ͂��Ȃ�Ȃ����A�̗p��͍��Y��������Ă���A����Ȃ�̐������Y����Ă����B
�@�Q�[�����ł͉Η͂��������N���X��C�Ɠ����i���ł���A����{�鍑�R�̌����C�ƌ������Ŗh�䐫�\���D������Ă���B
�@75mm��C����̐i���ŏ����ɐ��\���������Ă���A�s�s�A�v�ǂɔz�u���������Ƃ����ΐ�ԖC�Ƃ��Ẳ^�p���\�Ƒ��ς�炸�g������͗ǂ��B
�@����A�����Y���ł��Ȃ����߁A�����Ȑݒu�őS�ł����Ȃ��悤�C���g���A�i�����150mm��C�ɂ��܂��Ȃ��Ă��������Ƃ��낾�B
|
 |
��150mm��C�@�i��Z���\�ܑW�֒e�C�@�����֒e�C�j
�@����{�鍑�R�ł͋�����������l�N���\�ܑW�֒e�C�̉��ǂ��s���Ă������A�������s�ɏI��������߁u�V�K�J���v�ɂ���Ė{�C�������������B
�@�{�C�ł͎l�N���\�ܑW�֒e�C�̎�_�ł������˒������̒Z���A�������ɕK�v�ȍ�Ƃ̔ώG�i���������Ȃǁj���A����n�ł̎g���ɂ����ȂǑ����̌��_����������Ă���B
�@�R�k����̕���ł���h������v��J�n����^�p�J�n�܂Œ������Ԃ��������Ă���A���̒������Ԃŗ���ɗ���ꂽ�v�͖{�C�̐��\��傫�������L�����B
�@���a�͑O�C�ƕς��͂Ȃ�����������ɂ������W���I�ȑ����i���{����A�܂��A�Z�p�I�ɂ��o�l����������ȍ\���A���ȋُk�@�ō�����C�Ȃǎ��ɋߑ�I�ł������B
�@����C���������ʂ֎������������Ƃ����ނː��������߂������琳�����E�ʎY���s��ꂽ���A�����ł����̖͂R�������o���̂����Y����450��ɓ͂��Ă��Ȃ��B
�@����{�鍑�R�ł͊ԈႢ�Ȃ��ʊi�̕���ŁA���S�ʁA�����ɂ͉����ɂ���������w�������ԐړI�ɓ|���ȂǑ����̊�����c�������A�^�p�ł͌b�܂�Ă��Ȃ�������������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͏��Ղ���105mm��C�̐i���Ŏ�ɓ���鎖���ł��A�˒���4�Ɨ}���C���ł�����̂̍U���͂͋ɂ߂č����A�������˖C�A�����Ɏ�����O�̎��͂ƌ����Ă悢�B
�@�h��͂͗�ɂ���ėD������Ă���A����ɑ�Η͂�����邽�ߌ������̎x���Η͂Ƃ��Ă͎��ɗ��z�I�ŁA�{�C�̉^�p�ɂ���Ă͐�ǂ�傫�����E����B
�@�����Y�ł��Ȃ����ߑS�ł��Ȃ��悤�C��t���ĉ^�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ϋɓI���I�m�ȉ^�p�ɂĐ퓬��D�ʂɐi�߂Ă��������Ƃ���ł���B
|
 |
��37mm�ΐ�ԖC�@�i��l���O�\�����C�F��l��37mm���˖C�@�����ΐ�ԖC�j
�@�x�ߎ��ρA�m�����n��������킢����������{�鍑�R�́A������ׂ������A���b�ԗ��ɂ���Đ킢���L���邱�Ƃ�\�����A����ɑ��邽�߂̕���J�������݂��B
�@�{�C�͂��̌��ʊJ�����ꂽ���̂ŁA�]������^�p���Ă�������܂ł̖C�ɔ�א�i�I�ň����₷���A�����ł̏����荇��������I��܂ŕ��L���g��ꂽ�C�ł���B
�@�C�g�̊W���珉���͂���قǍ����͖������̂́A���b�̔����\�r�G�g��ԁABT��ԂȂǂɑ��Ă͏\���ȉΗ͂������A���Ȃ�̊�����������B
�@�Z�p�I�ɒ��ڂł���_�������A�^�����l��������v�ȋ������ԗցA���ǂ��d�˂�ꂽ�Ə��@�A�l����ꂽ��ɒa�������L�x�Ȏ�ނ̖C�e�Ȃǂ͓��ɒ��ڂɒl���邾�낤�B
�@�������A���̐��\�͂����܂ł����O�̂��̂ŁA��평�����߂���ƉΗ͕s���͌����ƂȂ�A�ؚ��Ȏԑ̂���邽�߂Ƀg�[�`�J���Ŏg����Ȃlj^�p���@�͎���ɕω����Ă������B
�@�y�ʂň����₷���M�d�ȉΗ͂ł��鎖����e���ʂ։^���E�z�����ꌃ��ɓ�������Ă��������A�y�Ί���}�V���x�̖{�C��z�����ꂽ�����͗��_�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[���ł́u�ꉞ�v�o�ꂷ����̂́A�h��͂ɂ����Ă��Η͂ɂ����Ă���C�ɗ��Ƃ�����̂킩��Ȃ���ԂƂȂ��Ă���A�ǂ��_�̓R�X�g�����x���������B
�@��Q���̕�[�͑������̂́A������v�Z�ɓ���Ă����Y���郁���b�g�͖����ɓ������A���݈Ӌ`���甖�����낤�B�i�ꉞ�A���b�ԁA�y��Ԓ��x�Ȃ�Ό����ł��邪�B�j
�@�i�����47mm�ΐ�ԖC��������������\�͔����ł��邱�Ƃ���A����{�鍑�ł͖{���Y��A��C��ΐ�ԖC�Ƃ��ĉ^�p�����ق��������͗ǂ��Ȃ�B
|
 |
��47mm�ΐ�ԖC�@�i�ꎮ�@���l�\�����C�F�ꎮ�@���l�\�������˖C�@�����ΐ�ԖC�j
�@����{�鍑�R��37mm�ΐ�ԖC�͉Η͕s���ɔY�܂��ꂽ���̂̂�����x�̐��������߂Ă������A���̖��͂�͂�傫���A��苭�͂ȖC���K�v�ł���Ƃ̌��_���o�����B
�@���̓����Ƃ��ĊJ�����ꂽ�̂�47mm���a�����{�C�ł���A37mm�ΐ�ԖC�Ƌ��ɓ��R�̎�͑ΐ�ԖC�Ƃ��Đ����̗p����A��풆�����瑱�X�Ɛ����������Ă���B
�@�����I�ȕ����͐����Ɍ��Ď��A���ɓ��R�Ƃ��Ă͒������ԗ��������l������Ă������߁A�����i�^�C���A�T�X�y���V�����j����͖��炩�ɋ@���������l�����Ă��������f����B
�@�C���̂�47mm�Ə��������̂ł��������A�S�|�e�A�֒e�̑o�����^�p�\�ŁA�����ȃT�C�Y�͗D�ʂȐݒu�ꏊ��ɗL�p�ŁA�g�������Ă͈ӊO�ƈ����Ȃ������悤�ł���B
�@�����A�S�|�Ƃ̗�����{�鍑�ł͗ǎ��ȖC�e�����Y�ł����A�Η͂͑������N���X�̖C�ɋy�Ȃ��������߁A���ǁA���̃n���f�͌���̎��s������d�˂��^�p�ŃJ�o�[���ꂽ�B
�@���������X�Ƒ���a���C�g�C�ɑS�Ă��œK�����邳�Ȃ��A����������Ɏ��c����������{�C�����A�͋y���Ƃ��e�n�ɓ������ꌃ�����C�����s���������B
�@�Q�[���ł�37mm�ΐ�ԖC�Ɠ��l�̈ʒu�t���ł���u�ꉞ�v���݂��郌�x���ŁA37mm�ΐ�ԖC����̐i���Ŏ�ɓ���鎖���ł���B
�@�ŏI�i���̑ΐ�ԖC�ł��邪�A�{�C�������Ă��Ă�����Ƒ��b�ԁE�y��Ԃƌ݊p�������x�̉Η͂��������A���˖C�̑��݂��l������Ɖ^�p���鉿�l�͂قƂ�ǖ����B
�@���Ƃ��ď����z�u����Ă���Ȃ狒�_�h�q�ȂǂɎg���Ȃ����������A�킴�킴�{�C����ĂĂ܂Ŏ�ɓ���鉿�l�͂��邩�ƕ������A�ۂƓ����邵���������낤�B
|
|
������{�鍑�R�����@�i�����j
�@���{�R�����̓����Ƃ����A�O����I�ȋ��������i�ɒ������Ⴂ�@�B���E�����ԉ����ł��낤�B
�@��������{�͍��͂̊W��A���Y�ł��Ȃ����̂������A�����͑�������w�������X�g�b�N�i�Řd���A����ȊO�̂��͉̂��Ƃ��������Y���Ă���Ƃ����ł���B
�@���ʁA�����i�͕s���C���Ŏ����ԉ����͔��ɒႭ�A�@�B���͐�ԕ����ɕt���Y�������݂̂Ƃ����L�l�ł������B
�@���烌�x���͍����A�q���[�}�����\�[�X�I�ɂ͌b�܂�Ă������̂́A��L�̗��R���痈�鎩���ԉ��E�@�B���̒x��A�����Ȏ呕���i�͌R�̍s���������������B
�@�ꕔ�A��֕����Ȃǂ̕ς�����ړ���i�����������������������A�����̕����͎����̑̏d�Ɠ����x�̑����i�������ĕ����˂Ȃ炸�A�i�R�ɂ����Ղ͑傫�������B
�@�Q�[���ł͕����A�߉q���A�����ԉ����A�����P�������g�p���邱�ƂɂȂ�B�i��ɂȂ�̂͋߉q���j
�@���{�R�̕����A�߉q���͈ړ��͂ɗD��A�Ύi�ߕ��A�Δb�\�͂����ɍ����A�B�x�̍����������đΕ����퓬�ł͂��Ȃ�̋������ւ�B
�@����Ńp���c�@�[�t�@�E�X�g��o�Y�[�J�̂悤�ȑΐ�ԉΊ�������Ȃ����߁A�d�Ί�Ƃ��܂��g�ݍ��킹�ĉ^�p�������B
|
 |
���O���C�n�E���h�@�iM8�@���b�ԁj
�@�n�[�t�g���b�N��37mm�C�𓋍ڂ����ԗ����^�p���Ă����A�����J�R�ł́A�퓬�\�͂�����̖�肩�琳���ȑ��b�Ԃ̊J�����v�悵���B�i���X�͐퓬�C���ړI�j
�@�{�Ԃ̊J���̓t�H�[�h�Ђ��S�����A�{�ƂȂ�ł͂̃m�E�n�E���������ꂽ���߂��A���^��C�����ɂ��ւ�炸���n�Ȃ��90km/h�O��̑��x�ő��s���\�ł���B
�@����A�s���n�ł̑��s���x��40km/h���������x�Ɗe�����b�Ԃ̕��ς����������̂ł��邪�A���n�ł̍����@�����������Đ����̗p���ꂽ�B
�@�ԗւ͘Z�ցA�Z��Ƃ�����{���\�������A�����đO�q�̓���������A����܂ő��b�ԂɌ����������Ȃ������A�����J�R�ɂ����Ă����ڂ���A8,000����鐶�Y�䐔���ւ�B
�@�o�ꎞ�ɂ͊��ɐ�Ԃ̏d���b�����i�݁A���ڂ��ꂽ37mm�C�͊��҂��ꂽ�Η͂Ƃ��Ă͒��������̂ƂȂ������A��@�A�ˌ�C�������Ȃ����Ȃ��A�m���Ȑi�R�ɍv�������B
�@�����e�i���X�A�^�p�������ɍ����A�������߂Ƃ��đ�������炭�͐��������ɂĕ��L���g��ꂽ�B
�@�Q�[���ł͎j�����l�ɂقڒ�@��p�Ƃ��ď��Ղ��瑦���Y���\���B
�@�i���A���ǂ������A���S�Ȏg���̂Ĉ����ɂȂ邪�A��Η͂������߁A�q�j�b�g�̌����ɂ��g���A���ړ���8�Ƃ������������������n���G���\�ł���B
�@�g������͍����A���x�ɂ���Ă͑���{�鍑�R�̃`�n���x�Ȃ�Ό��ނł���Η͂ɉ����A�R�X�g�����Ɉ������߁A����ɂ���Ă͐ϋɓI�ɍ��G�^�p���Ă��������B
|
 |
���X�`���A�[�g�@�iM3�@�y��ԁ@���X�`���A�[�g�̓C�M���X���j
�@�^�p�ʂŗD�ꂽ���\�������Ă����O����̌y��ԁAM2�y��Ԃ̗ǂ��ʂ��c���A��_�����̑���{���A���������ꂽ�̂��{�Ԃł���B�i�A�b�v�f�[�g�̈Ӗ��������j
�@�{�Ԃ͐��Y���ł���A�����J�����߂Ƃ��A�C�M���X�A�����ȂǘA���R�ŕ��L���g���A�n���ł͂��邪��@��ΐl�C���Ȃnjy��ԂƂ��Ă̐Ӗ��𒉎��ɑS�������B
�@�A�b�v�f�[�g�ɔ����AM2�y��Ԃɂčő�̎�_�ƌ���ꂽ���b�͂��Ȃ苭������Ă���A���{�R�̌y��Ԃł͂Ȃ��Ȃ��ђʂ�������x���̑��b�������Ă���B
�@�܂��A�@�e�A��C�͓��ɑ傫�ȕύX�͖������̂́iM2�y��Ԕ�j�A���X50���a37mm�C�Ƃ����y��ԂƂ��Ă͕W���ȏ�̉Η͂������Ă������߁A����͖��Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
�@�������A�y��Ԃ͂����܂Ōy��Ԃł���A��Ԑ킪�d�v�ł��������B����ł͐�͂Ƃ��Đ������鐫�\�ł͂Ȃ��A���Y���ɔ�r���Ċ���̏�͔��ɏ��Ȃ��B
�@�B��A�劈���̂��Α���{�鍑�R��ŁA������̐���ł͒ʏ�퓬�����邱�ƂȂ���A����{�鍑�R���b�l���ꂽ�{�Ԃ����킷���b�ȂǁA�ς����������o�Ă���B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��琶�Y���\�ł���A�����A�ړ��͂��L���A���G�͈͂��L���A�ƒ�@�C���ɍœK�ȕ���Ƃ��đ��݂���B
�@�܂��A�Α���{�鍑����ł͑ΐ�ԉΗ͂Ƃ��Ă��\���ʗp���鐫�\�Łi���x�͕K�v�����j�A����ɂ���Ă͍��G�A�ΐ�Ԑ�Ɗ���̕��͍L���邾�낤�B
�@�t�ɉ��B����ł͎�C���̒�@���C�����鎖�ɂȂ邪�A��Η͂����邽�߁A���܂��^�p���ēG�q��@�̌����Ȃǂɂ����p�������Ƃ��낾�B
�@�i���̓}�C�i�[�o�[�W�����A�b�v���`���[�t�B�[�ƂȂ�A�h��Ȑi���͖������A�n���Ȕ\�͏㏸�����҂ł���B
|
 |
���`���[�t�B�[�@�iM24�@�y��ԁj
�@��킪�i�ނɂ�ăA�����J�R��������P�͖c��Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A���ɖk�A�t���J�œ�����P�͋ɂ߂ċM�d�Ȃ��̂ł������B
�@�������l���������ʁA�����I�Ɍy��Ԃɂ����Ă���ΉE�����h��́E���ړI�Ɏg����Ƃ������Ƃ��d�v�ɂȂ�ł��낤�Ƃ̗\�������Ă��A��������{�Ԃ͒a�������B
�@��b�I�ȃR���|�[�l���g�͊����̐�Ԃ�M3�y��ԂȂǂ��痬�p����Ă��邪�A�V�Z�p�̓����ɉ����X�Α��b����������A�y��ԂƂ��Ă͍������\�������Ă���B
�@��C�ɂ�75mm�C�����ڂ���A�O�q�̂悤�ɌX�Α��b�̗̍p�������čU��̃o�����X�͗D�ꂽ���̂ł��������A���F�͌y��ԂƂ������Ƃőΐ�Ԑ퓬�ɂ͌��E���������B
�@���B����ł͂�����x�̊�����������݊������������̂́A�����ȂƂ�����ł̊�������A���̒��N�푈�ւ̓����⎩�q���֔z�����ꂽ���̕����L����������Ȃ��B
�@�{�Ԃ͉^�p���ȂǂɗD��A��r�I��y�Ɉ����邱�Ƃ��瓱�������e���ł͐������ɒ������ԉ^�p����Ă���A�^�p�J�n����40�N�O�㌻���ł����������������Ƃ����B
�@�Q�[�����ł͏I�ՂɃX�`���A�[�gV����̐i���A�ꕔ�}�b�v�̑����Y�Ŏ�ɓ���A�����Ȑ�Ԃɂ͂��Ȃ�Ȃ����̂̌y��ԂƂ͎v���Ȃ��퓬�͂����B
�@�������\������\�̗��������̑����V���[�}������ԂƂ��������ŁA����{�鍑�R��Ԃ�����Ȃ�Ȃ�Ƃ��݊p���x�Ő킦�邪�A�y��Ԃł��邽�߉ߓx�Ȋ��҂͂ł��Ȃ��B
�@�ŏI�i���^�Ƃ������ƂŎg������͔��ɗD��A��@�A�y���퓬�C���Ȃ�Ώ\�����Ȃ��鐫�\�ł��邱�Ƃ���A2�A3�����茳�ɂ���Δ��ɏd�邾�낤�B
|
 |
��M3�@���[�@�i����ԁj
�@���u����A�h�C�c�鍑�R��Ԃ̐�i�����_�Ԍ����A�����J�ł́A�����̎�͂ł���M2��Ԃł͋�����������ƍl���A����a�C������Ԃ̊J���������ꂽ�B
�@���̌��ʂƂ���75mm�C������Ԃ̓��������肵�A�{�Ԃ̗̍p�����肳�ꂽ�B
�@�{�Ԃ͓����̋Z�p�I�Ȗ�肩�����75mm�C���̓��ڂ��������A����37mm�C�ƌ������75mm�C��g�ݍ��킹�����C����ԂƂȂ��Ă���B
�@��]�C�����̗p���ꂸ���������ꂽ�w�i�ɂ́u���}�ɐ��֑�Η͂̑����𑗂�˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������}�ꂵ�̂��I�ȗ��R������A���܂莞�Ԃ��Ȃ������Ƃ��������傫���B
�@�֒e�̎g�p���\�ł���A�o�ꓖ���Ƃ��Ă͉Η͂̂���75mm�C���A�w�̍�������ǍD�Ȏ��E����Ƃ������ƂŁA�g������u�����v�͗ǂ������悤�ł���B
�@����ł��̌`����ڗ����Ƃ������A�܂��A���b������قǂ̌������Ȃ��������߁A���ɉ��B���ʂł̔�Q�͔��ɑ傫�������B
�@����75mm�C���̗̍p���ꂽM4��Ԃ����������ꂽ��͏��X�ɌP���p�A�x���ԓ]�p�A�������Γ���֓�������A�t�F�[�h�A�E�g���Ă���B
�@�Q�[���ł͔�r�I�������琶�Y���\�ŁA75mm�C�̑Α��b�U����60�A���x18�̂������œG�������C�g�C�𓋍ڂ�����Ԃ��o���Ă���܂ł͗D�ʂȗ����ʒu�ƂȂ�B
�@�������A�ړ������O��A��e���̎コ�A75mm�C�e��5�Ɛ퓬�p���\�͂͒Ⴍ�AM10�쒀��ԁAM4��Ԃ����������ꂽ���M12�ȂǑ�����֓]�p����̂��D�܂������낤�B
|
 |
��M4�@�V���[�}���@�i����ԁj
�@�A�����J���\����ėp����Ԃł���A50,000��O��Ƃ����c��Ȑ��Y�����������A�A�����J�݂̂Ȃ炸�A���R�e���E�ԌR�ł��g��ꂽ��Ԃł���B
�@�{�Ԃ͂������Ė}�f�Ȑ��\�ł͂��邪�A���̐��Y���̍����A�ėp���̍������琔�����̈���A���ǎ킪�a�����A�A���R�̎�͐�Ԃƌ����Ă悢�B
�@���\�����܂����ł��锽�ʁA��C�Ȃǂ����ǂ��ꂽA2�n�A���b�𑝂₵���W�����{�n�A105mm�֒e�C��������Η͎x���n�Ȃǂ��a�����Ă���A��p���ɂ͔��Ɍb�܂�Ă����B
�@�����I�A�����I�Ȉ��͂���A�����J�R�ł�75�`76mm�C���g���Ă������A�C�M���X�Ȃǂł�17�|���h�C��p�����t�@�C�A�t���C�Ȃǂ��펞���ɒa�����Ă���B
�@���[���b�p����ł͐��\�I�D�ʂɗ��h�C�c�鍑�R��Ԃɑ���p�Ɛ��őΉ����A�����m����ł͓��{�R�̐�Ԃ�ɖz�������B
�@���ɂ����Ă����L�����E���ʼn^�p����A�W�听�ƌ�����M4A3E8�i�C�[�W�[�G�C�g�j�́A���A�h�q�͂̌��@�������q���ł��ꎞ���g��ꂽ��ł���B
�@�Q�[�����ł́A75mm�W���C���̗p�����^�i�V���[�}��IV�Ȃǁj�ł̓h�C�c�̓��N���X�AIV�����F�^�ȍ~�ɑł������A���nj^�̒��C�g�^�ł���ƌ݊p�ɐ킦�鐫�\�ɂȂ�B
�@����ł��p���^�[�A�e�B�[�K�[�ɂ͂܂������R�ł����A�S�ʂɂ킽���ĉΗ͂̐��\����͊��҂ł��Ȃ����߁A�������Y�R�X�g�����������낦�Đ키���ƂɂȂ邾�낤�B
�@�܂��A���B����ł͐��\�s���ɂȂ�{�Ԃ��A�����m����ł͈��肵�����������邽�߁A����ɍ��킹���^�p�����ꏏ�ɍl���Ă����ׂ��ł���B
|

coffee break |
|
�`�퓬�ɏ��Ă镺��Ɛ푈�ɏ��Ă镺��`
�@�����̎�v�ȎQ�퍑�ł���A�����J�A�\�r�G�g�A�C�M���X�A�h�C�c�鍑�A����{�鍑�A�C�^���A�͍H�Ɨ͂�u���ꂽ�A���͂̈Ⴂ���畺��E�����i�ɑ���l�������傫���Ⴂ�A���ꂼ��Ɠ��̐F�����������Ă����B�����ł͂�����l����̂ɃA�����J�A�h�C�c�鍑�����グ�Ă݂����Ǝv���B
�@�h�C�c�鍑�͍��́A�����̖�肩��u�����ł�����x�̋K�́v�̌R�����\�z�������߁A��ɕi���̍�������E�����i�����߂��B����͌�̃e�B�[�K�[�A�W�F�b�g�퓬�@�A�p���c�@�[�t�@�E�X�g�ȂǍ����\����̓o��ɂȂ���A��R�X�g���������Ă��u�ő̗̂D�ʐ��v���d�����Ă����ƍl������B�m���Ƀh�C�c�鍑�R�̏d��Ԃ�W�F�b�g�퓬�@�͋����������A�������悭�P���i�P���ƌ������`������݂����Ȃ��̂����j����Ă����B�܂�A���K�͂̌R�Ȃ�u�퓬�ɏ��Ă�v�����i�ł͂������B����A�A�����J�����߂����̂͋t�������B���́A�H�Ɨ͂��������ăR�X�g�ʂŗL���ȕ�����ʐ��Y���A���ʂʼn�������ƌ����l���ŁA���\���}�f�ȕ���ł����X�܂ő����i���s���͂��悤�ȍ\�z�𗧂Ă��B�V���[�}������Ԃ̓h�C�c�鍑�R�̐�Ԃɔ�ׂĔ�͂����A�����̂�������ґ�ōL���ƈꌏ����5���h���O��Ő��Y���o���邵�A���̖��@�}�X�^���O�ł���5��5��h�����x�i�������Ȑ�ԂƂقړ����̒l�i�j�ō���Ă��܂��B������ꎞ�I�ɐ퓬�ŕ����Ă������玟�ւƐ��Y�⋋����u�푈�ɏ��Ă�v�Ɏ����Ă��������ł����B�|�����l����Ɓu�퓬�ɏ��Ă镺��v�Ɓu�푈�ɏ��Ă镺��v�͂܂������ʂ̂��̂Ȃ̂��낤�Ǝv���B
�@�푈�̏��������͕���̐������Ō��܂�悤�ȒP���Ȏ��ł͂Ȃ����A����Ȗʂ�������s�̌������l������̂͑���E���Ȃ�ł͂łȂ����낤���B
|
 |
��M26�@�p�[�V���O�@�i�d��ԁj
�@���B���ʂ̐���Ńe�B�[�K�[�A�p���^�[�ɑ��������A�����J�R��M4��Ԃ̐��\�s����Ɋ����AM4�ɕς���͂����߂��B
�@���̌��ʂƂ��ēo�ꂵ���̂��{�Ԃł���B
�@�{�Ԃ͗����̗������I�E���ƓI�ȖW�Q������A�Ȃ��Ȃ��{�i�������ꂸ�A���̊ԃA�����J�R�͔\�͂̒ႢM4�Ńh�C�c�鍑�̗D�G�Ȑ�ԂƐ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@���̊Ԃ̃A�����J�R�͔��Ɍ���������ɂ�����A�e�B�[�K�[�A�p���^�[�̓������ꂽ�퓬�ł͑��Q���傫�������B
�@�d��ԂƂ������ƂʼnΉE���b�͐\�����Ȃ��������A��͂�e�B�[�K�[�n��ԁAJS�n��ԓ��l�A�^���\�͂͒Ⴂ�B
�@�Η͏\����90mm�C�A�����ȏd���b�������A���������ēo�ꂵ�����̂́A���̎����͐�̗��R��������ɒx���A������x�̐�ʂ��������Ƃ���ŏI����}�����B
�@�Q�[���ł̓o����j���ǂ�����ɒx���A�قڏI�Ղœo�ꂷ��B
�@�������A�B�x�̍���M4�n��Ԃɔ�ׂĂ��퓬�\�͂͊i�i�ɏ�ł���A�{�Ԃ��o�ꂵ���Ȃ��M4�n��ԑS�Ă�{�Ԃֈڍs���Ă��ǂ����炢�ł���B
�@����͒x�����A�����Y�\�Ƃ��������ŃR�X�g������قǂ�����Ȃ����߁A��ʔz�����邱�Ƃ��������߂���B
|
|
��T-95�@�iT28�@�d��ԁj
�@�h�C�c�鍑�R���\�z�����W�[�N�t���[�g���C���A�����Ē��d��ԂɑR���邽�߂Ɍv�悳��A���ۂɎ���ԗ���2��قǍ��ꂽ�d��ԁi�������͋쒀��ԁj�ɑ�����ԗ��ł���B
�@�Ō����Ŗ�300mm�Ƃ����ɂ߂Č������b���{���ꂽ��A��C�ɂ͍����ђʗ͂��ւ�105mm�C�����ڂ���Ă���A�d��ԂƌĂԂɑ��������퓬�͂�^�����Ă����B
�@���ʁA�d���b�ɑ傫�Ȏ�C�͏d�ʉߑ��������čŏI�I�ɂ͎��d85�g�����Ă��܂��A���ڂ���Ă���M26�Ɠ����G���W���ł͏o�͂��܂��������肸�A�@���͂͗ł������B
�@�����₢�낢��Ȏʐ^�Ŋm�F�ł���悤�ɃL���^�s���͍��E1�{���ł͑��肸�A���E2�{���ƒ������`��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�����ɖ{�Ԃ̋@�����ɖ�肪�����������f����B
�@���ǂ̂Ƃ���A�퓬�݂͂̂����������������߂Ƀg�[�^���ł̃o�����X���������A���p�ɑς��Ȃ��ԗ��ɂȂ��Ă��܂������Ƃ���A�����A���s��ƌ����Ă悢�B�i������1��͎��̔j���j
�@�퓬�͖͂��͓I���������A���͘A���R�L���A�U���ɓݑ��Ȑ�Ԃ͕s�v�Ȃ��ߗʎY���Ȃ��ꂸ�A�����ׁX�ƌ����͑��������ŏI�I�Ɏ���ԗ�2��݂̂Ōv��̓L�����Z�����ꂽ�B
�@�Q�[���ł͖�����M26�p�[�V���O����i�����\�ƂȂ�A�d��Ԃɂ�������炸�ړ��͂�5�A�Η�135�E���x26�i�S��Ԃōō������x�j�ƃA�����J�R�ŋ��̐�ԂƂ��ēo�ꂷ��B
�@�j���̐��\�Ƃ͈قȂ钴����Ƃ��ēo�ꂷ�邽�߁A�S�Ă̔\�͂��o�����X�ǂ��ݒ肳��Ă���A���x�������ȏ�Ȃ�\�r�G�g�R�A�h�C�c�鍑�R��Ԃ����قǖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�����d��Ԉȏ�ɓo�ꂪ�x���A�قڍŏI�}�b�v�ł�������ł��Ȃ��_�͐ɂ������A�o����Ȃ�ΐ���S�Ă̐�Ԃ�{�Ԃɂ��A�S�̂悤�Ȗ��G��ԌR�c������Ă݂Ăق����B
|
 |
��M10 GMC�@�i�쒀��ԁ@���C�M���X���E�����@�����j
�@�����̃A�����J�R�ł͖{�i�I�ȋ쒀��Ԃ��������A�n�[�t�g���b�N�ɑΐ�ԖC�𓋍ڂ��������̎ԑ̂Ő퓬���s���Ă������A���R�Ȃ���퓬�͕s�����w�E���ꂽ�B
�@�����Ŋ���̎���Ԃ�����A���̒���M4��Ԃ̎ԑ̂�p���A���\�I�Ɋ��Ƃ܂Ƃ��ł������{�Ԃ��쒀��ԂƂ��Đ����̗p�����Ɏ���B
�@�{�Ԃ͍����@���͂�p�����i�R�\�͂����A����E�҂������ɂ���P��@����������A�����d���̂��ߒlj����b�͎{����Ă��炸�A�ނ��댳�������b�������Ă���B
�@�܂��A�퓬���̓I�[�v���g�b�v�ƂȂ��Ă���A�ォ��̍U���Ɋ낤���A����ɊO�C�ɂ��炳��邱�Ƃ��獻���E���o�E���Ȃǂɂ��炳��A���������͕]�����悭�Ȃ������B
�@�h�C�c�鍑�R��Ԃɑ��ĉΗ͕͂s���C���ł��������A����ɂ͎�C�ɂ�����镔�������ǂ���A���i���ȖC�e�iHVAP���j��p����悤�ɂȂ�Ɛ퓬�\�͂͊i�i�Ɍ��サ���B
�@�Q�[�����ł͓�����M4�V���[�}�����Η�60�E���x18�ƃh�C�c�RIV����Ԃɋ�킷��\�͂Ȃ̂ɑ��A�{�Ԃ͉Η�75�E���x20�ƌ݊p�̐킢�����邱�Ƃ��\���B
�@�h�䐫�\�͂�͂�Ⴂ���i��h��Ɏ����Ă�0�j�AM4��Ԃ�����ǂœ��邱�Ƃ���r�I�ȒP�ł���A�R�X�g���ő����Y���\�ɂȂ邽�ߔ�Q���C�ɂ����g���Ă�����B
�@�A�����J�R��Ԃ̖{����M26�p�[�V���O�ƂȂ邪�A����܂ł̒���Ԃ͐��\��������������ŁA�p�[�V���O�܂ł̌q���Ƃ��čl����Ȃ�Ζ{�Ԃ���͂Ƃ��Ă��ǂ��Ǝv����B
�@�i����̓w���L���b�g��M36(B1)�ŁA�w���L���b�g�Ŗh��͎�̉��AM36��90mm�C�����ƂȂ邪�A�������Ƀp�[�V���O���T���Ă���A�i�����Ă�����͒Z���ԂɂȂ邾�낤�B
|
 |
��M18 �w���L���b�g�@�iM18 GMC�@�쒀��ԁj
�@M10�쒀��ԂƂ͕ʂɐV�K�ԗ��Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ŁA�������C����ł͂Ȃ��A�@���͂������y���Ȑ퓬�W�J�E�����^�p��ړI�Ƃ����쒀��Ԃł���B
�@����܂ł�M4����Ԃ���h�����������̃A�����J�R����Ƃ͈�����悵�A�����ɔ�ԍ��͒Ⴍ�A�����e�i���X���ɗD��S�̓I�ɃX�����ŊO�ϓI�ɐ������ꂽ���̂ƂȂ��Ă���B
�@��e��z�肵�Ȃ��@�����d���̉^�p�v�z����d�ʂ͗}�����iM4���10t�ȏ���y�ʉ����ꂽ�j�A����ɂ���ē����y���ȋ@�����ɂ�葬�x��80km/h������قǂł������ƌ����B
�@��C�ɂ�76.2mm�C���̗p����Ă������A�{���̔C���ł���쒀�ړI�ł͂��̖C�͖��炩�ɉΗ͕s���ł���A�e�B�[�K�[�A�p���^�[�Ȃǃh�C�c�鍑�R��Ԃɂ͕s���ł������B
�@����֓��������ƁA�����ł͏d�ʌ��ɂ�鑕�b�̔������w�ƂȂ��Q�͑傫���������A�_���I�Ȃ�����u�q�b�g�G���h�����v��p�����^�p�Ő��X�̌����킢�������B
�@���b�̐Ƃ��䂦�ɗǂ��C���[�W�̂Ȃ��ԗ��ł͂��邪�A�y���������ĕK�v�ȏꏊ�֑����ɑ���ꂽ�{�Ԃ̕����͌��n�����ɂƂ��Ă͐S���������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�Q�[�����ł͒��Չ߂���M10 GMC����̐i���E���@�����ł̑����Y�ʼn^�p���鎖���ł��邪�A�͂����茾���Βᐫ�\�̎ԗ��ł���B�i�|�S�ł͐i���̊W�ő��݊����̔����j
�@��C�͂�����x�̉Η͂����邽�߂���Ȃ�̐퓬�͂ł͂���̂����A�j���̂悤�ȋ@���͗D���͂Ȃ��A���܂�̑��b�̕n�コ����N�����^�p���S�O���郌�x���ł��낤�B
�@�i�����90mm�C������M36�n�Ɍq���邪�A�������ɑ����Y�o���镺��E�R�X�g���l����Ɩ{�Ԃ̉^�p�Ӌ`�͂قƂ�ǂȂ��A�v���[���[�ɂ���Ă͎g�����Ƃ͖�����������Ȃ��B
|
 |
��M36�@�W���N�\���@�i�쒀��ԁj
�@M10�쒀��Ԃ͐�͂Ƃ��Ă͊m���ɗL���Ȃ��̂ł��������A���̎�C�̓h�C�c�鍑�R�̃p���^�[�A�e�B�[�K�[�ɑ��ėL���ȉΗ͂Ƃ͌������A�Η͂̑������]�܂ꂽ�B
�@�t�����X�ւ̏㗤���T�����A�����J�R�́A���̗v�]���d�v�����A90mm�C�𓋍ڂ����ԗ��̊J���ɒ���A���̌�̑I�l�E�^�p�����ɂ���đ��������ɖ{�Ԃ��̗p����Ă���B
�@�ԑ̂͏]����M10�̂��̂Ƃقړ����ŁA���X�̉��ǂ��{����Ă͂��邪�A���b�A�\�͂ɂ����Ă͖w�Ǖς�炸�A���ς�炸�h�䐫�\�Ɋւ��Ă͒���Ԓ��x�̔\�͂ł���B
�@�������A��C�͐�ɏq�ׂ��Ƃ��苭�͂Ȃ��̂ɂȂ��Ă���A���̎�C��90mm���˖C�����ɑΐ�ԖC�Ƃ��č��ꂽ���̂ŁA��ϋ��͂Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B
�@����90mm�C�́A�]����75�`76mm�C�Ŏ��������Ȃ������p���^�[�A�e�B�[�K�[�𐳖ʂ���ђʂł��A�������ˌ���싅�ɂ��Ƃ��A�X���b�K�[�Ƃ��Ă��قǂł������B
�@�h�䐫�\�̒Ⴓ�A�Ԃɍ��킹�I�ȈӖ������̋����v�̈��Ղ�����]���̕������ԗ��ł��邪�A�d�v�Ȏ������x�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�Q�[�����ł͒��Ձ`�I�Ղɍ����|���鎞���ɐi���E�����Y���\�ƂȂ�A�n�Βn�ɂ���Ԑ�ŋ�����������A�����J�ɂƂ��āA�d�v�ȉΗ͂ƂȂ�B
�@��C�̈З͂̓e�B�[�K�[���݂ƂȂ��Ă���A���x��22�Ə\���Ȃ��̂ŁA�{���̃p�[�V���O�o��܂�76mm�C��������ԂƓ��l�ɏd�v�Ȉʒu���߂鎖�ɂȂ邾�낤�B
�@�i����͎����I�ȉ��ǂŁAM36B1�i�ԑ̂��ς�����j�Ǝ�h�䐫�\�ɍ����o����x�ƂȂ��Ă��邪�A������Ƀp�[�V���O���T���Ă��邽�߁A�g�������邩�͔������Ǝv����B
|
 |
��M15 GMC�@�i��ԗ��j
�@��ꂩ��A�z���ς݂�M13�EM14�ł͉Η͕s���Ƃ̎w�E���オ��A���̎w�E�ɑΉ����邽�߁A��ɉΗ͂̑�����ړI�Ƃ��Ė{�Ԃ��a�������B
�@�Η͂Ɋւ��ẮA�����킪12.7mm�@�֏e2��ł������̂ɑ��A�{�Ԃ͂����37mm�@�֖C��lj����鎖�ʼnΗ͕s����₢�A�o�����X�悭�Η͂��グ�鎖�ɐ������Ă���B
�@�܂��A����܂ł̃A�����J�R���C���l�A�ԑ̂ɂ̓n�[�t�g���b�N���̗p����Ă��邪�A�����������ɏK���ē����悤��M3�n�[�t�g���b�N���̗p���ꂽ�B
�@�����m�̂Ƃ���A�A�����J�R�̋�R�́E����\�͂̍����͂���߂ċ���ł���A�h�q��ł��{�Ԃ̐ϋɓI���p�͂��܂葽���Ȃ������悤���B
�@����A�{���̔C���Ƃ͊O��Ă��܂����A�ΐl�E�y�퓬�C�������������Ȃ��Ă���A���̎������Ԃ̏o�Ă��Ȃ��퓬�ł͑���Ȍ��ʂ̂��鑶�݂ł��������Ƃ��f����B
�@�����I�ȉΗ͂Ƃ��Ă͔��ɍ����A�������̓_�����ڂ���A���N�푈�ɓ������ꂽ�莩�q���ł��^�p���ꂽ�B�i���q���ޖ��͕����ɓ����Ă���ŁA�����ȕ���ł������B�j
�@�Q�[���ł͒��Ղɍ����|���鍠�ɑ����Y���\�ƂȂ�A���̉Η͂����đ�퓬�����łȂ��A�y���Βn�퓬�����Ȃ��Ă��܂��s�v�c�ȕ���ƂȂ��Ă���B
�@���x��12�Ǝ��߂ł͂��邪�A37mm�@�֖C�̈З͂͂����܂����i�Α��b�U���͂�70�j�A���܂��҂���������Ȃǐ�p����ł͒���ԑ���̑Βn�퓬���s�������\���B
�@�i����̓~�[�g�`���b�p�[����M16 GMC�i�Βn���\�ቺ�j��M19 GMC�i�ĂёΒn���\����j�Ƒ\�̌���͊m���Ȏ�����A�m���Ɉ�ĂĂ��������B
|
 |
��M16 GMC�@�i��ԗ��j
�@37mm�@�֖C�𓋍ڂ���M15�ɑ��A�������4�A��12.7mm�@�֖C�𓋍ڂ����Ă���AM15�Ǝ�قȂ�R���Z�v�g�̑��C�ł���B
�@M13�̎�_�ł���Η͂��l����ƁA���ꂼ��AM15�͋��͂ȋ@�֖C��1�lj�����悢�AM16�͋@�֖C��P���ɑ��₹�悢�A����ȉ�������̗p�����ƍl�@�ł��邾�낤�B
�@������̎ԑ̂�M15�Ɠ�����M3�n�[�t�g���b�N���̗p����Ă���A��r�I�����Ȃ���ŁA�n���Ȃ�����Βn�E��퓬�Ɋ����B
�@���[���b�p���ʂł̐퓬�ł͑�C�Ƃ��Ďg��������ΐl�E�Βn�C���ɕt�����������A�Z���Ԃŋ��낵���قǂ̐��̒e�ۂ��h�C�c�鍑�R�ɗ��т����B�i����2000���ȏ�j
�@�܂��A�L���ȃG�s�\�[�h�Ƃ��Ă͑���̒��N�푈�ւ̓����ŁA������ł��������璩�N�����֔h�����ꂽ�������ɑ��A�J�̂悤�Ȓe�ۂ𗁂т��������L���ł���B
�@���ꂩ��̂��Ƃ���ΐl�퓬�ł͌v��m��Ȃ��E���\�͂������A�~�[�g�`���b�p�[�ƟӖ����t���܂łɂȂ������A�˒��̒Z������M15���������ɑޖ����Ă���B
�@�Q�[�����ł�M15�o�ꂩ���̌o�߂ł����i���E�����Y�ł���悤�ɂȂ�A���ς�炸���b�͔������̂́A�����Ŕ�r�I�����n��\�͂������Ă���B
�@M15�̂悤�ȑΑ��b�Η͖͂������A�Δb�̍U���͂͋��낵���قǍ����A�j���ǂ���u�~�[�g�`���b�p�[�v�Ƃ��ĉ^�p���鎖���\���B�i�������A���b�̖��Ŕ�Q�͏o��B�j
�@�ǂ���C�̏����͏\���������Ă��邽�߁A�ϋɓI�Ȑ퓬�ŗ��x�E�o���l�߂Ă����A���̐i����ł���M19�ɂȂ��Ă��������B
|
 |
��M19 GMC�@�i���ԁj
�@���B���ʂł̐�P����M15�AM16 �Ȃǂ̑�ԗ������A�n��퓬�ɂ����ē��Ă����A�����J�R�ł��������A�A�Ԏ킪�����邱�Ƃɂ���ăR�X�g�ʂł̕s�����������B
�@��������P���邽�ߎԑ̂�T�����Ƃ���A�ʎY���ꂽM24�y��ԃ`���[�t�B�[�ɒ��ڂ��W�܂�A���̎ԗ��𗬗p���邱�Ƃō����\���E�R�X�g�J�b�g���v�悳��A�{�Ԃ̊J���ɂȂ������B
�@�����͉��nj^�A���{�t�H�[�X40mm�@�֖C�A�㕔�̓I�[�v���g�b�v�����̗p����Ă���A�����������퓬��������ԗ���͍����钆�ł��x�ꂽ�v�ł͂���B
�@�I��߂��ɗʎY�ɓ���A������x�̐��Y�E�ʎY���v�悳��Ă������A�I�킪�K�ꂽ���_�Ŏc��̓L�����Z���ƂȂ�A�����Y����280���ƋL�^�Ɏc����Ă���B
�@���ɂ����Ă͂قƂ�NJ���̏�͖����A��̒��N�푈�A��팠����������i���D���ꂽ�H�j���{�̎��q���ɂ����ĉ^�p����A�������Ԍ����Ƃ��Ĕz�����ꑱ�����B
�@40mm�C�͋ɂ߂č����\�ł��������A�ԑ̂͏������A�ڎ��ɂ��Ə��A�g���N���I�[�v���g�b�v�Ƃ����X�̌��_�́A���P�Ƃ���M42�_�X�^�[�Ȃnj�p�@��ʼn��P����Ă������ƂɂȂ�B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɓo�ꂵ�A�A�����J�R���Ԃ̍ŏI�`�ԂƂ���M16 GMC����̐i���A�ꕔ�}�b�v�ł̑����Y�Ŏ�ɓ��邪�A�e����4�Ɛ퓬�p���͂ɂ͂���镔��������B
�@����Ɍ��������ΉE�h��͂��������킹�A�����������Ƒ��ԂƂ��ė��z�I�Ȏԗ��ł͂��邪�A�A�����J�R�ł�90mm�������˖C�A�퓬�@���D�G�ł��邽�ߑ��݊��͔����B
�@�����A�R�X�g���\��ł͂��Ȃ�D��Ă��邽�߁A�k�d���́A���X�L�[�g�Ȃǖ��ȍ����E�����\�@���}���E�Њd����̂ɍœK�ȕ���Ƃ��đ��݉��l�͂��邾�낤�B
|
 |
��M7�@�v���[�X�g�@�i�����֒e�C�@���v���[�X�g�̓C�M���X���j
�@�J���̂��������A�Ӑ}�Ȃǂ͎����s���ɂ��m�F�ł��Ă��Ȃ����AM3��ԁi�������M4��ԁj�̎ԑ̂Ɗ�����105�����֒e�C�𗬗p�����ȈՂȍ\�����������֒e�C�ł���B
�@�{�Ԃ͎��p�����d������Ă���̂������ł���A�v�������I�[�v���g�b�v�̍L���퓬���A����Ԃ̎ԑ̂����������@���͂ő����I�ɍ����\�͂��B
�@�����̓A�����J�R�p�̎ԑ̂��D�悳���\��ł��������A�{�Ԃ̓o�ꎞ���ɂ͂܂��A�����J�R�͖{�i�I�ȗ���ɎQ�����Ă��炸�A���I�ɃC�M���X�R�ւ̋������D�悳��Ă���B
�@�A�����J�R�ł͏d�Ί�̑�������n���Ȋ���ɂƂǂ܂�b��͂��܂蕷���Ȃ����A�������1�ł���C�M���X�R�ł́A���R�̞֒e�C�����D��Ă���������C���ɍD�܂ꂽ�B
�@�������A105mm�C�e���C�M���X�����Ő��Y���Ă��Ȃ�������莋����A�����A���Ԃɂ���Ă��܂����s���Ȗʂ����������A��q�̎�����ŏI�I�ȕ]���͍��������悤�ł���B
�@�A�����J�R�A�������e���̑���ʂ��Ă̖{�Ԃ̕]���͔�r�I�����A���I��������N�푈�ɓ��������ȂǁA�������炭�^�p���ꂽ�B
�@�Q�[���ł͒��Ղ�葦���Y���\�ƂȂ�A�ꕔ�̒���Ԃ�������ǂ��\�ƂȂ邪�AM3���[�̉��ǂ���M12�����O�g������ɓ����O�A���݉��l�͂�┖����������Ȃ��B
�@�����A�����Y�\�A105mm��C�Ƃقړ����\�͂ňړ��o���鎖�͕֗��ł���A�L�����y�[���E�X�^���_�[�h���킸105mm��C�Y����Ȃ�Ζ{�ԂY����ق����悢�B
�@�i�����M12�����O�g���ƂȂ��Ă���A5h�˒��������͂Ȏ����֒e�C�ƂȂ邽�߁A�o���l�����܂莟��A�����ɐi��������Ɨǂ����낤�B
|
|
��M12 �����O�g���@�i155mm GMC�F�L���O�R���O�@�����֒e�C�F�����J�m���C�j
�@�R�̊��S�ȋ@�B���A���ꂼ��̕����̘A�g�E�Z����ڎw���A�����J�R�ɂ���ĊJ�����ꂽ155mm����a�J�m���C�𓋍ڂ��鎩���C�ł���B
�@����a�̖�C�͉Η͂����������̂ł��������A��d�ʂ��畔�������ɂ͓���������߁A�@���͂̕t���ɂ���Ă��̌��_���Ȃ������߂ɖ{�Ԃ͊J�����ꂽ�B
�@����Ƃ��Ă͎b��F�����������ԂŁA�ԑ̂ɂ͉��ǂ���M3����Ԃ��A�C��M1917�n1918�n���̗p���Ă���A�̗p���ꂽ���ʂ����Ă������Ȃ��̂��������̊����͌��Ď���B
�@��p�I�Ȏv�z�������a�����C�͕s�v�Ɣ��f����A���炭�͑O���֓�������Ȃ���������피���߂���Ƒ�Η͂��K�v�ƂȂ�퓬�ɓ�������A�����ŏ��X�ɓ��p���������B
�@��������̑g�ݍ��킹�Ŋ�����������ł��邽�ߑ������\�͍����͂Ȃ��������A����ł��u����a�v�Ɓu�����v�̑����͋ɂ߂ėǍD�ŁA�b��I�ȕ���Ƃ͎v���Ȃ�������c���Ă���B
�@�u�b��I�v�Ƃ������ƂŐ��Y�䐔�͋ɏ��ŁA�����͎��߂����̂̊��������I�ȎԂł��������A��̎����C�ɑ傫�ȉe����^��������a�����C�̑c�ƌ����Ă��ǂ����낤�B
�@�Q�[���ł͔�r�I�傫�Ȏ˒��E�Η͂��ւ�A���Ղ��߂����������M3����Ԃ���̉��ǁAM7�v���[�X�g����̐i���Ŏ�ɓ���鎖���ł���B�i�ŏI�i���j
�@���b�͊낤�����̂́A�@���́A�ΉA�˒��̃o�����X�͗ǍD�ŁA��ԑ���̖C���ɂ��Η͏\���ƌ������̎x������Ƃ��Ă͔��ɗ���ɂȂ镺��ł���B
�@�e�������܂�ɂ����Ȃ����ߕ⋋���C�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͖̂��ł��邪�A���̖ʂ����܂��J�o�[���č����Η͂������������B
|
 |
��90mm AA�C�@�iM1�EM2�EM3 90mm���˖C�@�������˖C�j
�@���O���^�p����Ă���76.2mm�C�iM3 M1918 3�C���`�C�j�����������Ă������߁A����̍X�V�̂��߂ɍ̗p���ꂽ�C�ŁA���ǎ�͐�ԖC�Ƃ��Ă��g��ꂽ�C�ł���B
�@�Ȃ��A�X�V���ɂ͋�76.2mm�C�����ǂ���Ă��o�Ă������A�Η͂̌���A�Z�p�����ɂ�鐫�\�̔���I���オ�قڊm���ƂȂ������Ƃ���90mm�C�������̗p���ꂽ����ƂȂ��Ă���B
�@�{�C�̓����͑���a�Ȃ��疈��20���O��̔��ˑ��x�A�L���p�A���[�_�[���܂��x�Ȑ��䑕�u�Ȃǔ��ɋ��͂ȓ_�ŁA�З͂̓h�C�c�鍑�R��88mm�Ɣ�r���Ă����F�͂Ȃ��B
�@���炭�̉^�p��A��荂���\�ȃ��[�_�[���j�b�g�ł���SCR-584���p������悤�ɂȂ�Ɣ\�͂͂���ɔ���I�Ɍ��サ�A��풆�ō��x���̍��˖C�Ɏd�オ�����B
�@�q���̂悤�ȉ₩���͂Ȃ��������A�����I�\�͂�Y�吔�Ɍb�܂�Ă��������瑽���̐��ŗp�����A�G�q�͂̌����A�r���A�w�n�h�q�ȂǗl�X�ȏ�ʂŊ����B
�@���ɂ����Ă����̗D�ꂽ���\������nj^�����N�푈�ȂǂŎg�p�����ȂǁA���̎�̕���Ƃ��Ă͔�r�I�����Ԋ��Ă���B
�@�Q�[�����ł͒��Ձ`�㔼�ɂ�����76mmAA�C����̐i����ꕔ�}�b�v�̑����Y�A�ق��ɋ����i���ȂǂŎ�ɓ���邱�Ƃ��\�ł���B�i�ŏI�i���j
�@�����C�ł��邱�Ƃ���h��͂͒Ⴂ���A��\�͂͏\���Œ����˒�����������h�q�C���ɍœK�ȕ���Ɏd�オ���Ă���A���̖�����Ԃł͔��ɗ����������킾�B
�@��R�����͂ł���A�����J�R�ł͑j�b�g�̑��݈Ӌ`�͂�┖�����A���R�ŋ��̐퓬�@�����x20�~�܂�ł��邽�߁A�I�Ղ̒�������p�ɐ���͊m�ۂ��Ă��������B
|

coffee break |
|
�`����I�ȋߐڐM�ǂ̔����ƕs�m���Ȃ��̎��с`
�@��ꎟ���E��킩�����E���ɂ����č��˖C�̓��W���[�ȑ��݂ŁA�����̍��ŗp����ꂽ��C�e�i���˖C�e�j�͎������ƌ����u�ł��グ��ݒ肵�����ԂŔ����v�����镨�������i���˖C�e�͒����������Ƃ������E�j�ЂœG�@��j��ł���Ηǂ��j�B���̕����͍����⑊��̑��x�A����ɔ�s�ʒu�̌v�Z���s���ˌ����s�����߁A���x�Ȍv�Z���K�v�Ŗ������x�ɂ����Ƃ������_�����������A����ł��h�C�c�鍑�ʼn^�p����Ă����L����88mm���˖C���͂��߂Ƃ��e���ʼn^�p�������˖C�͈��̐�ʂ������Ă����B�������̑�C�e�͂��͂₻�ꂪ������O�ƌ�����悤�ȏł������B
�@�����ς����̂̓A�����J�ł������B�A�����J�͔���ȗ\�Z�Ƀ��m�����킹�A�Ȃ�ƖC�e�̒��ɏ��^�Z���T�[�i���[�_�[�j��g�ݍ��݁A�ˌ���A�C�e�t�߂ɕ����I�ȕ�����������Ŕ�������Ƃ������ٓI�ȖC�e������Ă��܂����̂ł���B����͋ߐڐM�ǁEVT�M�ǂȂǂƌĂ�Z�p�R�k��h�����߂ɓo�꒼�ケ���^�p�������������Ă������A��킪�i�ނɂ�ē������������Ă����A���ɕs���e���G�ɉ�������S�z�̂Ȃ������m�ł܂Ƃ܂��������g�p����A��C�̐��\�₠�������ς������B�����A���̍��ɂ̓A�����J�͕��ʓI�ɂ���ǓI�ɂ����ɗL���ȗ���ƂȂ��Ă���A�����Œe���Ɍ���̂��������̖C�e�ȊO�ɂ��]���̖C�e�E�@�e�e�����ꂱ���J�ł̂悤�ɂ�T����Ă����B���̂��ߌ��āE���j�̔��肪������������������A�e�탁�f�B�A�ł̌��ʕ]����3�`5�{���x�̐��x����i5�C���`�C�e�̏ꍇ�j�Ƃ�������邽�߁A���̐��ʂ����m�łȂ��Ƃ��������ꕔ����B���āA�����A��n�ł��̖C�e���g���Ă������m�̕]���͎��ۂǂ��������̂ł��낤���B
|
 |
��155mm L.�g���@�i�����O�g���FM59 155mm�J�m���C�@�����֒e�C�j
�@����܂Ńt�����X����155mm�����C���^�p���Ă����A�����J�R���A����X�V�̂��߂ɍ̗p�����V�^155mm�C�ŁA�������ɂ�203mm�C�������E�J������Ă���B
�@�����̃A�����J�R�ʼn^�p����Ă����C�A����Ɏg����C�e�͂��Ȃ�̎�ނ�����A�����ɞ֒e�C�A�J�m���C�����݂��邽�ߔ��ɕ��G�ł������B�iM1A1�AM1918A3�Ȃǁj
�@�{�C�͂��̒��ł��V�K�̗p�Ƃ������Ƃ�����A����܂ł̖��̂ƈقȂ閼���p�����A�{�i�I�ɉ^�p����邱��ɂ�M59�Ƃ������̂��m�肵���ꂪ�����Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B
�@�\���̊ȈՉ��A�R�X�g�팸���V�Z�p�����Ƃ����A�����J���ƌ|�̌������͑傫����������A���ʓI�ɖ吔�͏��X�ɑ����A���R�A�C�R�̑o���ŕ��L���g�p�����Ɏ������B
�@�����̖C�Ƃ��Ă͔��ɒ����˒������A�Η͂������Ă��邱�Ƃ���A���B����S�ʁA���I�Ղɂ͑����m����ւ��ϋɓ�������A�����C�u�����O�g���v�ƟӖ�����Ă���B
�@�������N�푈�ɓ������ꂽ��A�����ł͂��邪���q���ɂ���������1990�N�㒆�܂Ŕz�����ꑱ����ȂǁA���ɗނ����Ȃ��قǑ��̒�������ł������B
�@�Q�[�����ł͍|�S�̐����Ȃ�Β��ՁA���t�@�C���Ȃ�Ώ��Ղ���A105mm��C����̐i���œ��邱�Ƃ��\�ŁA��ΉE�˒�7�Ƃ����̂͂�┽���C���ƌ����Ă��ǂ��B
�@���C�Ƃ������ƂŖh��͂͊F���ɓ������A�U�����Ȃ��悤�ɂ���K�v�͂��邪�A�Q�퍑�̑S��C�ōō��̎˒������͂��̌��_�����������Ă����͓I�ł���B
�@�ő�˒����̉Η͒ቺ��͋C�ɂȂ���̂́A����ł��\�������A�i������105mm��C�ł���y�Ƃ������Ƃ���A�ϋɓI�Ɏ��X�Ɛi���œ������Ƃ��낾�B
|
 |
��BA-6�@�i���b�ԁj
�@�����ƂȂ���27�n���b�Ԃ̍X�V�ɓ�����A�����̘Z�փg���b�N�i�Ƃ����Ă����C�Z���X���Y�i�H�̂悤�����j�̃V���[�V��p���ĊȈՂɊJ�����ꂽ�̂��{�Ԃł���B�i�����s���L�j
�@�{�Ԃ́A��b�������g���b�N�ƌ������ō����E�@�����ɗD��A�܂��A������ԂƓ����̎�C�𓋍ڂ��Ă���A�����Ƃ��Ă͔�r�I��Η͂����B
�@���ʁA�A���b�͋ɂ߂Ĕ����A�d�@�֏e�̗��˂ŗe�Ղɑ��b������������Ă��܂��ƌ����v���I�Ȗ���A���j����������Ƃ����_������A�S�̓I�ȃo�����X�͂悭�Ȃ��B
�@�܂��A�R����R��̊W���炩�A�s�������E�͈͂����b�ԂƂ��Ă͋����A�������E�����Ԃ̍��s�����o���Ȃ��Ƃ�����_�����݂���B
�@�{�Ԃ̎���_�͌�X�̌�p�@�ɂ܂ʼne�����y�ڂ������A�R������ւ̎ԗ������̑��i�ƁA�\�r�G�g�R�̋@�B�����������邽�߂̈ꗃ��S�����B
�@�Q�[���ł͎j�����l�A���b���قƂ�ǎ����Ȃ��y���b�ԂƂ��đ��݂��A�L�����y�[���S�ʂŐ��Y�\�ł���B
�@���\�A�R�X�g�I�ɂ͈ړ���7�A���G4�A�����ƁA����Ӗ��O���q������Ă���A�قڍ��G��p�Ƃ��đ��݂���ƌ����Ă悢�B
�@��C�̐��x��12�ƒႭ�A�퓬�����ł��邱�Ƃ͖��m�ł���A�^�p���ɂ͐ϋɓI�Ȑ퓬�͔����A�o��������C���ł�����G�ɐ�O����悤�S���������B
�@�Ȃ��A�{�Ԃɂ͐i���E���ǁiBA-64���������߁j�����݂����A�܂��A�������G�p�����T-60�y��ԁi�����x���j�����邽�߁A�v���[���[�̍D�݂Ŏg��������Ɨǂ����낤�B
|
 |
��T-26 M33/M37�@�i�y��ԁj
�@���O���玩���̐�͑����ɗ��ł����\�r�G�g�R�ł��������A�̐S�̕���v�͂܂����n�ł��������߁A�����̐�Ԃ����{�Ƃ��č��Y��ԂY���悤�ƌv��𗧂Ă��B
�@�v���i�߂�ׂ������̐�Ԑ�i���A�C�M���X�鍑�̐�Ԃ�����������Ƃ��냔�B�b�J�[�X�Ђ̐�Ԃ����ڂ���A�����ȃ��C�Z���X�_��̌ケ�����{�Ƃ��ĊJ���͎n�܂����B
�@��{�I�Ȏԑ̐v�̓��C�Z���X���̐�Ԃɏ����Ă������A�����̓\�r�G�g�R�d�l�̂��̂ɕύX����A���Ɏ�C�͉��x���ύX���ꂽ���߂Ɏ�ނ͂�₱�������ɂȂ��Ă���B
�@�����^�ł̓��C�Z���X�E�͑���37mm�C�Ȃǂ����ڂ���Ă������A��p�̑傫��45mm�C�����p�������ƕ����͂�����ɕύX����A�����Ƃ��Ă͔��ɍ����Η͂������炵���B
�@�����E�������\���l�����1933�^�ňꉞ�̊����ƌ��Ă悢���A��{���\�̍������炻�̌�����ǂ͑����A�ԑ̂̍\���A�lj������ȂǑ����ʂɂ����Đi���𐋂��Ă���B
�@���Y�䐔��10,000���y�������Ă���A�\�r�G�g�̓S�|�Ɨ́E���͂������t���A�A�o�A�������b�l���ꂽ�{�Ԃ͂����Ŋ���Ȃnjy��ԂƂ��Ă����ɗD�ꂽ�ԗ��ł������B
�@�Q�[���ł͏��Ղ��琶�Y���\�Ȉ�ʓI�Ȍy��Ԃł��邪�A���G�͈͂���������߂ɑ����y��ԂƂ̔�r�ł͂��i���ɗ����̂ƂȂ��Ă���B
�@�Η͂̑傫���A�e���̑�������p�������퓬���\�ƌ��������͂�����̂́A�y��ԂƂ������ނ��炻���������g�����͂قƂ�ǖ������߁A���݈Ӌ`�͂�┖���ƌ�����B
�@�i�����T-60�y��Ԃւƌq������̂́AT-60����@�E�퓬�ǂ���ɂ����r���[�Ȋ����͔ۂ߂��A�{����@�Ɏg�����ǂ����ʼn��l��傫���ς�����̂ɂȂ邾�낤�B
|
 |
��T-60 M40/M42�@�i�y��ԁj
�@�����̌y��Ԃ��J���E�^�p���Ă����\�r�G�g�R�ł́A�X�̎ԗ��ɓƓ��̍l����g�ݍ������炻�ꂼ�ꉽ����������������A��ɂ��̋@�\�����ꂽ�肷�鎖�����������B
�@���ɐ������p�ȂǑ��@�\�������߂����͑傫�Ȏ��s�̈�ŁA����ɂ�菃���Ȍy��Ԃƌ�����悤�Ȏԗ������Ȃ��������߁A���̉��P��}��ׂ��{�Ԃ͏�����p�Ƃ��Ēa�������B
�@���@�\�������߂������̌y��Ԃ����b�s���ɔY�܂��ꂽ��������A�܂��͑��b�ɌX�Α��b���̗p��������x�̌��݂����m�ۂ������߁A�h�䐫�͂�����x���P����Ă���B
�@��C�͐�ԖC�ł͂Ȃ�20mm�@�֖C���̗p����Ă������A����͐퓬�@�Ȃǂɗp������@�֖C�ő�Η͂Ƃ͌����Ȃ����̂́A�y��ԂƂ��Ă͑傫�ȉΗ͂ł���B
�@�ߋ��̎ԁi�O�CT-40�Ȃǁj�ɔ�ב��b�A�����ȂǑ����̓_�����P���ꂽ���A�c�O�Ȃ��瑍���I�Ȑ��\�͐U��킸�A���p���E�퓬�͕͂s���C���ŕ]���͂��܂�ǂ��Ȃ������B
�@���D�G�Ȍy��Ԃ��J�������Ɛ��Y�͂����ɒ�~���ꂽ���A�{�Ԃ̓\�r�G�g�R�Ƃ��Ă͒������ϑԕ���ւ̓]�p���l�����ꂽ�ԗ��Ƃ��ėL���ŁA�O���C�_�[���A-40�͂悭�m����B
�@�Q�[���ł�T-26����̐i���A���@�����ɂ�鑦���Y�Ŏ�ɓ���y��ԂŁAM40�^�͍��G�͈͂�3�AM42�^�ō��G�͈͂�4�A�h��͂����ꂼ��Ⴄ�A�ƒ��ӂ��K�v�Ȏԗ��ł���B
�@�퓬�ԗ��Ƃ��Ă̐��\�͑����y��ԂƎ����悤�Ȑ��\�őO���ɐϋɓ����ł��鐫�\�ł͂Ȃ����AM42�^�͍��G�C���ɂ��\���g���邱�Ƃ��炻�̖ʂł͐ϋɓI�Ɏg�������B
�@�����Ƃ��A��@�p�ɂ͑��b�Ԃ������ɁA��R�X�g���ł͂��邪�I�Ղ͑����Y���ł��邽�߁A����قNjC���g���ĉ^�p���镺��ł��Ȃ����낤�B
|
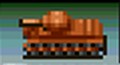 |
��BT-5 / 7�@�i����ԁF������ԁj
�@������ԂƂ�����`���̂͌��X�A�����J�Œ��ꂽ���̂ł��邪�A�A�����J�R�̉^�p��̂ɂ͍��킸�w�ǁi�Ƃ������܂������A���j�̗p����Ȃ������B
�@�������A�������ꂽ�C�M���X�A�\�r�G�g�Ȃǂł͂��ꂪ�̗p����A�{�Ԃ͂��̉^�p��́E��`�Ɋ�Â��ă\�r�G�g�ɂĊJ���E���Y���ꂽ��Ԃł���B�i�C�M���X�͏��q��ԁj
�@�{�Ԃ́A������ԂƂ���������A���i���͂�����Ɛ��\�ɏo�Ă���A���ӁE�s���ӂ����ɖ��m���B
�@��C�͓����Ƃ��Ă͑�Η͂�45mm�C/76mm�C�𓋍ڂ��A����r�I�y�ʂȎԑ̂������@���͂́A�\�r�G�g�R�ɋɂ߂č����@�����E��͂�^���鎖�ɐ������Ă���B
�@�������Ȃ���A�@������^���邽�߂ɋ]���ƂȂ��������i��ɑ��b�j�͉e�����傫���A�v���I�Ȕ�e���\�̒ቺ�������A���ʓI�ɑł���コ�̖ڗ��Ǝ�Ȑ�ԂƂȂ����B
�@T-34�̐��������������܂������߁A��풆���ɂ͉��ǎ���܂ޑS�Ă̐��Y���I���������A������ɂ͑Α���{�鍑��ɂ���������Ă���A�^�p�͈ӊO�ɂ����������B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��琶�Y���\�ŁA�j���ǂ���@���͂̍�����ԂƂ��ēo�ꂷ��B
�@�������A�@���͂����������Ŋ̐S�̐퓬�͂͂���قǍ����Ȃ��A�������̑���{�鍑�R��Ԃɔ�ׂ��L���A�h�C�c�鍑�R��Ԃɔ�וs���Ƃ��������Ȑ��\�ł���B
�@�̐S�̐i�����T-34�Ƃ��܂ЂƂŁA���N��ɂ���KV�n�AT-34�n�����Y�\�ɂȂ�Ƃ������������Ċ���̎����͔��ɒZ���B
�@�{�Ԃ́A�O���̂��̏ꂵ�̂��̐����킹�ƍl���A���Y�\��KV�n�AT-34�n����������Ȃ�A�f���ɂ�����ɏ�芷����̂��ǂ����낤�B
|
 |
��T-34�@�iT-34/76�i85�j�@����ԁ@��A/B/C���̂̓h�C�c�R�ł̕��ށj
�@�{��ԓ����ȑO�̃\�r�G�g�R��Ԃ́A�y���b�̉�����Ԃ���ł��������A���̌y���b���w�ƂȂ�A����E���O�̏����荇���ő傫�Ȕ�Q���o�邱�Ƃ����������B
�@���̖����������邽�߂ɒ���ԋ敪�̐v����V���A��������Ԃ̃m�E�n�E�������̂��{��ԁAT-34�ł���B
�@T-34�͔��Ɍ����̗ǂ����Y�v�A�D�ꂽ��e�o�n�ƍ����Z�p�A����76.2mm���85mm�C��p���������ΉA���̑������̋Z�p�ŁA�����\�U����⊶�Ȃ����������B
�@�����A�S�ʓI�ȋ@�B�I����͍����\�ł͂��������A�ׂ��������ł̌̏Ⴊ�����A�܂��A��ԕ��ɂƂ��Ă͂������ɂ��ǂ����S�n�E�g�������Ă͗ǂ��Ȃ������悤�ł���B
�@�\�r�G�g�̕���͍����\�ł����Ă��A�X�̕��i�͎g���̂Ă̂悤�ȒZ�����Ȃ��̂��������߁A�{��Ԃɂ����̉e�����o�Ă����̂�������Ȃ��B
�@�Q�[���ł�T-34�͔��Ɉ����ŁA�W����ԁA�e�B�[�K�[�A�p���^�[�ɔ�ׂčU�����x�ɗ�邪�A�ΉE���b�͌ܕ������s�����x�̐��\�ł���B
�@�搧�U�������̂��������̃Q�[���ł͂ǂ����Ă��s���ȗ���ɂȂ邪�A����ł����Ղ͏\���Ȑ��\�������A�㔼�ł�SU-100�̎�Ƃ��Ė��ɗ��B
�@���Ձ`�I�Ղɂ����Ă�T-34/85�́A��\�͂ɕs����������̂̑�ʐ��Y�����₷���A��ʂߐs�����قǐ��Y���Ă݂�̂��ʔ�����������Ȃ��B
|

coffee break |
|
�`��Ԃ̑��b�̕ω��Ɣ�e�|�X�Α��b�`
�@����E���ł͂���܂ŋN�����ߋ��̐푈�ƈႢ�A��킪�i�ނɂ��ԓ��m���������퓬���s������������O�ƂȂ��Ă������B���ɉ��B�ł͂��̉e���͑傫���A�e����Ԃ̐i���͂߂��܂����A�Z�p�A�v�z�A�^�p�����͑傫�����B����Ɏ���B����ɂ���Ď�C�̈З͂͂������A�G�̖C�e��@���ɂ��܂�����������͑ς��邩�Ƃ������͔��ɏd�v�Ȗ��ɂȂ����B�����̌����҂����̖��Ɏ��g���ʁA�o���������͂����ł������B
�@�u���������X�̂��鑕�b�Ŕ�e�������̕�����e�ӏ��̑��b�͌����Ȃ�A�^���G�l���M�[�U�����鎖���ł���v�|�܂�Ƃ���X�Α��b�i��e�a�n�j�ł���B
�@���́A���̍l�����̂͑��O���猤������Ă����̂����A�Ȃ��Ȃ����_�Ƃ��̌��ʂ��ؖ������Ԃ͐��܂�Ȃ������B�������A����T-34�Ƃ�����Ԃ��o�ꂷ��BT-34�̓\�r�G�g�̗D�ꂽ�S�|�Z�p�ƍl�������ꂽ�X�Α��b���̗p�������ŋɂ߂č�����e�ϐ��āA���̗L�p���𐢂ɒm�炵�߂��B����͐�Ԏj�ɂ����Ĉ�̑傫�Ȓʉߓ_�ƂȂ�A����ȍ~�̓h�C�c�鍑���͂��ߊe���̐�Ԃɂ����ĕ��L���X�Α��b���p������悤�ɂȂ����B����ɂ����Ă͖C�e�̔��B�ɂ��A�X���ɋ߂���ԂŒ���������Z�p���o�Ă������߁A����قǒ��ڂ���Ȃ��Ȃ����X�Α��b�����A����ł��d�v�ȋZ�p�ł��鎖�ɕς��͖����A���̗��_�E�Z�p�̓o��͈�̓]�����ƌ�����B�����A������O���I�ȑ��b���D��Ă��Ă��������Ռ��œ������j��A���̕��i����юU�鎖�ɂ���ē�������������邱�Ƃ����邽�߁A�����܂Ō����͑����Ă��荡����O�ʓ��ʋ��Ɍ����͑����̂��낤�B
|
 |
��KV-1�@�i�d��ԁj
�@��평���`�����ɂ����Ċ����d��Ԃł���A�J���ҁi�N�������g=���H���V�[���t�j�̖��O�������KV�Ɩ��t����ꂽ�B�i���ɂ����KW�ȂǗ��̂��Ⴄ�j
�@�{�Ԃ̓����͌������b�ł���A���̂��肠�܂鑕�b�͑�평���̃h�C�c�鍑��Ԃ��ǂ��������Ă��ђʂł��Ȃ����̂��̂ł������B
�@�������A���̑��b�̌������痈��d�ʂ̂��߁A���s�n�͏�ɂ����ς������ς��̐��\�ŁA��ԕ��͑��c����̂ɋ�J���₦�Ȃ������悤�ł���B
�@�h�C�c�鍑�ł͑�Η͂�88mm��C��ΐ�ԖC�Ƃ��Ďg�����Ƃ����������A�{�Ԃ͂����p���Ă��ђʂ͂Ȃ��Ȃ�����ŁA�ꎞ���h�C�c�鍑�ł͑���ƂȂ����B
�@���ǂ���r�I�����s���A�lj����b�̎{���ꂽ���́A�t�ɋ@�������l�����đ��b�����ꂽ���́A�Ή����ˌ^�ȂǑ����̃o���G�[�V���������܂�Ă���B
�@��ɖ{�ԂɑR�ł���h�C�c�鍑��Ԃ��z�������ƁA�@�����̈����Ɛ퓬�͕s�����珙�X�ɑ�������p�������Ă��������A����܂ł̌��т͔��ɑ傫�����낤�B
�@�Q�[�����̖{�Ԃ͔�r�I�������琶�Y���\�ŁA���ՂƂ��Ăُ͈�ȍd�����ւ�A�U�����ł���ǂƂ��Ĕ��ɏd��B
�@�h�C�c�鍑���p���^�[�A�e�B�[�K�[�����n�߂�ƈ�u�ɂ��čU��̗��ꂪ�t�]���Ă��܂����A�����Ȑi����������A�j�}���L���[��JS-2�Ɛ���B
�@����܂ł͕s���ȏł��䖝���Ēn���Ɉ�ĂĂ��������B
|
 |
��KV-2�@�i�d��ԁj
�@�d���b������KV-1�d��Ԃ̎ԑ̂��x�[�X�ɑ�^�̖C�𓋍ڂ��A�����h�䐫�\�A���͂ȉΗ͎x���ɓ��������d��Ԃł���B
�@�C�̊W����w�������A���̃V���G�b�g���犴�����閳�����͂��͂������Ƃ��v����قǂł���A���̊O�ς͂����ɂ��\�r�G�g�炵���B
�@��C�͍��З̞͂֒e152mm�C�A���������b��37�`50mm���x�̖C�e���y���͂����Ԃ��A���̐��\����Λ������h�C�c�R��t�B�������h�R����̓M�K���g�ƌĂꋰ���ꂽ�B
�@��평���̃\�r�G�g���ɂƂ��Ė{�Ԃ͔��ɐS�������݂ł͂��������A��͂�d��Ԃł��鎖����@�����͒������Ⴍ�A�w�̍������甭������₷���Ǝ�_���������B
�@�����ł͂��邪�ʎY���������A�e���ŋ��͂ȖC���J�������܂ő����Ő킢�����A���\�s���̎w�E�������ɉ������Ă��Ȃ��I��܂Ő킢�������悤�ł���B
�@�Q�[�����ł͑�평���ɐ��Y���\�ŁA���ՂƂ��Ă͖��͓I�Ȑ��\�������̂́A�}�C�i�X�v�f�������ŏ���1�A2�}�b�v���^�p����ΐ��\�I�ɑޖ��ł͂Ȃ��낤���B
�@�����ΉA�h��͂͗���ɂ͂Ȃ�̂����A�֒e�ł��鎖����C�̐��x�͒Ⴍ�i���x10�j�A�ړ��͂̒Ⴓ���炷���ɐ搧�����Ȃ��A�i�R�ɒǂ����Ȃ����̂���������B
�@���Ղ͂Ƃ������\�r�G�g�R�ɂ͗D�G�Ȑ�ԁE�����C��������Ă��邽�߁A�����Ɏg��Ȃ��Ƃ��ǂ���������Ȃ��B�i���ǁE�i�����SU-152����������́E�E�E�j
|
|
��KV-85�@�i�d��ԁj
�@�����I�ɗD�ǂ�T-34��ԁA�@�������]���ɏd���b������KV-1��Ԃ��^�p���Ă����\�r�G�g�R�͌ő̂ł̓h�C�c�鍑�R��Ԃ𗽉킵�Ă������A�e�B�[�K�[�o��ɂ�藧�ꂪ�t�]�����B
�@�ŐV�^��Ԃ̔z�������߂鐺�͑����Ȃ��Ă��������A���R�ł������������ɂ͎��Ԃ��K�v�ŁA�����Đ�ǂɗ]�T���������ߎb��I�ɐV��C���ǐ�Ԃ̓������v�悳�ꂽ�B
�@�������ɂ�IS-85�i���IS-1�j�̊J������q���Ă������߁A���̎b��I�[�u�͑Ó��Ȕ��f�ƌ����A�ԑ̂ɂ͊g������KV-1S�A��C��85mm�C���̗p����{�Ԃ͊����Ɏ���B
�@�{�Ԃ͂���܂�76.2mm�C�����i�i�ɍ����Η͂�����85mm�C���ڂ������Ő퓬�͂͊i�i�Ɍ��サ���A���A����ł��h�C�c�鍑�R�̐V�^��Ԃɂ͕��������A�܂��ł������B
�@�܂��AT-34��85mm�C�𓋍ڂ���v����i�߂��Ă���A�����IS-1�̉��ǂ��i�݁A���������ꂽIS-2�̊������ʂ��������������琶�Y�䐔�͏��Ȃ��A�����Ƃ��Ɏb��I�ƌ�����B
�@�\�͂͂��܂ЂƂ�������100mm�A122mm�A152mm�C�𓋍ڂ����V�v��Ԃ̓o��܂ł悭�킢�A�����Ȃ�������g�n�w�ɂȂ�܂Ńe�B�[�K�[�ȂNJi��̐�Ԃɗ������������B
�@�Q�[���ł͒��Չ߂��ɓo�ꂵ�AKV-1S��Ԃ���̍ŏI���ǂŎ�ɓ���鎖���ł��邪�A�Η͂����������ɂȂ���Ɏ������̂�������ԂƂȂ��Ă���B
�@�����ł��鎞�����l����ƉΗ�90/���x19�Ƃ����̂͊m���ɖ��͓I�����A�ړ��͂�3�ɁA�h��͂�T-34�ȉ��ƂȂ��Ă��܂����ߑ������\���傫���ቺ����_���傫�Ȍ��_�ł���B
�@����ɍŏI���ǂł��邽�߂���ȏ�̉��ǁE�i�����s���Ȃ��������͂��]�I�ł��邽�߁A��قǂ̎�����������{�Ԃ̓����A�^�p�͍l���Ȃ��ق����ǂ����낤�B
|
 |
��JS-2�@�iIS-II�F�X�^�[�����d��ԁ@�d��ԁj
�@�h�C�c�鍑���e�B�[�K�[�A�p���^�[�Ȃǂ̗D�G�ȍ����\��Ԃ����X�Ɠ������钆�A�\�r�G�g�ł͂����ɑR�ł��鍂���\��Ԃ̕K�v�������܂����B
�@���Ƃ��ƃ\�r�G�g�ł��V�^��Ԃ̊J���͐i��ł������̂́A�v��͕ύX����A����C�����͂ɁA��葕�b�������A�ƍŏI�I�ɏo���オ�����̂��{�ԂƂȂ�B
�@�퓬���͋����A���삷�鑤�ɂ͂������ɂ��g������̗ǂ���Ԃł͂Ȃ��������A122mm�C���̂̔j��́A���̞֒e���ʂɂ�镛�j��͂ɂēG��Ԃɑ傫�ȑŌ����������B
�@�܂��A�h��͂������A�h�C�c�鍑�̍����\��ԖC�������Ă��Ă��Ȃ��Ȃ��j��͏o���Ȃ������B�i���x�̍������Ȃ������_������t���Ĕj�鎖�͉\�ł������悤���B�j
�@�J�����ɂ͐V�^100mm�C�̓��ڂ���������Ă����悤�ŁA���ђʗ͂̑傫��100mm�����̗p����Ă����Ȃ�A�ǂꂭ�炢�̔j��͂�ꂽ���M�҂ɂ͌������t���Ȃ��B
�@�Q�[���ł͌㔼�ɍ����|�������Ƃ����KV��Ԃ��i���E�ꕔ�̃}�b�v�ő����Y���\�ł���B
�@�|�S�̐����ł͉ΉE���x���ɒႭ�ݒ肳��Ă�����̂́A���t�@�C���ł͋��������A�\�͂ɂ��Ȃ�̍������镺��Ƃ��Ĉ����Ă���A���ӂ��K�v���B
�@��ΓI�Ȑ��x�̓p���^�[�A�e�B�[�K�[�ɂ��Ȃ�Ȃ����A�������x���҂��Ό݊p�̐킢���\�ł���A�{�Ԃ��ǂꂾ���������𑵂����邩�Ői�R���x�͍��E����邾�낤�B
�@�i����JS-2m�@���@JS-3�̗���ňړ��͈��������Ő��\����A���ǂ�JSU-122�Ŗh��͂����������Ɏ�C�e�������Ǝg�����肪�ς�邽�߁A�����̍D�݂őI�Ԃ̂��ǂ��B
|
 |
��JS-3�@�iIS-III�F�X�^�[�����d��ԁ@�d��ԁj
�@JS-2�d��Ԃ̗D�G�������������\�r�G�g�R�ł́A���\���グ��ׂ�JS-2m��Ԃ���b�Ƃ������nj^�̊J���ɒ���A���̐��ʂƂ��Ēa�������̂��{�Ԃł���B
�@���ł�JS-2�̓o�ꂵ�����_�Ńh�C�c�鍑�R�̔s�k�͔Z���ƂȂ��Ă���A�{�Ԃ̊J���͑h�C�c�鍑�p�Ƃ����������̎��܂��Ă̊J���ł������ƌ����Ă悢���낤�B
�@���ɖh��ʂ̋����͒������A���X�D�G�ł������X�Α��b�͂���ɐi�����A�����Ƃ��Ă͋ɂ߂č����h�䐫�\���l�����A�܂��A����Ɍ�����ʐ�i�I�ȊO�ς������ƂƂȂ����B
�@�����A�C���A�ԑ̃T�C�Y�A�d�ʂ��l�������ꍇ�A�v�ɂ͂��Ȃ薳��������A�\�r�G�g��Ԃ��ƌ����Ă悢�ł��낤���S�n�̈�����퓬���̋������͉��P�ł��Ă��Ȃ��B
�@�Η͂�JS-2�ƕς��Ȃ����̂܂܂ł��������̂́A�����Ƃ��Ă͂��̎p�͔��ɃV���b�L���O�Ȃ��̂ŁA���̃p���[�h�Ŗ{�Ԃ��������������̏��Z�ɋ���ȃC���p�N�g��^�����B
�@���̌��ʁA���������͍������\�����V��Ԃ̊J����]�V�Ȃ�����Ă���A�{�Ԃ̓o��͐��̐�ԊJ�������������N�������[�ƂȂ��������ƌ����Ă��悢��������Ȃ��B
�@�Q�[���ł̓\�r�G�g�ŋ��̐�Ԃł���A�����ɏ������������Ƃ�JS-2m���i�����\�B�i�����A�M�҂̓\�r�G�g�L�����y�[����2�A3��i���ł����������邪�A���̌�ł����Ⴊ�Ȃ��j
�@���l�ȏ�Ɍł�������A��ΉA�Əd��Ԃ̓������ɒ[�Ɍ���Ă��邪�A�ړ��͂�3�܂Œቺ���Ă��܂����߂ɁA�i�������������Ă��i�������鉿�l�����邩�ǂ������œ_�ƂȂ�B
�@�ŏI�i���̐�Ԃł��邽�߂ɐS��I�ɂ͐i�����������Ȃ邪�A�I�Ջ@��������߂���\�r�G�g�R�ł͈ړ��͒ቺ�͒v���I�ł���A�i�������������Ă��ɏ����̓��������������낤�B
|
 |
��JSU-122�@�iISU-122�@�ˌ��C�F�����C�j
�@�\�r�G�g�R�ł�T-34�AKV�̎ԑ̂𗬗p�����D�G�Ȉ��킪�l�X���܂ꂽ���AJS�d��Ԃ̎ԑ̂��{�i���Y�����悤�ɂȂ�ƁA���̎ԑ̂��x�[�X�ɂ�������̊J�����v�悳�ꂽ�B
�@�{�Ԃ����̌v��ɂ����̂ŁA�������̐�ԂƂ̕��i�E���Օi�E�e��̋��ʉ���ړI�Ƃ��A���A��r�I�^�p���y�ł��鎩���C�Ȃ�Α���͂Ƃ��Ċ��҂ł��鎖���_���ł������B
�@��C�ɂ͓�������̎�ނ����ɋ������Ă������A152mm��^�C�ł͋����ʂ����肸�A�ŏI�I�ɋ����ʂ��\����122mm�C�iJS-2�Ɠ����̂��́j�����ڂ���Ă���B
�@�����̉Η͎x���E�G�h�q�Ԃ̓˔j����C���ł������悤�����A�ΐ�Ԕ\�͂�������������A�ΐ�Ԑ퓬�Ɏg���鎖�����������B
�@����ɂ��A�@�B�����̎g���Ղ��������āA��C��JS-2�����ΐ�Ԑ�ɗL���ł������ƌ����b�����邪�A�Ȃ�ɂ���122mm�C�͋��͂ł��������͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�Q�[�����ł͌㔼��JS-2�AJSU-152�Ȃǂ���̉��ǂɂ���ē��鎖���\�ł���B
�@JS�n�ɔ�זh��͂͗����̂́A��C�̈З͂͋��́i�e����������邪�A�������͋t�Ɍ��j�ł���A�ړ��͂�5�ƌ������Ŏg������͗ǂ��B
�@�^��������̌���������JS�d��ԂɔC���A�{�Ԃ͉I�ĉΗ͎x���ɓ�����ȂǁA�U��̃o���G�[�V�����𑝂₷���߂ɐ���͕����ɉ����Ă��������B
�@�ꉞ�A�֒e�^�ɉ��ǂ͏o������̂́A���̓��e�͎�̉��ł��邽�߁A�{�Ԃ̓\�r�G�g�R�̎����I�ȋ쒀�E�ˌ��E�����C�n�̍ŏI�i���ł��낤�B
|
 |
��JSU-152�@�iISU-152�@�ˌ��C�F�����C�j
�@�҉Η͂��ւ���SU-152�͔��ɗL���ȕ���ł��������A�x�[�X�ԑ̂ł���KV-1�n�d��Ԃ̐��Y���I���������A���D�ꂽ���\��ڎw����������ԑ̂̐�ւ����s��ꂽ�B
�@�{�Ԃ̎ԑ͓̂����ɐ��Y�̎n�܂���JS�iIS�j�n���̗p����A�v�͐��������߂�SU-152�P���������獂���U���́E�h��͖͂���A�܂��ɋ�����SU-152�ƌ�����B
�@�\�r�G�g�R�̏d�ԗ��͌��X�����Ŗ��@���Ȋ����̋����ԗ����������A�{�Ԃ͒��ł����ɂ��̃C���[�W�������A��Ԃƌ������͓S�̉�Ƃł����������Ɠ��̑��݊��������Ă����B
�@������SU-152�Ɠ����ŁA��C�͑��ς�炸152mm�֒e�C���p�����Ă������A�\�͓I�ɂ��\���ȉΗ͂ł��������߁A�h�C�c�鍑�R��ԁA�ΐl�A�Ό��z���ɖ��\�̈З͂������B
�@�h��ʂł͐������ꂽJS�n�ԑ̂�p���������琫�\����͒������ASU-152�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǖh��͍͂��܂�A���̑������\���瓯�R�d�����C�̌���łƍl���Ă悢���낤�B
�@���\�I�Ȑ��\�A�G�ɋ��|�S��A���t����̂ɏ\���ȑ��݊�����������ǂ�������ʔz������A�F�D���ɂ������A�o���ꂽ�����瓯�R�Ƃ��Ă͑听�������߂��Ԃł������B
�@�Q�[���ł͌㔼�ɓo�ꂵ�AJS-2�n����̉��ǁASU-152����̐i���œ��鎖���ł��邪�A�֒e�C�^��ԓƓ��̈�������\�͓I�ɐU���Ȃ��ԗ��ƂȂ��Ă���B
�@�����I�ɂ�SU-152�Ƒ卷�Ȃ��A����ɏ���_�͕��������t�������A�h�䐫�\�����サ�����x�ő��ς�炸�ΐ�Ԑ퓬�ɂ͕s�����ł���A�g�����͌���I�ɂȂ邾�낤�B
�@���ǐ��JSU-122�Ƌ��͂ł�����̂́A�����JS-2����̉��ǂœ�������y�ł���A�{�Ԏ��̂̐��\�����������_���l������ƁA��͂��̕���ƌ��킴��Ȃ��B
|
 |
��SU-100�@�i�쒀��ԁj
�@T-34���x�[�X�ɊJ�����ꂽSU-85������Ɋg���������A�����ڂ��炵�Ē���ȉ��nj^100mm�C�𓋍ڂ����̂��{�Ԃł���B�i�����C���쒀��Ԃ��̔��f�͔��ɔ����ł���j
�@�{�Ԃ̓����͌^�Ԃ�100�������Ƃ���A�ɂ߂č����Η͂��ւ�100mm�C�ł���A���̈З͂̓e�B�[�K�[II�̐��ʑ��b������ђʉ\�ƌ����Ă����B
�@���łɃh�C�c�鍑�R�̋��͂Ȑ�Ԃ����������햖���ł̓o��ł��邽�߁A�ɂ������ΐ�Ԑ퓬�͊F���ƌ����Ă悭�A��ɕ����̉Η͎x���ʼn^�p����Ă���B
�@���͂ȉΗ͂������ʁA�d�S���O���ɂ������Ă��܂����ߎԑ̃o�����X�������A�܂��A�傫���C�e�̓x�[�X�ł���T-34�ԑ̂ɂ͑傫�����ASU-85�ɔ�ד��ڒe�����Ⴉ�����B
�@�Q�[���ł̓L�����y�[�����Ƃɉ��֎������Ⴂ�A�j���ł͖�����T-34/85����̉��ǂ܂��͑����Y�ŁA���z�ł͒��Ղ���T-34�n�̉��ǂł̂ݎ�ɓ���鎖���ł���B
�@�@�e�������A���b��JS�d��Ԃɗ����̂́A��C�̉Η͂͋ɂ߂č����i��t�@�F135/23�j�A�U���͂����Ȃ�Γ�����̃h�C�c�鍑�d��ԂƂ��قڌ݊p�ɓn�荇�����Ƃ��\�ł���B
�@�j���ǂ���C�e�̐������Ȃ����ƂƁA�O�q�̂Ƃ��葕�b�ɏ��X�̕s�������邽�߁A���܂��⋋�Ԃ�n�`���ʂ𗘗p���A�ł������g���ł߂Đ퓬��L���ɍs�������B
�@�Ȃ��A�i���E���ǂł́A�Z�C�g�iSU-122�j�ւ̉��ǂ��\�����A�ǂ��l���Ă���̉��̂��߁A�{�Ԃ̓�����͓��ɉ��ǂ͕K�v�Ȃ����낤�B
|
|
��SU-122�@�i�ˌ��C�F�����C�j
�@���^�����C�̐����ɂ���Ă��̎�̕���ɗL�������������\�r�G�g�R�́A�C�E�ԑ̂̑�^�������肵�AT-34����Ԃ��x�[�X�Ƃ����V�^�����C���J�������B
�@���ꂪ�{�Ԃł���A��ɕ����̉Η͎x����ړI�Ƃ����������C�ɂ�122mm�֒e�C���̗p����A�ΐl�E�Ό��z������Ƃ��Ă͋ɂ߂č����Η͂��^�����Ă���B
�@�ȑO�̏��^�����C���Η͂Ƃ��ėL���ł��锽�ʁA���Z���A�h��ʂȂǂɓ�_������ꂽ������{�Ԃł͂��̕������傫�����P����A���ɑO�ʑ��b�͌����{����Ă����B
�@��C���֒e�C�ƌ������őΐl�E�ΐw�n��ɐϋɓ�������Ă������A�h�C�c�鍑�R�����͂ȐV�^��Ԃ𓊓�����Ƒΐ�Ԑ���l�����Ă��Ȃ��_���w�ƂȂ�A�\�͕s�����I�悵���B
�@�ŏI�I�ɒZ���Ԃ�1,000��ȏオ���Y���ꂽ���A�ΐ�Ԑ�ɂ͕s�����ł���Ɩ��m�ɔ���������͐��Y��~�������A����ɑ��̑ΐ�ԖC�ւƐ��Y�͒u��������Ă���B
�@���\�ȕ���ł͂Ȃ��������A����I�ȓ����\�͂����ԂƂ��Ă͎v����������ł���ƌ����A�\�r�G�g�R���@���Ɍ����I�Ȏ��p�����d�����Ă������{�Ԃ���f�������ł��邾�낤�B
�@�Q�[���ł͎j���ǂ���ΐl�E�b�ɋ����ԗ��Ƃ��ēo�ꂵ�A��r�I��������T-34����Ԃ���̉��ǁA�܂���ɑ����Y�Ŏ�ɓ���鎖���ł���B
�@���\�I�ɂ̓I�[�\�h�b�N�X�Ȟ֒e�C�^��ԂŁA�ΐl�E�b�ɓ������ċ������ʁA���x���Ⴍ�Α��b�Η͂��Ⴂ���߁A�ΐ�Ԑ�ɂ͗p���Ȃ��ق����ǂ��B
�@�ϋɓI�ɓ�������قǂ̐��\�Ƃ��������AT-34��{�Ԃɗ��p����Ȃ�SU-100�ɂ�������L�p�ł���A�i�����SU-152�Ɣ����ł��邽�߁A���S�Ɏ�̕��킾�낤�B
|
|
��SU-152�@�i�ˌ��C�F�����C�j
�@�ߋ��A�c�Ȍ`�Ȃ�������̑�Η͂Ő���������^�d�����C�AKV-2�͑�킪�i�ނɂ�ċ��������i�ݔ�鑹�Q���傫���Ȃ�A�V�^�̑�^�d�����C�����߂�ꂽ�B
�@���̗v���ɉ����ĊJ�����ꂽ�̂��{�Ԃł���A�ԑ̂ɂ�KV-1S���p�����A�C���̂�152mm�ƌ��a�������Ȃ����̖̂C�g������Ⴂ�A�퓬�͂͊i�i�Ɍ��サ�Ă���B
�@KV-2�����ɖ����̂���v�őg�ݗ��Ă��Ă����̂ɑ��A�{�Ԃł�KV-1S�̑啿�̎ԑ̂��]�T���������鎖���ł������߁A�^�p���́u��r�I�v�ǍD�ł������B
�@�S�|�e�ȂǂƈႢ�A�ђʐ����d�����Ȃ��֒e�C�Ƃ͂���152mm�Ƃ����C�e�͋ɂ߂č����Ռ���^���鎖���ł��A�h�C�c�鍑�R�d��Ԃɑ��Ă��Η͂͗L���ł������B
�@�h��ʂł͊��ɑ��b�s�����w�E����Ă���KV-1S�Ɠ����̑��b�ł��������߁A���̖ʂƁA�ԓ��̃K�X���C���ꕔ��肭�����Ȃ������_�͉��P�ł��Ȃ������悤�ł���B
�@�h�C�c�鍑�R�̐V�^��Ԃɂ����������Ȃ��Η͂������Ă���������u�n���^�[�v�Ƃ��Ă�AJS-2�ȂNj��͂Ȑ�Ԃ��o�ꂷ��܂ŏd�v�Ȏ������悭�x�����B
�@�Q�[���ł�KV-1S����̉��ǂȂǂŎ�ɓ���鎖���ł��邪�A���\�I�ɂ͐U��킸�A�j���Ƃ͉����������ꂽ�]���ƂȂ��Ă���B
�@�Η͂̓h�C�c�鍑�R�̃e�B�[�K�[���݂������x���v���I�ɒႢ��e�������Ȃ��A�h��͂�KV-1S�ȉ��ƂȂ��Ă��܂����߁A��͓I�ɂ͕]���ł��Ȃ�����ƌ����Ă悢�B
�@SU-122���l���S�Ɏ�̕���ł���A�i����JSU-122�AJSU-152�Ɍq������̂̂킴�킴�i���ߒ��ɖ{�Ԃ��o�R����K�v�͖����A�����ȂƂ��둶�݈Ӌ`�̔������킾�낤�B
|
 |
��ZIS-AA�@�i��ԗ��F���ԁj
�@�\�r�G�g�����ő��O�����ʐ��Y����Ă���Zis-5�g���b�N�����ǂ��A��@�e�����t������ԗ��ł���B�i���̓A�����J�̉�Ђ����Y���Ă����g���b�N�ŁA�R�s�[�i�j
�@���̃g���b�N�̓N���V�b�N�Ȍ`��ō����ȑf�ȃ��g�����̋������̂��������A���̕����Y���͍����̏�����ɂ����A�ύڗʂ�3t�ƕK�v�ȏ�̉^�p�����������킹�Ă����B
�@���R�A�R�������̗��_���������킯�������A�����E�l���̉^����d�Ί�̌�������C���Ƃ��ĕ��L���g���A���̒��ɂ͖{�Ԃ̂悤�ɑ�ԗ��Ƃ��Đ��܂�ς�������̂��������B
�@�{�ԁiZIS-5�Ɖ���j��7.62mm4�A����@�e�����ڂ���A��평���ɂ����Ă͍����ΉA�g���b�N�Ȃ�ł͂̍��@�������������킹�����Ƃ����피�܂Ŋe�n�ŕ��킵�Ă���B
�@���̌�͉��ǂ��p�Ɍb�܂�Ȃ��������Ƃ���A������苟�^������ԗ��E��Ԃɏ��X�Ɍ�サ�Ă��������A�ȈՂȑ�ԗ��Ƃ��Ă͑傫�������������ނł͂Ȃ��낤���B
�@�]�k�����AZIS�n�ԗ��ɂ͊����ނ�����A��Ί�͂܂��܂��Ŏ������͏��̂��߁A���̎Ԏ킪���ꂼ��ǂ̂悤�ɓ]�p���ꂽ���M�҂̋����͐s���Ȃ��B�iZIS-1x�A42�n���j
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��瑦���Y���\�ŁA��R�̎��������\�r�G�g�R�ł͕K�{�ƌ��镺��ƂȂ��Ă���A���R�ɂƂ��Ă͋M�d�ȑ�Η͂ł���B�i25mmAA�Ȃ̂ŋ��炭ZIS-1xAA���j
�@�ړ��������u���֘H�v�̂��߈��H�ɂ͎ア���A�R�X�g�͔j�i��250�A�@���͂�8�A���x�̒Ⴓ������ΑΒn�Η͂܂ł���ƌ����A����Ӗ��\�r�G�g�̕|���E���ʂ������ƌ����Ă悢�B
�@�i�����ZUS-37�ŁA��̎g������ቺ�ƈ��������ɐ��\���オ�����߂邽�߁A���\����邩�g���������邩�A���ۂɉ^�p���Đi�����邩���Ȃ����f�������B
|
 |
��ZSU-37�@�i���ԁj
�@�{�i�I�Ȏ�������ԗ��������Ă��Ȃ������\�r�G�g�R�́A�D�G�ȃh�C�c�鍑��R���瑽��Ȕ�Q����A�U�X�Y�܂���Ă����B
�@�킪�����킯�łȂ��A�ꓖ����I�ȑ�ԗ��͊�炩�������̂��A���{�I�ɖ{�i�I�ȑ�ԗ������������̂����̌����ł���B
�@���̏�Ŕj���ׂ�����̌v�悪�\�肳�ꂽ���A�ŏI�I�ɂ͎ԑ̂ɑΐ�Ԏ����C�̗��p�A�ΖC�ɂ͑���a��37mm�@�֖C���̗p����A����Ċ����ƂȂ����B
�@�ΖC�̓{�t�H�[�X���ƌ�����������З͂͏\���ł��������A�\�r�G�g�̎�_�ł�����d�q�@��̎コ���炩�C������̐���͎キ�A�@�q�Ƃ͌����Ȃ������悤���B
�@���Y�䐔�����Ȃ��A�����I�Ɍ����ꍇ�̃|�e���V�����͂���قǍ����Ƃ͌����Ȃ��������A�M�d�ȑ�Η͂Ƃ��Ďg�p����A�������N�Ԏg�p����Ă���B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɂ��������铖����ɓo�ꂵ�AZis AA����̐i���A�������͑����Y�Ŏ�ɓ���B
�@�\�r�G�g�R�ł̃v���C���͑�ԗ������ɏd�v�Ȃ̂����A�V������Zis AA�������E�D�G�Ƃ������ƂŖ{�Ԃ̑��݈Ӌ`�͂�┖���B
�@Zis AA�ɔ�ׂ��ꍇ�A�����I�ɂ͊m���ɋ����Ȃ�̂����A���ڍU���̎d�|���₷���ɉe������ړ��͂��ቺ���Ă��܂��_���l�b�N�ƂȂ�B
�@�����ȂƂ���A�ǂ�����^�p���Ă��卷�Ȃ����߁A�v���[���[�̍D�݂łǂ�����^�p���邩���f���Ă��܂�Ȃ����낤�B
|
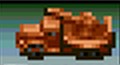 |
��IAG-10AA�@�i�������˖C�@�����炭YaG-10AA�j
�@���M�҂��v���ɂ����IAG�łȂ����O���琶�Y����Ă���YaG�̎��ł͂Ȃ����Ǝv���A����Ă����O��Ƃ��ċL�q���s���B
�@YaG-10�͓����̃\�r�G�g�ł����Ƃ���^�̃g���b�N�ŁA��ʂł͂Ȃ��������̂̑��O������ɗʎY����Ă���8t�g���b�N�ł���B�i�m��300������Ƃ̐��Y�䐔�ł������Ǝv���B�j
�@���̎�����\�r�G�g�͓S�|�Z�p�ɗD��Ă������A���R�E�R�ċ@�ւȂǂ̋Z�p�͂܂��܂����n�ł��������߁A�ꕔ�̕��i�͊O�����i�A�����J�Ȃǁj�ŁA�R�s�[�Z�p���g���Ă����B
�@���Ƀ\�r�G�g�炵�������Ŏ��f�ȊO�ς̃g���b�N�ł��������A�L���ύږʐς�8t�Ƃ����ύڗʂ͎��p���ɗD��Ă������߁AM1931�^76mm��C�𓋍ڂ�������C�����ꂽ�B
�@���m�Ȏ��������Ȃ����߂͂�����Ƃ͌����Ȃ����A���̃g���b�N�̐��Y�䐔�����Ȃ������ɁA�{�ԂւƉ��ǂ��ꂽ�ԗ���100���Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���ƕM�҂͍l�@����B
�@���R�ɂ������̕s���ȗ��ꂩ��ڗ����͖����������A���̑��݂���\�r�G�g�R�ł��������l��������ƒn��Η͂̌���������Ă��������f���邾�낤�B
�@�Q�[�����ł͐i�����Lj�ؖ����A�����Y�݂̂̂Ƃ����o������Ȃ̂����A�\�r�G�g�R�j���L�����y�[���ł̓v���[���[�ɐ����������邽�߂����Y�s�ƂȂ��Ă���B
�@����āA�X�^���_�[�h�A���z�L�����y�[������̕���ƂȂ��Ă���A�j���L�����y�[���Ŏg���Ȃ����A������ł͋@���́E�˒����������ď�肭���p���Ă��������B
�@�����A�����@���́A���˒��A�\���ȉΗ͂Ǝg�������Ă͋ɂ߂č����A��ɉ^�p����������ł��邪���߂Ɉꕔ�������������Ă���_�������ɂ��܂��B
|
 |
���J�`���[�V���@�i�����֒e�C�F���������P�b�g�C�j
�@�h�C�c�鍑�R�̉^�p����l�[�x�����F���t�@�[�̗L�����A�L�͈͂ɂ킽�鐧���͂�g�������Ēm�邱�ƂƂȂ����\�r�G�g�R�́A���R�ɂ������������{�Ԃ��J������Ɏ������B
�@�{�Ԃ̓����͋��낵���܂łɊȈՉ����ꂽ�\���ł���A�Η͓I�ɂ���x�ōő�16���̃��P�b�g�e�˂ł���Ƃ��������Ƃ��Ă͌��O��ȋ��͂Ȃ��̂ł���B�iBM-13�^�j
�@�ȗ����̓x�����͂����܂����A���x�ȓd�q�@���Ə��@�͈�ؓ��ڂ��Ă��Ȃ����߂ɖ������͗�邪�A�{�Ԃ��甭�˂���郍�P�b�g�̉J�̓h�C�c�鍑�R�ɋ��|��A�������B
�@�\�r�G�g�R�ł́u�J�`���[�V���v�i���̌o�ܕs���j�A�h�C�c�鍑�R����͓Ɠ��̉�����u�X�^�[�����̃I���K���v�ƌĂ�A���ɃJ�`���[�V���͓��������̃��P�b�g�C�̑㖼���ƂȂ����B
�@�Ȃ��A�{�Ԃ̎c�������т͔��ɑ傫�����̂ŁA����ɂ����Ă����W�^�E�i���^�̎q�������푶�݂��A����z������Ă���B
�@�Q�[�����ł͔�r�I�������琶�Y���\�ł���A�R�X�g�����Ɉ����ŁA�i���E���ǂȂ��̎g���̂ă��j�b�g�Ƃ��ēo�ꂷ��B
�@�{�Ԃ̍ő�̕���́u�ړ���̊ԐڍU�����\�ł���v���Ƃł���A�ړ��͂��ő���ɗ��p�����˒������̓A�����J�̃����O�g����C�ɕC�G���邾�낤�B
�@�U���͓I�ɂ͈�ʓI��105mm��C�Ƒ卷�͖������A��L�̃����b�g����K�v�Ȏ��ɂ�2�A3���j�b�g���Y���A�ϋɓI�ɉ^�p�������B
|
 |
��76mm AA�C�@�iM1931 76mm���˖C�@�������˖C�j
�@�\�r�G�g�R�ɂ���ĉ^�p���ꂽ���˖C�ł��邪�A�������̓h�C�c�鍑�̃��C�����^���Ђł���A�����Ȍ_��ɂ���đ������瓱�����ꂽ�C�ł���B
�@�J�������J���������ɐ��\�E�ˌ������͗ǍD�ŁA�{�C�͖�6.6kg�̖C�e��9,000m�ȏ�ł��グ�鐫�\�������A�����������̍��˖C�Ƃ��Ă͏\���Ȑ��\�ł������B
�@�C�g�̒���(L55)�������{�鍑�R�ȂǑ������N���X��퍂�˖C�Ƃ̔�r�ł͏d�ʂ������������A�����ł͏���A�A�����ˑ��x�������ƉΗ͖ʂł͗D�G�ł���B
�@�����ȖC�ɔ�ׂ�Ƌߑ�I�ȍl�������Ȃ��荞�܂�Ă���A��Ƃ����炷���߂̈ꕔ�������A�L�߂̋�p�A�S�����̐����ˌ����\�ȂǑ����̎v�z�����荞�܂ꂽ�B
�@���Y���͑����������̂́A�h�C�c�鍑�R�̏����̖ҍU�ɂ�肩�Ȃ�̐����j��Ă��܂��A���nj^���V�^85mm���˖C�̉e�ɉB��Ă��܂��������犈��̘b�͑����Ȃ��B
�@�C���̗��x���Ⴉ�����A�h�C�c�鍑�R�̐i�R�����������A��p�̊J�������������A�ȂǂȂǎ�芪�����͂��܂�Ɉ����A���������}�V�ȉ^�p������Ă���Ɖ���܂��B
�@�Q�[���ł͈�ʓI�Ȍ������˖C�Ƃ��ēo�ꂵ�A�I�[�\�h�b�N�X�Ȑ��\�ŕȂ̖����C�ƂȂ��Ă���A��͂ɗ�铯��R���T�|�[�g����d�v�ȉΖC�ł���B
�@�j���L�����y�[���ł͎������˖C�̐��Y����������Ă����O�A�{�C���g�����ɂȂ邪�A��ʓI�ȍ��˖C�Ɠ����悤�ɑ҂������A���_�ւ̓����ȂǏ�肭�g���Ă��������B
�@�i�����85mmAA�C�Ƒ���a�C�ɂȂ邪�A���\�͎v�킵���Ȃ�����̉��Ƃ����悤�Ȋ����ł��邽�߁A�i�������邩�ǂ����̓v���[���[�̍D�݂ɂ��B�i�M�҂͐i�������Ȃ��B�j
|
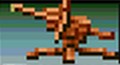 |
��85mm AA�C�@�i52-K M1939 85mm ���˖C�@�������˖C�j
�@�����^�p���ł�����76mm���˖C�̐��\�ɉA�肪�����n�߁A���ǂ��s��ꂽ�����ʂ͎v�킵���Ȃ��A��苭�͂ȉΗ͂����߂�O������̐��ɓ����邽�߂ɍ̗p���ꂽ�C�ł���B
�@���ǂ̊����76mm M1938�̐��\������قǏオ��Ȃ�������������A���a��85mm�A�C�g��L55�Ə\���Ȕ\�͂��m�ۂ���A�h�C�c�鍑�R��88mm
Flak 36�ɕC�G����\�͂ł������B
�@�{�C�͖{���̊�������邱�ƂȂ���A��ʓI�ɂ͓]�p���ꂽ�C�̊��L���ł���A�Βn�p�ɉ��ǂ��ꂽ���̂�T-34/85�ASU-85�쒀��ԂȂǂɓ��ڂ���A�҉�^���Ă���B
�@�ΖC�Ƃ��Ă͎˒���10,000m�ȏ�A76mm��C�����̋�p�E�@�\�������Ă��������瑼���̏�ʍ��˖C�Ƒ��F�Ȃ��������A�B��A�A�����ˑ��x�ł͎����Ă����B
�@�\�r�G�g�R�ł͋ɂ߂đ傫�Ȑ������c�����C�ƌ����Ă��悭�A�{���̑�C�Ƃ��āA���ǂ���Βn�C�Ƃ��Đ��b���Ȃ����A�ꕔ�̖C�͌���ɂ����Ă������Ƃ�����������B
�@��b�I�Ȕ\�͂̍����A�^�p�̂��₷�����炩��풆�Ƀh�C�c�鍑�R���b�l�������̂͂��̂܂܂��̐�́i85mm Flak M39(r) �j�Ƃ���A���ɂ����Ă����������ɍL���L�߂�ꂽ�B
�@�Q�[�����ł�76mmAA�C����̐i���Ŏ�ɓ���鎖���ł��邪�A���\�̌���͎v�킵���Ȃ��A�t�Ɏ�̉����Ă��܂��ʂ����邽�߈����̓���C�ƂȂ��Ă���B
�@�g�������Ă͈�ʓI�Ȍ������˖C�Ɠ����ł͂��邪�A�i�����Ƃ̔�r�ł͔\�͂ɑ卷�͖����A�ʂ����Đi��������Ӗ������邩�ǂ������܂��]���ɕ����ԁB
�@��ɏ�ʂ̕���ŕ��������낦�Ă��������Ȃ�ΐi�������Ă����͖������A�����̃v���[���[�ɂƂ��Đi�����ē���قǂ̉��l�͂قƂ�ǖ������낤�B
|
 |
��122mm��C�i�\�r�G�g�j�@�iM1931/37 122mm�J�m���C�@�����֒e�C�j
�@���O��苌���Ȗ�C�̍X�V���s���Ă����\�r�G�g�R�ɍ̗p����A�̗p��͑�풆�E��������i���^�p���ꂽ���e���ł���B
�@�Ȃ��A�N��ɂ����1931/37�ȂǂƖ��̂���Ⴄ���A����͑�G�c�Ɍ����Ό��������̈Ⴂ�ɂ���Ĕ��ʂ��\���B�i������ɍו�������Ƒ���_�͑����B�j
�@��C�Ƃ��Ẳ^�p�͓��R�Ƃ��āA���͂ȉΗ͂��������������x���A�v�ǍU�߂ɂ��^�p����Ă���A�������̌�����������y�����ʂł̌��������܂Ŋ�p�ɂ��Ȃ����B
�@�O���^�C�v�ł͍\����̗��R���������ɓ���������̂́A����^�C�v�ł͂�������P����A�����̐��ɓ����E�g�p����Ă���B
�@�܂��A�C�e�̓����ɂ���č����Η͂��������킹�A�ΐl�͂��Ƃ��e�B�[�K�[�A�p���^�[�Ȃǃh�C�c�鍑�R�̌ւ��Ԃ�����������ђʂ��\�ł������ƌ����B
�@�Q�[���ł͑����Y���\�ƂȂ��Ă���A�����̕W���I��105mm��C�ɔ�ׁA�ΉE�˒��E���x������ɂ����Ă���i��̖�C�ƂȂ��Ă���B
�@���̃X�y�b�N�́A����a�E��Η͂��D��Ŏg�p����\�r�G�g�̃C���[�W�����̂܂ܖ�C�ɂ��������ł͂Ȃ����낤���B�i�M�҂̕Ό��܂ށB�j
�@������ア�Ƃ���͑�����C�Ƃ���قǕς��Ȃ����A�O�q�̓��������Ȃ�֗��ł��邽�߁A�\�r�G�g���g���Ȃ�ΐ����j�b�g�͍����Ă��������B
�@�i�����152mm��C�ƁA����������͂Ȗ�C�ł���A���ߑ��߂̐i����S���������Ƃ��낾�B
|
|
���\�r�G�g�R�����@�i�����j
�@�\�r�G�g�̕��������͈�ʓI�ɑ_�����ƌĂ�A���̑_����������т��d�˂����̂��e�q�ւƏo������`�ɂȂ�B
�@�\�r�G�g�͘A�M�`�Ԃ��Ƃ��Ă������Ƃ�����A�����͑����̐l�킩��\������鎖�����������B
�@����Ȓ��ł́A�����镺���m�̌��t���ʂ��Ȃ��Ƃ����������X�������悤���B
�@�܂��A�Љ��`�Ƃ������Ƃň�ʕ��̒��ɊĎ��������ꍞ��ł�����ƁA��ʓI�ȌR�Ƃ͏��X�F������������悤�ł���B
�@�Q�[�����ł͎�ɑ_�����A�@�B�������A�e�q�ԌR�����A����ɓ������A�X�L�[�����������B
�@�Љ��`�I���l�ςɂ�����l���̌y���A�S�苭�����R�f���Ă��A�����̕���������ł͂��邪�d�߂ɐݒ肳��Ă���悤�ł���B
�@�B�x�����_������n�`���ʂ̍����ꏊ�ɍ\����A������Ƃ����ǂƂȂ�B
�@���܂��g���������j�b�g�̈�ł��낤�B
|
|
���_�C�����[�@�i���b�ԁj
�@��@�^�_�C�����[�i�f�B���S�j���g�����ǂ��A������x�̐퓬�\�͂�t�^���邽�߂Ƀe�g���[�N�Ɠ�����2�|���h�C�𓋍ڂ����ԗ��ł���B
�@���̒�@�^�̑f�s�͗ǂ��A�T�X�y���V�����ɓƗ����˂�p���Ă������ƂƁA�Ⴂ�M�A��ɂ���Ĉ��H�ɋ����g���N�鎖���o�������߁A���̎�Ƃ��Ă̑����͋ɂ߂ėD�G�ł������B
�@��C�̉Η͂͂���قǍ����Ƃ͌����Ȃ��������A�{�Ԃ̎�C������@�A��q�A�y�퓬�ł��鎖���l������ΕK�v�\���ȉΗ͂ŁA�����I�ȃo�����X�͐▭�ł������ƌ����邾�낤�B
�@���ɑ����͑�ϗD�G�ŁA�傫�ȏՌ��������łقƂ�ǂ��z���ł���قǂł���A���̂��Ƃ��牢�B��������łȂ��A���H�ȃA�t���J�A�A�W�A���ʂւ������C���ɏA���Ă���B
�@�O�ς�������C�M���X�R�����ӂ̊Ԃɍ��킹�̑��b�ԂȂ̂��낤�Ƒ唼�̐l���v���̂��낤���A�{�Ԃ͂��̊O�ςƂ͗����ɋɂ߂č����^�p���E��b���\�����������b�Ԃ������B
�@�ׂ����s��̉��ǂ��ϋɓI�ɐi�߂��A���ɗD�ꂽ���b�Ԃł��������Ƃ������������g���Ă���A���b�ԂƂ��Ă̈�̂�������ɓn���Ď����������B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��瑦���Y���\�ŁA�o�ꂷ��N����l����ƈړ��́E�ΉE���G�\�͂̂���������\���Ȕ\�͂̑��b�Ԃł���B
�@������ł���コ�͂ǂ����悤���Ȃ����A�R�X�g�͔��Ɉ������Q���C�ɂ�����ʂɎg����_�͍��]���ŁA����ɑ����o����_���n���ɕ֗����B
�@�i����̓n���o�[III�ƂȂ邪��̉��Ƃ��������������߁AAECIII�������Y�ł��鎞����҂��A��C�ɂ�����ɐ�ւ����ق����ǂ���������Ȃ��B�i��AECIII�͑�Η͂Ȃ��j
|
 |
���n���o�[III�@�i���b�ԁj
�@�K�C�Ђ̐��Y���C����肩�琶�Y��~�ɒǂ����܂ꂽ�K�C���b�Ԃ̌�p�Ƃ��ă��[�c�Ђ��J�����A�ʎY��͑����̐���ɑ��荞�܂ꂽ�V���b�Ԃł���B
�@�V�Ƃ͂����Ă���b�����̓K�C���b�ԂP�����v�ƂȂ��Ă���A�����^�͂قڂ���Ɠ����ňႤ�_�̓G���W�����x�A����^�ł͐V�����A�X�Α��b�Ȃǂ�������Ղ��_�ł��낤�B
�@�G���W����4�C������6�C���Ɋ���������ŋ@���͂͑O�C�𗽂��A�H�ʂ���r�I�ǍD�Ȃ�Ύ���70km/h����@���o��������L���͈͂�C������ԂƂ��Ĕ��ɗL�p�ł������B
�@�����^��15mm�@�֖C�ȂǕ����͑O�C�Ɠ������������A����^��37mm�C�����ڂ���Η͂�������A���̌^�͉ΉE�@���͂̃o�����X����{�Ԃ̌���łƂ�������B
�@�ԑ͔̂�r�I���ǂ��{���₷�����̂������炵���A�{�Ԃ̈ꕔ�͔��ɑ傫���ˊp���������a��7.92mm�@�e�������ւƊ�������A��ԗ��Ƃ��Ă��^�p����Ă����B
�@�X�̐��\�ɓˏo���������̖����Ԃł͂��邪�A���p�ʂő傫�����_�͂قƂ�ǖ����A���m�B�ɂƂ��Ă͈�ʐl�ɂ�����u��O�ԁv�I�ȎԂ������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�Q�[���ł͗�ɘR�ꂸ�����Ȓ�@���j�b�g�Ƃ��ēo�ꂵ�A���Ղ̓_�C�����[����̐i���A��Ɏ��@�����ɂ�鑦���Y�Ŏ�ɓ���B
�@�o�ꂪ�}�[�NIII�ł��邽�ߕ����͋@�֖C�d�l�ƂȂ��Ă���A���ł�����ɉΗ͂͒Ⴍ�A���b������������u�퓬�v�ԗ��Ƃ��Ă̔\�͂͂قƂ�NJ��҂ł��Ȃ��B
�@�i�����AECIII�Ő퓬�\�͈͂�C�ɏオ�舵���₷���Ȃ邪�A���\�͂������Ȃ邽�߁A�{�Ԃ��^�p���Ă���Ȃ���̓_���ǂ��l���邩�Ői���f�������B
|
 |
��AECIII�@�i���b�ԁj
�@�����ԃ��[�J�[��AEC�Ђ��J���E���Y���s�����C�M���X�R�̎l�֑��b�Ԃł���B
�@���X�A�R�ɂ�锭���ł͂Ȃ��AAEC���Ǝ��Ɍ����E�J����i�߂Ă������̂ł��邪�A�߉q�R���̎��T���ɓW�����ꂽ���̂����̎A�`���[�`���ɂ���Ď��グ��ꂽ�B
�@��ւ��ɂ��O�쓮�E�l�쑕�b���\�ł���A�g���N�^�[�����̑�^�^�C���͍U��ɂ킽��L���ȋ@�����̊m�ۂɍv�������B
�@�Η͂ɂ��Ă�AEC�̕��j�ɂ��A�V���[�Y���Ƃ����ď�ɑ�Η͂̂��̂��̗p����Ă���A��C�͏����^��40mm�C�A����ł�75mm�C�Ƒ��b�ԂƂ��Ă͔j�i�̉Η͂����B
�@���Y�䐔�͏����ƌ����Ă������A���b�ԂƂ��Ă̋@���́E�Η͂͋ɂ߂č����A�U��̃o�����X�͑����I�ɗD�ꂽ���̂ł������B
�@�ɂ��ނ炭�́A�h�䐫�\�̍������痈�鑕�b����A�傫�ȃ^�C���Ƒ�^��C���ڂ̂��߂ɑ����b�Ԃɔ�ׁA��ԑ̂��傫���Ȃ��Ă��܂����_�ł��낤�B
�@�Q�[���ł͑O�����琶�Y���\�����A�j���̐��Y�䐔�f���Ă��r�����琶�Y�o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@����đO���ɏd�_�I�ɐ��Y���Ă������ƂɂȂ邪�A���̎��_��75mm�C�i���x18�j�����ɓ��ڂ��Ă��邽�߁A���b�ԂƂ��Ă͐\�����Ȃ����\�ƂȂ��Ă���B
�@�C�M���X�R�̕��Ȃł͑��b�ԁA�y��Ԃ̃J�e�S���ɑ�������̂͑����Đ��\�����[�Ȃ��̂��������A�B��A����͂Ƃ��ē����ł���{�Ԃ͋M�d�Ȑ�͂ɂȂ邾�낤�B
�@�܂��A�㔼�ɂ͑O�q�̂Ƃ��萶�Y���o���Ȃ��Ȃ邽�߁A���Y�ł��邤����2�A3���j�b�g�̓X�g�b�N���Ă��������Ƃ���ł���B
|
 |
�����[�J�X�g�@�i�y��ԁF����ԁj
�@�J���̓A�����J�ł��邪�A���̃A�����J�ł͐퓬�p�Ƃ��Ă͍̗p���ꂸ�A���^���ꂽ�C�M���X�ɂď����������ς��̌y��Ԃł���B
�@�{�Ԃ́A�����Ƌ��ɋ@���I�Ɏd�|�����P�퐏����ړI�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂́A���̉^�p�v�z�ɂ͓���ς�������̂łȂ��X�y�b�N�ł������B
�@���̑傫�ȗ��R�Ƃ��āA�A�����J�R�ł͖{�Ԃ𓋍ڂł���O���C�_�[�������Ă��Ȃ����������������邪�A�d�ʓI�A�@�B�^�p�I�ɂ���̂��镔���������B�i�A�����J��ρj
�@����A�{�Ԃ����̂܂ܓ��ڂł����^�O���C�_�[��ۗL���Ă����C�M���X�R�ł͖{�Ԃւ̋��������܂�A�A�����J�ւ̗v�]�������ċ��^�Ɍ��т��Ă���B
�@�Ȃ��A�C�M���X�R�̑�^�O���C�_�[�ɂ���Ď��H��������Ă��邪�A�����d�˂Ďg�p����鎖�͖����A�����Ƃ����Ĉ�x����̎��H�Q���ł������ƌ����Ă���B
�@�J�^���O�l����@����Ɍy��ԂƂ��ĕ����E�@�����͏\���ł����������b�ɗ�邽�߁A�^�p�̎�ԂƔ�Q�\�z���v�Z����ƐϋɓI�ɓ������ɂ��������ƍl�@�ł��邾�낤�B
�@�Q�[�����ł͏I�ՂɃX�`���A�[�g�n����̐i���܂��͑����Y���\�ŁA�ŏ�ʌy��ԂƂȂ���̂́A�X�`���A�[�g�ɗ��_�������A�ǂ��_�̂Ȃ��y��ԂƂȂ��Ă���B
�@�v���I�Ȃ̂͋@�e�ɂ��؋�U���͂̑r���ŁA�퓬�@�ȂǍq��@���Ј��E�����ł��Ȃ��Ȃ������͋ɂ߂đ傫���}�C�i�X�_�ƂȂ邾�낤�B
�@�R�X�g�I�ɂ͈����ŁA�I�Ղł܂Ƃ��ɒ�@�̂ł��闤�テ�j�b�g���{�Ԃ����Ȃ����Ƃ���A�u�d���������̂Ŏg�������Ȃ��v�ƌ����ʒu�t�����������]����������Ȃ��B
|
 |
��A9�iCS�j�@�iMk.I���q��ԁ@����ԁj
�@�C�M���X�R�̃��B�b�J�[�XMk.I�AMk.II��Ԃ̌�p�Ƃ��č̗p���ꂽ��Ԃł���A���E���Q�ɂ��o�ς̒����s�̗p�Ƃ��ꂽA6��Ԃ̗�������ގԗ��ł���B
�@�{�Ԃ͓��͂ɂ�����C���i�������j�A�����ɓƓ��Z�p���p������ȂǑ傫�Ȑi��������ꂽ���A�G���W���͈�ʌ������nj^���̗p�����ȂǁA�u���J���̐�ԁv�Ƃ͌�����B
�@�V���̋Z�p�����݂��邢��u�ߑ�ɂ�����{�i�I�Ȑ�Ԃ̈����O�v�̐�ԂŁA���R�ɂ����鍡��̐�Ԃ̂�����m�Ɏ��������A�{�Ԏ��̂̐��\�͎v�킵���Ȃ������B
�@��C�͓����ŐV�s��2�|���h�C�i40mm�j���̗p����Α��b�Η͂͏\���ł��������A��͂�Ƃ��������ǂ���֒e�����ĂȂ�������CS�^�i�֒e�C�^�j�����Y����Ă���B
�@A6���R�X�g���ɂȂ錩���݂ł���������A9�͂��̖ʂ��l������A��r�I�����ȃR�X�g�Œ��B���\�ƂȂ������A���̂��������b�͔����U��̃o�����X�͗ǂ��Ȃ������B
�@��̕��ނł͏��q��ԂƂ��ċ敪���ꂽ�����j���͗ǂ��Ƃ͌������A�����I�Ȑ��\���U���Ȃ��������Ƃ��琶�Y�䐔�����Ȃ��A�����ʼn^�p���ꂽ���Ԃ͒Z�����̂������B
�@�Q�[���ł͏��Ղ��瑦���Y�ł��钆��Ԃł��邪�A���̒ᐫ�\�Ԃ�A�����Ȑi����A�����ȉ���Ղ�͒���ԂƂ��������y��Ԃɋ߂��B
�@�����ē�������A9�AA9CS�AA10�����Y�\�Ƃ�������Ӗ��a�V�ȕ������C���i�b�v�ƂȂ��Ă���A��폘�Ղɂ����铯�R�̐�Ԏ�ʁE�Ǘ�����荬���ɒ@�����ށB
�@�i����A13�n�ւƂȂ��邪�A��X���Y�o����A�����J�n��Ԃ�������̎�͐�ԂƂȂ铯�R�ł́A�{�n��͂قڕK�v�Ȃ���������Ȃ��B�i�K�v�ł��N�����E�F���������x���j
|
 |
��A13Mk2�iCS�j�@�iMk.IV���q��ԁ@����ԁj
�@Mk.III���q��Ԃ̑��b���莋���Ă����C�M���X�R�ł́A��葕�b�������A������Ɠ����x�̑��x���o���鏄�q��Ԃ�~���Ă����B
�@�����葁��Mk.III��Ԃɒlj����b���{���������s�����Ƃ���A�lj����b�ɂ��d�ʂ̑����͂��قNj@�����ɉe����^���Ȃ����Ƃ��킩��A�����Mk.IV�Ƃ��Đ����̗p�����B
�@��{�I�ɑ傫�ȉ��ǂ͎{����Ă��Ȃ����A�r�������̕����̕ύX���s���A�ΐl�Η͂̋����Ȃǂ��{����Ă���B
�@�傫�ȓ����͖C���Ɏ{���ꂽ�lj����b�ł���A���тȌ`�ƂȂ������̕����͓����ɋ�Ԃ����������A��e���̏Ռ������炰����ʂ����҂��Ă����B
�@���̒lj����b�̌��ʂ͕s���ł��邪�A�����̃t�����X��A���̌�̓A�t���J����Ȃǂ֑����ē�������Ă��鎖����A������x�̌��ʂ͂������̂�������Ȃ��B
�@�֒e�����ĂȂ���C��֒e�C�ɕύX����CS�^�Ȃǂ����݂��A���Ȃ��Ȃ��������̉��nj^�����݂���B
�@�Q�[�����ł͏��Ղɉ^�p���鎖�ɂȂ邪�A�ᐫ�\�Ői���\�ł̃��C���֒͞e�̌��Ă�uCS�v�ƂȂ��Ă���A������ԂƈقȂ���������Ȉ����ł���B
�@�i������A9CS�i�֒e�^�C�v�j�A�i����͔�r�I���ʂ̐�Ԃł���N�����E�F���ƁA��́E�쒀��ԁH���݂Ƃ����_�����̌n���̐i���E���ǂ���藝�����ɂ������̂Ƃ��Ă���B
�@�C�M���X��͐�Ԃ͍��Y�n�E�A�����J�n��2�n�����������A������������悤�Ȑ��\�̏�ɈႢ�����m�ɂȂ�̂͒��Չ߂��̂��߁A�O���ł̐i���E���ǂ͍l���Ȃ��ق����ǂ����낤�B
|
 |
���N�����E�F�����q����@�i����ԁj
�@�C�M���X���L�̋@���͂��d���������q��Ԃ̂�����1�ł���A���͎̂O�����푈�Ɋ����l���ɗR������B
�@��������G���W���͐퓬�@�ɍ̗p����Ă���~�[�e�B�A�𓋍ڗ\��ł��������A�퓬�@��D�搶�Y����W����\�͕s���̑��G���W�����ꎞ�I�ɍ̗p���ꂽ�B
�@���ʓI�ɓo�ꎞ����ݑ��A�Η͕s���A���b�s���ƕs���ȗ���ɂ�����Ă��܂����B�i�ԑ̃T�C�Y�̊W����17�|���h�C�̓��ڂ��s�ł������B�j
�@�\����̖{��Ԃ�1��̃e�B�[�K�[�ɑS�ł�����ꂽ�G�s�\�[�h��A�����^�̓G���W���̊W��A�Z�p�I�ȐM�������Ⴉ������Ƃ��܂�ǂ��Ƃ���̂Ȃ���Ԃł���B
�@�������A����^�C�v�ł̓G���W�����{���̂��̂֊�������A�o�[�W�������オ�邽�тɒlj����b���{���ꂽ�B�i�G���W�������ɔ������n�̃Z���g�[����̋@��ύX���܂܂��B�j
�@�ŏI�I�ɂ͋@�B�I�ȐM������������ƂƂ��ɁA���E�ő����x���̋@�����鎖�ɐ������A�͕s���Ȃ�����C�M���X�R��͂̈ꗃ���߂Ă���B
�@�Q�[�����ł͗D�ꂽ�������Ȃ��A��͂��镔���̑����}�f��Ԃ�1�ɂ����������A�ő�̓����ł������@�������ړ�5�ƗD������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@�o�ꎞ������s���C���̉ΉE���x�͒v���I�ŁAIV����ԑ���ɂ��s���A�p���^�[�E�e�B�[�K�[����ɂ͊��S�ɕs���ƌ������킢���������邾�낤�B
�@�i������R���b�g�i�`�������W���[�j�ƏI�Ղɂ͂�◊��Ȃ���ԂƂȂ��Ă���A�o�[�W�����Ⴂ���낭�ɖ�������Ԃ�͂��͂�C�̓łƎv����B
|
 |
���`�������W���[���q����@�i����ԁj
�@�x�d�Ȃ�D�G�ȃh�C�c�R��ԂƂ̐킢�ŁA���˒��̒����ΐ�ԉΗ͂�K�v�Ƃ��Ă����C�M���X�R�����s����̏�ɊJ������17�|���h�C�𓋍ڂ�����Ԃł���B
�@�ԑ̂ɂ̓N�����E�F���n�̂��̂����̂܂g����\��ł��������A���ڂ���V�^17�|���h�C�͂��̎ԑ̂ɂ͂��܂�ɂ��傫�����A���ǁA�ԑ̂͊g�����ǂ���Ďg��ꂽ�B
�@�ȑO���Η͕s���ł�������Ƀe�B�[�K�[�A�p���^�[�̏o���ł���ɉΗ͕s�����[���������C�M���X�R�ł�17�|���h�C�𓋍ڂ����{�Ԃ͑Җ]�̂��̂ł���A��͋����ɍv�����Ă���B
�@�C���̌`������킩��悤�ɁA���Ȃ薳���Ȑv�ŖC���ڂ����Ă���A�h��ʂŕs���ȓ_�͔ۂ߂Ȃ���A�@���͂Ȃǂ̑����I�Ȑ��\�������č������̂ł͂Ȃ������B
�@�����A�����I�ȉΗ͕s���ŏ�ɋٔ����Ă����O���ł͎����O�̍����Η͂͊��A���̂��Ƃ��猈���Ĉ����ʂ���ł͂Ȃ�������������������B
�@�A�����J���狟�����ꂽ�V���[�}���A���̉��ǎ�t�@�C�A�t���C���D�G�ł��������߁A�{�Ԃ͏������Y�őł���ꂽ���A�Η͕s���ł����������̃C�M���X�R���悭�x������Ԃł������B
�@�Q�[���ł͒��Ձ`�I�Ղ��{�Ԃ̓o�ꂷ�鎞���ł���A�N�����E�F������̐i���A�����Y�œ��邱�Ƃ��ł��A�o�ꂪ���x���ޖ��͂�⑁���Ƃ����Z���I�ȕ���Ƃ��ēo�ꂷ��B
�@�p���^�[�����̉Ήi105/22�j�������̖̂h�䐫�\�͒Ⴍ�A�搧�ł��Ȃ��퓬�ł͋ɒ[�ɕs���ȏ�ԂƂȂ�g�����̓����Ԃł��邪�A�����Η͂䂦�ɐ��ɂ͉����Ă��������B
�@��C�e�������Ȃ��h�䐫�\�͒Ⴂ�A�Ǝg���̂Ăł��銴�͔ۂ߂��A�K�v�Ȏ����ɕK�v�Ȃ����^�p�����̌�͑��ޖ��Ƃ����g��������ԗǂ����낤�B�i�i��������[�Ȑ��\�̃R���b�g�j
|
 |
���t�@�C�A�t���C�@�i����ԁj
�@�e�B�[�K�[�Ƃ̐퓬�ŁA���R��Ԃ̉Η͕s����Ɋ������C�M���X�R�́A�V�^��17�|���h�C�𓋍ڂ����Ԃ̊J���𐄂��i�߂鎖�ƂȂ�A�{�Ԃ̓o��͂��̌v��ɂ����̂ł���B
�@�������ɂ̓`�������W���[�������悤�ɊJ������Ă������߁A��x�͊J�����L�����Z������Ă��邪�A����Ԃ̐��\���v���������ǍD�Ȃ��Ƃ����]���ĊJ���E���Y���n�܂����B
�@��C��17�|���h�C�͉Η͏\���ŁA�{�Ԃ͗L���ȕ���ł͂��������A�������Y���s�������̎��Ԃ͂Ȃ��Ȃ������A�܂Ƃ܂�����ʐ��Y�ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�@�܂��A�ԑ̂̓V���[�}�����̂��̂ŁA�d��Ԃƒ��ڐ퓬���o���邾���̔\�͖͂����A����̎�̓V���[�}���ɕ⏕�t�@�C�A�t���C1��Ƃ������悤�ɁA�Η͎x���ԂƂ��ė��p���ꂽ�B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղɍ����|���鍠�ɉ��ւ���A�V���[�}��IIA����̐i�����\�ƂȂ�A�I�Ղɂ͑����Y���\�ƂȂ�B
�@���\�I�ɂ͑��A���b�ɗ��p���^�[�ƌ������Ƃ���ł���A�Η͂����Ȃ�Ώ\���Ȑ��\�i���x��22�ƍ����j�������Ă���A���A�����A��Η͂������_�����͒��ӂ������B
�@���x��������A�C�M���X�R�̒��ł̓e�B�[�K�[�A�p���^�[�Ƃ��܂Ƃ��ɓn�荇���鐔���Ȃ����j�b�g�ł���A�����Y�\�ȏ�ԂȂ�A�ϋɓI�ȉ^�p�E�퓬���\���B
�@�ǂ����Ă������d��Ԃɔ�ׁA���b���s���ɂȂ邪�A�����͒n�`���ʂł��܂��J�o�[����A��Q�͂�����x�h���邾�낤�B
|
 |
���R���b�g���q����@�i����ԁj
�@�J�����ł�����17�|���h�C�𓋍ڂ����`�������W���[�͊m���ɉΗ͂͗D��Ă������̂́A�h�䐫�\�E�@���͂Ɍ����A�����I�Ȕ\�͂͗�������̂ł������B
�@���̖��ɒ��ʂ����C�M���X�R�́A���B�b�J�[�X�̐i�߂Ă�����ԊJ���v��ɒ��ڂ��A���̊J���v����㉟�����A���ꂪ�����������邱�ƂƂȂ�B
�@�{�Ԃ́A�N�����E�F���̉��ǎԑ̂ɏ��^������17�|���h�C���̗p�����g�ݍ��킹�I��Ԃł͂��邪�A���̗��҂̑����͐▭�ł���A�������\�͋ɂ߂ėǍD�ł������Ƃ����B
�@�����I�Ȃ̂���C�ł���A�t���T�C�Y��17�|���h�C�ɔ�זC�g���Z���Ȃ��Ă���A����Ɠ����C�e�����p�ł��Ȃ��Ƃ������������āA����17�|���h�C�ł�����ƌ����Ă悢�B
�@���̎�C�̓R���p�N�g�Ȋ���ɑ傫�ȉΗ͂������Ă���A�h�C�c�鍑�R�̃p���^�[���x�̉Η͂��������ƌ����Ă���B�i���x�Ƃ͌����A��͂����Ă����悤�ł͂��邪�j
�@���H�������x��A��펞�̐퓬�ɂ͂قƂ�ǎQ��ł��Ȃ������{�Ԃł͂��邪�A��b���\�̍�������A�������炭�̊ԁA���J���ɂĉ^�p����Ă���B
�@�Q�[���ł͑�햖���ł̓o��ƂȂ��Ă���A�����Y�i���R�X�g���j�A�N�����E�F������̐i���A�`�������W���[����̉��ǂɂē��肪�\�ƂȂ�B
�@�h�C�c�鍑�R�̒��C�g�^IV����Ԃ������i���x�͓���20�j�����悤�Ȑ��\�ł��邪�A����Ԃł��鎖�������āA��햖���̐�ԂƂ��Ă͔\�͕s���ł��銴���͋����B
�@��ʂ̉��ǁE�i�����������߁A�{�Ԃ̉^�p�͎�ł��������ɂƂǂ߁A�A�L���[�Y�Ȃ�17�|���h�C�i105/22�j��������Ԃ����C���ɉ^�p����ق����ǂ����낤�B
|

coffee break |
|
�`�|���h�ƃC���`�`
�@�����m�̂悤�ɃC�M���X�鍑�ł͍��ۋK�i�̃L���A�Z���`�ł͂Ȃ��A�|���h�A���[�h�A�C���`�Ȃǂ̒P�ʂ��̗p����Ă���B�Ƃ͂����Ă��|���h���[�h�̓A�����J�ł��g���Ă���̂����A���[�g�����̊W��A�@�I�ɂ̓��[�g���@���̗p����Ă����B���Ȃ݂Ɍ��݂̓��{�ł̓|���h���[�h�̎g�p�͖@�ɂ���ċ֎~����Ă���B���̒P�ʂ̈Ⴂ�͈�ʓI�ɒP���ȍ�������������A�q��@���̂̌����ɂȂ�����ƌ��݂ł��l�X�ȉe���𐢂̒��ɗ^���Ă��邪�A���ɂ���Ă͓���I�Ɏg���Ă���P�ʂł����邽�߁A������o�������݂�������̂��낤�B�i���݂̃C�M���X�ł͖@�I�ɍ��ۋK�i���D�悳��Ă���B�j�{��ŃC�M���X�鍑�̕���ɂ悭�g����P�ʂ��ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
�@��ԖC�i�d�ʂ܂��͌��a�j�@2�|���h�C��40mm�@6�|���h�C��57mm�@17�|���h�C��76.2mm�i77mm�j�@3�C���`�C��76.2mm�i77mm�j
�@�����̂ɕt������@QF�iQuick Firing�j�����˖C�i�ΐ�ԁj�@CS�iClosed Support�j���ߐږC�i�֒e�j
�@��C�i�d�ʂ܂��͌��a�j�@25�|���h�C��87.6mm�@5.5�C���`�C��140mm
�@�M�҂͓��R���{�l�Ȃ̂Ń|���h���[�h�ŒP�ʂ�`�����Ă������̑z���͂ł��Ȃ����A�����ƃC�M���X�̐l�Ȃ������i�|���h���[�h�j�̕����������肭��̂��낤�B
|
 |
���A�L���[�Y�@�i�쒀��ԁj
�@�{�Ԃ̃x�[�X�̓A�����J��苟�����ꂽM10�쒀��Ԃł���A�C�M���X�͉Η͋�����}�邽�߁A�������̈ꕔ�ɂ����Ď�C�����͂�17�|���h�C�ւƊ������A�^�p���J�n�����B
�@�������ꂽ��C�͌��X�̎�C�������Ȃ�Η͂��オ���Ă���A���L�����ɓ�������A���̉Η͂����ĉΗ͎x������C���Ƃ��Ċ����悤�ł���B
�@�Ȃ��A���m�Ȑ��Y�䐔�͕s���ŁA�ǂ̒��x���{�Ԃɉ������ꂽ�����m�ł͂Ȃ����A�����E������Ƃ͂���قǓ���Ȃ�������A������x�܂Ƃ܂����䐔�Ɨ\���ł��邾�낤�B
�@�ԑ̎��̂͂�◊��Ȃ����̂́A��C�͋��͂Ȃ��̂ł���A�A���R�̔������{�i�I�ɂȂ鎞���ɂ̓C�M���X�R�ɂƂ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ��ԗ��ł������悤���B
�@�Q�[���ł͏I�Ղœo�ꂵ�A�h�C�c�鍑�̃p���^�[�Ɠ����̍U���́A�ɂ߂Ĉ����ȃR�X�g�A�ƁA�C�M���X�R��Ԃ̒��ł̓t�@�C�A�t���C�ɕ��ыɂ߂č����g��������ւ�B
�@�^�p�ʂł͂��t�@�C�A�t���C�ɗ�镔���͂�����̂́A�I�Ղ̃C�M���X��ԂƂ��Ă͒�������U���͂�����_�A�����C�ȉ��̐��Y�R�X�g�ł���Ƃ����_�͓��M�ɉ�����B
�@���ʁA�ԑ̂͒���ԃN���X�ł��邪���߂ɑł���キ�A�܂��A�I�[�v���g�b�v�̐퓬���ł��邱�Ƃ����h�䂪0�ƂȂ��Ă���A�W���C�𗁂тȂ��悤���ӂ������B
�@����������Α������Y���\�ł��邽�߁AM10�E���o��������}���Ői�������邱�Ƃ��������낤�B
|
 |
���}�`���_II��������@�i�d��ԁF������ԁj
�@��O�ɊJ�����ꂽ�}�`���_�͏d���b�E�����E���^�E�ėp�p�[�c�ϋɍ̗p�����Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ł���A��ԖC�܂ł����Ȃ��ꂽ���߉Η͓I�ɒ����������̂ł������B
�@���ʁA�����ɑޖ��̌��肳�ꂽ�}�`���_�ɑ��A�C�M���X�R�͌�p�@�̊J��������A�X�Ȃ鑕�b�lj��Ǝԑ̂̑�^���A��ԖC�𓋍ڂ����{�Ԃ̓o��ƂȂ�B
�@��ɂ���ĕ�����Ԃ̓����͂͂�����Əo�Ă���A�d���b�E���x���o�Ȃ������Ɉ��H�ɋ����A�Ƃ܂��ɕ��������ւ̍œK���͍��������B
�@���������Ɍ���@���̖͂����͑債�����ɂ͂Ȃ炸�A�D�ꂽ���b�͑����̐�ԖC�E�ΐ�ԖC�̖C�e��e���Ԃ��Đ����̕�����ǂ�������B
�@�e���ʂɂĊ��Ă������A��{�I�ɞ֒e�����ĂȂ��v���I�Ȏ�_�ƁA�h�q����U���ɓ]����悤�ɂȂ�Ƌ@�����̖R�������w�ƂȂ�A����ɐϋɉ^�p����Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�����ɂĒ��C�g�C�̗̍p���i�ނƏd���b�����܂���ɗ����Ȃ��Ȃ�A����ɑ�������͑ނ��Č��������A��������ׁX�Ɖ^�p����A�I��܂Ŋ��Ă���B
�@�Q�[�����ł͕�����ԃ}�`���_����̐i���A�������͐��Y�ɂĎ�ɓ���鎖���\�ŁA�i������o�����^�C���Ɛ����ȕ�����Ԃ̌n���ƂȂ��Ă���B
�@���b�͌��������ꋭ�����A�A�ړ��͂̒Ⴓ�ɉ����A�j���̞֒e���g���Ȃ����f���Ă���C�͑Α��b�Η͂����ƂȂ��Ă���A�����I�Ȏg������͗ǂ��Ȃ��B
�@�������A���Ղ̕ǖ��Ƃ��Ă͔�r�I�D�G�Ȃ��߁A�^�p����Ȃ�Ώ����̓����ɂƂǂ߁A�����m�ɂ��������ʼn^�p�������B
|
 |
���o�����^�C����������@�i�d��ԁF������ԁj
�@��풆�̃C�M���X�R�ɂ����čł��M�����������A���Y���E�R�X�g�ɗD��A��ԕs���̋��n�Ɋׂ��Ă���������ǂ��x������Ԃł���B
�@�O�q�̐����ǂ���A�����I�ȕ]���͂��Ȃ荂����ɁA��ԕs���Ƃ��������w�i����`���āA�C�M���X�R�Ƃ��Ă͒��������Y�䐔��8000����z���Ă���B
�@���\�I�ɂ̓}�`���_II�ɗ�鑕�b�E���j���A�����^�ł�40mm�C�ł��������߂ɉΗ͕s�����w�E����A�ƂĂ��V�K��ԂƂ͌����Ȃ����̂ł������B
�@�������Ȃ���A�{�Ԃ̌����Ȑv�͍����@�B�I�M�����鎖�ɐ������A�����ɐ��Y�R�X�g��傫�������鎖�ɂ��������Ă������߁A���ꂪ��ʐ��Y�ւƌq�����Ă���B
�@�u�^�p���₷����ʐ��Y���₷���v�Ƃ������_���猩��ΐ푈�̓���Ƃ��Ă̎g������͍����A�{�Ԃ̓o��̓C�M���X�R�ɂƂ��Ď��ɂ��肪�������̂ł������B
�@��피���ɂ͐��\�I���E���������ߏ��X�ɑޖ����Ă��������A�ꕔ�̓\�r�G�g�Ȃǂɑ����č��]������Ƒ����ł������B
�@�Q�[�����ł̓}�`���_II���i���A�������͒��Ոȍ~�ɑ����Y�ɂĎ�ɓ���鎖���\�ƂȂ�B�i�o���XI�^�Ȃ̂�75mm�C�j
�@�Η͂����[�A�ړ��͂�4�A���b�Ɏ����Ă̓N�����E�F���ȉ��A�~�߂��R�X�g���V���[�}���ȏ�ƁA�͂����茾���đ��݂��^�����x���ł���A�g�����R���w�ǖ����B
�@������Ԃ͔�r�I���������Y���\�ƂȂ邽�߁A�ǂ����Ă��g�������̂Ȃ���M�����[�ł͈��킸�A��œI�ɑ����Y�Łu���̏�v�����^�p����̂��������B
|
 |
���`���[�`����������@�i�d��ԁF������ԁj
�@�}�`���_������Ԃ̐��\������ɑς����Ȃ��Ȃ�A��p�Ƃ��ē������ꂽ�̂��{�Ԃł���B
�@�{�Ԃ́A������ԂƂ������̓Ɠ��̍l��������@���͔͂��ɒႭ�A����Ɋm�����������H���j���A75mm�C���x�Ȃ�Β��˕Ԃ���d���b�����B�i��e�����ɂ����j
�@��Ԑ�ɗp������悤�ȉ₩���͂Ȃ����̂́A���H�̑�����������Ƌ��ɋ삯�����A���̌������b�œG�e�˕Ԃ��A�����ɂƂ��Ă͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ł������B
�@�܂��A�ɂ߂č������H���j���͓��M�ɉ����A���̑��s���͒ʏ�Ȃ�ΐi�����ׂƔ��f�����悤�ȏꏊ�ł��p�ӂɓ��荞�ނقǂł������悤�ł���B
�@�Q�[���ł͉Η͂̂Ȃ�����ԂƂ����C���[�W�������A���̓ݑ����̓v���[���[�Ɏg���ɂ����Ƃ�����ۂ�����ɐA������B�i�ǂƌ����Ă������܂ŏd���b�ł͂Ȃ��̂����E�E�E�j
�@�����^�͖C�̊W����Δb�Η͂��キ�i�O���^��C�͑Α��b�Η͂̂݁A����^�ʼn��ǂ����j�A���̓_�ł���∵���ɂ��������������A�ǂ����Ă��}�C�i�X�_�������ڗ��B
�@���Ɉړ����D������Ă���킯�ł��Ȃ��A����ɐ��x�̒Ⴓ����搧�̎��Ȃ���C�A�R�X�g���͒v���I�ŁA�i��Ŏg�����R�͂���Ƃ����Č�������Ȃ����낤�B
�@�����^�p������Ȃ�A�����̏��Ƃ��čT���߂̐��ʼn^�p���A�ϋɓI�ȑ����ւ̓����͂ł��邩����T�����ق����悢�B
|
 |
���n���o�[AA�@�i��ԗ��j
�@�h�C�c�鍑�R�̍q��U���ɑΉ����邽�߁A��Η͂����߂Ă����C�M���X�R�ł͗ǍD�ȋ@�����E�^�p�����������n���o�[���b�Ԃɖڂ����A������ԗ��Ɏd�グ���B
�@�ԑ̎��̂ɑ傫�ȕύX�͖����������A�����͋@�֖C�̕ς��ɑ傫���ˊp���m�ۂł���7.92mm�@�e���l�쓋�ڂ���Ă���A�ꔭ�̉Η͂ł͗����̂̒e����ɂ͏\���ł������B
�@���̎ԗ��̗ǂ��ʂ������悻�����p������ւ̊��҂Ƌ��ɐ��������ꂽ���̂́A�o�ꎞ�ɂ͐����قƂ�ǘA���R���ɂ��������ߎc�O�Ȃ��犈��E��b�Ȃǂ͂قږ����B
�@�{�Ԃ͐�ǂ���L�Ӌ`�Ɋ��p����Ȃ��������A���b�����ɐ����ł����Η͂͗��R�ɂƂ��Ĕ��ɐS�������̂ŁA���ݎ��̂����B�ɑ傫�Ȉ��S��^�����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���̓_���l������Ɖ����ł������ł��A�@�q���ɗD���n���o�[�ɖڂ�t�������R���͔��ɗǂ����f���������Ƃ������A�{�Ԃɂ����Ă͕������ɊԈႢ�͖��������ƌ�����B
�@��ԗ��Ƃ��Ċ���̏�͂Ȃ��������̂́A����͓����R�ɑ��ċ�̋��Ђ͖��������Ƃ��l�����A�{�Ԃ͓����R�̖c��オ��������Ȑ��͂������Ă����̂����m��Ȃ��B
�@�Q�[�����ł͔�r�I���Ղ��瑦���Y���ł��A����Ȃ�̉Η͂Ɉ����ȓ_����肭�Z�������ԗ��ŁA�قڎg���̂Ċ��o�Ŏg����ԗ��ƂȂ��Ă���B
�@����Ȉꌂ��������p�r�ɂ͌����Ȃ����������낦�Ďg���ɂ͋ɂ߂ēs���悭�A�˒��ɗ��{�t�H�[�X��C�̗���Ȃ����J�o�[��������ɂ����x�ǂ��B
�@�i����̓N���Z�[�_�[AA�i��ɑ����Y���o����悤�ɂȂ�j�ŁA�n���Ȃ���������Ȑ��\���オ�����߂邽�߁A�i������͑��₩�ɐi���������Ƃ��낾�B
|
 |
���r�V���b�v�@�i�����֒e�C�j
�@�k�A�t���J�ł̐킢�ɂ����āA�h�C�c�鍑�R�̎����֒e�C�ɎU�X�ꂵ�߂�ꂽ�C�M���X�R�́A���l�̐�͂����R�Ɏ�荞�����ƌ����E�J�����n�߂��B
�@�J���H���̓V���v���Ȃ��̂ŁA�ԑ̂̓o�����^�C����ԁA�C��25�|���h��C�𗬗p�Ɗȑf�ɍς܂���A����ňꉞ�`���������Ƃ̔��f�Ő��Y���J�n���ꂽ�̂��{�ԂƂȂ�B
�@�����֒e�C�Ƃ͌������̂́A���\�͂�����ʂŋɂ߂Ĉ����A�C�𑀍삷�邽�߂̎ԓ��X�y�[�X�̊m�ۂ������ƌ����A�����I�Ȏ��s��ł������B�i���Y���������Ă���j
�@���̒v���I�Ȍ��_�������A�C���ɂ܂Ŕ�������悤�ȕ���ł��������߁AM7�v���[�X�g���A�����J��苟�^�����悤�ɂȂ�ƁA�����܂��������ő�������ނ����B
�@�Q�[�����ł͒��Ղ���o�ꂵ�A�j���ǂ��萫�\�̈��������֒e�C�Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���B
�@�������ɑ���{�鍑�R�̈ꎮ�����C���̓}�V�ł��邪�A�ΉE�˒��͋��ɕs���C���i30/3H�j�ł���A���đ����̓�����ɔ����肷��͔̂ۂ߂Ȃ��B
�@���X�A�C�M���X�R�ł͂܂Ƃ��Ȏ����֒e�C���̂����Ȃ��A���肵�Ďg����̂�M7�v���[�X�g�݂̂Ƃ����L�l�ł��邽�߁A�܂��͉^�p���邩���Ȃ��������̔��f�ƂȂ邾�낤�B
�@�i�ߕ��U�߂ɂ͑���C�E�����֒e�C�Ɠ������L���ł��邽�߁A�����Ă��Ă����͖������A�{�Ԃɗ��肫��̂͊댯�ł���AM7�v���[�X�g�̓o���͑��߂ɐ�ւ��Ă��������B
|
 |
���Z�N�X�g���@�i�����֒e�C�j
�@�r�V���b�v�͊��S�Ȏ��s�ł��������A�������^�p����Ă���M7 �v���[�X�g�i�A�����J���狟���j�̗D�G���ɖڂ����Ă����C�M���X�R�ł́A�������{�Ƃ��Ė{�Ԃ��J�������B
�@�{���̓V���[�}���n�ԑ̂��g�p����\��ł��������A�����̓s���ɂ��J�i�_�̃�����Ԃ̎ԑ̂��̗p����Ă���B�i������Ԏ��̂̓V���[�}���n�Ɠ����̎ԑ́B�j
�@�܂��A�r�V���b�v�Ɠ����C�𓋍ڂ��Ă������A�r�V���b�v�̂悤�Ɏˊp����������Ă��܂�����A�퓬���̃X�y�[�X�������Ƃ������͖����A�w�E����Ă������_�͂قډ��P���ꂽ�B
�@�r�V���b�v�Ɣ�ׂ��ꍇ�A���\�͔���I�ɏオ���Ă��邪�A���ł��ˊp�����P���ꂽ���͔��ɉe�����傫���A�r�V���b�v�ɔ�ׁA��蒷���˒��鎖�ƂȂ����B
�@�S�̓I�ȉ^�p���\���ǍD�ŁA�o�ꂩ�珙�X�ɐ��𑝂₵�A�C�e���K�i�O��M7 �v���[�X�g�i�C�M���X�R25�|���h�C�͖�88mm�j�ɑ����Ď�͎����֒e�C�ƂȂ��Ă���B
�@�{�Ԃ͐��������ɂ���ăG���W���E�d�C����̑����Ɏ�̈Ⴂ������A������s�ʎY�^�A�ʎY�^�Ƌ�ʂ��A���ꂼ���Mk.I�AMk.II�ƌĂԁB�i�Q�[�����ł͋�ʂȂ��B�j
�@�Q�[���ł͒��Ղ���o�ꂵ�A�r�V���b�v���鐫�\�ő����Y���\�ƂȂ��Ă���B
�@�j���ǂ���˒���4H��1H�㏸���āi�r�V���b�v��3H�j���\�͌��サ�Ă��邪�A25�|���h�C�̉Η͖͂�C�̂���ƈꏏ�ł���A��͂蕨����Ȃ��͂���B
�@�e���i�ԐږC�̒e����10���j���疳�⋋�Œ����Ԃ̊Ԑڎx�����\�ł��邪�A�O�q�̂Ƃ���Η͕s���͖��ł��邽�߁AM7 �v���[�X�g�ւ̐i���͕K�{�ɂȂ邾�낤�B
|
 |
��40mm�{�t�H�[�X�@�i�������˖C�j
�@�X�E�F�[�f���̃{�t�H�[�X�Ђ��J��������@�֖C�ł���A�������\����A���R�̊͑D�ɐϋɓI�ɑg�ݍ��܂ꂽ���A�����̍��X�ō̗p���ꂽ����C�ł���B
�@�{�C�͘A���R�����łȂ��ԌR�␕���R�ł��g���A����E���ɂ����čł��������ł����W���[�ƌ����Ă悢�قǂŁA�G���������藐��Ďg�p�����ʔ����C�ƌ�����B
�@���X�̓X�E�F�[�f���C�R�����̖C�ł��������A�˒��A�Η͋��ɂ��ꂾ���ɏI���ɂ͂��������Ȃ����\�ł��������߁A���R�^�����݂��A������������̗p���ꂽ�B
�@40mm�ƌ������a�͊e���̍��˖C�ɔ�ׂĔ��[�Ȃ悤�Ɏv���邪�A���̖C��L60�Ƃ������C�g���̗p���Ă��邽�߁A������75mm���˖C�Ȃǂɔ�ׂė����̂ł͂Ȃ��B
�@�ނ���40mm�ƌ����K�x�ȑ傫���ƒ��C�g�ɂ���Ď˒��͒����Ȃ�A���˖C�ɋ߂����������@�֖C�ƌ������ŘA�����ˑ��x�������A�o�����X�͋ɂ߂ėǍD�ł������B
�@���܂�̗D�G���ɍ̗p���鍑�����o���A����͖C�g��L70�Ƃ�蒷�����̂ɃA�b�v�f�[�g����A����ɂ����Ă��Ȃ������ƌ������낵�����܂������\�E�������ւ��Ă���B
�@�Q�[���ł̓C�M���X�R�B��̑˖C�Ƃ��ēo�ꂵ�A�����Y�̂݁A�i���E���ǂȂ��Ƃ��������ŏ��Ղ���g�������\�ƂȂ��Ă���B
�@�������A�����Y�Ŏ�y�Ɏg���鍂�˖C�Ƃ����Ε������͂������A�Η͕͂��A�˒���3�Ƌ����A�������˖C�Ƃ̔�r�ł͖��炩�ɗ���Ă��邽�߁A�c�O�Ȃ��琫�\�I�ɂ͔������B
�@��������Ζ��ɂ͂����A���˖C�Ȃ�ł͂̑҂������Ɏg���ɂ͎˒����Z���A�ړ��E�W�J�̎�Ԃ��l����Ɨ��h�q�p�Ɗ�����ċɏ������^�p����̂��������B
|
|
���C�M���X�鍑�R�����@�i�����j
�@���O�̑�s���̒��A�o�ϓI�Ȋ�@�Ɋׂ��Ă����C�M���X�鍑�ł͑�K�͂ȍΏo�팸���������A����͌R�ɂ��傫�ȉe���������炵���B
�@�X�V�����͂��̑����͍X�V���ꂸ�A����̒��B�E�J���ɂ��e�������Ď��A��ꎟ���E���̐폟���ɂ�������炸�A�����i�͈ˑR�Ƃ��ċ��̌n�̂܂܂ł������B
�@�P�����̏e���͂��߂Ƃ��A������ʂ̐A���n�ł͐키���������������d�����ꂽ�Â��R���ȂǁA���̉e���͑����i�A�R����������炩�ł���ƌ��Ď���B
�@��풆������X�e���K���Ȃǂ̒Z�@�֏e�A�s�A�b�g�i�ΐ�ԃO���l�[�h�j�������i�ɑg�ݍ��܂��Ɛ퓬�\�͂͒��ˏオ�������A����ł��h�C�c�鍑�����Ƃ̔�r�ł͎��ɂ����B
�@�C�M���X�l���L�̃W�����u�����Ƃł����������s���̐��_�͌��݂ŁA�⋋�E�����\���ł���Δ��ɗǂ��키����A���炩�ɗł���ΓP�ށE�~�����S�O���Ȃ��_��������Ă����B
�@�����Ƃ͏�����������邪�A���Ȃ̂��鏫�Z�������I�ŁA���[�����X�E���@���E�f���E�|�X�g�A�o�[�i�[�h�E���[�E�����g�S�����[�ȂǓƓ��̍l�������l���������������ɋ����[���B
�@�Q�[���ł͕����i�O���E����j�A�����ԉ����A�����A���������o�ꂷ�邪�A�j���̗���������f���Ă��S�ʓI�ɔ\�͂��Ⴍ�A��g���ɂ����������\�ƂȂ��Ă���B
�@���ɋ@�����ɖR�����_�͑傫���A�W���I�ȕ����͂Ƃ����������ԉ������A�����̕�����Ԏ��̈ړ��͂�2�ƌ����������i�R�ɒ����������������Ă���ƌ����Ă悢�B
�@���R�����ɂ͉������猇�_�����邽�ߕҐ��͊��S�Ƀv���[���[�̍D�݂ɂȂ邪�A�ꍇ�ɂ���Ă͕�����p���������Ō����j��A�⋋�ԂŏC���Ƃ����v���Ȑ�̂��K�v���낤�B
|
|
|
�������@�i�L���E�����E�j
�@�Ȃ����Q�[�����ɐ��������̌Ñ㋰���B
�@�G������̂ɓf���o���Ɖ͑S�Ă��Ă��s�����Ƃ����B
�@���̐��Ԃ͓�ɕ�܂�Ă���B
|
|
|
���@�B�������@�i�L�J�C�J�z�w�C�j
�@�p���[�h�X�[�c��g�ɂ܂Ƃ�����̕����B
�@�߂Â����̂ɂ͗e�͂Ȃ��@�֖C�|�˂𗁂т���Ƃ����B
�@�ǂ��������e�N�m���W�[�œ����Ă���̂��͓�ł���B
|
|
|
|
 |
��Bf109�@�i�퓬�@�j
�@�o�C�G�����Ёi��̃��b�T�[�V���~�b�g�Ёj�����ɑ���o�����h�C�c�鍑�R�̎�͐퓬�@�ł���B
�@�o�����X�̗ǂ��퓬�@�ł��������A�G���W������Ƃ���@�̂̕��G������A�����̔Y�݂��������퓬�@�ł�����A���@�ƌĂ��܂łɂ͗l�X�ȉ��ǂ��{���ꂽ�B
�@���ǎ�͔��ɑ������܂�A��G�c�Ɍ�����F�^�ɂĂЂƂƂ���̉��P���I�����AG�^�Ŋ����`�ԂƂ������Ƃ���ł��낤�B
�@���Ȃ݂ɁA�e�^�Ԃ̃A���t�@�x�b�h�ɂ�F�Ȃ�t���[�h���q�AG�Ȃ�O�X�^�t�ȂǁA�l�����������Ƃ��Ă����Ă���B�i�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�j
�@�Q�[���ł͑O���`���Ղ܂ŗ���ɂȂ�퓬�@�ł���B
�@�j���̃��[�^�[�J�m�������̒x��ɂ��Η͕s���A�R���ʂɂ��Z���q�������f���AF�^�ōq�������̌��E�i�R��50�j�AK�^�ʼnΗ͂̌��E�i��80�j�ɓ��B����B
�@�I�Ղł́AG�^�iK�^�i���͏ȗ��j�����C��Me262�ւƐi�����\�ƂȂ邽�߁A���̐퓬�@�����͓I�Ɍ����Ă��Œᐔ���j�b�g��G�^�ȏ���X�g�b�N���Ă��������B
�@���܂��^�p����A���Ղ܂ł�Bf109G�A�������炵�炭��Fw190�A�I�Ղ�Me262�����Ɨ����g�ނ��Ƃ��ł��A���ɂ͍���Ȃ����낤�B
|

coffee break |
|
�`�퓬�@�̋@�e���ډӏ��ƃv���y���������u�`
�@��풆�ɉ^�p���ꂽ�퓬�@�͋@��ɋ@�e�����Ă�����̂��������݂���B����͗��ɋ@�e������������������b�g���������߂ŁA��̓I�ɂ́u�@�e�̓��ɓ��ڂ��鎖�ŃX�����ɂł���v�u�ˌ��Ώۂɍ��킹��Ə������m�ɂȂ�v�u�@�e���O�t�����邽�߂̕⋭���K�v�Ȃ��Ȃ�v�Ȃǂ���������B�������A���������������ɂ͒P���ɍl���Ă��@�e�Ńv���y����ł������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ炸�A���̔��z���o�������ł͋Z�p�I�ɂ�������̂������B
�@�|�����^����ɁA�ӊO�ȕ��@�Ŏ����������̂͑�ꎟ���E���ł̃t�����X�ł������B���̕��@�Ƃ́u�v���y���������Ȃ��悤�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�e�ۂ������邱�Ƃ�O��Ƃ���悢�v�Ƃ��������̂ŁA���ɋ����Ȏ�@�ł������B�����A����ł��o�ꓯ���̌��ʂ͐��ō̗p�@�i�\���j�GL�j�͑�ꎟ���ő傫�Ȋ�����c�����B���ꂩ���A�b�l�����t�����X�@�̋Z�p���Q�l�Ƀh�C�c�鍑�̃t�H�b�J�[���v���y�������ƌ����l�����v�����A�u�v���y�����e���Əd�Ȃ��Ă��鎞�ɂ͋@�e�삳���Ȃ��v�{�i�I�ȍ\���ݏo�����B���ꂪ�v���y���������u�ł���B���̑��u�͓o��Ƌ��ɔ����I�ɐ��E���֍L����A����ȍ~�����̐퓬�@�ɍ̗p����D�ꂽ�퓬�@��a���������B�v���y���������u�Ƃ͂���قlj���I�������̂ł���B�������A�Η͏d���Œe�ۂ���T���K�v���������@�ɂ͈ˑR�Ƃ��ė����E�����@�e���̗p�������̂������A�A�����J�@�A�C�M���X�鍑�@�ɂ͗����E�����@�e���̗p�����@�����������B�܂��A���̑��ł��Η͕s����₤�̂Ƀ|�b�h�`��ŗ����ɋ@�e���݂����ȂǁA�ꍇ�ɂ���Ă͋@��@�e��������ł����������ߑ���E���ɂ����Ă͋@�e�̓��ڕ��@�͑���ɓn��B
�@�@�e�̐ݒu�ӏ��͎g�p�ړI�E���ɂ���čD�܂��ӏ��͕ς��A����Ȏ�������e���̍����A�퓬�@�̂�����A�\�z�ƌ������̂������̂�������Ȃ��B
|
 |
��Fw190�@�i�퓬�@�j
�@������͂ł�����Bf109�͍����\�ł͂��邪�A�V���ɂ͈����ɂ����A���G�ȃG���W���\���̂��ߐ��Y�����܂���N�����Ă����B
�@�������炭���͌����̕s�����������邽�߂ɊJ�����ꂽ�̂��{�@�ł���B
�@�����x�퓬�͋��ł��������̂́A���̋@�̂̏�v���A�������Y���ƃ����e�i���X���ABf109�Ɣ�r�����c�̂��₷���ŁA�����Ŏg�p����邱�ƂɂȂ�B
�@���̔ėp�����瑽���̉��ǎ�ݏo�������AD-9���o�邱��ɂ͊��ɍH�ƕi���̒ቺ�A�����퓬�@�̋ɒ[�Ȑ��\���ォ��v���悤�Ȑ��ʂ͏o�Ȃ������B
�@����{�鍑�Ɠ����ŁA���I�ɗŁA�����Y�Ƃ��ቺ����A�J�^���O�f�[�^�Ɠ����悤�ɂ����Ȃ��̂͂ǂ��ł��ꏏ�ł���A�ƌ������Ƃ��납�B
�@�{�@�̓h�[�o�[�̐����ꎞ�D�悳�ꂽ�A���R���m�ɂ͍D�G��ƌ����A�^�����\�����Ő퓬�@�f������{�R�ɂ͗�����퓬�@�ƌ����邱�Ƃ������悤�ł���B
�@�Q�[�����ł͘A���R�퓬�@�ɔ�ׁA���Η͂͗�邪�A���肵�����\�����ABf109�iBf109��k�^�ł��U���͂�80�A���x18�j�ɕς���ė���鑶�݂ł���B
�@�퓬�U���@�^��G�^�AF�^�����ڔR���ɓ�͂�����̂́i�@�֖C�{�^���N2�����͉\�����j�A������x�̖h�q�͂�������500kg���e����3�ƍU���\�͍͂����B
|
 |
��Ta152�@�i�퓬�@�j
�@Fw190�̍����x�^�C�v�ł���D�^������Ɍ����E���W�����A���̐��ʂƂ��ēo�ꂵ���̂��{�@�ł���AMe262�̏o���E�������T�|�[�g����퓬�@�Ƃ��Ċ��҂��ꂽ�B
�@Fw�̔��W�^�ł͂��邪�A�^�Ԃ�Ta�ƂȂ��Ă���̂́A�v�҂̖��O��p����悤���̎�����薽���K�����ύX���ꂽ���ɂ����̂ł���B
�@��܂��ȍ\����Fw�̂���P���Ă���A�ڗ������ł̕ύX�_�͏��Ȃ����̂́A�ו��ɂ͂��Ȃ葽���̕ύX���������Ă���AFw190D�̐��\�����鐫�\���B
�@�������Ȃ���A�h�C�c�鍑�i�i�`�X�����j�ł̓��b�T�[�V���~�b�g�т��������ɍ������A��ʐ��Y�ɓ��ݐꂸ�A�I��܂łɏ��������Y����A�ꕔ�������ɗ��܂����B
�@�v�ǂ���̋@��E�����e�i���X���̗p����Ă����P-51�}�X�^���O��D�ɏ��鐫�\�Ƃ̘b���o�Ă���A�D��ʎY����Ă�����̗��j�͂܂��������������Ȃ��B
�@�Q�[���ł̖{�@�́AFw190D9���i���E���@�����ɂ�葦���Y���\�ŁA���V�v���퓬�@�̒��ł��g�b�v���x���̐��\�������A�Η�120�E���x20�ƍU���͂͌Q���Ă���B
�@�����̉���ȃW�F�b�g�퓬�@�������x���������߁A�I�Ղł��i���������̂܂܉^�p���邱�Ƃ��\�ȃ��x���ł���A�I�Ղł͗���ɂȂ��͂ƂȂ邾�낤�B
�@�i������Fw190D9�Ƃ���y���i�����Ta183�Ƌɂ߂č����\�͂ƂȂ��Ă���A���͂̈ꗃ�Ƃ��ĉ^�p����̂��悢�B
|
 |
��Me262�@�i�V�����@���x�@�퓬�@�j
�@��햖���ɓo�ꂵ���h�C�c�鍑�̌ւ�A���E���̃W�F�b�g�퓬�@�ł���B
�@�o�ꂵ�������͖����ł͂�����̂́A�����J�����Ԃ������Ă���A���̊Ԃɑ啝�Ȏd�l�ύX�A�������̂Ȃǐ������̍�������z���A����Ǝ��p�����ꂽ�B
�@�{�@�͓����̃��V�v���@����Ƃ��Ȃ��قǂ̑��x�������A����30mm�Ƃ������͂ȕ�������A�ɂ߂č����퓬�\�͂������ƂƂȂ����B
�@�������A�����\�Ȉ���Ń��V�v���@�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǔR��͈����A�܂��A������Ƃ�������~�X�ŃG���W���̔j������������A����������ȂǑ����̖������B
�@�����̃W�F�b�g�G���W���Z�p�ł̓W�F�b�g�G���W�����̂̉ғ��������ɂ߂ĒZ���A�ɒ[�ȍ����\�������̂́A���̉^�p�E�����e�i���X�͔��Ƀf���P�[�g�Ȃ��̂ł������B
�@�R���N���������ꂽ��`�ł����^�p�ł����A�؋Ԃ̒Z�����璷���Ԃ̍��ɂ͕s�����ł��������A�o�ꂩ��I��܂ł̒Z���Ԃł��Ȃ�̌��Đ����グ���B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɍ����|�������Ƃ���Ői�������ւ���A�ꕔ�̃}�b�v�ł͑����Y���\�ł���B
�@�{�@�͈ړ��́A�R���̓��V�v���@�Ƒ卷�Ȃ��ݒ�ł�����̂́A�Η͂�140�A���x22�Ɛ퓬�\�͂͋ɂ߂č����B�i�������A�e���Ȃ����Ƃɒ��Ӂj
�@���Y�R�X�g�͍������ABf109G�iK�j����̐i���ł���R�X�g�����܂肩����Ȃ����߁A�L�����y�[���ł͏��Bf109G�^�ȍ~������X�g�b�N���Ă��������B
|
|
��Ta183�@�i�t�b�P�o�C���@�퓬�@�j
�@�������x���s���锚���@�ɑ��Ă��L���Ȑ��\�����h�C�c�鍑�R�̐�D�Ƃ��ĊJ������Ă������A�A���R�ɂ��J���H��̐苒�ɂ�芮���Ɏ���Ȃ������@�ł���B
�@�������ł��邱�Ƃ��琫�\�͖��m�������A�y�[�p�[�v������ł̐��\�͔�r�I�����A�h�C�c�鍑�̋Z�p�͂��l����Ƃ���ɋ߂����\���������ꂽ�ł��낤�Ǝv����B
�@�v�ɂ��Ă����̓��ւ̃G���W���ݒu���ޗ��Ɛ�i�I�Ȃ��̂ŁA����Ɉꕔ���ʕ��i�̓����i��Ƃ��č��E�݊��̗��Ȃǁj���Ȃ����ȂǁA�������������Ɏ������ꂽ�B
�@�����Ԃ��Ƃ͎c�O�Ȃ���Ȃ��������̂́A��������鐫�\���犮�������Me262�ƕ���Ńh�C�c�鍑�R�̎�͐퓬�@�ɂȂ������Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ����낤�B
�@���A�U��U��ƂȂ����J���ҁA�J�������͘A���R�E�ԌR�̓��ɂ킽��A���̐��ʂ͊e���̑��ȍ~����܂ł̃W�F�b�g�퓬�@�ɐF�Z���e����^�����Ƃ����Ă��ߌ��͖����B
�@��풆�������邱�Ƃ̖��������{�@�̓h�C�c�鍑�ɂƂ��Ė����l�Ȃ��̂ł��������A���E�I�Ȏ��_�Ō���ƁA���A�W�F�b�g�@�j��ɗ^�����e���͌v��m��Ȃ����̂ł������B
�@�Q�[���ł̓h�C�c�鍑�R�ŋ��̐퓬�@�Ƃ��ČN�Ղ��A�|�S�̐����ł͐��E�������[�g�����A���t�@�C���ł͏I�ՂɁA���ꂼ��Ta152����̐i���Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��o����B
�@�Η�160�E���x24�E�h���80�Ƃ������\�͐퓬�@�Ƃ��Ă�������ō����x���̂��̂ł���A�퓬�͂̍�������x�����ׂ��G�퓬�@�͓������x�����H�����炢�ƌ����Ă悢�B
�@�ړ��́A�R���A�����̃o�����X���ǂ��A�g������ɂ��D��Ă��邱�Ƃ���A�����ł���悤�ɂȂ����Ȃ�����ɓ����������B�i���ɃC���h�N�U�ł�Ta152���Y�シ���i���\�j
|
 |
��He162�@�i�T���}���_�[�@�퓬�@�j
�@�ɒǂ����܂ꂽ�h�C�c�鍑���A�`���t�]��}��ׂ��v�E�J�������̂��{�@�ł���B
�@�{�@�͔�퓬����B�x�̒Ⴂ���ł��ȒP�Ɏg���A�M�d�z���̎g�p���ɒ[�Ȃ܂łɌ��炵�A����ɑg�ݗ��Ă��ȈՂł���Ƃ����\�z�ɉ����Đv���Ȃ��ꂽ�B
�@���̉^�p�Ӑ}����u�����퓬�@�v�i�t�H���N�X�C�F�[�K�[�j�Ƃ��Ă�A��햖���ɐ��Y�̊Ԃɍ���������������֓������ꂽ�B
�@�{�@�͋}����ȏ�ɒ����s�����ڗ����A�S�̓I�Ȑ��\�͂��܂�ǂ��Ȃ��������̂́A�����ɗʎY�ł���W�F�b�g�퓬�@�Ƃ��Ċ��҂��ꂽ�悤�ł���B
�@�M�ғI�ɂ͒����s���̏�ɂ��łɔs��F�Z���̎����ɓ����A����ɐ��Y���C���̌������������Ă����Ƃ���ŏI��Ƃ����A�s���̐퓬�@�ł���Ǝv���B
�@�㐢�A�����܂Ō������炢�ȗ�������A�������w�������W�F�b�g�G���W�������퓬�@�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ����낤�B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղő����Y�\�Ƃ��������Ŏg����悤�ɂȂ�B
�@���K�W�F�b�g�퓬�@�ɔ�q�������A���\�́A�����Ȃǂ���邪�A�ς��Ƀ��V�v���@������鐫�\�R�X�g���Ŏg����̂����͂��B�i�����͕ύX�s�j
�@�퓬�\�͂�Ta152H���������x�̂��ߖ����Ɏg�����Ƃ��Ȃ��A�������ɂ͂�荂���\�ȃ��P�b�g���ǒn�퓬�@Me163���o�Ă��邽�߁A��̕���ƌ����邾�낤�B
|
 |
��Me163�@�i�R���[�g�@�ǒn�퓬�@�j
�@���E���A���B����p�����H�������ꂽ���P�b�g���i���̐퓬�@�ł���B�i���P�b�g���ł͑��ɑ���{�鍑�R�̍��ԓ������邪�A�����͐퓬�@�ł͂Ȃ��j
�@���P�b�g���i�Ƃ����v�V�I�ȋZ�p�́A����܂ł̐퓬�@��ے肷��悤�Ȉ��|�I�ȏ㏸�\�́A���x�������炵�A�U�߂邾���Ȃ�ΒN���������قǂ̐��\�����Ă���B
�@���ʁA��舵���̓���L�Q�������܂ޔR�������߁A�㏸����������̓O���C�_�[�Ƃقڕς��Ȃ����h���ȓ_�A�؋Ԃ̒Z���A�\���I���Ȃǃ}�C�i�X�v�f�����������B
�@���ɔR���}�̂̈����������ŋN���鎖�̂͑����A���̏E���̓��e������ƁA�^�p���邾���ł��傫���J�͂�v���A���펞�ł�������������߂��Ă����悤�ł���B
�@���Ղ��������͊���ł������A�A���R�ɂ���Ď�_���\����Ă����ƁA�z����n�������ꂽ��A���h���Ȋ��~����_��ꂽ��Ǝ���Ɋ���̋@��������čs�����B
�@��s�@�j��A�ꎞ�I�ɂƂ͌����ڊo���������𐬂������{�@�ł��������A�R�ɂ���Ė����ɐ퓬�@�Ƃ��ĉ^�p���ꂽ�̂��s�K�������̂����m��Ȃ��B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղɑ����Y���\�ƂȂ�A�R���A�q�������A�e���ƈ��������ɋɂ߂č����퓬�\�͂����퓬�@�ƂȂ��Ă���B
�@�R�X�g�����Ɉ����A�����葁�����R�i�ߕ����ӂ̐����m�ۂ������A�g���̂Đ퓬�@�ɉ^�p����ȂǁA�g���ǂ�������߂�ΗL�����͍����B
�@�ɒ[�ȃX�y�b�N�ł��邽�߁A���C���Ƃ��Ďg���ɂ͌��������A���܂��g�����Ȃ���Ύ��R�̐���\�͂����߂鎖���o���邾�낤�B
|
 |
��Me110�@�iBf110�@�퓬�U���@�j
�@�쒀�E�퓬�U���@�i���\�@�j�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂̋쒀�퓬�ł͖{�@�̓K���ɍ��킸�A�ŏI�I�ɂ͐퓬�U���@�Ƃ��ĉ^�p���ꌋ�ʓI�ɐ��������߂��o����^�@�̂ł���B
�@�{�@�͋��i�쒀�E��q���j�ł̊�������҂��ꂽ���̂̑Ήp��ɂĈ���I��Q����A����ɂ��i����ł͏�ɗł��邱�Ƃ������A����Ɋi����ɂ͎g���Ȃ��Ȃ����B
�@�������A������̐��i�ł���퓬�U���@�Ƃ��Ă͍������������ꌂ���E�E�������i�s���\�A�d�����Ƃ��������ƔC���̑��������ɂ悭�A���̕���ł͑听�������߂��B
�@�����̖����������������������ŒႢ�]�������ꂪ���ł��邪�A���ۂɂ͑����o���@�ɔ�ׂč����ėp���������Ă���A�傫�Ȑ��������߂��@�̂ł���Ǝv���Ă悢���낤�B
�@�Q�[���ł͐퓬�U���@�ɑ����Ă���A���Ղ��琶�Y���\�ŁAE�^����500kg���e�̓��ڂ��\�ƂȂ�B
�@���\�I�ɂ͓��ɏG�ł������͂Ȃ����̂́A���͐퓬�@�ɋy�Ȃ����̂̎��Ȗh�q���炢�͉\�A���e���ڗʂ������đΒn�U���͂܂��g����Ƃ���Ӗ����\�@�ł͂���B
�@�S�ʓI�Ȑ��\���Ⴂ���߁A�������ƌ������ɂ͗���Ȃ����A��평���̐퓬�őΒn�U���ɉ^�p����ɂ͂����Ă����̋@�̂ł���B
�@�i�����Me410�ƂȂ邪�A���̔N��̐퓬�U���@�͒��Ղɂ����Ă����ɑ����Y���\�ɂȂ邽�߁A����قǐ_�o���Ɉ����K�v�͖����B
|
 |
��Me410�@�i�z���j�b�Z�@�퓬�U���@�j
�@�������N�U�ɒ������쒀�퓬�@�Ƃ��ĊJ�����ꂽMe110�̌�p�ł���B
�@�Q�[���ł͐퓬�U���@�ƕ��ނ���Ă��邪�A���ۂɂ͓����A�쒀�퓬�@�Ƃ��č̗p����A���̌�A�퓬�U���@�E��Ԑ퓬�@�Ȃǂ̔C�ɂ����B
�@�o�ꓖ���Ƃ��Ă͉^�����A���x�A�����d�ʁA�ǂ���Ƃ��Ă��D��Ă���A�o�ꂩ�炵�炭�̊Ԃ͂��̑��x�A�Η͂����쒀�퓬�@�Ƃ��č����\�U��������B
�@�������A�}�X�^���O��X�s�b�g�t�@�C�A�Ȃǂ̒P���퓬�@�̐��\���オ�����ɂȂ��Ă���ƁA��ΓI�Ȕ\�͕s�����ڗ��悤�ɂȂ�A����ɋ쒀�퓬�@�Ƃ��Ă͎g���Ȃ��Ȃ����B
�@�Q�[���ł͐퓬�U���@�Ƃ��ĕ��ނ���Ă���A���̕����ʂ����đ�ʂ̑�^���e�𓋍ڂ��邱�Ƃ��\�ł���B
�@��U���͂�60�ƍT���߂̉Η͂ł͂��邪�A���̐��x��14�A500kg���e�̓��ڐ���3�A�����Ń^���N��2���ډ\�Ɓu���\�̒Ⴂ���\�@�v�I�Ȉʒu�t���������B
�@�����Ȕ\�͂͐퓬�@�قǂł��Ȃ��A����U���@�̂悤��B���e���ł���킯�ł��Ȃ��A���X������Ȃ��C����������ȋ@�̂ł͂���Ǝv���B
�@�i�����Fw190�퓬�U���@�^�C�v�ɂȂ�A�䂭�䂭��Do335�AHo229�ւƐi������E�E�E�̂����A�����������Fw190G�����Y�ł���悤�ɂȂ邽�߁A�C���g���K�v���Ȃ����낤�B
|
 |
��Do335�@�i�v�t�@�C���@�퓬�U���@�j
�@�O��Ƀv���y���������A���̓��قȊT�ρA�X�}�[�g������l�C�̍����퓬�U���@�ł���B
�@���^�ƌ����邻�̓Ɠ��ȃ��C�A�E�g�͗D�ꂽ�������A�^���������҂��ꂽ���A�{���Y�ɓ������Ƃ���ŏI����}���A�Ƃ��Ƃ����퓊���ɊԂɂ͍���Ȃ������B
�@�{�@�̗\��X�y�b�N�͔��ɍ����������̂́A�e�X�g�i�K�ł͗\��X�y�b�N�������Ƃ͂ł����A�v�����悤�Ȑ��\�ł͂Ȃ������B
�@�������A�o���ł���ɂ�������炸�P���퓬�@�ɋ߂��^�����\�������A���A�X�}�[�g�ȋ@�̂Ƃ����퓬�U���@�炵����ʕ����邱�ƂƂȂ����B
�@�\��ł͂��Ȃ�̔h���^�J������������Ă���A�{�@�̉��ǂ��i�݁A�{���̐��\���o����悤�ɂȂ��Ă����Ȃ�A���̗��j�͂܂�������������������Ȃ��B
�@�Q�[���ł̖{�@�͏I�Ղ�Fw190G/F����i�����\�ƂȂ�A�ꕔ�̃}�b�v�ł͑����Y���\�ł���B
�@�U���@�Ƃ������_�Ō���ƁA�O�g��Fw190G/F��500kg���e�𓋍ڂ���̂ɑ��A�������250kg���e���ڂƏ��X�Βn�U���͕͂�����Ȃ�������B
�@�����A�ړ��͂�13�A�R����80�I�[�o�[�A��U��130�A���x16�ƗD���̂���������[�łȂ����߁A�����ɂ���Ă͒������i�s�p�퓬�@�Ƃ��Ă��g����B
�@�g������͏�ʃ��x���ł���A�i�����Ho229�Ɗm���ŁA���Ȃ��Ƃ����@�͂��낦�Ă��������B
|
 |
��Ho229�@�iGo229�@�퓬�U���@�j
�@�q���̂������s�@�ɓ���Ă����Z�p�ҁA�z���e���Z��ɂ���ĊJ�����ꂽ�S���^�̐퓬�U���@�ł��邪�A���^�݂̂��������������ŗʎY�Ɍ��т��Ȃ������@�ł���B
�@�G���W���J���̓s����A�����^�̓O���C�_�[�I��s�������s���A�G���W�����p����ɐ����Ȕ�s�������s��ꂽ���A���x���̎����̌�A���̂ɂ���ăe�X�g�@�͎���ꂽ�B
�@�����A���̔�s�����ɂ���Ė{�@�̗D�ꂽ�_�������m�F����A���ɑ��x�ɂ����Ă͂��Ȃ�̐��\�����A�����܂��R��������҂����悤�ɂȂ�A�����J���E�����ւƌ��т����B
�@�{�@�ɂ͒��ڂ��ׂ��Z�p�������p�����Ă���A��������邾���ł��ȈՂȍ\���A�M�d�ȋ����ނ��ɗ͗p���Ȃ��A����ȓh����p���Ă������ƂȂǂ���������B
�@���ɂ��̓���ȓh���Ƃ������̂͒Y�f�ނ��p�����A�@�̌`��Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��X�e���X�����@�̂ɗ^�����B�i�͌^��p���ăi�V���i���W�I�O���t�B�b�N�ɂĎ��e�X�g���s��ꂽ�j
�@���Ȃ݂Ƀz���e���Z����4�l�Z���ł��������A�����Ō����z���e���Z���Ƃ͎��j�A�O�j�̂��Ƃł���B
�@�Q�[�����ł͖�����Do335����̐i���i�ŏI�i���j�Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��ł��A���l��A�ُ�ȂقǗD�����ꂽ���\�Œ������\�퓬�U���@�Ƃ��ēo�ꂷ��B
�@�Βn�h��A���e�̑傫������Βn�U���ɂ͂������̂̑��ċ��\�͍͂����A���A�ړ��͂ƔR���̃o�����X�������A���ۂɎg���Ă݂�Ɛ��l�قǂ̐��\�������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��B
�@�������A����ɂ�����Ȃ��������\�@�ł��邱�Ƃ͊m���ł���A��������ΐ�͌���͊m���ł��邽�߁A�g������ɋ^��������Ȃ���Α�ʂɓ�������̂��ǂ����낤�B
|
 |
��Ar234B�@�i�u���b�c�@����U���@�F�����@�j
�@�ׁX�ƒn���Ȏ��ЌR�p�@�A���А퓬�@�̃��C�Z���X���Y���s���Ă����A���h�Ђ����ɑ���o�������E���̃W�F�b�g�����@�ł���B�i�����ɂ̓W�F�b�g�����@�ƌ����Ȃ��Ǝv�����j
�@�{�@�̌����͔�r�I�����J��シ���Ɏn�܂��Ă����̂����A�̐S�̃G���W���J�����x��A����ɂ��̃G���W���D�挠��Me262�Ɏ��ꂽ�����珉��s�܂ł͂��Ȃ�Ԃ��J���Ă���B
�@�@�̂͏o���Ă��G���W���������ő����������߂��A1943�N��ɓ����Ă悤�₭�G���W���̖�肪�������Ď���@�͏o���オ��A�ǍD�Ȕ�s�����E���\���琳�������ꂽ�B
�@���̋@�͈̂ꕔ���_�͂������������I�ɗD�ꂽ���\�ŁA���ɑ��x�ɏG�ł����Ƃ���i���x�ɂ�邪�y��700km/h�ȏ�j�A�����̈�ʓI�Ȑ퓬�@�ł͒ǐՂ���o���Ȃ��قǍ����������B
�@�����^�͂��̍������������������̒�@�C���ɏA���A����^�͔��e�݂艺�����ł͂�����̂̔����^�Ƃ��Ă��̗p����A�L���ȃ��}�[�Q�����͂��ߏ������e�n�Ŋ��Ă���B
�@�{�@�́u�����@�ɑ������v�Ƃ����b���悭�o��A����͌��X����@�@�ł��������A���e�q�������������A�����p�������R�����������Ȃǂ����R�Ƃ��ċ������邾�낤�B
�@�Q�[�����ł�B�^���o�ꂷ�邪�A�����Ȕ����@�����łȂ��h�C�c�鍑�R�B��́u����U���@�v�ƂȂ��Ă���A������Ju88S�̍ŏI�i���Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��\�ł���B
�@�h��͂�@���͍͂������Ȃ����A�R�������Ȃ����������͖����A�����ʂ����ɏ��Ȃ��ȂLj����Â炢�@�̂ł��邱�Ƃ͊m���ŁA�R�X�g���������������̕���Ƃ������������B
�@�����U���@�Ƃ��Ă͖��͓I�����A�{�@���������Ɠ������邭�炢�Ȃ�R�^�ł�D�^�ł�Ju87����x�ɕ������Y���A��C�ɓ�������ق����Η͓I�ɂ������I�ɂ����҂ł��邾�낤�B
|
 |
��Ju87�@�i�X�c�D�[�J�@�}�~�������@�j
�@���̊��ȋ@�̂����������������Βn�U���ƁA��평���`�����ɂ킽��U�����Ɏg�p���ꂽ�W�F���R�i�����j�̃��b�p�ƌĂ��Ɠ��̃T�C�������ŗL���ȋ@�̂ł���B
�@�]�T�̂��铋�ڗʁA�}�~�������ɑΉ�����_��ȉ^�������������A��평���ɂ͑劈��������B
�@�T�C�����͑�평���`�����ɂ��ĈЊd�p�Ƃ��đ傢�Ɏg��ꂽ���A���݂������炩�ɂ��Ă��܂����ߌ�Ɏg���Ȃ��Ȃ����B�i�@�̎��̂����������鉹���������悤�ł���B�j
�@�����̊���͔��ɉX�����A�������Ńh�C�c�鍑���ł͋}�~�������@�����ō��̍U���@�Ƃ������������o�Ă����قǂł������B
�@�������A�ڊo��������͂��������̂́A����ɓG�퓬�@�̔\�͂��オ���Ă���Ƃ����܂����Q�����債�A�P�Ƃł̍�킪��������Ԃɒǂ����܂�邱�ƂƂȂ�B
�@�܂��A���̕����͌�ɁA�U���@�E�����@�ɑ��閳���ȋ}�~�������@�\�͂̒lj��i�v���܂ށj�ȂǁA�ꎞ�A�h�C�c�R�̍q���̖͂������������ƂɂȂ����B
�@�悭���������ɉh�Ɛ��ނ�`�����悤�ȍU���@�ł��邪�A���̗ǍD�ȉ^�����ƑΒn�U���ɑ��鐶�����̍����́A���̃��[�f���卲�ȂǑ����̖Ҏ҂B
�@�Q�[���ł͑Βn�U���Ɋւ���\�͂��ۗ����ėD��Ă�����̂́A���̐퓬�͂܂��������҂ł����A�i������܂߂đΒn�U����p�Ƃ��đ��݂���B�i����C�^�͍͊ڌ^�j
�@�ŏI�i��D�^��1.4t���e�͖��͓I������퓬�̖͂����A�q�������̒Z�����l�b�N�ƂȂ�A�㔼�͎j���ǂ���r��Ȕ�Q���邱�Ƃ������A�������̓���@�ł��낤�B
|
 |
��He111�@�i�����@�j
�@���ԗA���@���J�����������A�\�����̊����i�i���Ԍ^�j�ɑ����i�̒����A�G���W���̉��P�Ȃǂ��{���A�R�d�l�Ƃ��Ċ����������̂��{�@�ƂȂ�B
�@��평���̉��B���ʂł͎�͔����@�Ƃ��Ċ������A�����@�Ƃ��Ă͒v���I�ȂقǑ�h�䐫�\���Ⴍ�A���ɑΉp��ł͒��������Q���o�����B
�@���̌�͎���ɐ퓬�ɗp�����邱�Ƃ͖����Ȃ�A��ɃO���C�_�[�����E�A�������ւƓ]�p����A��햖���ɂ͐퓬�ɎQ�����邱�Ƃ͂قڂȂ��Ȃ��Ă����B
�@�Q�[���ł̓h�C�c�鍑�R�ɂƂ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ��u�U���@�v�Ƃ��Ĕ��ɏd�v�ȃ|�W�V�����ł���B�i��������@�Ƃ��Ă��^�p���邪�B�j
�@�{��̔����@�̓��j�b�g����10�ƂȂ��Ă���A250kg���e���������ςȍU���@�Ƃ��ĉ^�p���\�ƂȂ��Ă���B�iMD��ADV��헪�ł͔����@�̃��j�b�g����6�j
�@���̂��߁A�����I�ɍq�������̒Z���ɔY�܂����h�C�c�鍑�ɂƂ��āA�������U���@�Ƃ��ĉ^�p�ł���{�@�͋M�d�ł���A���������łȂ��U���@�Ƃ��Ă��ϋɓI�Ɏg���Ă��������B
�@�i�����He177�i�{��ł̃h�C�c�鍑�ŋ��̔����@�j�ŗD�G�ł��邽�߁A���܂�g�킸�Ƃ���炩�͈琬�E�X�g�b�N���Ă����đ��͖������낤�B
�@�{��ł̓O���C�_�[�@�E�A����p�@�̊T�O���������߁A���̕��ʂł��܂芈��̏�͖����A�U���@�Ƃ��Ă͑劈��Ȃ̂����E�E�E�M�ғI�ɂ͕��G�ȋC���ł���B
|
 |
��Do17�@�i�����@�j
�@�R��������̐���铽�I�ɗX�֗p�̍����@�Ƃ������ڂŊJ������A�R�p�ɍœK�����ꂽ��͋��ԉ��M�ƌĂ�I��܂Ŋ����@�ł���B
�@�ꉞ�A���ڏ�͗X�֗p�Ƃ͌������̂́A���̋@�̌`��͒N���ǂ����Ă��R���]�p���\�Ȃ��̂ł���A�{�@�̓o��͎��Ӎ��̌x���S��傢�ɐ������悤�ł���B
�@���̓����͟Ӗ��̂Ƃ��艔�M�̂悤�ȃX�����ȋ@�̂ŁA���̌`��Ɣ����Ĕ�r�I��v�ȋ@�̂ł��������A�c�O�Ȃ��瓖���̌v��ɂ������悤�ȍ����\�����@�ł͂Ȃ������B
�@�����^�ł͐��\�I�ɖ����Ȑ��\�E�����ɂ͒������������߂ɔ��ɑ����̉��ǂ��{����A�ŏI�^�ł���Z�^�ɂĂ���Ɓu��r�I�v�o�����X�̗ǂ��@�̂ƂȂ��Ă���B
�@�����A���O�̐v�@�ł͌���������킢�������Ƃ͕s�\�ȏ�A�����ǂ������Ƃ���Ńh�[�o�[���ԍ��ɂ͋��������������A��Q�̑�������{���̔C����������Ă������B
�@��풆���ɂ͐��Y���I���A�c�����@�͓�������ȂLjꕔ�̐��ŏI��܂Ő킢�����A�܂��A�Ɉꕔ�̋@�͉��ǂɉ����G���W�����ڂ��������A�V�K��Do215�ւƓ]�������B
�@�Q�[�����ł�Z�^���o�ꂵ�A���Ղ��瑦���Y���\�ł��邪�ᐫ�\���ڗ����A���R�X�g���Ƃ������x�ł���ƌ����������̖��������@�ƂȂ��Ă���B
�@���\���痐��ɓ�������ΑS�ł͖ڂɌ����Ă��邽�߁A�^�p����Ȃ�Ώo������萧���ł̉^�p���D�܂����A���̓_����ϋɓI�ɂ͎g���ɂ����@�̂ł���B
�@�i�����Do217�n�Ŗ�p�����Ɍ����Ȑi����]�߂邪�A�i���y�[�X��������Do217�n�������Y�o���鎞�����������߁A�i�����Ƃ��Ă��{�@�̉��l�͒Ⴂ�B�iDo215�͓o�ꖳ���j
|
 |
��Ju88�@�i�����@�j
�@�h�C�c�鍑�R�̎�͔����@�ŁA�u�l�X�ȗv���v���牄���E���ǂ��s���A���p�r��Ƃ��đ����̓���C���E���ɓ�������Ă���B
�@�{�@�́A�����A�퓬�@���������ȍ����E���p�r�����@�Ƃ����R���Z�v�g�������Ă������A�����̐퓬�@�̐i���͋ɂ߂đ����A�����ɂ͊��ɍ����Ƃ͌����Ȃ����x�ł������B
�@�܂��A�h�C�c�鍑�R�����@�̗�ɘR�ꂸ�A�����Ȑ��\�ł͂Ȃ��������A����ł������@��̒��ł͔�r�I�ǍD�Ȑ��\�̕��ނł���A�l�X�ȉ��ǎ�A�^�p�@�����܂�Ă���B
�@�����͂������A�O���C�_�[�A�A���A�~�T�C����́A��́i�P���@�j�A�����A��Ԑ퓬�ق��A��C���͂������G�p�܂ł����Ȃ��A�܂��ɑ��p�r�����@�ƌ����銈��ł���B
�@�������A��犈��̏ꂪ�����Ƃ���ΓI�Ȑ��\�͉^�p�@�ł܂��Ȃ���킯�ł��Ȃ��A�O���ł́u�{�@�̔\�͂ł͐퓬�͕s���v�ƍŌ�܂Ō���ꑱ�����܂I����}�����B
�@�Q�[���ł�He111�Ɠ������d�v�ȃ|�W�V�����ɂ��邪�A��X�̌^�����\�̊��ɃR�X�g�������A�����I�Ȑi���𐋂���He111�iHe177�j�ɔ�ׁA���n���ȑ��݂ƂȂ��Ă���B
�@�j���ł͗l�X�ȉ^�p�E����������{�@���A�Q�[���ł͂قڔ����A�Βn�U����p�ƂȂ��Ă���A���̕ӂ�����ɒn�����ɔ��Ԃ�������v�����낤�B
�@�i����S�^��Ar234B�ƗB��W�F�b�g����U���@�ւƐi�����邪�A�i��������܂ЂƂ̐��\�ł���A���̎����Ƃ��ĉ^�p���邩�ǂ����͂��Ȃ�����ȂƂ���ł���B
�@���\�I�ɂ͂���قLj����Ȃ��̂����A�ɂ����@�̂ł���ƌ����悤�B�i�R����3���ɓ͂����AAr234B�ł͂���ɉ�����Ƃ���͂��ɂ����j
|
 |
��Do217�@�i�����@�j
�@Do17�̐����Ȑi���^�Ƃ��ĊJ���E�̗p����A���ڗe�ʂ̑傫���A�ėp���̍������獂���\�@�Ƃ��ďd��Ă����@�̂ł���B
�@�O����Do17�Ǝ��Ă͂��邪�A���g�͍ŐV�̋Z�p�ŗǂ��܂Ƃ߂��Ă���A�o�́E���ڗʂ͏\���ŁA�h�C�c�鍑�R�����@�̒��ł����Ȃ�D�G�ȋ@�̂ł������B
�@������Ju88�n�AHe111�ȂǂƔ�r���Ă����F�͂Ȃ��A�J�낻�������鐫�\�ŁA�����̍��E����C���ɏ]�������B
�@�q�������͕�����Ȃ����̂́A�����O�̔ėp���͔��ɍ����A�t���b�cX�̉^�p��A�Δ����@�쒀�E��Ԑ퓬�^�C�v�ȂǗl�X�ȃ^�C�v�����܂�Ă���B
�@�D�ꂽ�����@�Ɍb�܂�Ȃ������h�C�c�鍑�R�ł͂��邪�A�{�@�̓o��͂܂��ɑҖ]�ł������ƌ����邩������Ȃ��B
�@�Q�[�����ł�Do17Z����i�����\�ł���ADo217E�ɐi�����E��K��M�^�ƃ}�C�i�[�`�F���W�������B
�@K�^����͈�̓����ł���ASM�~�T�C�����^�p�\�ƂȂ邪�A�̐S�̍q�������͒Z���iK�^�ȍ~�R��66�j�AHe�n�AJu�n�̎g������ɂ�����s���ȗ���ɂȂ��Ă���B
�@�I�Պԋ߂ł�K�^�������Y�\�ƂȂ�A��J������ASM�~�T�C�����g���鋭�݂͂�����̂́A�@�̎��̂̃R�X�g�̍�������ʎY�ɂ͌����Ă��Ȃ����낤�B
�@���C�������@�Ƃ��ĉ^�p���悤�Ǝv���Ώo���Ȃ����Ȃ����A���̏ꍇ�ADo�n�����@�ɂ�╨����Ȃ���������͕̂M�҂����ł͂Ȃ��Ǝv����B
|
 |
��He177�@�i�O���C�t�@�����@�j
�@�������������オ���Ă����d�����@�v����L�����Z�����Ă��܂����h�C�c�鍑�R�́A�L��ȗ̓y�����\�r�G�g�ɑ��A�L���Ȑ�p�̂Ƃ�锚���@�������Ȃ��Ɋׂ����B
�@���̗���͊e���ʂŐ�ǂ��i�ނɘA��Ďv���������[���Ȏ��ԂƂȂ�A�{�@�͂��̏�Ŕj���邽�߂ɊJ���E���Y����A�����ւƓ������ꂽ�B
�@�{�@�͓����̐V�Z�p�𐔑���������A2��̃G���W����1�ɂ܂Ƃ߂������G���W�������A�}�~���������l�����Ă������ߋ@�̂����ʂɏd����v�A�ȂLjَ��ȕ��������X����B
�@���̓��ٓ_���Ђ����A�����^�͋ɂ߂Ĕ\�͂��Ⴍ�A�퓬�����̏�ł̋@�̑����������Ƃ����������̂ł��������A���ǂ��i�ނɏ]�����p�I�Ȑ��\�ւƂ������Ă������B
�@���ق��䂦�ɑ��̔����@�Ƃ͔�r���ɂ������A�h�C�c�鍑�R�����@�̒��ł͔�r�I���\�������A�������͍����������̂Ǝv����B
�@�Q�[�����ł̓h�C�c�鍑�R�ŋ��̔����@�ł���A�\���ȔR���A�傫�����ڗʁA�Ί�ASM���g�p�\�Ɣėp���������A�f�̔\�͂���^�p�ʂɂ����Ă��������\���ւ�B
�@�A�����J��B-29�قǂ̖h�q�\�͎͂����Ȃ����̂́A����ł������ԍ����s����ōŒ���K�v�Ȗh�q�\�͂͂���A250kg���e�����邱�ƂŒ����Ԃ̒n��U�����\���B
�@���̒Z���h�C�c�鍑�R�@���������A��x�̕⋋�Œ����Ԃ̍s�����\�Ȗ{�@�͋M�d�ł���A�o����܂Ƃ܂��������^�p�������B
�@�{�@�̃R�X�g�͔��ɍ�����ʐ��Y�͂��ɂ������̂́A�i������He111�̃R�X�g�͂���قǂł��Ȃ����߁AHe111����i��������̂��ł������I�ȓ�����@���낤�B
|
 |
���㎵���퓬�@�@�i�퓬�@�j
�@�R�����ƂƂ��Ă̓������ł�������{�鍑�ł́A��ɊJ�����ꂽ��Z�͐�̐����Ɉ��������V���ȗ��R�@�̊J�����v��A�����̃��[�J�[�ɑ�����@�̊J���𖽂����B
�@���A�����A�O�H�̊e�Ђ͎���@���쐬���A����������r���������{�����Ƃ���A�o�����X���悭����Ɍy���ȉ^�����\���������킹�������̎���@���{�̗p�ƂȂ����B
�@���̋@�̓����͋ɂ߂č����^�����\�ł���A�i�����\�����Ȃ�Γ������ɑ��݂������E���̂ǂ̐퓬�@�����D��Ă����ƒf�����Ă��ǂ��قǂł������ƌ����B
�@��풼�O�܂ł̒����E�\�r�G�g��ɂ����Ă͑���̐퓬�@�������ł��������Ƃ�����傫�Ȑ�ʂ��c�������A����̗���͔��ɑ����A����͌���}���ɑ�������ނ��Ă���B
�@�y��ɑ�����ł��낤�{�@�ɂ́A�y��Ȃ�ł͂̔�e���̖h�䐫�\���Ⴂ�A�����̕n�コ�A�����x���\�ɂ����ȂǑ��X�̎�_������A���̓_�����������Ԃ͒Z�������B
�@�Ȃ��A�`���I�ɑ���{�鍑�R���d�������퓬�@�̑I�l��u�i�����\�d���v�̎p���͖{�@�������炵�����̂ƌ����A�ǂ��Ӗ��E�����Ӗ��o���ō���̐퓬�@�J���ɉe����^�����B
�@�Q�[���ł͏��Ղɓo�ꂵ�A�j�����l�A�����E�\�r�G�g��ł�����x�̊����҂ł��邪�A���͂��߂Ƃ��鎟����@�o���͈�C�ɂ��̑��݉��l�𗎂Ƃ��B
�@�͂����茾���Ώ��Ղ݂̂̐퓬�@�ł���A�i������܂߂Ė����ɑ����Ďg���K�v�͖����A���ق�������퓬�@�̓o���͂��ׂĔp�����Ă����܂�Ȃ����낤�B
�@�i����͔��ɂȂ邪�A��������i�������d�˂Ă����\�I�ɂ͒��Ղ܂ł̐퓬�@�ƂȂ��Ă��邽�߁A�{�@�┹�͎�ŏ����������x�ɂ����ق�������ł���B
|
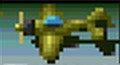 |
���뎮�͏�퓬�@�@�i�͏�퓬�@�j
�@���킸�ƒm�ꂽ����{�鍑�R�̊͏�퓬�@�ł���A��평���̖��o��Ԃ̊���Ԃ肩��`���I�Ƃ�������퓬�@�ł���B
�@���̐��̂͏d�v�ȕ�����I�ʂ��A�ł�����肻�̕������d�����A����ɂ���قǕK�v�̂Ȃ��Ƃ�����o�b�T���Ɛ�̂Ă�Ƃ����ɒ[�ȃR���Z�v�g�̐퓬�@�ł������B
�@���̃R���Z�v�g�͓����Ƃ��Ă͎a�V�Ȃ��̂ŁA�o�ꎞ�Ƃ��Ă͐��E�ő����x���A�����20mm�@�֖C�̑�Η͏d�����Ƃ܂��ɍU�߂邽�߂̔�s�@�ƌ����Ă悢�B
�@�ߍ��Ȍy�ʉ��̂������ŏd�����ł����Ă��^�����\�͔��ɗǂ��A�ɒ[�ȃo�����X�ł͂���������평���ɑ听�������߁A���r���𗁂т��B�i�n�����Ƃ̑g�ݍ��킹���傫���j
�@�������A���̐����͖{�@�̑����z���������A���{�R�͌㑱�ƂȂ�ׂ��V�^�퓬�@�̊J�����v���悤�ɐi�܂Ȃ��Ȃ�Ƃ������z�Ɋׂ��Ă��܂����ƂɂȂ�B
�@���ɂ͒����킢�̒����b�l����A�A�����J�R�̎�ɓn���Ă��܂����@�̂�����A�����͉�͌����Ɏg����_�̖\�I�A����p�̊m���ɂȂ������B
�@�Q�[���ł͓��^����o�ꂵ�A����ȍq���́A������@�Ɣ�r���Ĉ��|�I�ȉΉA������̍��B�x�A���ɂ��@���킪�\�ƁA���Ղł̓C���`�L�������܂ł̐��\���ւ�B
�@�������A���Ղɍ����|����G������̎������シ��ƁA���ǎ���܂߂đ���f���Ȃ��Ήi���x�j�A��e���̂��낳�i�h��́j���퓬�ɒǂ����Ȃ��Ȃ�A�g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B
�@���ǎ�͗��R���/�O��^�A�C�R�ܓ�^�ƂȂ邪�A�܂Ƃ��Ȃ��̂͌ܓ�^�̂݁i����ł����x14�j�ł���A�I�Ղɂ͂قڑS�Ă������⎇�d���Ȃǂɐ�ւ��邱�ƂɂȂ邾�낤�B
|

coffee break |
|
�`�퓬�@�Ƃ��Ă̗��A�H�Ɛ��i�Ƃ��Ă̗��`
�@����{�鍑�̎O�H�뎮�͏�퓬�@�͐��E�I�ɂ��L���ŁA�o�ꓖ���A�قڊԈႢ�Ȃ����E�ō���̐퓬�@�ł���B�����O�̌y���������������ɂ߂č����i���\�͂������A���ɒ����q�������͐i�s��@����ɂ����ď�ɑ傫�ȓ꒣����ێ��ł����B����͊J���w�̗܂��܂����w�͂ɂ���Đ����������̂ŁA���̋�J�����ꂽ�u�Ԃł��������B��평���̊���͓��ɂ��炵���A�܂��ɖ��o��Ԃƌ����ĉߌ��͖����قǂł������B
�@�������A�퓬�@�Ƃ��đ听�������߂����ɂ������_�͂���A�h�������@�̋��x�͌����ėǂ��Ȃ������B�����čL��̐��ɑΉ����邽�߁A����̐������낦�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����E���ɂ����ďd�v�ȁu���Y���v���ǂ��Ȃ������B�����̑���{�鍑�͎Q�퍑�̒��ł����x�ȋZ�p��ێ����Ă��������������A����ł����Ȃ��݂̐E�l�C���̍��ł�����A���Y�H����@�B�����邾���̍��́E���������肸�A���ǂ͐l�̎�ɂ��ʓ|�ȍ�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����̂ł���B���̖ʓ|���́A��ʓI�ɗ��ƃA�����J��P-51�Ƃ̔�r�ł͐��Y�H������3�{�̍�������Ƃ�������قǂŁi�M�҂͍ו��H���E�R���|�[�l���g�P�i�ł������5�`6�{���炢�̍��͂��邾�낤�Ǝv���Ă���j�A���̂悤�Ȑ��Y���l�����u�H�Ɩʁv���猩��Ɨ��͂͂��߂��猆��@�ł͂Ȃ������̂����m��Ȃ��B
�@�Ƃ�����A��킪�u�퓬�@�Ƃ��Ă̌���@�v�ł��鎖�ɕς��͖����A�퓬�@�̗��j�ɐV����1�y�[�W���c�������ɕς��͖����B
|
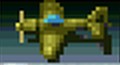 |
�����@�i�͏�퓬�@�j
�@���̐����Ȍ�p�@�Ƃ��ĊJ������Ă�������{�鍑�R�̊͏�퓬�@�ł��邪�A����@���x���̂��̂�8�@�������������ŏI��܂łɊԂɍ���Ȃ������@�ł���B
�@�Q�킵�Ă��Ȃ����ߊ���͖������A�����悻���Ǝ����悤�ȗ���ɉ����x�z�Z�t�ɂ��v�A�ڗ����́A�ɂ��������ɏo��Ȃ��������c�ɂ����Ȃǂ���l�C�͍����B
�@�v�̕��j�͏d�����A�������^�����\�������Ƃ������̂ŁA��҉ׂ��ɂ߂ēs���̗ǂ��v�����\�ł��������A�J�����͂Ȃ��Ȃ����̗v���ɓ͂��Ȃ������ƌ����B
�@�@�̂͋��͂ȕ����A���x�A�^�����\�邽�߁A�K�R�I�ɋ��͂ȃG���W�����K�v�ƂȂ�A��s�@�Ƃ��Ẵo�����X���l����Ƒ�^�ɂ����邨�����A�������啪��^�ƂȂ��Ă���B
�@���s����̑����x�d�Ȃ鎎��̒��A�G���W���̊J���E�œK�����s��ꂽ��͔�s�e�X�g�ɂ����Ă���r�I�ǂ����т����߂�悤�ɂȂ�A�����ł���Ɛ��������ꂽ�B
�@�������A�����̑���{�鍑�R�ł͐퓬�@�̎�ނ̑����ɂ�鐶�Y�̍����ɉ����A���͂̒ቺ����{�@��ʎY�ł���]�T�͊��ɖ����A�Ƃ��Ƃ����邱�Ƃ͖��������B
�@�Q�[�����ł͖����ɗ��n����i���œ��邱�Ƃ��\�ƂȂ邪�A�ŏI�i���̊͏�퓬�@�Ƃ��Ă͒Ⴂ���\�ŁA���܂�ǂ��Ƃ���̖����@�ł���B
�@�j���ł̊�������ɍ��̗͂����������̐퓬�@�ł��邽�߁A�d�����Ȃ��ƌ����Ύd�����Ȃ����A���\�͏��c�����������������x�Ő퓬�͂͂�◊��Ȃ��B
�@���݂̂ɓ�������Ă��܂����Ƃ��g������̒ቺ�������A�������ɂ͎g������̗ǂ����d���Ȃǂ����邽�߁A�����ȂƂ����ȊO�Ői��Ŏg�����R�͖������낤�B
|
 |
�����d�@�i�ǒn�퓬�@�j
�@�C�R�@�ł�����̂́A����ł̉^�p��O��ɊJ������A����^�����@�ɑ��m���ȑΏ����ł���悤�v���ꂽ�ǒn�퓬�@�ł���B
�@���d�ɗv�����ꂽ�\�͂́A�Z���ԂœG�����@�̂��鍂�x�ɍ����㏸���\�Ȃ��ƂƁA���̍������ێ��ł��邱�ƁA��^�@�ɑ��ėL���ȉΗ͂�L���邱�Ƃł���B
�@��^�̑�n�̓G���W���𓋍ڂ���K�v�����������ƂƁA�ォ��`���[�W���[�݂ł���悤�v���ꂽ���Ƃ��瓷�������A���̑������i���ɑO���j�������ł��낤�B
�@�Ȃ��A�����@��B-29�ƘA�z���Ă��܂����������A���d���J������邫�������ƂȂ����̂͒�������ł̔�����Q�ł���A�ΕĐ�J��ȑO����̊J���@�ƂȂ�B
�@�J���i�K�ł͂�����x�ǍD�Ȑ��т����߂����̂́A�Ǐ��Ŗ�肪�������A���ɃG���W������̖��͑傫���A���̖��͐��������ꂽ����O���ł͕s�]�����悤���B
�@�������Ȃ���A�S�̓I�ɖڗ�������ʂ͂Ȃ����̂́A�ꕔ�A�D���ɂĉ^�p���ꂽ�{�@���傫�Ȑ�ʂ��グ�A���ݔ\�͂̍��������炵�߂��B
�@�����̑���{�鍑�@�ǂ�ɂ������邪�A�{�@����ɘR�ꂸ�����e�i���X�ƍ��i���R��������A�ƁA�ɂ��܂��@�̂��Ǝv����B
�@�Q�[�����ł͉Η�120�Ɣ��Q�̍U���͂��ւ邪�A�ǒn�퓬�@�Ȃ�ł͂̔R���̏��Ȃ��A���x����߂�14�Ǝg�����肪�����̂��Ȃ�܂����B
�@�i����͎��d���i��ꒅ�͉j���k�d���k�d���Ɣ��ɗD�G�ŁA�i����̕���𑁂������������ꍇ�̓X�g�b�N�E�琬�͕K�{�ł���B
|
 |
�����d���@�i�ǒn�퓬�@�j
�@���̃��f���ł��鎇�d�͂����ނ˗ǍD�Ȑ��\���������A�ƂȂ�����ǂ̂��ߊJ���r���Ŗ����ɐ��Y���J�n���ꂽ���Ƃ�����A�ǂ����Ă����_���c�����܂܂ł������B
�@���̌��_�����ǂ��A�����Đ����H���E���i�_�����������A�}�C�i�[�`�F���W��}�����̂��{�@�ƂȂ�B
�@�����A�}�C�i�[�`�F���W�Ƃ͌����Ă��A���Ȃ�̉��C������Ă���A�x�[�X�̋����A���d�Ɣ�r����Ɖ^�p���\�E��s�����͌��\�ȈႢ���������B
�@�J�^���O�X�y�b�N�I�ɂ̓A�����J�R�̍ŐV�s�퓬�@�ƌ݊p�ɐ킦�鍂���\�@�ł��������A���Y�\�͂̒ቺ���琶�Y�䐔�������Ă���A��ǂ����E����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B
�@�܂��A�ꕔ�A�ɂ߂ċǒn�I�ɂ͐�ʂ��オ���Ă����悤�����A�����������퓬�ł�����{�鍑�R�̑��Q�͑傫���A�ŏI�I�ȃX�R�A�ł͌��ǂ̂Ƃ��둹�Q�̕����傫�������B
�@�Q�[�����ł͗��d����̐i���A���@�����ɂ�鑦���Y�Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��\�ŁA�㔼�Ȃ���ł���y�ɐ��Y�ł���B
�@�ΉE���x�i120/16�j���ɏI�Ղɂ����Ă̐퓬�@�Ƃ��Ă͕��ϓI�Ȕ\�͂������Ă���A���A�͍ڋ@�����̂��ߋ��ł̉^�p���\�Ƃ����A�g������̗ǂ�����ƂȂ��Ă���B
�@���\�͗��ܓ�^���y������A�ȏ�̉^�p�\�͂��������킹�Ă��邽�߁A�����I�ȗ��̌�p�@�Ƃ��Ĉ����̂������߂ł���B�i������͖̂h��͒��x�j
�@�i����͋ɂ߂ċ��͂Ȑk�d�ƂȂ��Ă���A�{�@���̂̉^�p���\�̂悳�ɉ����A�i�����D�G�Ƃ����A�����s������̋ǒn�퓬�@���B
|
 |
���k�d�@�i�ǒn�퓬�@�j
�@�v���y�����㕔�ݒu�Ƃ����A���̓Ɠ��ȃt�H��������l�C�����ɍ����ǒn�퓬�@�ł���B
�@�㕔�v���y���̌����͑����ł������͂���Ă������A����������p������Ă��炸�A�{�@���������O�ɏI��A�J���j������邱�ƂɂȂ�A���ǂ͎��p���ł��Ȃ������B
�@�v���y�����㕔�ɂ����ꍇ�A�q��w�I�ɑ����̃����b�g�����邪�A���ʃf�����b�g�����ɑ����A�����������@�Ŋw�p�I���ʂ��m�F�o���Ȃ��͔̂��Ɏc�O�ł���B
�@�����A�����b�g�E�f�����b�g��V���ɂ������ꍇ�A�����̍q��Ȋw�ł̓f�����b�g�̕����d���Ȃ�ƍl�����邽�߁A�ɒ[�ȍ����\�@�̎����͖����ł͖������Ǝv����B
�@�{�@���������A���ۂɐ���֓�������Ă����Ȃ�E�E�E�ƍl���邾���ł���������A���ǂ̂Ƃ��늮�����Ȃ��ق����悩�����̂�������Ȃ��B
�@�Q�[���ł�150�Ƃ����ɂ߂č����Η͂�L���A���x��20�Ɣ��ɋ��͂Ȑ퓬�@�ŁA��G���A�����J�̃p���^�[�iF9F�j�Ƃ͌݊p�ɓn�荇�����Ƃ��\�ł���B
�@�i���������d���Ɣ��ɂ���y�ŁA����{�鍑���g���Ȃ�A�����j�b�g�̓X�g�b�N���Ă��������Ƃ���ł���B
�@���ʁA�e���R���A�ړ��͖͂R�����A��`�̏��Ȃ��}�b�v��L��}�b�v�ł͉^�p�����ɂ������߁A���S�҂ɂ͂��܂肨���߂̏o����@�̂ł͂Ȃ��B
�@�i����̐k�d���ł͂���Ɏg�����肪�����邽�߁A�{�@�̂܂܉^�p���邩�A�i�����邩�A�͂��܂��H���������A�Η͂Ɛi�R�\�͂��l���ĉ^�p�������B
|
 |
���H���@�i�ǒn�퓬�@�j
�@�A�����J�R�����@�ɑ��L���ȍU����i�������Ȃ��������{�R�́A�h�C�c�鍑�ƌ��������ɂ��Me163�̏�����ɓ���邱�Ƃɐ����A���̃R�s�[�Ƃ��ĊJ������Ă����B
�@�����Ƃ��A�R�s�[�Ƃ͌����Ă����A�����̔�Q�ɂ��A�啪�����������Ԃœ͂��Ă��邽�߁A���S�ȃR�s�[�ƌ����킯�ł͂Ȃ��B
�@�J���͓��{�R�j�������ʂقǂ̘A�g�̐��ōs���Ă���A���R�A�C�R�A�O�H�Ɗ�����̂Ői�߂�ꂽ�B
�@�������A�}���ꂽ�J�����ނȂ����I����}���A���ǁA�J���@�����@���������݂̂ŁA�퓬�ɎQ�����邱�Ƃ͖��������B
�@�]�k����2010�N7���ɁA��t�Ŗ{�@�̔R���^���N�ۊǏꏊ�Ǝv����n���{�݂���������Ă���A���̂��Ƃ�����p�����߂��������Ƃ�����������B
�@�Q�[�����̏H���̓��P�b�g�퓬�@�̐��\�E������O�ʂɑł��o�����҉ΉE��q���͂������ŁA�I�Ղɐ��Y�\�ƂȂ�B
�@�Η͂�140�A���x��24�iTa183�����j�ƂȂ��Ă���A���ł͌������Ƃ���G�Ȃ���Ԃ̒������\�@�ŁA�ǒn�I���m�ۂ̂��߂̎�́E�⏕�Ƒ劈��Ȃ̂͂قڊԈႢ�Ȃ��B
�@���̒Z���A�R���E�����̏��Ȃ������_�ƂȂ邪�A�M�ғI�ɂ͕Г��ؕ��̎g���̂ċ@�Ɗ�����Ďg�����ɂ́A���̌��_���܂��������Ȃ����Ǝv����B
�@�܂��A�{�@�͍|�S�̐����F�C���h�Ő��Y�\��2�o�^����Ă�����ƕς��������������B�i�����2�A���t�@�C���ł͏C������Ă��邱�Ƃ���o�O�̉\���������Ǝv����B�j
|
 |
���ꎮ�퓬�@�@���@�i�퓬�@�j
�@���Ɏ������Y���ő���{�鍑�̎�͐퓬�@�̈�[��S���Ă����퓬�@�ł���B
�@���̌y�ʂ��A�T���߂̕�������y��ɑ����邾�낤�B
�@�v�v�z�ɂ��ɂ߂ėD�ꂽ�^�����\�A�y�ʐ��������������ŁA�i����ɂ����Ă͂��Δ��������\�������B
�@���ɂ܂��b�œ��ɗL���Ȃ̂������������̊���ł��낤�B�i�G�s�\�[�h�͒����Ȃ邽�ߏȗ��j
�@�Q�[���ł͈�^�`�O�^�����Ԃɓo�ꂵ�A���Y�A�i�������ɉ\�ł���B
�@���͉^�����\���ǂ��Ƃ����x���o�Ȃ��퓬�@�̂��߁A�ǂ����Ă����e�����킵�Ċi����Ɏ������ރX�^�C���ƂȂ�B
�@������l�����Ă��U�����x�����Ȃ�Ⴍ�A�ō��i���ł���O�^�ł������Ոȍ~�͐搧�U������ꂸ�A����������B
�@���Ղ͍q�������������o�����X���ǂ����߁A�g�����肪�悭�j���ǂ���̊���������邪�A���Ոȍ~�͍D��Ŏg�����Ƃ��Ȃ����낤�B
|
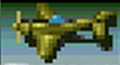 |
���P���퓬�@�@���c�@�i�퓬�@�j
�@�\�r�G�g�Ƃ̐퓬�ɂ��A���B���ʂ̐퓬�@�v�z�ɐG�ꂽ���{�R�́A�^�������d�������y��݂̂̔z���ɋ^��������A�V���Ȑ퓬�X�^�C�������퓬�@�̊J�������݂��B
�@���̌��ʊ��������̂��d�퓬�@�Ƃ��Ă̖{�@�A���c�ł���B
�@�{�@�̓����́A����܂Ŏ����悤�Ȑ�@���g�킴��Ȃ��������{�R�ɁA�V���Ȑ퓬�X�^�C���������炷���ƂɂȂ�B
�@�{�@�́A�^��������邱�Ƃ���ω��ɓK���̂Ȃ��V���ȏn���p�C���b�g����͌h�����ꂽ���A�D�ꂽ���x�A���x�A�Η͎͂Ⴂ�p�C���b�g����͑傫�Ȏx�����W�߂��B
�@����ŁA���������̕Ȃ̂�����������ƂȂ�A�����Ύ��̂��������A�����ɂ͂�����x�̘B�x���K�v�ł������悤�ł���B
�@�Q�[�����ł̖{�@�́A���Ɍ��E�������n�߂��������D�u�Ɠo�ꂵ�A�U����90�A���x16�Ƃ����Η͂̓h�C�c�鍑��Fw190A�Ƃقړ����ŁA�g�������Ă��قړ����ł���B
�@�����n�ł͗��ɕς���͂Ƃ��đ傫�ȗ͂����邾�낤�B
�@�i����ɂ��b�܂�A�l���펾���̎�ł��邱�Ƃ���A���Ձ`�I�Ղł̊��������Ă���B
|
 |
���O���퓬�@�@���@�i�퓬�@�j
�@���B�@���霂Ƃ�����X�����ȋ@�́A�h�C�c�鍑���烉�C�Z���X�擾�����ǂ��{�����G���W���A���O���ڗ��_����l�C�̍����퓬�@�ł���B
�@�傫�ȓ����Ƃ��Ă͋�₪�嗬�ł���������{�鍑�R�@�̒��ō��x�ȉt��G���W�����̗p���Ă���_�ł͂Ȃ��낤���B�i���ς�炸�s���ɂ͕t���܂Ƃ��邪�E�E�E�B�j
�@�܂��A�{�@�͌y��̕��ނɓ���Ǝv���邪�A�����I�ȑ����i�͌y������邽�߁A��T�Ɍy��Ƃ͌����Ȃ����ނ̓���@�̂ł���A����������ł��낤�B
�@���\�I�ɂ́A���x�͏o�邪�^�����\�͌����č����Ƃ͌������A���G�ȉt��G���W���͉ғ����̒ቺ�������Ă��܂��A�n���̐������łȂ���Ύ�ɗ]��@�̂ł������B
�@���ʁA�����e�i���X���s���͂��Ƃ���ɖ\����悤�ɂȂ�A�Ⴂ���i���x��ێ�ŃJ�o�[�ł���Ζ{���̍����|�e���V�������⊶�Ȃ����������ƌ����Ă���B
�@��������{�鍑�̂��Ƃ������鎿�̒ቺ�ɂ���ĉ^�p�͋ɂ߂Č��������̂ł��������A����ł��{�y�h�q�̂��߉ʊ��ɉ��x����֔�т������B
�@�Q�[�����ł͌㔼�ɍ����|���邠����Ő��Y���\�ƂȂ�A�i���͖��͂ɗ����퓬�@�A�k�Ԃւƌq����B
�@�ΉE���x��120/16�Ə\���ł���A�h��͂������Č㔼�ł��ʗp���鐫�\�ł���A���A�@���́E�q�������ɗ��A����@�ł��邽�ߊ͍ڂ��s�Ƃ����g���ɂ���������B
�@��Q���̕�[�����Ȃ��Ȃǃf�����b�g�����Ȃ�傫���A��͂Ƃ��ĉ^�p����ɂ͖�肪�������߁A��ŏ������^�p����ɂƂǂ߂��ق����������낤�B
|
 |
���l���퓬�@�@�����@�i�퓬�@�j
�@���{�R�̎��q��Z�p�����܂��������A�����Ȑv�Ȃ�������Ƀo�����X�̐������퓬�@�ł���B�i���̃A�����J�R�^�p�e�X�g�̎��_�ɂ��]���j
�@���N���X�̑����퓬�@�Ɣ�r���Ĉ��菬�����̂������ŁA�ΉA��e�h��Ɋւ��鐫�\�͓��{�R�퓬�@�Ƃ��Ă̓g�b�v���x���ɓ���B
�@�{�@�́A�����e�i���X���{���ꊮ���Ȃ�Ύv�����������\�Ԃ���������A�����ɂ���Ă͉ғ������������Ⴉ�����B
�@�o�ꂵ�������������̂��߁A���Y�i���̒ቺ��n���H�̑����Ɠ������ɂ�閳�����ȃ����e�i���X�A�K�\�����̃I�N�^�����ቺ�ȂǗl�X�ȉe�����������悤�ł���B
�@�ꕔ�̕����ł͓w�͂ɂ�郁���e�i���X�ŋ��ٓI�ȉғ������ւ������A����͈ꕔ�̓��ʂȘb�ł����āA�S�̓I�ȉғ����Ō���Ƃ�͂�Ⴂ�B
�@���̕]���ł͗D��ɒ[�ɕ]������邱�Ƃ������悤�ł͂��邪�A�M�ғI�ɂ͒P�̐��\�͍����������A�푈���Ɏg���Ȃ����^�p���\�͋ɂ߂ĒႩ�����ƍl�@����B
�@�Q�[�����ł̖{�@�͏��c����̐i���A���@�����ɂ�鐶�Y���\�ł���B
�@���\�̓A�����J�̃}�X�^���O�Ɏ��Ă���A�ڗ��Ƃ���ł͕������������x�ŁA�����{�R�퓬�@�ƈ���đ�^���e���ς߂�B
�@�o��`�I�Ղɂ����Ĕ��ɗ���ɂȂ邪�A���x��16�Ƃ������ƂŏI�Ղ͐搧�����Ȃ����Ԃ��o�Ă��邽�߁A�ł��邾���B�x�̍�����Ԃʼn^�p�������B
|
 |
�����퓬�@�@�i�퓬�@�j
�@����{�鍑�Ō�̐퓬�@�ł���A�^�p���Ԃ����܂�ɂ��Z���A�ق��̗��R�@�̂悤�ɖ��̂̒����Ȃ������@�̂ł���B
�@�@�͎̂O����̂��̂ł��邪�A����͖{���A�O����Ŏg����\��ł������@�̂��A�G���W�������܂�̒Ⴓ����]��ƂȂ��Ă��܂��A�@�̂����p���ꂽ���Ƃɂ��B
�@�O����͌��X�t��G���W���𓋍ڂ��Ă������A���s����̏���G���W���֊������Ă�������������Ƃ���A�z��O�̗ǍD�ȃo�����X�������A�����Ɍ��킪�a�������B
�@�{�@�͊��ň����₷���A�^�p�E���������₷���ƗǍD�ȕ]���ł������ƌ����Ă��邪�A���������������A������Z���ł��邽�ߐ^�U�͖��m�ł͂Ȃ����낤�ƕM�҂͍l����B
�@�������A����{�鍑�R�ƃA�����J�R�̌��X�R�A���Ƃ炵���킹�čl����ƌ����ĒႢ���\�ł͂Ȃ��A�ނ��뎞��Ɍ��������������\�ł������ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�@�̂����̂܂ܗ��p���ꂽ�����^���͂��߂Ƃ��A�œK���E���ǂ��Z���ԂŐϋɓI�ɍs���Ă���A���̂��Ƃ�����{�@�ւ̊��҂��傫���������Ƃ��f����B
�@�Q�[���ł͏I�Ղ֍����|���邠����ɓo�ꂵ�A�O�������̐i���A�ꕔ�}�b�v�ł͑����Y�Ŏ�ɓ���B
�@�o�ꎞ�����l����ƉΗ�120�E���x14�Ƃ������\�͏����Ȑ퓬�@�Ƃ��Ă͂��Ȃ�Ⴍ�A�������̂�������鐫�\�ł���A�ǂ��_�͑�h�䐫�\���G�łĂ��邭�炢�ł���B
�@�V����͋k�Ԃʼn^�p���ɂ����W�F�b�g�퓬�@�ƂȂ��Ă��܂���A�������̗��R�@�A�C�R�@�ɂ͑���̐퓬�@�����邽�߁A�ϋɓI�ɖ{�@���g�����R�������_���ɂ����B
|
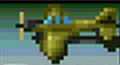 |
����㎮�͏㔚���@�@�i�͏�}�~�������@�j
�@��평���`�����ɂ����Ĕ��ɍ������������ւ�A�������A���R�̊͑D�߂����@�Ƃ��ėL���Ȋ͏㔚���@�ł���B
�@�{�@�͐������̈��m�q��@���h�C�c�̃n�C���P���Ђƒ�g���Ă������Ƃ�����A���{�@�Ƃ��������A�ǂ��炩�ƌ����ƃh�C�c�@�ɋ߂������������Ă���B
�@�����ȂƂ���A�����J��SBD�ɔ�r���ď���ʂ͏��Ȃ��̂����i�����\�͍����Ȃ��j�A����������x����ρA���E�㎵�͍U�Ƃ̘A�g���\�ł��������Ƃ�������ʂ��グ���B
�@�������A���̊������피�܂łł���A�A�����J�R�̐퓬�Ԑ��������n�߂�Ɩh�e�����̕n�コ���Ђ����A����ɔ�Q�͑���A��]���ċ��Ԋ�������Ԃɒǂ����܂��B
�@�{���Ȃ�A��피�Ŏ�����@��Ɍ�コ���͂��ł��������A��ɘR�ꂸ�J���E���Y�̒x��͉��P���ꂸ�A���\�Ɍ��E�����Ă��I��܂Ŏg���������邱�ƂƂȂ����B
�@���Ղ����X����������������̂́A�ŏI�I�ɂ͐��Y�z�����ꂽ�w�ǂ̋@�̂����āE�j��Ă���A����͖{�@�̋A�җ��i������̐������j�����낵���Ⴉ���������Ӗ�����B
�@�Q�[�����ł͊��Ɗ��ȋ}�~�������@�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă���A���炭����Ό�����Y�^�̓��^���^�p���\�ƂȂ�B�i���^�ւ̉��ǂ͕K�v�Ȃ����낤�B�j
�@����{�鍑�L�����y�[���ł͏����`���Ղɂ����ċ@�������̎�͍U���@�ł���A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����݂��낤�B
�@�����A�j���ǂ��蒆�Ոȍ~�͂�����Ƃ������ɑ��S�łƌ����ꍇ�������邽�߁A��p�̐i����A�a�����z�������܂ł͏o���邾����q�����ʼn^�p�������Ƃ���ł���B
�@�Ȃ��A�Ί͑D�̏ꍇ�́A�{�@�̐��Y�E�z�����͗��E�͍U�Ƃ̘A�g�ɂ�������邽�߁A�����łǂ̂��炢�̐����K�v���A��������l���Ăق����B
|
 |
���a���@�i�͏�}�~�������@�j
�@�͏㔚���@�̔\�͕s���i���ɑ��x�j����F��������������{�鍑�ł́A�͏㔚���@���ᑬ�ƌ��������ł��j��ׂ��V�^�����͏㔚���@�̊J���ɒ��肵���B
�@�v�����ꂽ���\�́A�����̑���{�鍑�ł͓��ꓞ�B�ł�����̂ł͂Ȃ��������A���^�̋@�̂ɍŐV�Z�p��ɂ����Ȃ��ςݍ��ނƌ����`�ʼn��Ƃ����������Ă���B
�@���ꂪ�{�@�ł���A����܂ł̒ᑬ�Ȋ͏㔚���@�Ƃ͂܂������Ⴄ�A�͏㔚���@�Ƃ��Ă͂���܂łɖ������x���\�����ٍʂ�����݂Ƃ��ēo�ꂵ���B
�@�O�����Y���͐���G���W���𓋍ڂ��Ă������A���̃G���W���͓����̑���{�鍑�̋Z�p�͂ł͈�������̂łȂ��A���\����Ƃ͋t�ɒ������ғ����ቺ�������Ă��܂��Ă���B
�@��������͋��G���W���֎d�l�ύX���Ȃ���A�@�̎��̂̋Z�p�I���͑啪�����������A���͊��ɑ���{�鍑�̐��ފ��ɓ����Ă���A�i�����疞���Ȑ��\�͏o�Ȃ������B
�@�]���̒Ⴂ�@�̂ł͂��邪�A�������A�@�\�̗L�����͔�r�I�����A�R�S�̂ŕ��u�����̂悤�ɗD�ꂽ�����A�^�p���@���{����Ă���A�傫�Ȑ�������������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɍ����|���鍠�ɋ��͔����i���A�܂��͑����Y���\�ƂȂ�A���Ȗh�䐫�\�A���e���ڗʁA�q�������A�ǂ���Ƃ��Ă����ɗ���ɂȂ鑶�݂ł���B
�@�{�@�͔��ɍ����D��������Ă���A������x�̎��Ȗh�q�����Βn�U�����\�ƌ����A�ɂ߂ė��z�I�Ȋ͏㔚���@�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�ł�����葁�������ɉ��������B
�@����Ői���A�܂��͏I�Ղ̈ꕔ�}�b�v�ł̋����i���ł͗������ƂȂ�A��̎g�������Ēቺ���������Ă��܂��A����ɂ͒��ӂ��K�v���낤�B�i���������͍̂����\�͍U�j
|
 |
���㎵���͏�U���@�@�i�͏�U���@�j
�@����܂Ŋ͏�U���@�̊J�����s�������Ă�������{�鍑�R�ł́A�{�@�̊J���ɂ�����ӋC���݂͍����A�J���l���E�@�̑f�ނȂǑ����̃��\�[�X���ɂ������Ȃ��������ꂽ�B
�@�����������̈ꕔ�Ƃ��ẮA�v���y���s�b�`�A���h�ɓ����I�Ȃ��̂���������A�t���b�v�Z�p���̗p����Ă��邱�Ƃł���B
�@���̐��ʂƂ��Ċ��������{�@�́A���{�j�㏉�̑S�������P���͏�U���@�ƂȂ�A�����Ƃ��Ă͐��E�I�Ɍ��Ă��Ő�[�Z�p���ڂ̍ŐV�s�E�ō���͏�U���@�ƂȂ����B
�@�Ȃ��A���̎�ɂ͒�����s�@���i�O���A���nj���^�j�A�O�H���̂��̂����݂��邪�A��ʓI�ɋ㎵���͏�U���@�ƌ����A������s�@���ł���B
�@��평���ɂ͑劈����������̂́A�������������������i�݁A�G�̑�C�ΉΗ͂��オ��n�߂�Ɣ�Q�͂����܂����債�A�X��������͂����Z���ԂɏI����Ă���B
�@��ɘR�ꂸ��p�@�̊J���͐i�܂��A�����ɂ͓��U�ɂ��g�p����A�ŏI�I�Ɏc�������̂�1�����A�����͑��̑���{�鍑�R�q��@�Ɠ��l�̉^���ł������B
�@�Q�[���ł͗��Ƌ��ɓo�ꂵ�A�C�R�@�̈���Ƃ��ė��E�͔��ƃg���I���Ȃ��B
�@���\�͂���قǍ����͖������A���G�͈͂��L���A���������ډ\�ł��邱�Ƃ���A���E�͔��Ƃ̔䗦���l���Ȃ���C�펞�ɂ͕K���{�@�������Ă��������B�i�����߂��͋֕����j
�@�i����͓V�R�ŁA����������\�͌����č����Ȃ����̂́A�ǂ������̓����͎p���ł��邽�߁A�i������͏o������葁�߂ɐi���������߂���B
|
 |
���V�R�@�i�͏�U���@�j
�@���������������i�㎵���͍U�̌�p�@�Ƃ��ĊJ������A�傫�Ȕ�Q����Ȃ�����I��܂ʼn䖝�����킢�������@�̂̈�ł���B
�@�{�@�́A���\�Ɍ���G���W���ɂ���đO���^�E����^�ɕ����鎖���o���A�O���^�ł͗_�G���W���A����^�ł͉ΐ��G���W�����̗p����Ă����B
�@�J�����̎����@�ł͉ΐ����p�����Ă������̂́A�����̎���������Ă܂��_���̗p����A��ɉΐ��ւƉ��C����Ă���B�i�_�G���W���͕i���ɑ傫�Ȗ�肪�������B�j
�@�Z�p�ʂł͒��^�t���b�v�A4���v���y���Ȃǎ���ɉ����������̐V�Z�p����������Ă���A�����͓����̊͏�U���@�Ƃ��Ă͓����I�Ƃ������邾�낤�B�i�����ړI�ɂ���������B�j
�@���ʁA���ł̎��܂킵���琡�@�ɐ��������߂�ꂽ��A�@�̋��x���A�O�q�̃G���W�����ȂǁA�������������Ă������A���������ǂ����Ƃɉ��P����Ă������B
�@�͏�U���@�Ƃ��Ă͔��ɍ����\�Ȗ{�@�ł͂��������A�o�ꂵ�������ł͊��ɖ{�@���������邾���̐��͑��݂����A�a���̒x��������܂��B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղɂ��������鎞���ɐi���A�I�Ղő����Y���\�ƂȂ�A����x��ƂȂ����㎵���͍U�̍X�V�@�Ƃ��Ă͍œK�ȋ@�̂ƂȂ�B
�@�͏�U���@�Ƃ���������A�i������o�����h��Ȋ���͖w�NJ��҂ł��Ȃ����A�Ί͖h��͂̍����A���G�͈͂̍L���A�����̓��ڂ��\�ƑΊ͔C���ł͊����҂ł���B
�@�i����͗������ƂȂ��Ă���A�m���ɋ����{���\��������̂́A���ӕ���������Ȃ��@�̂ƂȂ�_���ǂ��l���邩�A����Ŗ{�@�̉^�p���@�͌��܂邾�낤�B
|
 |
���������@�i�͏�U���@�j
�@��햖���A��@��ɂ����Ēʏ�U���A�}�~�������A���������Ȃ��閜�\�@���K�v�ł���Ƃ������ɓ����邽�߁A�J���E���Y���ꂽ�@�ł���B
�@���\�@�Ƃ������Ƃŗv������鐫�\�͔��ɍ����A����@�̊J���͓�q���ɂ߁A��������@�ƏI������@�ł͂܂������ʂ̋@�̂Ƃ����Ă悢�قǂ̉��ǂ��������Ă����B
�@���̂��Ƃ��痬���Ƃ������X�̖��O�Ɂu���v�Ƃ�����t������藬�����ƌĂ��Ɏ���A�ɏ����̐��Y�Ȃ�����R���̑傫�Ȋ��҂�w�����Đ��ɕ������B
�@����{�鍑�R�@�Ƃ��Ă͒������t�K�������̗p����Ă��邪�A����͋��x��d�ʂȂǂ̖�肩�猋�ʓI�ɍ̗p���ꂽ���̂ł���A�{�@�̑傫�ȓ����̈�ƌ����Ă悢�B
�@���̋t�K�����A�@�̂̐�i�I�ȊT�ςƃX�}�[�g��������ɂ悭�܂Ƃ܂����O�ς邱�ƂɂȂ�A����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����ɔ�s�@�Ƃ��Ĕ������ƌ����l�����Ȃ葽���悤�ł���B
�@�������A����{�鍑�ł͊��ɋ@�������͉�ŏ�ԁA�n���H�����Ȃ��Ȃ��Ă����ȂǁA�{�@���E�^�p����͎͂c���Ă��炸�A�c�O�Ȃ���ڊo������������邱�Ƃ͖��������B
�@�Q�[���ł͑�햖���ɓo�ꂵ�A�a���A�V�R�̐i���ɂē��邱�Ƃ��\�ŁA�ꕔ�}�b�v�ł̑����Y�E�����i���ɂ���Ă���ɓ���͏�U���@�̍ŏI�i���^�ł���B
�@���\�@�Ƃ������ƂŊm���ɑ��ړI�p�r�Ɏg���鍂���\�A�����������A��r�I�g���₷�����ނɓ���̂����A�t�ɓ��ӂȕ��삪�������ߎ�C���p�N�g�Ɍ�����̂��ɂ����B
�@�ُ�ȂقǗD������Ă���a���̑��݂���{�@�̑��݂�����ł��܂������ɂ����_�ł���A�g�������\�ɂ���قǓ�͖����ɂ��ւ�炸�A���s���ȋ@�ƂȂ��Ă���B
|
 |
���ꎮ����U���@�@�i�ꎮ���U�@����U���@�j
�@���O�A�����̐��E�I�ȌR�k�̔g�ɂ��A�v��ǂ���ɊC�R�͂��ł��Ȃ��Ȃ����C�R�́A���ߍ��킹�ɗ��ォ�痋���E�����ɏo���ł���@�̂��v�悵���B
�@�v�掞�̗v�����\�͔��ɍ������̂ŁA�J���ɂ͑�����肪�t���܂Ƃ������A�ŏI�I�ɍq���͂�D�悵�A��n�͂��ɒ[�Ȍy�ʉ����s���Ƃ�����@�Ŋ��������̂��{�@�ł���B
�@�y�ʉ��͋ɂ߂ĉߍ��ŁA�^�����\���҂����߂ɖh�e�����͏Ȃ���A���ɂ������Ă͂���ɔR���^���N�Ƃ��ė��p�����ȂǁA�ƂĂ������܂ōl���Ă����Ǝv���Ȃ��قǂł������B
�@�����^�ł͑呹�Q���o���A��ɖh�e�����E���@��̒lj��������{���ꂽ���A�����V���b�g���C�^�[�Ƃ����������قǂ̑ł���コ�͂قƂ�lj��P����Ȃ������B
�@�ꕔ�ł̓����V���b�g���C�^�[�ƌ�����قǑł���キ�Ȃ��̂ł͂ƌ����Ă��邪�A���Y���E��Q�E�I�펞�c�������l����Ɛ������͂��Ȃ�Ⴍ�A�ł���コ�͎����̂悤���B
�@�Q�[���ł̖{�@�͍q���͂̒������ő�̓����ŁA�v�Ӑ}�ǂ��藤��U���E�����ɍœK�ȋ@�̂ƂȂ��Ă���B
�@����ő�\�͂͊F���ɓ������A�퓬�@�ɍU�������Α呹�Q�͂قڊm��Ƃ����A�^�p�ɋC���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��f���P�[�g�ȋ@�̂ł���B
�@�R�X�g�����߂ł��邽�߁A���Q���o�Ȃ��悤�o���邾���G�퓬�@���쒀�����n��ʼn^�p����̂����z�ł��낤�B
�@�i����͑�^���e�̕������\�ȋ�͂ƂȂ邪�A��햖���ɋ߂Â��Ă̓o��̂��߁A�����ɐ��\�I�Ȍ��E���������琔�@���c���ē���ւ̐�ւ����l����Ɨǂ��B
|
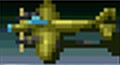 |
������@�i����U���@�j
�@��풆�����߂���������ɍ̗p���ꂽ�����@�ŁA�}�~�������A�����\�͂��t�^����Ă������Ƃ��瑽�C�������Ȃ����p�����������킹���@�ł���B
�@�J�����̗v���͗����̑��x�A�}�~���ɑς���@�̋��x�A�ꎮ���U�����̍q�������A������x�]�T�̂���ύڗʂƂ����ߍ��ȏ������������A����@�͂����ނ˂�������������B
�@�������A���̐��\�邽�ߕ����͍���@�̂̌y�ʉ����O��A����������팸����Ȃǐ��\�ƈ��������ɋ]���ɂ��������������B�i�������A�ꎮ���U�̔��Ȃ���h�e�����͂���j
�@����@�͑啿�ȋ@�̂Ȃ���悭�܂Ƃ܂����X�}�[�g�ȋ@�̂ł��������A�v�����G�Ő��Y�����������Ⴍ�A���ǂ͍Đv�ɂ���Ċȗ������Ȃ��ꐫ�\���ቺ�������̂��ʎY�����ꂽ�B
�@����ɕs�K�Ȃ��Ƃɍ̗p����Ă����_�G���W�����s������g���u���̑����������A�S�ʓI�ȐM�����E�ғ����͂��Ȃ舫���Ȃ��Ă��܂��A�O���̕�����͕s�]�ł������ƌ����B
�@�����̎���Ƃ͌����A�����\���������^�͗ʎY���̂��߂ɒᐫ�\�ɂȂ��Ă��܂��A�G���W���̓s������ғ����������A���������O�Ƃ͂�������Ă��܂����s�^�ȋ@�ł��낤�B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղɍ����|���邠����Ɉꎮ���U���ŏI�i���A���@�����ɂ���đ����Y���o���闤��U���@�ƂȂ��Ă���B
�@���e���ڗʁA�q�������ɕs���͂Ȃ����A�ꎮ���U���l�ɑ�h�䂪�قږ����ɓ������@�ƂȂ��Ă��邽�߁A�^�p����Ȃ�ΐ�����őΒn�E�Ί͔C���֓����������B
�@�Βn�������ꂽ�@�ƍl����Ύg���₷�����\�͑Ó��ł��邪�A���R�X�g�������A����A�����@�n�Ȃǎg���₷���@�͑��ɂ����邽�߂��̎��̔��f�ʼn^�p����悢���낤�B
|
 |
����s���@�i����@����U���@�F��s���j
�@��^4���@�ł���A���̖��O�������Ƃ���A����ւ̒������\�i�Ƃ����������ꂪ��j�Ȕ�s���ł���B
�@�{�@�̓����́A��s���Ƃ��Ă͓������E�ō����x���A����ɂ����Ă����ɍ������x���̐��\�ł���A���x�A�q�������A���S���A���x�A�h��ΉA�S�Ăɂ����ČQ���Ă���B
�@�܂��A�C���ɂ����Ă͒n��U���͂������A�����A�����A�ꍇ�ɂ���Ă͌y���쒀�퓬�����Ȃ���Ƃ������\�@�ł������B
�@�o�ꂩ��I��܂�170�@�O�㐶�Y����A�����̐퓬�E�A���C�������Ȃ������A�����ɂ͔�s���Ƃ������펩�̂ɐ��\�I���E�������n�߁A�ŏI�I�ɐ����c�����̂͐��@�ł������B
�@�Q�[���ł͎��@�����ɂ��㎵���d������i���A�܂��͑����Y���\�ƂȂ�B
�@�㎵���d�������C�ɐ��\���オ��A��ɓ���邱�ƂŎ萔��啝�ɍL���邱�Ƃ��o���邽�߁A�v���ɐi���E���Y�Ŏ�ɓ���Ă��������B
�@�h��ΉA���ڗʂ͒�߂����A����ȊO��B-24�̎g������ɋ߂��A�����ė����A��`�E�`�̑o���ŕ⋋�Ƒ���{�鍑�R�̗���U���@�Ƃ��Ă͕ʊi�̈����ł���B
�@���ۂɂ͖��\�@�ł��邪�A�Q�[���ł͂����܂ŗ���U���@�����̂��߁A�h��Η͂͋ɂ߂ĒႭ�A�^�p���͂����܂ōU���@�E�����@�Ɗ�����Ďg���̂��ǂ��B
�@�i����͔��x�ԂƐ����Ȕ����@�ɖ߂邪�A���ꂼ��꒷��Z�ł��邽�߁A�D�݁A�����ɂ���Ă��܂��i�����������Ƃ���ł���B
|
 |
���㎵���d�����@�@�i�����@�j
�@�����̑���{�鍑�R�ɕҐ�����Ă�����A��O�������@�͐��\���Ⴂ��A�������Y���o���Ă��Ȃ��ƌ����v���I���_������A�V���Ȕ����@�v�悪�����オ�����B
�@�R���̗v���������͎̂����̓�����̂������A�������ɂ��̑S�Ă͐��荞�߂��ɍ������i���������@�͓����̗��s�ł������j���ŏd�v������Đv����Ă���B
�@���ʓI�ɑ����I�ȋ@�̐��\�ł͋ߑ�I�Ȕ\�͂��������킹�Ă������A1��1�̕������ώ@����ƁA���ڔ\�͂̕s���A�q�������̒Z���ȂǁA�Ë����ė�镔���������B
�@�B��̒����ł��������������A�d�����@�Ƃ��������Ƃ̑����̈����A���q��@�̒��������\����ő��E����A���ɗ����Ă����Ƃ������������A��������̔�Q�͑傫�������B
�@�����A����{�鍑�R�̍q��@�Ƃ��Ă͋@�B�I�M�����͋ɂ߂č����A�����d�����@�������菬�������̋@�͉̂^�p���ɕx�݁A�����͂�����ɂ������̔C���ɂ��Ă���B
�@��풆���߂����琫�\�s���ɂ�菙�X�ɑ�����ނ��Ă��邪�A���p���͏\���ŐM��������������������A��평���̌���@�ƌ����Ė��͖������낤�B
�@�Q�[���ł͏��Ղ�������ɑ����Y���\�ł͂�����̂́A�i����̓o�ꂪ���Ȃ�x���A���Ղ��߂��邠����܂Ŗ{�@���^�p���邱�ƂɂȂ�B
�@�Ƃ͌����A����{�鍑�ł͗���U���@�����߁A��R�̓��C���i�b�v�ɕx��ł���A�{�@�łȂ���Ȃ�Ȃ���ʂ͏��Ղ݂̂ŁA���ՈȊO�͕K�{�Ƃ����킯�ł��Ȃ��B
�@���Ղ��������A�Βn�U���Ɗ���͂��Ă���邪�A���\�ɕs������������f���ɗ���U���@��͏�}�~�������@���g���ق������R�̋����Ɍq���鎖�ɂȂ�B
�@�i����͋��͂ȓ���ƂȂ��Ă��邪�A�o��܂łɂ͑啪�Ԃ�����A�^�p��������A�ނ��낻��܂łɖ{�@�̃X�g�b�N���ǂꂭ�炢���蓖�ĂĂ��������d�v�ɂȂ邾�낤�B
|
 |
�����@�i�l���d�����@�@�����@�j
�@�^�p���̔����@�͋��������i��ł���A�{�i�I�Ȕ����@�A��������Y���A�^�������d���������̂����߂��A���̊J���E�������J�n���ꂽ�B
�@�O�@��A�ۗ��i�S���d���j�����҂͂���̐��\�ł�������������A�J���ɂ͂��Ȃ�̗͂�������A����{�鍑�̋Z�p�͂��ő���ɓ�������Ă���B
�@�{�@�́A�������@�Ɣ�r���A���ς�炸�R�����ڗʁE���x�ʂ̔\�͕s�����w�E���ꂽ���A�����₤�قǂ̗L��]��^���\�͂鎖�ɐ������A����������鎖�ɂȂ����B
�@�o�ꎞ�������������ɁA�퓬�ւ̓����͏��Ȃ��������̂́A�^�p���ꂽ�����ł͂����ނˍD�]�Ă����悤�ŁA���̎����獂�����\�������Ă������Ƃ��f���邾�낤�B
�@�{�i�I�ȑ�ʐ��Y�v��͍��͂̒ቺ��������{�鍑�ł͖��d�ł��������A����ł��S�苭�����Y���������A��햖���Ƃ��Ă͔�r�I����600�@�ȏオ���Y����Ă���B
�@�]�T�̂���\�͂ŗ����ȂǑ����̑��C���ɓK�p�ł����A���\�����������C�����s�\�͂͑���{�鍑�ɂƂ��đҖ]�̕��ł��������A�@������z���������x�������B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղɍ����|���鎞���ɐi���E�����Y���\�ƂȂ�A���ڔ\�͂̑傫���u�ǒn�I�ȗ���U���@�v�I�Ȕ����@�Ƃ��Ĉ��������o����B
�@��햖���̔����@�i�����@���܂ޔ�r�j�Ƃ��Ă͔R�������Ȃ߂ƂȂ��Ă���A�R���̑����ꎮ���U�E��́E�������������ł͎�g���ɂ����������鎖���������낤�B
�@�������A�]�T�̂��铋�ڗʂ͔��ɖ��͓I�ɂȂ��Ă���A�{���̔����C���ɉ����A500kg���e�𓋍ڂ�����͂ȗ���U���@�Ƃ��Ă��^�p�ł���_�����������B
�@�܂��A�i����͕x�ԂƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�g���ɂ����������Čh�����Ă��Ă��A���@�̓X�g�b�N���Ĉ�ĂĂ��������B
|
 |
���x���@�i�����@�j
�@�A�����J�A�\�r�G�g�{�y�������悭�������邽�߁A����{�鍑�A�h�C�c�鍑���͔͈͂������o����悤����ȍq�������A�������Ȃ��������x��s�A�哋�ڗʂ��v�悵���@�̂ł���B
�@�{�@�ɗv�����ꂽ���\�͓����̑���{�鍑�̋Z�p�͂ł͓�������o���Ȃ����̂ł���A�����I�Ȑ��\���l������v��������������ꂽ�������͕ς��Ȃ����x���ł������B
�@�n�܂����J���͍�����ɂ߁A�G���W�����\�A�@�̍\���A�������x�ɑς�����ϋv���A���p�ɑς����鑕���i�Ȃǖ��͂��܂�ɂ������A���͂�J���Ƃ������͋�s�ɋ߂������悤���B
�@�J���͗��C�R�����ɂ����̂ŁA�q��@���[�J���Ђ�����ɉ�����Ă������A���̓����ł��J���͖��d�ł���Ƃ������R����v��̌������A���~�̐��͏�ɂ������Ƃ����Ă���B
�@6������^�@�Ƃ������_�Ŏ�������Ȃ��Ƃ͖��m�ŁA�����ɒ������x��s�A�哋�ڗʂƂ����v���͂��͂△�d�ƌ����A��풆�̊��������݂��������ɍŏI�I�ɃL�����Z�����ꂽ�B
�@��͑�a�Ƃ����{�@�Ƃ����A����{�鍑�R�̍\�z������̂̑傫���ɂ͋�������邪�A����Ƃ��Ď��p�I�A����I�A�����I�A�����I�ł��������Ɩ����A�ہA�ł��낤�Ǝv���B
�@�Q�[���ł́A�|�S�̐����Ȃ�ΐ��E�������[�g�����A���t�@�C���ł͖����ɔ���i���œ��邱�Ƃ��ł��A����{�鍑�̔����@�ŏI�i���`�Ԃł���B
�@����ȓ��ڔR���������A500kg���e�̓��ڂ��\�ȏ�A�����B-36������h��͂���������Ă���A�����A�Βn�U���@�Ƃ��Ă͎Q�퍑���ōŋ����x���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�������A�����p��Ί킪�������߂ɓG�퓬�@�ɂ͂��܂��Ƃ����܂��g�������o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����߁A�퓬�@�ɋC�����A�g���ǂ�����킫�܂��ėL���ɉ^�p�������B
|
|
��F2A�@�o�b�t�@���[�@�i�u�t�@���[�@�퓬�@�F�͏�퓬�@�j
�@���O�ɋ����������C�R�@�̍X�V���s�����߁A�J���E�{�̗p���ꂽ�͏�퓬�@�ł���B
�@�������̒����������O�@�܂��A�����̐V�Z�p�E�q�_�̑�������������ĊJ���͍s���A������̐퓬�@�Ɣ�r���Ă����F�̖����A�ނ���D��Ă����퓬�@�ł������B
�@�������A���̐��\�͂����܂œo�ꓖ���̂��̂ŁA���H�ւ̓������ɂ͂��łɒ��������@�̂ƂȂ��Ă��܂������߁A���֎Q�킵���퓬�@�Ƃ��Ă̕]���͍����Ȃ��B
�@�{�@�̓����͂Ȃ�Ƃ����Ă����̋@�̂̊�䂳�ł���A���̓����͌�̊C�R�@�AF4F�Ȃǂ̃L���b�g�n�Ɉ����p����Ă������B
�@�����m����ł͌y���E�y���ȓ��{�R�@�ɖ|�M���ꑁ�X�Ɖ^�p������߂��Ă��܂������A���B���ʂł͊������A���Ƀt�B�������h�R�ł̊���͗L���ł���B
�@��ʓI�ȕ]���͌����č����Ȃ��A���Y���ꂽ�@��������قǑ����͂Ȃ��������A�A�����J�C�R�@�̕������m�Ɏ��������@�ł���Ƃ����邾�낤�B
�@�Q�[���ł͂��̐��\�̒Ⴓ���瑶�݊��������A���Ղ̂ݐ��Y���\�Ƃ��������ȋ@�̂ł��邪�A���F4F�AF4U�ւƐi���E���ǂ��\�ƂȂ�B
�@�{�@�̐^�̉��l�͓��ė����̊͏�퓬�@�����x14�̎����ɐ��x16���ւ�u�͏�퓬�@�vF4U�ւ̐i�����\�ȓ_�A���̈�_�ɂ���B
�@�|�S�̐����ł͑��݉��l�͂قږ������i���L�����y�[���ł͊m�����Y�ł��Ȃ��j�A���t�@�C���ł͂����������x16������F4U�i���ł��邽�߁A���܂��^�p�������Ƃ���ł���B
|
 |
��P-40�@�E�H�[�t�H�[�N�@�i�퓬�@�j
�@���B���ʂł̐퓬�@�̊����m�����A�����J�́A�����̃G���W���ɒ��ڂ��A���B���ʂŊ���퓬�@�Ɠ��������̃G���W�����̗p�����퓬�@���J�������B
�@���̐퓬�@���{�@�ł���A�����I�Ȑ��\�͖}�f�ł�����̂́A�v�͔��ɗD�G�Ŕėp���͋ɂ߂č����A���Nj@����܂߂����Y�䐔��10,000�@���y������B
�@�{�@�͒������ʂő���{�鍑�R�@�ƌ������J��L�����t���C���O�E�^�C�K�[�X���͂��߁A�t�����X�A�C�M���X�������̍��ɂ���������Ă���A���������Ŋ��Ă���B
�@��풆������͑��X�ƍŐV�s�퓬�@���o�ꂵ�A���X�ɐ��Y���͌����Ă��������A����ł�������܂ŐV�K���Y�͑����A���X�̐��ɓ������ꂽ�B
�@�Q�[���ł͏��Ղ��琶�Y���\�ŁA�j���ǂ���}�f�����邻�̐��\�͎�͂Ƃ��Ă͎����Ȃ����̂́A���x�����߂Ώ\���Ȑ�͂Ƃ��ĉ^�p���\�ł���B
�@�������̑����퓬�@�Ɣ�ׁA�ǂ����Ă������C���[�W�͂��邪�A�t�ɑ傫����镔���͖����A�J�o�[�ł��Ȃ���ΓI�Ȑ��\�͐��őΉ��������B
�@�i�����P-47�T���_�[�{���g�A�������瑱����P-51�}�X�^���O�ƗD�G�Ȍn���ƂȂ��Ă��邽�߁A����̑������t�@�C���ł͏��Ղ���R�c�R�c�ƈ�Ăčs�����Ƃ����z�I���B
�@����A�A�����J�L�����y�[���i�|�S�j�ł͑Γ��A�ΓƂɂ���Ċ���̋@��傫���������邽�߁A���[�g�ɂ���Ă͊���̏�͏��Ȃ����A�Œ�ł��������̓X�g�b�N���Ă��������B
|
 |
��F4F�@���C���h�L���b�g�@�i�͏�퓬�@�j
�@��͐퓬�@�̍����������̗p�����ɂ�F2A�ɕ��������̂́A���ݐ��̍��������������A�����J�C�R�ɐ����̗p����A�͏�퓬�@�Ƃ��Ĕz�����ꂽ�퓬�@�ł���B
�@�{�@�͍̗p����������F2A�ɗ�������A���̌�̐����̗p�O�̉��ǂő啝�Ȑ��\����ɐ����A�����ď��X�ɐ��𑝂₵�A����͊͏�퓬�@�Ƃ��ĕs���̍���z�����B
�@���M���ׂ��_�Ƃ��āA�@�̂̊�䂳���グ���A���̋@�̂̏�v���ɂ�鉶�b�ŋ}�~�����\�����ɍ��������B
�@�{�@�̓X�y�b�N��̃f�[�^���평���̔�Q���C���[�W�Ƃ��ĕt���܂Ƃ��A�ǂ����Ă�������͏�퓬�@�ƌ����邱�Ƃ������悤�����A���ۂɂ͓��ʗ��킯�ł͂Ȃ��B
�@�����������Ɉ���I�ɑł��������ꂽ���A�i���������ꌂ���E�ɓO����A�P�ƂłȂ��K���`�[���Ő퓬�ɓ����铙�A�퓬�X�^�C���̊m����͌݊p�ȏ�ɐ�����B
�@�Ⴂ�]�������ꂪ���ȋ@�̂ł��邪�A�����Ƃ��Ă͏\���ȉΗ͂�����ɖh�e�������[�����Ă���A�퓬�X�^�C���̊m���܂Ŏ��Ԃ����������_������܂��B
�@�Q�[���ł͔�r�I���Ղ��琶�Y���\�ł��邪�A���ɔ�ׂĉΉE���x�͗��A�퓬�͂͒Ⴂ���ނɓ���B
�@���ɁA�A�����J�L�����y�[���ł͑������{�鍑�R�������x�ł��邱�Ƃ�����A����ȉ^�p����������܂����Q���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@��ǂ����o����܂ł͐ϋɓI�ɍU�߂Ȃ��A���܂��҂���������A�����ɂ��͂����݂𗘗p����ȂǁA���܂���p���g���ĉ^�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�i����͎��ɐ����Ȃ��̂ƂȂ��Ă���AF6F��F8F��F9F�ƒi�K�I�����͊m���ł��邱�Ƃ���A���܂��^�p����ĂĂ��������B
|
 |
��F6F�@�w���L���b�g�@�i�͏�퓬�@�j
�@�{�@�́A�{��F4U�J�����s���̕ی��I�ȊJ���@�ł��������A����F4U�͊̐S�̊͏�@�\�ɓ�̂��镔���������A���A�����͏�퓬�@�Ƃ��č̗p���ꂽ�B�i�Γ���O���J���j
�@F4F�̌�p�@�ł���A�e����œ���ꂽ����܂ł̐퓬���ʂ��t�B�[�h�o�b�N���A�����ɑΉ������\�͂��l�ߍ����ʁA�S�ʓI�ɍ������\�����@�̂ƂȂ����B
�@�ɂ߂č����\�ƌ��������͖����̂����AF4F�P�����f���ȑ��c���E��v�ȋ@�̂͌��݂ŁA���u�����ی��@�v�Ƃ��Ă̐������猘���Ȑv�ł���A��^�Ȃ���܂Ƃ܂�͂悢�B
�@F4F���l�A���������͂�@�̂̏�v������}�~�����\�������A������x�����ȑ��c�����Ă����Ȃ���s�ł����悤�ł���B
�@�e�\�͂͗��Ɣ�r���Č݊p�`���镔���������A���\�I�D�ʂ����A�Ő������߂����ފ��ɓ������������X�ɋ쒀���Ă������B
�@�Q�[�����ł͎����I�ɗ��ܓ�^�Ƒ����`�œo��ƂȂ邪�A�͏�퓬�@�ƌ������Ƃœ��R����@�Ɉ���y�Ȃ����\�ƂȂ��Ă���B
�@���̂��߁A��ɊC��Ŏg�p���邱�ƂɂȂ邪�A���ܓ�^�Ɣ�r���ĔR���E�����E�h��͂ɗD��Ă��邽�߁A���x�����グ�Ă��܂��ΗL���Ȍ`�Ő퓬���\�ƂȂ邾�낤�B
�@���x14�Ǝ�Ⴂ�̂��C�ɂȂ邪�A�������ɂ͊͏�퓬�@�Ƃ��ĉ^�p�\��F4U�R���Z�A�i���x16�j�����݂��邽�߁A�A�g��p���ė�������I�ɗ��Ƃ������Ƃ���ł���B
�@�i�����F8F�i���x18�j�A���V�v���͏�퓬�@�Ƃ��Ă͂قڍŏ�ʂ̐i����ł���A�C��̂Ȃ��L�����y�[�����[�g�ł�����̓X�g�b�N���Ă��������B
|
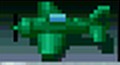 |
��F8F�@�x�A�L���b�g�@�i�͏�퓬�@�j
�@�w���L���b�g�̓o��Ő킢��D���ɐi�߂Ă����A�����J�́A������@�Ƃ̐퓬�������\�A�����Ăǂ̋��ł��^�p�ł���͏�퓬�@�̊J���ɒ��肵���B
�@���̋@�̂͌}���\�͂��d�v������A����ɔ�����\�A�㏸�\�́A�^���\�͂̊l���ɗ͂�������Ă���B
�@�@�̂̑傫����F6F���������Ŕ�r�I�����ȋ��ł��^�p���\�ł���A���̏����ȋ@�̂ɓ��ڂ��ꂽ��^�G���W���̂������ō������\�鎖�ɂȂ����B
�@���ʁA�@�̂̏k�����痈��R�����ڗʂ̌����ɂ��q�������̒ቺ�A�y�C���[�h�̌����͔�����ꂸ�A�ėp���ɂ͂������̂ƂȂ��Ă���B
�@�}���@�Ƃ��Ă͗��z�I�ł͂��������A�o�ꎞ�������V�v������W�F�b�g�̉ߓn���i��햖���j�ł��邱�Ƃ����풆�̊���͏��Ȃ��A�ނ�����ɑ����ɂĉ^�p����鎖�����������B
�@�Q�[���ł͏I�Ղɂ��������鎞����F6F����i�����\�ƂȂ�A�}�b�v�ɂ���Ă͑����Y���\�ł���B
�@�R���̊W����q�������͗����̂́A���x��14����18�Ƒ啝�Ɍ���i�Η͓͂����j�A����Ƀ��P�b�g�e�������\�Ɨ���@�ɕ�������炸�̗ǍD�Ȑ��\�����B
�@�i������F6F�A�i�����F9F�p���^�[�ƌn����ėD�G�ŁA���ɑ����m���ʂł̓O���}���̌ւ�D�G�Ȋ͏�@���v�������ɖ��i�������Ƃ��낾�B
|
 |
��F9F�@�p���^�[�@�i�p���T�[�F�N�[�K�[�@�͏�퓬�@�j
�@�A�����J�C�R���̃W�F�b�g�͏�퓬�@�����A�����E�z���͑�킪�I����Ă���ł���A���ۂɂ͑���̐푈�Ŋ������̋@�̂ł���B
�@�J���̓L���b�g�n�ŗL���ȃO���}���Ђ��肪���Ă���A�L���b�g�n����̊�䂳�͖{�@�ɂ��p����A�܂��A������̓����ł���ێ�I�Ȑv�����݂ł������B
�@�W�F�b�g�ւ̉ߓn���ł���@�̂炵���A�{�@�ɂ��G���W����^�������ȂǑ����̖�肪���������̂́A�Ȃ�Ƃ����p�܂ł��������������ꂽ�B
�@�ێ�I�Ȑv�ł��邪�䂦�Ƀ��V�v���@�Ƃ̔�r�ł������E�^�����E�^�p���͗D��Ă���Ƃ͌����Ȃ��������A���C�R���̃W�F�b�g�@�Ƃ������Ƃł�����x�̑�ʔz��������Ă���B
�@�������A���̐��\�̓W�F�b�g�@�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ����[�ŁA��Ɍ�ޗ�����ǂ��ꂽ�t���b�v�ȂǓ�����i�̍q��Z�p����������A�啝�Ȑ��\���オ�}��ꂽ�B
�@���ǂ��ꂽ�@�̓N�[�K�[�ƌĂ�A���ς�炸�����ȃW�F�b�g�퓬�@�ɂ͗���Ă������̂̈��萫�E�M�����͔��ɍ����A�ꕔ�̔�퓬�^�̓x�g�i���ւ��Q�킵�Ă���B
�@�Q�[���ł͖�����F8F����̐i���Ŏ�ɓ���u�����I�ɓ��R�ŋ��̐퓬�@�v�ŁA���ɍ|�S�ł́u�Α���{�鍑�킩�{�y��v�ł��������Ȃ��M�d�ȋ@�̂ƂȂ��Ă���B
�@�ΉA���x������߂ł��邽�߂Ƀh�C�c��O�鍑�A����{�鍑�R�̓���Ɍ���肷�邪�A�������\�͂ɉ�����D���̂������P�b�g�e�A�i���̂��₷���͂���ɏ��邾�낤�B
�@�e�L�����y�[���ł͖{�@�̑�ʔz�������₷�����������Ă��邽�߁A�i�������������Ύ��X�Ɛi�������퓬��D�ʂɐi�߂����Ƃ���ł���B
|
 |
��P-51�@�}�X�^���O�@�i���X�^���O�@�퓬�@�j
�@�A�����J�̊J���́A�H�Ɨ͂��������A���ٓI�Ƃ�����قǂ̒Z���ԂŊJ�����ꂽ�퓬�@�ł���B
�@�{�@�ɂ͌��X�A�����J���G���W�����g���Ă������A�C�M���X�R�֎x�������ƃC�M���X�R�͂���������̃}�[�����G���W���ւƊ��������B
�@���̊����ɂ����ł����������x���\�͋��ٓI�ȉ��P�E����������A����ȍ~�̐��Y�@�͂��ׂă}�[�����G���W�������ڂ����B�i�A�����J�ł̃��C�Z���X���Y�܁j
�@�܂���̉Η͕s���͂��������̂́A�����Ƌ��ɉΗ͕s������ɉ��P����A��풆�ł͑傫�Ȑ��������߂��퓬�@��1�ɓ��邾�낤�B
�@�Q�[���ł̃}�X�^���O�͍U���́A�����ɗD��A�o�ꎞ�ɂ͑������퓬�@�Ƃ��ďd�AMe262��Fw190D9��������悤�Ȍ㔼�ł��������\���[�{�Ƃ��ďd��B
�@������q�������̒����A���P�b�g�e�E��^���e���ډA�U����120�E���x16�A�I�Ղ͑����Y�\�ƁA���̎g������̂悳�͍ō����x���ł���B
�@���̊m�ہA�n��G��͂̈Ј��E���j�ƃv���[���[�ɂƂ��Ă͗���ɂȂ�퓬�@���낤�B
|
 |
��F4U�@�R���Z�A�@�i�͏�퓬�@�j
�@�t�K�����Ƌ��̂������I�Ȋ͏�퓬�@�ŁA��v�͏�퓬�@�̍���F6F�ɒD��ꂽ���̂́A��n�͂̃G���W�������������\�A�����d�ʂ̑傫�����琳���̗p���ꂽ�B
�@�{�@�̓e�X�g���ʂ͗ǍD�ł��������A�����̃A�����J�C�R�ꎩ�d���d���A���c�Ȃ���̎��E���悭�Ȃ��A������̑��x�ʼn^�����\��������ȂNJ���̖�肪�������B
�@�������A��^�@�Ȃ�ł͂̕����d�ʂ̑傫���A�K�x�ȑ��x��ۂ��Ƃŋ��\�͂��m�ۂł��邱�Ƃ��玝���O�̊�ʂ����X�ɔ������A��풆���ȍ~�͊���̏�𑝂₵�Ă���B
�@���V�v���@�ł���̂�Mig-15�̌��ċL�^��ێ����Ă�����A�R���Z�A�E���C�_�[�ƌ�����\�g��т̘b����������ƁA�{�@�͒n���ł͂��邪�b��̑����@�̂ł�����B
�@�Q�[�����ł�F2A�o�b�t�@���[����i�����\�ŁA����������͑����Y���\�ł���B
�@�{�@�̓}�X�^���O������ɔz�������u�A�����J�R���̐��x16�����퓬�@�v�ł���A�i������ɑ��i���ł���ɂ߂č�����͂ɂȂ�B�iF2A����̐i�����O��j
�@��^���e�A�܂��̓^���N��2���ډ\�ŁA���\�I�ɂ͔R���E�ړ��͂̏��Ȃ��}�X�^���O�Ƃ������Ƃ���ł���A�}�X�^���O�o��܂ł̂Ȃ��Ƃ��Ă͔��ɗD�G���B
�@�������A�i����F4U�Ŏ~�܂��Ă��܂����߁A���Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��g������̗ǂ��Ɉ�����Ă��A�{�@����퓬�@�Ƃ��ĉ^�p����̂͂����߂ł��Ȃ��B
|
 |
��XP-79�@�t���C���O�����@�i�ǒn�퓬�@�j
�@�S���^�Ƃ��������Ƃ��Ă͈ٗ�̌`����̗p���A�����ă��P�b�g���i�𗘗p����Ƃ����ӗ~�I�ȊJ���@�ł���B
�@�ǒn�퓬�@�Ƃ���������A����G�ϐ�������}�㏸�\�͂����߂�ꂽ���ƂƁA�����B�ŗL�Q�ȃ��P�b�g���i���g����O����A�@�̂͋ɂ߂ď�v�ȑf�ށE�\���ŏo���Ă����B
�@���̂��Ƃ����풆�ɐڐG�E�Փ˂��������Ă��A������x�͑ς�����ƍl�����Ă���A���ꂪ���ő̓����肪��U�����Ɗ��Ⴂ�H����Ă�������������B
�@���ǂ̂Ƃ���A���P�b�g�G���W���͂��납�W�F�b�g�G���W���ւ̑�ւł��^�p�͍���ŁA�������Ɏ��S���̂��������J���͑ł����A�������邱�Ƃ͖��������B
�@����ł����̓�����͂��肦�Ȃ��ƌ����Ă��邪�A�ǂ��l�߂�ꂽ���͓��U������̂����R�ŁA�A�����J�������ǂ��l�߂��Ă����ꍇ�́A�̓�����ɂ��g��ꂽ�Ǝv����B
�@�����`�̃A�����J�ł́A�l���y���̓��U���̂������̑����A�푈�p����h�邪���킢���̂��߁A���ɂ����������\�z�������Ă��B����ĕ\�ɂ͏o�Ă��Ȃ����낤�B
�@�Q�[���ł͋��̂݉\�Ƃ�������ɁA�Η�160�E���x20�Ƃ����ɂ߂č����퓬�͂������Ă���A���Y��p�i�������Ƃ���������g���̂ă��j�b�g�ƂȂ��Ă���B
�@�|�S�̐����ł̓A�����J�{���ւ̐N�U�}�b�v�ɓo�ꂵ�A�v���[���[�̃��j�b�g�W�J����ł͖��^�[�����Y����邱�Ƃ������B�i�M�҂�7�^�[���A���ł��ꂽ�j
�@�G����Ƃ��ɂ͉���ɋ����d�|����ƕԂ蓢���ɍ������Ƃ��قƂ�ǂȂ̂ŁA�o�������n�ォ��ł����Ƃ������B
�@����A���t�@�C���ł͒��Ղ��瑦���Y���\�ƂȂ�A�v���[���[�����R�Ɏg�����Ƃ��\�ŁA�e�}�b�v�J�n����̐��m�ۂɑ傢�ɗ͂����Ă���邾�낤�B
|
 |
��P-38�@���C�g�j���O�@�i�퓬�U���@�j
�@�{�@�͂��Ƃ��ƍ����x�퓬���l�����x�d���ō��ꂽ���߁A�^�����\�͌����č����Ȃ����̂́A�����I�ɂ͓����̐퓬�@�ɔ���퓬�͂����Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B
�@�h�C�c�鍑�R���R����́u�o���̈����v�A����{�鍑�R����́u��͂��v�ȂǂƌĂ�A���⎞���ł���قǕ]���̕ς�镺������������낤�B
�@�{�@�͍q�������������A�o���̔n�͂������d�����͉Η͏\���ł��������A�o�ꂩ�炵�炭�͓K�����퓬�X�^�C���E�C�����Ȃ��Ȃ������炸�A�傫�Ȕ�Q�������B
�@���ɑ���{�鍑�R�ł͖{�@��ፂ�x�ɗU������Ő��\�𗎂Ƃ��i����Ɏ������݁A��������Ă��邱�Ƃ��Z�I���[�ƂȂ��Ă����悤�ł���B�i���{�ł̒�]�������j
�@�������A����ɖ{�@�ɍœK�Ȑ퓬�X�^�C���E�C�����m������n�߂�Ƃ����܂��L�����V�I�͋t�]���A���\�I�Ȑ��\����`���Đ������̐�ʂ��c�����B
�@���ł��L���Ȃ͎̂R�{�\�Z�叫�̏�����ꎮ����U���@�̌��ĂŁA���̈ÎE�𐬌��������͖̂{�@�ł���B
�@�Q�[���ł́AH�^�Ƃ��̐i���^��L�^���o�ꂵ�A����L�^�͍|�S�̐����A���t�@�C���ŋ��\�͂̕]�����ɒ[�ɈႢ�A�V�ƒn�̍�������B�i�|�S��90/13�A����110/15�j
�@���ꂼ�ꑾ���m����i�Γ��j�A���B����i�ΓƁj�ł̕]���ł���Ǝv���邪�A�|�S�̈����ł͐��x���Ⴍ�����A�u�퓬�v�U���@�Ƃ��Ă͂قƂ�ǎg���Ȃ����Ƃɒ��ӂ������B
�@�S�̓I�ɖh��͂̍����U���@�Ƃ��ĉ^�p���邱�ƂɂȂ邪�A����L�^�����͕ʊi�ł���A�u���t�@�C����P-38L�͋����v�������͓��ɓ���Ă����ׂ��ł���B
|
 |
��P-47�@�T���_�[�{���g�@�i�퓬�U���@�j
�@�ʏ�̐v���@�Ƃ͈قȂ�A�܂������A�G���W���Ȃǂ̑I�l����n�܂�A���̌�ɋ@�̐v�E���ǂ��s��ꂽ�Ƃ�����������Ȓa���o�܂����퓬�@�ł���B
�@���̐v���@�Ɏ��������R�Ƃ��Ă͖{�@�ɑ���A�����J�R�̗v�����\�����ɍ����A���̎����ɂ͍��o�͍����\�G���W���Ȃǂ��K�v�����������Ƃ���������B
�@�v���g�^�C�v�̐��\�͂��܂ЂƂł��������A�����ō��̃G���W�����\�ƁA�J�[�g�x���Z�t����Ƃ���D�G�ȊJ���w�ɂ��l�X�ȉ��ǂɂ���āA�ŏI�I�ɋɂ߂ėD�G�ȋ@�ƂȂ����B
�@��_��������Ƃ���G���W���I�l�ォ��v���s���Ă��邽�߁A�K�R�I�ɋ@�̂��G���W���T�C�Y�ɔ����đ�^�����Ă��܂����������A�@�̐��\���炵�đ債�����ł��Ȃ������B
�@���X�A���A�����A�d�����ƗD�G�Ȑ��\�����������̉��ǎ�@�ݏo�������A���ɉ��B�ł͑�ʐ��Y���ꂽD�^�A�����m����ł͂��Y���͏��Ȃ����̂�N�^�̊��L�����B
�@�{�@�͑ł��ꋭ����ΉA�����đ��x���D��Ă���ƁA�p�C���b�g�B���炷��Δ��ɗ����������݂ł���A���̑��ݎ��̂��������̂������ƌ����Ă���B
�@�Q�[�����ł͎�ʂ͖������Ձ`�I�Ղ�P-40����̐i���������͑����Y�œ��肪�\�ŁA���x�͗�邪�Η͂͏\���A��^���e�A���P�b�g�����\�ƁA�����܂����ėp�����ւ�B
�@�敪�͐퓬�U���@�䂦�ɐ퓬�@�ɂ͂��Ȃ�Ȃ����̖̂h��͍͂����A���P�b�g�e�͗D���[�u������Ă���A�U���@�Ȃǂ̋쒀���n�߁A�Βn�U�����\�Ǝg������͂��Ȃ荂���B
�@�i�������̓s������g������Ԃ̌�����ɂ����_�̂���@�̂ł͂��邪�A�A�����J�R�ɂ͑��ɍU���@����������A�i�����P-51�ƗD�G�ł��邽�߁A���ɖ��͂Ȃ����낤�B
|
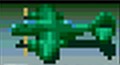 |
��A-20�@�n�{�b�N�@�i�n���H�b�N�@����U���@�@���C�M���X���̓{�X�g���j
�@�_�O���X�Ђ̊J�������y�����@�i�U���@�j�œ���ȑ�����G�ł��_�̖��������@�����A�����ėp���ɑ���̂��₷���A�@�̂̏�v�����瑽���̍��ōL���g��ꂽ�@�ł���B
�@�o�ꓖ���A�{�@���y�������A�����J�R�ł͍̗p���ꂸ�A�t�����X��I�����_�Ȃǂō̗p�E�����A�悤�₭���R�ł��{�@�̗D�G���ɋC�t���A�x��č̗p���ꂽ�G�s�\�[�h�͗L�����B
�@�\�r�G�g�R�ɑ�ʋ��^���ꂽ�_�͋����[���A�\�r�G�g�R�ł͖{�@����ɓ��ꂽ��ɐϋɓI�ȉ^�p���s���A�h�C�c�鍑�R�Ƃ̐킢��D�ʂɐi�߂�菕���ƂȂ����B
�@�����A���ڗʂɂ����Ă����ɗD��Ă����킯�ł͂Ȃ��������A�@�̂̃T�C�Y�A��s���\���l����ƃo�����X�͗ǂ��ƌ����A���ꂪ���]���̏��ȁi�䂦��j�ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@�C�M���X�R�ł͈ꕔ�̋@�̂����ǂ����x���@�Ƃ�����A����^�ł͎�̉��ǂɂ���Ă�肢�������Βn�U���@�Ƃ��Ă̐��������߂���ƁA�����͖��������ǎ���a�������B
�@�n���ł���Ȃ���������̍��ʼn^�p���ꑽ���̐�n�ɕ����A�����ɔC���𐋍s�����{�@�͂܂��Ɏ��������ƌ����ɑ��������@�ł������B
�@�Q�[���ł͏��Չ߂��ɓo�ꂵ�A�i���E���ǂ̖����Ɨ������n���Ȏ�Ƃ��đ��݂��Ă��邽�߁A���g���̂Ċ��̋����@�ƂȂ��Ă���B�i�C�M���X���ł͍��G�Ȃǂ��j
�@��s�E�h�䐫�\�͍����Ƃ͌����Ȃ����A���ɑΒn�Η͂ɂ͔��Ɍb�܂�Ă���A�U���͂����Ȃ�}�~�������@�����ł��邱�Ƃ���u�ꌂ�v��������C���ɂ͍œK���B
�@���R�ł͔����@���D�G�����邽�ߑ��݊��͔������A����ł��Βn�E�Ί͉Η͂̑傫���͖��͓I�ł��鎖����A1�A2���j�b�g�����Ă���Ɩʔ����g�������o���邩������Ȃ��B
|
 |
��B-25�@�~�b�`�F���@�i����U���@�j
�@�{�@�́A��P�ɂ����{�{�y�����𐬌����������ŗL���ł���A�������������łȂ��A�ꕔ���������ł��^�p����A���������̐��A�n��Ŋ����o������U���@�ł���B
�@�����A�V�����[�J�̃m�[�X�A�����J�����J����S���������A����J���@��]�p������������A��������1�N�O��Ŋ����ƌ����ُ�ȂقǒZ���Ԃō��グ�����͓��M�ɉ�����B
�@B-17�̂悤�ȑ�^�@�ɔ�הh��ȕ����͖������A��r�I�����ŏ�v�Ȑv�ł���A����蒆�^�@�ƌ��������₷���A�R�X�g�I�ȗD�ʐ������ʐ��Y���\�ł������B
�@�O�q�̂Ƃ����^�@�̂悤�Ȕh�肳�͂Ȃ����̂́A���^�@�Ȃ�ł͂̃o�����X�̂悳������ł���A�n���ł͂��邪�f���ȑ��쐫�A�@�����A�����ϋv�x�͍����]�����Ă���B
�@�܂��A���e���ڗʂ𑝂₵�����Nj@��A�����C���@�A�͂��܂�75mm�C���ڂd�U���@�Ȃǂ����݂��Ă���A���̎����獂���ėp���������Ă����ƌ����悤�B
�@���܂�ɂ��n���Ŗڗ������_�����Ȃ����A�t�Ɍ��_�炵�����_���ڗ������A�M�ғI�ɂ́A���ɂ����ē��퐶���Ɍ������Ȃ��K���i�̂悤�ȑ��݂������̂��낤�ƍl�@����B
�@�Q�[���ł͔�r�I�������琶�Y���\�ł���A�i���E���ǂ͈�ؖ����̎g�����蕺��Ƃ��ēo�ꂷ��B
�@�R�X�g�I�ɂ���قǗD�ʐ��������A��������U���@�Ȃ��A-20�n�{�b�N�̗D�G�����ڗ����߁A�����̃v���[���[���u�{�@���g�����炢�Ȃ�n�{�b�N���v�Ƃ�������ɂȂ�Ǝv����B
�@����ȓ��Z�����݂���킯�ł��Ȃ����߁A�g���Ȃ�ΐ��@����ʼn^�p���A�ł�����葼�̕���Y�����ق����ǂ����낤�B
|
 |
��SBD�@�h�[���g���X�@�i�͏�}�~�������@�j
�@���O�ɓo�ꂵ���ɂ�������炸�A����I�ȋZ�p�E�\���𑽗p���A�J�킩��I��܂őS�ʂɓn���Ďg�p���ꂽ����@�ł���B
�@�{�@�͋}�~�������@�Ƃ���������A��ʓI�Ȑ퓬�@������v�Ȑv�ƂȂ��Ă���A�Ȃ����^�����\���D��Ă���Ƃ����A���z�I�ȋ}�~�������@�ƌ����邾�낤�B
�@���{�R�̖ҍU��h�����U�ɓ]����܂ŁA�A�����J�ɂƂ��Ĉ�Ԍ����������ɔ��ɗǂ����������A�����̓��{�R���K���߂銈����������B
�@�Ȃ��A���ӕ���ł͂Ȃ����̂́A�y�����Ȃ���Ȃ����悤�ŁA���̌��ċL�^�܂Ŏ����Ă����肷��B
�@���f�����Ă����Ƃ͂����A���{�R�̃G�[�X�p�C���b�g��䒆�ы@�����āE�����ɒǂ����͖̂{�@�ł���B
�@�Q�[���ł̓h�C�c�鍑��Ju87�Ǝ����g�������ĂŁA����ɂ���Ɣ�הR���������A��h�䂪�����i�Ί͖h��Ɏ����Ă�60�j�A���֓��ڂ��\�Ǝ����s������ł���B
�@�j���̂悤�ɋ��܂łƂ͂����Ȃ����̂́A��̖h��͂����镪�A�퓬�@���̍U���łقڑS�Ŋm���Ju87�ɔ�ׂ�Ɛ������͗y���ɍ����B
�@���ƘA�g���A���܂��@�������̈���Ƃ��ĉ^�p��������͂ł���B
|
 |
��SB2C�@�w���_�C�o�[�@�i�͏�}�~�������@�j
�@SBD�h�[���g���X�̍X�V�̂��߂ɊJ������A�����Ƃ��Ă͈ٗ�ȏ�����ʐ��Y�ɂ�����z�������ꂽ���A���҂Ƃ͗����Ɍ���ł̕]���͂��܂�悭�Ȃ������@�̂ł���B
�@���]�̂����_�ɂ́A���c���̈����A�Ǝ�ȋ@�́A��������ɂ�鍓���������Ȃǂ��������A�̂낭�łȂ��ȂǂƂ����s���_�Ȃ��������t�����Ă��܂����B
�@�������Ȃ���A���]�ɂ��ւ�炸�������ԉ^�p����錋�ʂƂȂ��Ă��邪�A����͒������Z�������邩��ł���A�{�@�̍q�������A�����d�ʂ��ɂ߂ėD��Ă�������ł���B
�@�����̒����͓����̃A�����J�R�A���ɊC�R�ɂƂ��Ă͓s���̂悢���̂ł����āA���ʓI�ɑ���{�鍑�̌ւ��a�A�����ȂǁA�A���͑��̊͒��̟r�łɑ傫���v�������B
�@�Ȃ��A�g���ɂ����͂��������̂̋@�̓I�ɂ͂���Ȃ�ɐ��������߂����ނɓ���A���Y���~�߂�ꂽ����A����A���炭�͐��J���ʼn^�p����Ă���B
�@�Q�[���ł͒��Ղ���o�ꂵ�A�h�[���g���X����̐i���A�܂��͑����Y���\�ŁA�h�[���g���X���m���ɏ��鐫�\�œo��ƂȂ�B
�@�h�[���g���X�ɔ�א��Y�R�X�g�͏オ���Ă�����̂́A����ɉ����������Ȑ��\������o�Ă���A�g���₷���A���ɑΊ͍U���ɑ��鍂���\�͂́A���^�p���ɏd�邾�낤�B
�@�i�����AD-1�X�J�C���[�_�[�ƂȂ��Ă���A���͂Ȑi�����\�ł��邽�߁A�C��̑�������{�鍑����ł͑�Ɉ�ĂĂ��������B
|
 |
��TBD�@�f�o�X�e�[�^�[�@�i�͏�U���@�j
�@�����A������ׂ����ɔ����A�V�^�̋��ɓ��ڂ���͍ڋ@�̈�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�A�����J�R�̊͏�U���@�i�����@�j�ł���B
�@�P�t�̗̍p�ɂ��킦�A�������̋@�̂�ŐV�Z�p�𓊓����ꂽ�{�@�́A���������͐��E�ō����x���̐��\�Ƃ��Ē��ڂ���A����ČR�ɍ̗p���ꂽ�B
�@�������A�q��@�̔��B�������������ɂ����āA�̗p���琔�N�Ă̎��H�Q���͏{��傫���߂��Ă̎Q��ƂȂ��Ă��܂��A������������Ԃł̎Q��ł������B
�@����̊C��Ɏ�o����Ă��邪�A����x��ƂȂ��Ă��܂����{�@�ł͑�ΖC�A�����ŐV�s�퓬�@�̖Ԃ���蔲���鎖�͓���A��������Q���肪�����Ă���B
�@��x�̏o���łقڑS�łƌ��������N�����Ă���A���̏𗝉����Ă����R���ł͎�����@�iTBF�A���F���W���[�j�ւ̐�ւ����}�����ƂȂ����B
�@����̗���ƌ�������܂łł��邪�A������������������Ă���A�{�@�ɂ�����̏�͂������̂�������Ȃ��B
�@�Q�[�����ł͋��ɏ�������SBD�h�[���g���X�Ƃ̃R���r�őΊ͑D�A�Βn�C����S������@�̂ƂȂ�B
�@�R�������Ȃ��@�̐��\�������Ȃ����ߎ�̎g���ɂ����������邪�A���G�͈͂��L���i���G5�j�A�����̓��ڂ��\�ł��鎖��������܂͑��ɂ͊�������ċN�������B
�@�i�����TBF�A���F���W���[�ƌ����Ȑi�����\�ŁA�����Ղ��͈�C�ɂ͂ˏオ�邾�낤�B
|
 |
��TBF�@�A�x���W���[�@�iTBM�F�A���F���W���[�@�͏�U���@�j
�@���͂�J�풼�O�Ƃ������_�ɂ����ăA�����J�R�ɔz������Ă���TBD�f�X�o�[�^�[�́A���\�s���A�@�������Ƃ��Ă̍q�������̒Z�������m�ƂȂ��Ă���A�����X�V�𔗂�ꂽ�B
�@�{�@�͂��̍X�V�@�ł���TBD�ő�̎�_�ł������q���������̉������͂��߁A����Ɍ������������E����\���ɂ���ē����̕W���I�ȗ����@���������̐��\���߂Ă����B
�@���X�A���̖����@�ł������������ȍ̗p�E���\���s��ꂽ�����ɐ^��p�U�����������A��ɓ��R�̌��ӂ�\�����̔@���A���F���W���[�F���Q�҂Ɩ��t����ꂽ������L���ȋ@�ł���B
�@�����@�Ƃ��Ă͂��Ȃ�d���ATBD�Ƃ̔�r�ł͑啪���̂��d�ʂł��������A��^��n�͂̃G���W�������͂Ȑ��\��{�@�ɗ^���Ă������߁A���x�I�Ȗ��͂��قǂȂ������B
�@�d�ʂ����������@�̂͂�͂�傫���A���̂܂܂ł͍͊ڂɋɂ߂ĕs���ł��������ߗ��͐�ݍ\�����̗p����Ă��邪�A���̎����Ƃ��Ă͐����͔��ɐ�i�I�Ȃ��̂ł���B
�@���킱����q��^�p�̎d��������傫����Q���������̂́A�����@�Ƃ��Ĕ�}�ł������{�@�͎���ɓ��p�������A����{�鍑�C�R�̏d�v�͑D�𑽂��C�ɒ��߂Ă���B
�@�Q�[���ł͑Ί͔C���ɋ����@�Ƃ��ēo�ꂵ�A���Ղɍ����|���邠�����TBD����i���E���@�����ő����Y���\�ƂȂ�B�i���������ډj
�@�i��������̐��\����͑傫���A�����@�ł������I�ɍ������\�������Ă��邱�Ƃ���A�C�ゾ���łȂ�����ōU���@�{���[�_�[����̋@�Ƃ��Ďg���̂��ʔ�����������Ȃ��B
�@�i����͍����\���\�U���@AD-1�ŁA�������\�͂���ɏオ����̂̍��G�͈͂����͏k�����Ă��܂��A����Ă��̏�̏��悭���f������Ői�����s�������B
|
 |
��AD-1�@�X�J�C���[�_�[�@�iA-1�@�͏�}�~�������@�j
�@�P���E�����E�����E�U���@�Ɠ��藐�ꂽ������܂Ƃ߂邽�߂Ɍv�悳�ꂽ�@�ł���A��풆�̑�ʔz���͊Ԃɍ���Ȃ������������\�Ԃ肩����x�g�i���ւ��Q�킵���@�ł���B
�@�����I�ɂ͗����@�E�U���@�̑o�������˔��������Ɋ�p�ȋ@�̂Łi����{�鍑�R�̗������ɋ߂��j�A���^�E�y�ʂł���Ȃ�����O�C�̋@���y���ɗ������\�������Ă����B
�@���ЂƂ̊J��������L���ɐi�߂邽�߂Ƃ͂����A�A�����J�C�R�̉ߍ��Ƃ�������v���������Z���ԂŒB�������_�O���X�ЁA�n�C�l�}�����̊J����b�͂��܂�ɂ��L���ł���B
�@���\�̒��ł����ɐύڗʂ͑o���@�E�l���@�ɔ���قǂŗ]�T������A�{�@�̔z����ł́u�^�ׂȂ��̂̓L�b�`���i�䏊�j���炢���v�ƃW���[�N����ь����قǂ̂��̂ł������B
�@���e�A���P�b�g�e�A�����ȂǖL�x�ȕ������g�����Ȃ������悭�l�����Ă���A���y�C���[�h�����������߂̃p�C�����ӏ��̑����͂��̓�����ǂ������Ă���ƌ�����B
�@�x�g�i���ł͕��m�B�̃W���[�N�b������ۂɕ֊킪���e����ɓ��������ȂǏ�k�܂݂�̉R�̗l�ȋ@�̂ł��������A���V�v���U���@�Ƃ��Ă͂���قǍ����\�ł������B
�@�Q�[���ł͍����\���\�@�Ƃ����j���ǂ���̍��X�e�[�^�X���ւ�A�g������̗ǂ��U���@�Ƃ��ēo�ꂷ��̂����A�ɂ������o��܂ł��j���ǂ��薖���ƂȂ��Ă���B
�@SB2C�ATBF�̂ǂ��炩��ł��i���\�ƌ����������@�ŁA���萫���ǂ����Ƃ����q�̂ǂ��炩���g���ɂ����Ɗ������炻�̋@�����i������ȂǁA�_��Ȑi�����\���B
�@�͍U�̓����ł�����G�͈͂̂ݑ傫����̉����Ă��܂����A�������\�ł͏��镔�����������߃X�e�[�^�X���C�ɓ���Ύ��X�������Ă����͖������낤�B
|
 |
��B-17�@�t���C���O�t�H�[�g���X�@�i�����@�j
�@�����A�ݑ��ł���Ƃ��ꂽ4���ł���Ȃ�����ɂ߂č����ɔ�Ԏ����\�ŁA�ΉE�h�䐫�\���ɂ߂č����A���������ő劈���������\�����@�ł���B
�@�{���͐i�U���Ă����G�̌}���ɓ����邽�߂ɓ���\�͂��d�����ꂽ�����@�ł���A���ʓI�ɂ��ꂪ�����ΉE�h��͂鎖�Ɍq�������B
�@�G�̐i�U����C�ݐ������v�ǁA����ȁu�h�q�v�z�v����t���C���O�t�H�[�g���X�i���ԗv�ǁj�ƌĂ�A���̖��ɒp���鎖�̖������X�̌��т������Ă���B
�@���ɉ��B����ւ̓������͑����A���̐���ł͐������̍��E�����ɏ]�����i���ɒ������C���j�ڊo�������т������A�h�C�c�鍑�R�̎�����h��ɐH���Ԃ��Ă������B
�@����ő����m����ɂ���r�I�������瓊������Ă���A������̐���ł͓����̂����Ȃ��s���ȏɂ��ւ�炸�A���ȂǑ���{�鍑�R�@�q���点�Ă���B
�@�Q�[�����ł̖{�@�͏������琶�Y���\�ŁA���ՂƂ��Ă͌��O��ɐ��\�̍��������@�ƂȂ��Ă���B�i���Ȃ݂ɖ{��ł�4�������@�͗D������Ă���Ǝv���Ă悢�B�j
�@�R�X�g��3000�ƍ������̂́A���̐��\�̍����̓R�X�g�Ɍ����������̂ł���A�@�e���x�̈����A���e���ڗʂ̏��Ȃ������������Ă����Y���邾���̉��l�͂���B
�@�������I�ՂŎg�p�\�ɂȂ锚���@���������\�ŁA�����A����U���Ƒ劈��͂قڊm��A���Ղ���{�@���ʓ�������͔̂����ƌ����Ă����������ł͖����B
�@�i����͖{�@������ɋ��͂ɂ����悤��B-29�ƂȂ��Ă���AB-17�AB-29�A�����čŏI�i����B-36�ƃA�����J�R�̋��낵�������鎖���o���邾�낤�B
|
 |
��B-24�@���x���[�^�[�@�i�����@�j
�@��풆�ɐv�E�J���E���Y����A��킪�I���O�ɐ��Y���I�������ƌ����ꕗ�ς�����o�����������@�ł���B
�@�o�ꓖ���̃A�����J�R�ł͓����̔����@�AB-17�̐l�C�����ɍ����A�{�@�͎�ɃC�M���X�ւ̋����p�Ƃ����s���Ȉʒu�ɗ�������Ă����B
�@�������A���������C�M���X�R�ł͖{�@�̍q�������̒����AB-17���傫���ύڗʂ���肭���p���A�A���A�ΐ��A�����������Ə_��ȉ^�p���s���A���r���𗁂т��B
�@���̌�̓A�����J�R�ł��ϋɓI�ȉ^�p���J�n�����Ƌ��ɁA�D��I�Ȑ��Y�������s���A�����I�ɐ��𑝂₵�A���ɂ̓A�����J�R�Ő��Y���̈�ԑ��������@�ƂȂ����B
�@��햖���ɂ̓h�C�c�鍑�̓��ւ̔����ɂ��]�����Ă���A�������A�H��ȂǁA�I��𑁂߂�ׂ������̌R���{�݂�j�銈��������B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��琶�Y���\�ŁA�h��͂���B-17�ɗ����̂́A�q�������A���ڗʂł͏���AB-17���l�A�����@�Ƃ��ďd�v�Ȉʒu���߂�B
�@B���e�A250kg���e�̓��ڗʂɂ���̗]�T������A��`�̏��Ȃ��}�b�v�ł�����⋋���C�ɂ������S���Ďg����̂����݂��낤�B
�@�����ȂƂ���A���͂Ȕ����@�AB-17�̉e�ɉB�ꂪ���Ȗ{�@�ł��邪�A�n���ɋ����q�������ɂ��]�T�����邽�߁AB-17�ł͉^�p���Ԃ�����Ȃ���ʂł͐ϋɓI�Ɏg�������B
�@�i�������͏I�ՂƂȂ邪�A�ɂ߂ċ��͂Ȕ����@B-36�ɐi���\�ŁAB-17�ƈႢB-29���X�L�b�v���Ĉ�C��B-36�ւ̐i�����\�ł���B�i�g�킸�Ƃ��O������X�g�b�N�����j
|
 |
��B-29�@�X�[�p�[�t�H�[�g���X�@�i�����@�j
�@��풆�����猻��A���̔��e���ڗʁA�����x���\�A�������\���h�q�\�͂������A�҈Ђ�U����������@�ł���B
�@����{�鍑�̐푈�p���\�͂����킶��ƍ��A�����̂��Ȃ��Ȃ�����͓O��I�Ȕj�����s�������Ƃ͐�������܂ł��Ȃ��B
�@���q���e�𓊉������̂̓G�m���E�Q�C�i�L��1945�N8��6���j�ƃ{�b�N�X�J�[�i����1945�N8��9���j�ł���B
�@�{�@�͓����Ƃ��Ăُ͈�Ȃ܂ł̍������\�������A�q���́A�����d�ʁA�h�q�\�́A���̑��������S�ĂɏG�łĂ���A�S�Ă̒��ŌQ�������\�ł������B
�@���̍����\�͐��X�̋Z�p�Ɏx�����邱�Ƃ��琬�藧���Ă���A����Ƃ��Ă̊����x�����ɍ����A�A�����J�̒�͂��f����B
�@���{�ł͌�������ɖڂ������Ă��܂������ł��邪�A�����C�������������Ȃ��Ă���A�ނ����_�W���̌��������n���Ȕ����ɂ��L�͈͔�Q�̕����������낤�B
�@�Q�[�����ł͌��X4�������@���D������Ă��邱�Ƃ�����h��͂������A�����Ɏg���Ă悵�A�Βn�U���Ɏg���Ă悵�Ɣ�̑ł����̂Ȃ����\�ƂȂ��Ă���B
�@�{�@���܂ސi������B-17��B-29��B-36�̗���ɂȂ�A�i�����A�i��������͂Ȕ����@�ŁA���Ղ�B-17�Y���Ă����g���g�����q�Ői���ł���B
�@�ł��邾�����߂ɐ������낦�ċN�����������@���B
|

coffee break |
|
�`���낵�������\�ň��|�I�����������G�ł͂Ȃ����������@�EB-29�`
�@B-29�ƌ����Γ��{��j�����A�L���A����������ʼn�ł��������ŗL���Ȕ����@�ł���B���̔����@�͓����̐�i�Z�p�̉�Ŕ��ɍ����ȋ@���������A�A�����J�̋���ȍ��͂ɂ���đ�ʐ��Y����Γ���ɑ����������ꂽ�B����{�鍑�ɂ͗D�G�Ȑ퓬�@��������������̂́A�����������Ă��Ă������x���s�����͂Ȏ��q�Ί������B-29�̌}���͓���A�R����ɂ͑����̓w�́E�H�v���K�v�ł������B����Ɍ}�������݂��퓬�@�͋t�Ɍ��Ă����قǂŁAB-29�u���v���āE���ނ����퓬�@�͕S�P�ʂŐ�������قǂł���B�����ǂ�����{�����������W����B-29�͂���قLj��|�I�Ȕ����@�ł������̂ł���B
�@�����AB-29�������狭�͂ň��|�I�ȑ��݂ł����Ă����G�ł͂Ȃ������B��q�@�̋��Ȃ����ł͌}���@�̕s�ӑł��������Ă����ꍇ�����������A����{�鍑�R�̍��˖C�͖吔���̂͏��Ȃ��������ӊO�ȂقǗD�G�ő�����B-29�����āA�܂��͐퓬�E��s�s�\�ɒǂ�����ł���B�܂��A���B����ɂ�����x��������P�̐r��Ȕ����@��Q�̋L�����N���ł�������������{�{�y�����ł͔�Q���x���������ȌR�{�݂ւ̔����͍T�����A�ς��ɊC�H�֍q��@������T���ȂǑ���{�鍑�R�̐�͂��ߏ��]��������Âȉ^�p���s��ꂽ�B�����Ė����ɂ͒ፂ�x����̋��s�����ʔ������s��ꂽ���A���̎��ɂ͂�������B-29�ł������@����Q�����Ă���BB-29�͊m���ɋ��͖���Ȕ����@�ł��������A���G�ł͂Ȃ������̂��B
|
 |
��B-36�@�s�[�X���[�J�[�@�i���̂͐����Ȃ��̂łȂ��R���J���[����������@�����@�j
�@���[���b�p���ʂ̍Ԃł���C�M���X�鍑���ח������ꍇ��z�肵�A�A�����J�R���J�����Ă�����^�����@�ł���B�i���́u�v�悵�Ă����v�Ƃ����̂͊J�����ɏI����}�������߂ł���j
�@�����^�ł̓��V�v���G���W��6����p���Ă������A��ɔ\�͕s�����w�E����A����^�ł͂���ɃW�F�b�g�G���W����4���lj������Ƃ��������܂�����X�P�[���ȋ@�̂ł������B
�@��풆�ɂ͊������Ȃ��������Ƃ�����ɉ^�p�E���Ă������̂ق����L���ł���A���V�v������W�F�b�g�ւ̉ߓn���ɒa���A�^�p����Ă������Ƃ��犈����Ԃ͈ӊO�ƒZ���B
�@�@�̂̑傫�����琫�\�ʂł͂��Ȃ�̗]�T������A�q�������A���ڗʂ�B-29���y������قǂŊm���ɍ����\�ł͂������A���A���ʁA�R�X�g�͋ɂ߂č����A���ꂪ�ő�̌��_�ł������B
�@�A�����J�R�炵���Ȃ����R�X�g�A�����\�Ƃ����ґ�ȋ@�̂ł��������A���B�R�X�g���A���nj^���܂ތ�p�@�����ł�����ʂŋɂ߂ėD�G��B-52�ɔs�k���A���X�ɑޖ����Ă���B
�@�Z�����Ԃ̊���ł͂��������A���q�F���ڎ���@�A�l�X�ȉ��ǂȂǂ�����ɍs���A���s�����������܂߂Ă��̃m�E�n�E�͌R�ɂƂ��ėL�Ӌ`�Ȃ��̂������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[���ł͒�����̕��ނɑ����邽�߈��|�I�Ȑ��\���ւ�A�A�����J�R�����@�̍ŏI�i���Ƃ��Ė�����B-24�AB-29����̐i���œ��邱�Ƃ��\�ł���B�i�|�S�ł͓��{�{�y��̂݁j
�@B-29�ȏ�̒���ȍq���́A���ڗʁA�h�䐫�\�A�����Η͂͂���������͂Ȃ��̂ŁA���ɔ����Η͂͒��Ձ`�I�Ղ̐퓬�@���݂ɋ��͂ł��邱�Ƃ���g������͋ɂ߂č����B
�@�����@�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ��������A�M�ғI�Ɂu�����v�ȊO�ɏ������Ƃ����܂�Ȃ��A���ꂭ�炢�������߁A�G����p�Ђɏo����悤�Ȕ����@����������Ă݂Ăق����Ƃ���ł���B
|
 |
��PBY�@�J�^���i��s���@�i����U���@�j
�@�Γ���J��O���^�p����A�J���͋����������������ɂ�������炸�A�^�p���A�ėp���̍��������풆�͂��Ƃ��A�������ɏd�ꂽ�A�����J�R�̌����s���ł���B
�@�{�@�͎�ɏ����A�������͂��߂Ƃ����C��C���̂ق��A�~���A�A���A�g�q�Ȃǂ̔C�������蓖�Ă��A�ǂ��炩�Ƃ����U�߂邽�߂�������I�A�⏕�I�ȔC���ɒ����������������B
�@�h�肳�͖������A�����̔C����ɂ��Ȃ��邻�̔ėp���͘A���e���ł��D�]�ŁA�A�����J�R�݂̂Ȃ炸�A�C�M���X�R��J�i�_�R�ȂǑ����̍��ł��̗p�E�^�p����Ă���B
�@���nj^���������݂��A���ł�5A�^�͓���ȍ\���ɂ��ԗւ𓋍ڂ��������p�@�ɂȂ�ȂǁA���X�̑f�s�̂悳�ɉ����đ����̉��ǂ������]�T�̂������v�ł��邱�Ƃ��킩��B
�@��s���x�͂��Ȃ�x�����ނɓ���A���Δ��������\�������n���ȋ@�̂ł��������A�����ő����̔C���ɑς����鍂���ėp���͒N�����F�߂錆���s���ł������B
�@������e���ŏ��h�E�h�Њ����@�Ƃ��Ă��炭���A�傫�����̗��ꂽ���݂ł��v�͗��p����A�V�Z�p�̓����Ƌ��Ɍ��͑����Ă���B�i�{���o���f�B�A�n��s���Ȃǁj
�@�Q�[���ł͗���U���@�Ƃ��č��t�@�C���œo�ꂵ�A���@�����ɂ�葦���Y�A���ǐi���Ȃ��̒P�̂Ƃ��ĉ^�p���\�ƂȂ�B
�@���ۂ̊���Ƃ͒������]���ŁA���X�y�b�N�ɉ������X�e�[�^�X���̗p����Ă���炵���A���ʓI�ɑ���{�鍑�̓����������悤�Ȑ��\�̂��ߎg������͎��Ɉ����B
�@�A�����J�R�ł͗���U���@�ɑ�p�ł��鍂���\�����@���ڗ����A���̏�C�R�����́A�����ƂȂ�Α�ʎ����ŋ쒀�̗͂ʎY���\�ł��邱�Ƃ���A�{�@�̊���͂���قǂȂ����낤�B
|
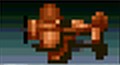 |
��I-15�@�i�퓬�@�j
�@��평���Ɋ����퓬�@�����A���ۂɂ͑���肩�Ȃ�O�ɔz���E�^�p����A���O�ɂ�����X�y�C���A�m�����n���Ȃǂ̏����荇���ł̉^�p�̕����L���ȋ@�ł���B
�@�{�@�͓������s���Ă����`��E�@�\�̂قƂ�ǂ���������Ă���A���t�@�ŋr�͌Œ莮�ƌ������㑊���̐v�ɁA�����I�Ȋɂ��K�������^�����Ă���B�ibis�̓K�����p�~�j
�@��{�I�ɐ��\�ɗ�鍑�Y�G���W�����g��ꐶ�Y����Ă������A�����̌v��������\���Ⴍ�Ȃ��Ă��܂������߁A�ꕔ�̋@�̂ɂ̓A�����J����A�������G���W�����g��ꂽ�B
�@�����\�ȍ��Y�G���W���̐��Y���O���ɏ��Ɓi�ƌ����Ă����C�Z���X���Ǖi�����j������ւ̓]�����i�݁A���̋@�̂���ɒ������ʂ�X�y�C���Ő킢�ɎQ�����鎖�ƂȂ�B
�@���˓����ɂ͋������������������ɋ��̍s���Ȃ��@�̂ƂȂ��Ă������A�ɂ߂ėǍD�ȉ^�����\������nj^I-15bis�ibis��2�̈Ӗ��j�����܂�A�Βn�U���ɏ]�������B
�@�����͋��͂Ƃ͌����Ȃ��������A�Βn�U���Ƀ��P�b�g�e�ȂǕς�����������\�ł��������߁A���炩�Ɍ���肷�鐫�\�ł��ŏI�I�ɑ�피�܂ʼn^�p���ꂽ�B
�@�Q�[���ł͂��������ɂ����đ����Y�Ŏ�ɓ��邪�A���\�̕��͒������Ⴍ�A�{���̔C���ł���퓬�@�Ƃ��Ă͎g���Ȃ��@�ƂȂ��Ă���B
�@�͂����茾���قڐ��Y�̉��l�͖������A�����̐퓬�@�Ƃ��Ă͒��������P�b�g�e�̕������\�ł��邽�߁A�����ȓ_���������Ďg���̂Ă̑Βn�U���@�Ƃ��Ďg���Ȃ����Ȃ��B
�@�i���悪I-16�ƐU���Ȃ����߃L�����y�[���ł̉^�p�Ӌ`�͂܂������Ȃ����A���Y�킪������X�^���_�[�h�}�b�v�ł͏ꍇ�ɂ���đΒn�U���@�Ƃ��ē�������̂��ǂ����낤�B
|
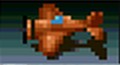 |
��I-16�@�i�퓬�@�j
�@I-15���l�|���J���|�t�ɂ���Đv���ꂽ�퓬�@�ł��邪�AI-15�����t�@�ł���̂ɑ�������͒P�t�@�ŁA���E���ƂȂ�������r�����p�������@�̂Ƃ��ėL���ł���B
�@�{�@�͓o�ꎞ�_�ł͂قڐ��E�ő��ƌ����鑬�x���\���ւ�A�������Ɋe���Ŏ嗬�ł��������t�@�ɑ��Đ��\�ł��傫������t���A���������x�̋@�ł������B
�@�킢�ɓ��������ɂ�Đ����E���ǂ���Ă��������Ŕ��Ɍ����I�Ȑ��\������}���Ă���A�����A�G���W���A���b�ȂǗl�X�ȖʂŒ������������{���ꂽ���������[���B
�@�����\�͑����̐�i�I�ȋZ�p�ɂ���Ďx�����Ă���A���̋Z�p�̑�������̒P�t�@�ɂ����ē�����O�ɂȂ���̂ł��������Ƃ���{�@�͒P�t�@�̐�삯�ƌ����Ă��ǂ����낤�B
�@�^�p������I-15���l�ɑ��O�`��평��������������J�펞�ɂ͊��ɋ��������Ă���A���ɂ�����^�p���@���قƂ��I-15���l�ł��������A���Y���̂͑�풆���s���Ă����B
�@�����^�ƌ���^�ł͉��ǂɂ���Ă��Ȃ�̐��\��������A�����^�ł͌y���ȒP�t���{�R�@����ɋɂ߂ė������̂�����^�ł͗��ꂪ�t�]����Ȃǖʔ����@�ł��������B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ�I-15����̐i���A�������͑����Y�Ŏ�ɓ���AI-15����傫�����\���サ�Ă�����̂́A��͂���͌��������\�ƂȂ��Ă���B
�@��킲�������Ȃ�Ȃ�Ƃ����Ɏg���郌�x���܂Ő��\�͏オ���Ă���̂����A���������퓬�@�Ƃ̔�r�ł͖��炩�ɗł���A�����Ƃ̒��ڐ퓬�͏o����Ή���������B
�@������I-15�Ƃقړ����ł��鎖����u�ǂ����Ă��v�Ƃ����ꍇ�ȊO�͎g���K�v�͖����A�g���Ȃ���P�b�g�e�̕����ɂ��Βn�U���@�Ƃ��Ẳ^�p���K�C���낤�B
|
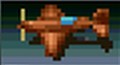 |
��Mig-3�@�i�퓬�@�j
�@���݂ł��L���ȃ~���R���E�O���r�b�`�v�ǂ̃~�O�퓬�@�̑c�ł���B
�@���_�������A���X�ɐ��Y���ł����Ă��܂���1�^�ɑ��A�������̉��ǁE�v�������E�������{���A���H�ɑς����鐫�\�܂Ői���������̂�3�^�A�{�@�ƂȂ�B
�@�{�@�͍��x�ł̐퓬�����ӂł���A���x�ł͂��̐��\�𑶕��ɔ����ł������A���ł̔\�͕s�����Ђ����A�h�C�c�鍑�@�Ɉ���y�Ȃ����\�ł������B
�@�������A�����Ƃ��Ă͔��Q�̑��x���ւ�A�������̃��R�u���t�퓬�@�A���{�[�`�L���퓬�@���͏���ʂ���⑽�������悤�ł���B
�@�Q�[������Mig�퓬�@�̓\�r�G�g�R�ɂƂ��Ă͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��퓬�@�ł���B
�@�ΉE���x�ɓ������̂́A��h��͂�⍂�߂őł��ꋭ���A�B�x�̍���3�^��7�^�i���������Me262�ɑ���ǂƂ��Ă��\���g����B
�@�Ȃ��AMig�n�̉^�p���y���݂�����A���t�@�C���̃\�r�G�g�L�����y�[���������߂���B
�@���x�̕������A�|�S�̐�����������x�������Ȃ��Ă���A�\�r�G�g�퓬�@�ɂ��U����v�������y���߂邾�낤�B
|
 |
��Mig-7�@�i�퓬�@�j
�@��Ɋւ��퓬�ɑ��A�ꎞ�ɒu���ꂽ�\�r�G�g�R�ł͍����x����̐i���@�ɑR���ׂ��}���퓬�@�̊J��������A���������̂��{�@�ł���B
�@�������A�����Ƃ͌������̂̓o�ꎞ�ɂ͂��łɑ�����ɓ����Ă����A���͘A���R�E�ԌR���Ɉڂ����A�����x����̋��Ђ͂قƂ�ǖ����Ȃ��Ă����B
�@���̌��ʁA�����̗p�͂��ꂸ�A�����������E�����@�Ƃ��Ċ��������ɂ����Ȃ��B
�@����܂ł̃\�r�G�g�R�@�ƈႢ�A�@�̂̐v�v�z�E�����i�͂��낢��Ɖ��ǂ�V�v���{����Ă���A��̐퓬�@�J���ɉe����^�����ƌ����Ă���B
�@��풆�̃~���R���퓬�@�ő�\�I�Ȃ��̂�3�A5�A7�A9�Ɗ���������E�J������Ă��邪�A�����ȂƂ���A������̋@�̂��听�������߂��Ƃ͌������A�����͎��ɏ��Ȃ��B
�@�{�@����ɘR�ꂸ����Ȃ��A����������ƒv���I�Ȍ��ׂ���������A�܂����\�͗ǂ����R�X�g�ʂ�^�p�ʂł̖��Ő����̗p����Ȃ������̂�������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͏I�Ղ̍ŏI�i���^�Ƃ������ƂŃ\�r�G�g�R�ŋ��̐퓬�@�Ƃ��ČN�Ղ��AMig-3����̐i���A��햖���ɑ����Y�œ��肪�\�ƂȂ�B
�@��ΉE���x��Bf109k�Ɠ������x�i80/18�j�Ƃ������̂́A�h�䐫�\��70�z���ƃW�F�b�g�@���݂ɂ��Ȃ荂���Ȃ��Ă���A�h�q�p�ɍœK�ƌ����鐫�\�E�ʒu�t���ɂȂ��Ă���B
�@�����͋@�֖C�̂݁A����ɂ��̋@�֖C�̉Η͕s�������̗���Ȃ��͊�������̂́A�R�X�g�͗}�����Ă邽�ߐ��\�͐��ŃJ�o�[����Ɨǂ����낤�B
|
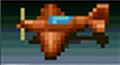 |
��Yak-7�@�i�퓬�@�j
�@��평���`�����A�\�r�G�g�R�ł́A�����I�ɒx��C���������퓬�@�z�������Ƃ��������������A�ˑR�Ƃ��āu�}����̐퓬�@�v�Ȃ�ł͂̒�i���ɔY�܂���Ă����B
�@���̒��ŗD�G�ȗ��K�@�ł�����I-27�ɒ��ڂ��A������x�[�X�ɉ��ǁE�퓬�@�Ƃ��ĕK�v�Ȓ������s���Ċ��������̂��{�@�ł���B
�@�O���f����Yak-1�ŕ]���̈��������d�S�̌����T�d�ɒ�������Ă���A���������ł��������߁A�����P���ɂ�����ƁA���ǂ͑���ɓn��B
�@�{�@�͌��������悭�l�����Ă���A���̂������ŒZ���Ԃɑ����������Y����A���s���ĉ��ǂ������ɐi�݁A�����^�ƌ���^�ł͂��Ȃ�\�́E����������_���ʔ����_�ł���B
�@��荂���\��9�^�������ɓo�ꂵ�����Ƃɂ��A�{�@�͐��Y���Ԃ��Z�����̂́A���S�ʂ��͂��߁A�������Y���ł͗��K�@�Ƃ��đ������g��ꂽ�B
�@�Q�[���ł�Yak-1����̐i���A���@�����ɂ�萶�Y���\�ƂȂ�B
�@�����Ȑ퓬�@�Ƃ��Ă͐����ȂƂ���͕s���ł���A�����ĉ^�p���邱�Ƃ��O��Ȃ���P�b�g�e�����A�퓬�U���@�Ƃ��Ďg���̂��������B�i����ł��Βn�U���͂͒�߁j
�@�嗤���Ƃ̗���@�Ƃ���������A�R���͍T���߂ő����Z���A���e���ڕs�Ƃ����}�C�i�X�_�����݂��A�v���[���[�ɂƂ��Ă͎g���ɂ�������̈�ɂȂ邾�낤�B
�@�i�����Yak-9�ł����Bf109G�Ɠ����x���Ƃ����Ȃ�Ƃ������Ȃ������Ȑ��\�ł͂��邪�A��R�̃o���G�[�V�����s����₤���߁A���@�͕ێ����Ă��������B
|
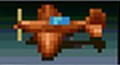 |
��Yak-9�@�i�퓬�@�j
�@���`�����x�퓬�ɍœK�����ꂽ���ǔ�Yak-7����ɊJ������A��풆�ɂ����郄�R�u���t�n�퓬�@�̂Ȃ��ł����Ƃ��D��Ă���Ƃ����퓬�@�ł���B
�@����܂ł̃��R�u���t�n�퓬�@�͒ፂ�x�ł̊i����Ɏ��ɒu�������̂ł��������A�{�@�͊�ƂȂ������nj^Yak-7�̐��\�������p���A���`�����x���\������ɐL���Ă���B
�@�����ɂ͋��͂�20mm�@�֖C�����ڂ���Ă���A����ɂ�⏬���Ȕ��e�Ȃ�Ζ��Ȃ������\�ƁA��A�Βn�ɂ����ė]�T�̂���Η͂��������킹�Ă����B
�@�@�̂̑f�ނɂ͖ƕz�A�������p�����A�@�̂̑傫���⓯����̋������퓬�@���l������ƁA���ߏd�C���ł��鎖�͖����ł���A���̓_����ō����x�͍T���߂ł���B
�@���x�ȊO�ɂ�������͂��������A�����ȋ@�̂ɋ��͂ȃG���W���Ƃ����g�ݍ��킹�͋ɂ߂đ������ǂ��A���ʁA�����ėp���ɂ��b�܂�A������퓬�@�Ƃ̔�r�ł����F�Ȃ������B
�@��⑀�c�̓���퓬�@�ł������悤�����A���i�`�t�����X�l�����̕]���ł͍D�]�Ă���A�����S�������ɂ���铙���ǂ�������꒷���g��ꂽ���@�ł������B
�@�Q�[���ł�Yak�n�ŏI�i���Ƃ��ďI�Ղɓ��n����i�����\�ƂȂ�A���\�A�o�ꎞ�����畺���ɗ��Mig-7�̕⍲��I�ȑ��݂ł���B
�@���\�I�ɗD������Ă��镔���͊F���ŔR�������Ȃ��A�����͑��ʂł��e�������Ȃ��Ȃǎg���ǂ���͓���A�h��͂���r�I�����Ƃ��납��ǒn�퓬�U���@�Ƃ��Ẳ^�p���������B
�@���݂̂ł���Ηǂ��Ƃ������Ȃ�A�{�@�����đS�Ă̐퓬�@��Mig-7�ő����Ă����͂Ȃ����A�Βn�U��������ɓ����Ƃ�͂�{�@���K�v�ł��낤�B
|
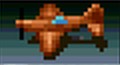 |
��LaG-3�@�iLaGG-3�@�퓬�@�j
�@���ԓI�ɁA�ᐫ�\���������]���̈������ŗL���ȁA���{�[�`�L�����̃\�r�G�g�R�P���ؐ��퓬�@�ł���B
�@�{�@�̓����́A�O�q�̈����]���ɉ����A�헪�����Ƃ��ċM�d�ł���������g����������A�@�̖̂w�ǂ̕�����ؑ��ō\�����Ă��鎖���������邾�낤�B
�@�헪������ߖ�ł���ƌ��������b�g�͈ꎞ���傢�ɂ��Ă͂₳�ꂽ���A�@�̂͏d���A�������\�͑����@�������������x�ŁA�S�̓I�Ȕ\�͓͂����퓬�@�ɔ�ג������Ⴂ�B
�@���܂�̐��\�̒Ⴓ����A�u�����v�Ȃǂƕs���_�ȌĂ��������Ă�����̂́A�ؑ��Ȃ�ł͂̏�v���͑�평���ɂ͔�r�I�L���ł������B�i����ł����͑��������j
�@�ؑ��ƕ����ƁA����̗D�G�ȗ���U���@�A�C�M���X�R���X�L�[�g���v�������ׂ邪�A�{�@�ɂ����Ă͑�ʐ��Y�䂦�̎G�ȍ�肪����Ɣ�ו��ɂȂ�Ȃ���i�����������悤���B
�@�\�r�G�g�R�ł͐헪�\�z���班���̍����\�@�����A��肪�G�ł���ʂ̐퓬�@��K�v�Ƃ��Ă������߁A���J�ɍ���Ă����Ȃ�A�����܂Œᐫ�\�ł͂Ȃ�������������Ȃ��B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��瑦���Y���\�ŁA�i���A���ǂ͈�ؖ����ƌ����A����Ӗ��d�h�Ȑ퓬�@�Ƃ��đ��݂���B
�@�j�����l�ɐ��\�͒Ⴍ�A�搧�����Ȃ��A�Η͕s���A�h��͂��Ⴂ�ƁA�^�p���@�����߂�ׂ��Y�����Ɍ��ǎg���ǂ��낪�����Ƃ�������قǔ����Ȑ��\�ł���B
�@���߂�La-5����^�ALa-7������ɐi�����\�ł���Ή��l�͂���̂����iLa�n�͖{��ɓo�ꂵ�Ȃ��j�A�c�O�Ȃ����Ƃ��ăX�g�b�N���邭�炢�̉��l�����Ȃ����낤�B
|
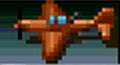 |
��Il-2�@�i�V���g�����r�N�������́@�U���@�F�퓬�U���@�j
�@�C�����[�V����������J���w�������������U���@�ŁA���Y������36,000�@���z���A��s�@�j��ɂ����čł����Y���ꂽ�R�p�@�ł���B�i�Q�l�F���ԋ@DC-3��10,000�A�y�Z�X�i��40,000���j
�@�{�@�͔��ɗD�ꂽ�h�䐫�\�������Ă���A���̐��\�͗D�ꂽ�v�ɉ����A��e���l���������i�z�u�A����ɐ����Ɏ{���ꂽ���b�ɂ���Ď�������Ă����B
�@���b���ɂ���ċ@�̂͏d���A���x��^�����͌����ėD��Ă����Ƃ͌����Ȃ����A���肠�܂鑕�b�͂��̌��_�����鉿�l�������A�p�C���b�g�B�͖{�@�ɐM�����悹�Ă����Ƃ����B
�@���Y�����ɂ���ĒP���A�����A�������A�ؐ����A�܂������ɂ���������邪�A����̓h�C�c�鍑�R�̐N�U�ɂ���ė��L�����A���̎��̏�ŏ_��ȉ��ǂ����������ɂ��B
�@���Ɍ���^�ł͕����A����@�e������������O�ƂȂ��Ă���A���̎�����͖{�@��������q��������Ԃłǂꂾ������Ȑ��ɑ��荞�܂�Ă��������f����B
�@�d���ȋ@�̂ŌQ��Ĕ�щ��{�@�͌y��@�֖C�ł͂Ȃ��Ȃ����Ăł����A�h�C�c�鍑�R����͍����a�A���Ԑ�ԂȂǂƋ�����A�c���h�q�̂��߂ɑ傢�ɖ\��܂�����B
�@�Q�[���ł͔�r�I���Ղ��琶�Y���\�ƂȂ��Ă��邪�A�����Z���A�Η͍͂T���߁A���r���[�Ȗh��́A�R�X�g���A�Ƃ��Ȃ�Ȃ̋����@�̂ƂȂ��Ă���B�iIl-10�����R�X�g���j
�@�����\�ȋ@�������Ȃ��\�r�G�g�R�ł͎g�������Ȃ��Ƃ����̂��߁A�{�@���䖝���ĉ^�p���A����Ƃ�SB-2�ł��ˌ������������������A�v���[���[�͂���Ȕ��f�𔗂���B
�@�i�����Il-10�i���z�ł͏I�Ց����Y�A�j���͐i���ł̂ݓ���j������������������\�Ƃ͌������A���_�I�ɂ��̌n��͎�̕���Ɣ��f���邵�������̂�������Ȃ��B
|
 |
��Il-10�@�i�U���@�F�퓬�U���@�j
�@�����h��͂��ւ�e�n�Ŗ\��܂����Il-2����킪�i�ނɂꋌ�������Ă����A��Q���ڗ��悤�ɂȂ�Ɓu�V����Il-2�v�����߂���悤�ɂȂ��Ă����B
�@����ɓ����邽�ߊJ�����ł������퓬�@�𗬗p���AIl-2���݂̖h��́A�����Ď��㑊���̑��x�A�@���͂��������킹���U���@�̊J�����s���A���������̂��{�@�ł���B
�@���X�̋@�̂��퓬�@�i����������Ȃ������퓬�@�����j�ł��邽�߁AIl-2��ł͊i�i�̋��͌���ɐ������Ă���A�������̐퓬�@�Ɣ�r���Ă������̂ł͂Ȃ������B
�@�h�䐫�\��Il-2���l�ɋɂ߂č����A�����ċ��\�͂܂ŏオ���Ă���Ƃ������z�I�ȍU���@�ł��������A���������I�Ղł��������߂ɐ��Y���A�O���ւ̔z�����͑����Ȃ��B
�@������23mm�@�֖C�A���e�A���P�b�g�e�Ȃǂ���ӂꂽ���}�Ȃ��̂ŁA�����I�ɖڐV�����͖������A�a�V�������߂Ȃ��������͋t�ɖ{�@�̊����x�����߂�����ł������ƕM�҂͎v���B
�@����͓��������ōL���p�����A���N�푈�ɓ������ꂽ�ꕔ�̋@�͎�Ȃ��犈������������A�W�F�b�g�̔g�E���V�v���@�̏h�����A�^�p���Ԃ͒Z���Z���ł������B
�@�Q�[�����ł͐퓬�U���@�Ƃ��ēo�ꂵ�A�j���L�����y�[���ł͖�����Il-2����̐i���ŁA���z�L�����y�[���ł͉����Ė����ɑ����Y���ł���悤�ɂȂ�B�i�ŏI�i���j
�@Il-2����̖h��͂͂���ɋ�������Ă��邪�A���ɗD����������_�������p����Ă��邽�߂ɒ��r���[�Ȋ��������A�^�p���ɂ͕Ȃ������邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B
�@���e�A���P�b�g�e�������ɑ����ł��镐���ʂ��ґ͂�����̂́A���ۂɎg���ē��������悤�ł���A�f���ɔ����@��Βn�U�������Ŏg�����ق����ǂ����낤�B
|
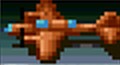 |
��SB-2�@�iSB���������@�@����U���@�j
�@�c�|���t�v�ǂɂ���đ��O�ɊJ�����ꂽ�����@�ŁA�@�̂̋K�͂��炵�Čy�����@�ɑ������A�ނ��뗤��U���@�ɋ߂��Ƃ�����@�ł���B
�@�O���I�ɂ͎a�V�ȕ����̖����@�̂ł͂��������A�S�������ȂnjX�̕����ł͐�i�I�ȋZ�p�����Ȃ��荞��ł���A�\�r�G�g�ł͑傫�����������@�̂ł������ƌ����Ă悢�B
�@�a�������Ƃ��Ă͔��ɗD�ꂽ��s���x���ւ�A�����^�ł�300km/h�ȏ�A���nj^�ł�450km/h�O��̑��x���������o���A����͓����̈�ʓI�Ȑ퓬�@�����������̂ł������B
�@�����\�Ȃ����Ɋ���͖ڊo�����A�����A�t�B�������h�A�X�y�C���ȂǑ��O�̏����荇���ɓ�������A���Ȃ�̐�ʂ��c����������G������͌x�����ׂ������@�Ƃ���Ă����B
�@�������A������J�킩���평���܂ł������Ƃ���ŁA����ȍ~�͐i�������퓬�@�ɑ傫�����\������������A�퓬�ȊO�̔C���ɏA�����́A�g���̂Ăɂ������́A�e�X�̓�����B
�@�ŏI�I��6000�@���y������@�����Y���ꑽ���̔C���ɏA�������A�ߎS�ȍŊ��𐋂���@�������A�ǂ������������Y��`�I�ȐF�����̔Z���@�̂ł������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[���ł͔����@�łȂ�����U���@�Ƃ��ēo�ꂵ�i�����A���G�͈͗D���̂��߁j�A���O�̋@��ł��邽�ߐ��\�͒Ⴂ�����Ղ��瑦���Y���\�ƂȂ��Ă���B�i�i���E���ǂ͖����j
�@�Βn�Η͍͂T���߂ōq�������������B�@�Ɠ����悤�ɒZ���A�����\�͂��قڊF���őł���ア�ƌ��_���ڗ����A���G�͈͂�4�ƍL���A���̓_�����͕]���ł���B
�@�퓬�U���@����ł���呹�Q�͊m��ł��邽�߁A�X�^�[�������Ɍ����u��Q�͂ǂ��ł��悢�A�Ƃ������G�Ɉꌂ������v�ƌ������悤�Ȏg���̂ėp�r�ɂ����g�����͂Ȃ����낤�B
|
|
��TB-3�@�i�����@�j
�@��p�ʂ��甚���@���d�v�����Ă��Ȃ������\�r�G�g�R�ł́A�����@�̗̍p�ɂ͏�ɏ��ɓI�ł��������A�{�@�͂���Ȓ��ł����������������ꂽ�d�����@�ł���B
�@�v�́A�����Ȑ����ɂ�鍇��̂悤�Ȃ��̂ł���A��^�@�̐v�ɒ�]�̂���c�|���t���ȊO�ɂ������̋Z�p�҂��Q�����Ă����B
�@�l���̑傫���͋����@�̂̓\�r�G�g�R�@�Ƃ��Ă͋ɂ߂č����ύڗʂ��ւ������A�v�E���Y�͑��O�̂��̂ł���A��평���`��풆���ɂ����đ������������i��ł��܂����B
�@��풆���ɂ͊��ɑO������͑ނ��Ă���A���̑����͗A���C���A�O���C�_�[�E����Ȃǂ̐퓬�ȊO�̔C���ʼn^�p����A�n���Ȃ���������ȓ������������B
�@�c�|���t���͏l������ɂ���^�f���瓊���i��Ɏߕ����ꂽ���j����Ă��܂������A�����A�������ꂸ�ɋ�����A�{�@�̉��ǂ���Ȍ�p�@�̊J�����i��ł�����������Ȃ��B
�@�Q�[���ł͏��Ղɐ��Y���\�ŁA�L���ȍU���@�������Ȃ��\�r�G�g�R�ɂƂ��āA�B��܂Ƃ��ȍU���@�֑�ւł���M�d�ȋ@�̂ł���B
�@�h�䐫�\�Ȃǂ͖J�߂�ꂽ���\�ł͂Ȃ����A���e���ڗʁA�R���i�s���͈́j�Ɋւ��Ă̓\�r�G�g�R�̒��ł���ʃN���X�ł���A�ϋɓI�ȉ^�p�ŗ��R���x���������Ƃ��낾�B
�@�L�����y�[���ł́A�Ȃ������Ոȍ~�͐��Y�s�Ƃ���㩂��d�|�����Ă��邽�߁A����������Ăł��\�Z�Ƒ��k���Ȃ���o���邾���m�ۂ��Ă��������B
�@�i����͓������l���@��Pe-8�i���ɃR�X�g�������j�ŁA��C�ɐ��\�������グ���邽�߁A�i������͌o���l�����܂莟��A���݂₩�ɐi��������̂��ǂ��B
|
 |
��Pe-8�@�i�����@�j
�@�\�r�G�g�R�ŗB����ɓ������ꂽ�u��p�v�����@�ł���A��b�I�Ȑv�̓c�|���t�����S�����Ă������A�l���̉e������y�g�����R�t���ֈ����p���ꊮ�������@�ł���B
�@TB-3�̌�p�Ƃ��ꂽ�{�@�͐�i�I�ȋZ�p�A�h��v�z�������ċ@�͔̂�r�I�ǍD�ȏo���ł��������A�c�O�Ȃ��炱������G���W���������A���\�͐U���Ȃ������B
�@�����̗p���ꂽ���_�̃G���W���̓~�N�[����1,350�n�͎l���ł��������A����͔����@�p�r�Ɍ������A����ȉ��̔n�͂ł�����B-17�̃G���W���ɔ�ׂĂ��������������̂��낤�B
�@���\�����X���@�ł��A�����x�̔�s���\�Œ�������s���\�ł�����������A�����ň��̐��\���m�F�����Ə���������������x�������֔����Ȃǂ֏]�����Ă���B
�@��ɃA�����J���G���W������{�Ƃ������͂ȃG���W������������ƁA�ꕔ�̋@�̂ɂ��ꂪ�̗p�����̐��\������ʂ��������A�헪�I�v�z�����ʔz���͂�͂肳��Ȃ������B
�@�����@���d�����Ȃ��\�r�G�g�Ő��܂ꂽ�������ɕs���ȉ^��������t���Ă���A�傫�ȉ��ǂ����ꂸ�����Ȑ��\���Ȃ������{�@�͂����������z�ȋ@�ƌ����邾�낤�B
�@�Q�[���ł͏I�Ղ������TB-3����̍ŏI�i���A�R�X�g�͍������ꕔ�}�b�v�ł̑����Y�œ���o����\�r�G�g�R�ŋ��̔����@�ł���B
�@�j���قǐ��\�]���͒Ⴍ�Ȃ��A���N��̑��������@�Ƃ̔�r�ł��傫����镔���͏��Ȃ����߁A���Ɉ����₷���@�̂őΒn�U���E�����̑o�������Ȃ���_�����]�����B
�@�܂Ƃ��ȍU���@�������Ȃ��\�r�G�g�R�ł́u�U���@�֓]�p�ł��锚���@�v�Ƃ����M�d�������\�̋@�̂ł���ATB-3�̏��ȉ^�p�E�X�g�b�N�ő��₩�ɐi�����s�������B
|
 |
���O���W���G�[�^�[�@�i�O���f�B�G�[�^�[�@�퓬�@�j
�@�C�M���X�R�ő��O���^�p���Ă������t�퓬�@�A�u���h�b�O�͔�s���\�E�������ɗD��A�����I�ɗD�G�Ȑ퓬�@�ł��������A�Ȃ��Ȃ��ǂ���p�@�Ɍb�܂�Ȃ������B
�@����Ȓ��Ő퓬�@�̍X�V�ɔ����Ă����C�M���X�R�ł͊���̌v��i�߁A���̒��ł����Ƃ��D�ꂽ���\�����{�̗p���ꂽ�̂��{�@�ł���B
�@�������̋@�̂ɔ�s���x�A�����i�A�����͂���܂ł̃C�M���X�R���t�@�Ƃ͔�ו��ɂȂ炸�A���t�@�Ƃ��Ă͍Ő�[���a�V�A�|�p�I�Ƃ���������̂ƂȂ��Ă���B
�@�����A���̗���Ƃ͎c���Ȃ��̂ŁA�{�@���z���E�^�p����邱��ɂ͒P�t�@�̃n���P�[����X�s�b�g�t�@�C�A�ABf109���o�ꂵ�Ă���A���t�@�͊��ɉߋ��̂��̂ƂȂ��Ă����B
�@���̂��Ƃ��犈��̏�͓��R�����A�唼�̋@�̂͑��X�ɑ������痣�E�������ɑ���ꂽ���A�ꕔ�͊C�R�ʼn^�p����V�[�O���f�B�G�[�^�[�Ƃ��Ă�����x�̊�������߂Ă���B
�@����Ƃ����傫�ȕǂɖ|�M���ꂽ�s�^�Ȑ퓬�@�����A���t�@�Ƃ������ނł͊m���ɐi�����Ă���A�C�^���A�̃t�B�A�b�g�n�Ƌ��ɍq��j��ł̑��݈Ӌ`�͂������@�̂��ƕM�҂͎v���B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ����ՁA�����ɂ������̎p�����邱�Ƃ��o�����A�ꉞ�A�i�����\�ŃV�[�t�@�C�A�ւƌq����B�i����������\�͔ߎS�Ȃ��̂����j
�@���t�@�Ƃ������ƂŐ��\�͋ɂ߂ĒႭ�AJu-87���}������ɂ����L���Ƃ����L�l�ŁA�{�@�Y����\�Z������Ȃ�U���@�ȂǑ��̕���Y����ق����܂������L�Ӌ`�ł���B
�@���͂�Q�[���ɑ��݂��鎖��郌�x���Ő��Y���S�O���Ă��܂���s�@�����A�v���o�����炽�܂ɂ͐��Y���ċ�����Ă��Ɩ{�@��������邾�낤�B
|
 |
���X�s�b�g�t�@�C�A�@�i�퓬�@�j
�@�����I�ȑ傫�ȑȉ~���A���������ɓn��{���ꂽ���ǁA���̊O���Ɖ��ǂɂ��A���ɂ͋~���퓬�@�ƌĂ��܂łɂȂ����C�M���X�鍑�̏ے��Ƃ��Ăׂ�퓬�@�ł���B
�@�h�[�o�[��n�艟����h�C�c�鍑�@��S�苭���쒀�E���ނ��A���̌�̔����ł��劈�Ă��邱�Ƃ���A����퓬�@��1�Ǝv���Ă悢���낤�B
�@�{�@�͗��j�������A��������Ȃ��قnjJ��Ԃ��ꂽ���ǂ̌��ʁA�����^�ƍŏI�^�ł͕ʐ퓬�@�ƌ�����قǂ̐��\���ŁA�啝�Ȑ��\���オ�}���Ă���B
�@�������A��b�I�Ȑv�͏����^�P���Ă���A�����^�`�ŏI�^���Ƃ����ē`���I�Ȋ�b�v���p�����Ă���ƌ����Ă悢�B
�@�Q�[���ł̃X�s�b�g�t�@�C�A��IX�^���炻�̐^�������A����XIV�^�ɂăC�M���X�鍑���V�v���@���ōō��̐��\������Ɏ���B
�@IX�^�͑�Η�100�A���x16�A���P�b�g�e�ɂ�鋭�͂ȑΔb�U���͂Ƃ����\�͂��������A���m�ۂ͂��Ƃ��A�n��G��͂̈Ј��ɂ��p���邱�Ƃ��ł���B
�@�����Ȑ퓬�@�Ƃ��Ďg�������A�����Ń��P�b�g�e�����A���[�{�Ƃ��Ďg�����Ƃł���ɐ�ʂ����҂ł��邾�낤�B
|
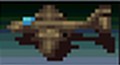 |
���~�[�e�B�A�@�i�퓬�@�j
�@�O���X�^�[�̊J�������C�M���X�R���̃W�F�b�g�퓬�@�ł���A�A���R���ł܂Ƃ��ɑ��֎Q�������B��̃W�F�b�g�퓬�@�ƌ����Ă悢�B
�@�����̃W�F�b�g�@�Ƃ��Ă͐v�̓I�[�\�h�b�N�X�ł���A�ނ��냌�V�v���@�ɋ߂��ێ�I�Ȃ��̂Ŋv�V�I�Ȃ��̂͂قƂ�ǎ������A�����ځA���\�A���ɂ܂��ɖ}�f�ƌ�����B
�@�����A����̓p�C���b�g�B�ɂƂ��Ă͊���e�����V�v���@�ɋ߂����o���������킹�邱�Ƃ��Ӗ����A���V�v���@����e�ՂɈڍs���₷���Ƃ����v��ʃ����b�g�鎖�Ɍq�����Ă���B
�@�G���W���Ȃǂ̖�肩�珉���`�����^�Ɋւ��Ă͂������ɂ��J�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�ނ��냌�V�v���@����������ɗ��悤�Ȑ��\�ŁA�C����V1�}���Ȃnj���I�Ȃ��̂ł������B
�@�������A���ǂ��i�݁A�G���W���ȂNJe���̖�肪��������n�߂�Ƌ��ɐ��\�͔���I�ɏオ�葱���A���ɂ�Me262�������邩������ׂ�قǂ̗͂邱�Ƃɐ������Ă���B
�@��풆�̊���͏��Ȃ����A���͂���Ȃ���ǂ��i�݁A���\�A�R�X�g�A�p�C���b�g����Ȃǂ̖ʂŗL���Ȃ��Ƃ��瑽���̍��œ�������A������1970�N�O��܂ʼn^�p���ꂽ�B
�@�Q�[�����ł́u�ꉞ�v�o�ꂷ��̂����A�ꕔ�}�b�v�ł̑����Y�݂̂ŃL�����y�[���ł͎擾�s�Ƃ����������A�C�M���X�R�ɓ�������Ȃ�قǂł���B�i�����͟T�������Ǝv�����j
�@���\�̓A�����J�R��F9F�p���^�[�Ɠ����ŁA�Η�140�E���x20�ƃ��V�v���@����Ȃ�Α��͗L���ɐ퓬���d�|���邱�Ƃ��ł��邪�A��͂�L�����y�[���Ŏg���Ȃ��̎��͌������B
�@�i���ɉ�������������������̂�������Ȃ����A�h�C�c�鍑�R�@�̂悤�ȋ���Ȑ��\�ł��Ȃ����߁A�ꕔ�̃X�^���_�[�h�}�b�v�ł����g���Ȃ��Ɗ��S�Ɋ�������ق����ǂ����낤�B
|
 |
���^�C�t�[���@�i�퓬�@�j
�@�n���P�[���̋������ɔ����A��@�Ƃ��Đv�E�J������A����^�g�[�l�[�h����s���Y�g�[�l�[�h���{�@�Ƃ����o�܂āA����Đ��������ꂽ�B�i���m�ɂ͂��Ⴄ�������j
�@�{�@�͔\�͓I�ɂ̓X�s�b�g�t�@�C�A�ɗ�镔���������A�퓬�@�Ƃ��Ă͎g�����ɂȂ�Ȃ����x���ł��������A�ፂ�x���\�̔\�͂������A�퓬�U���@�Ƃ��ĉ^�p����Ă���B
�@�ꎞ�͑����\�͂̒Ⴓ����A���Y�I���ԍۂ܂Œǂ��l�߂�ꂽ���A���̃C�M���X�R�퓬�@�������ł������悤�ɁA���X�̉��ǂ��{����A�������̐퓬�U���@�ɐ��������B
�@�����͗ǍD�Ȃ��̂ł���A�@�e�A���e�A���P�b�g�e�̂�����̉Η͂��͋������̂ŁA���㕺��̔r���ɖ҈Ђ�U������B
�@�Q�[���ł͒��Ղ��߂��������肩�琶�Y���\�ƂȂ�A�j�����l�A�퓬�@�Ƃ��Ẳ^�p�͌��������̂́A�����ɗD��A�퓬�U���@�Ƃ��Ă͂܂��܂��̔\�͂ł���B
�@��^���e��2���ډ\�A���P�b�g�e�Ȃ��4���ډ\�ƑΒn�U���Ɍ���Ε����͔��ɏ[�����Ă���A�u������x����킦��U���@�v�Ɗ�����Ďg���̂��ʔ�����������Ȃ��B
�@��̋��\�͂��������킹�Ă���A���Ȗh�q���x�̐퓬�Ȃ������x�\�ł��邽�߁A���̓_�͍U���@�����^�p���₷�����낤�B
�@�i����̓e���y�X�g�ƂȂ��Ă���A����������R���Z�v�g�̐퓬�@�ŁA�����悤�Ȏg�������o����B
|
 |
���e���y�X�g�@�i�퓬�@�j
�@�C�M���X�鍑�ł̓^�C�t�[���̉��nj�p�@�Ƃ��ă^�C�t�[��II���J�����Ă������A�l�X�ȉ��ǂ��{�������ʁA����͂��͂�^�C�t�[���Ƃ͕ʕ��̐v�ɂȂ��Ă����B
�@�����Ŗ��̂��e���y�X�g�ƕύX���A���������邱�ƂƂȂ����̂��{�@�ł���B
�@�{�@�̓G���W�������A�`��v������ł̉����������Ƃ����ӂƂ��A���ʼn^�p���邱�Ƃ��O��ł���A��풆�ōő����x���̑��x���ւ�B
�@V-1�̌}���ɓK���鑬�x�ł��������߁A�����̔C���ɑ����̗p����A��n�ɂ���Ă�Me262�̌}���ɂ��̗p���ꂽ�B
�@�������A���̐�����A�^�������͂���قǗǂ����̂łȂ��A�{�i�I�Ȋi�����͋��ł���A���ł͈ꌂ���E����Ȑ�@�ł������悤�ł���B
�@�Q�[�����ł͏I�Ղɂ���������ӂ肩��^�C�t�[������̐i���A�����Y���\�ƂȂ�B
�@���x��14�A��^���e�̓��ڐ���2�ƁA�ǂ��炩�Ƃ����ΐ퓬�@�����퓬�U���@�Ƃ��Ă̐����������B
�@���ނ͐퓬�@�ł͂��邪�A�����A�퓬�@�Ƃ��ĉ^�p����ɂ͐��\������Ȃ����߁A�����ő�^���e��ς݁A�퓬�U���@�Ƃ��Ẳ^�p���K���Ă��邾�낤�B
|
 |
���n���P�[���@�i�퓬�@�F�퓬�U���@�j
�@�t���[���[���t�퓬�@�̋������ɂƂ��Ȃ��A����̍X�V�̂��߂ɊJ���E���Y���ꂽ�P�t�P���퓬�@�ł���B
�@�{�@�͓����J���̃X�s�b�g�t�@�C�A�i�S�����j�Ƃ͈قȂ�A�����ȋZ�p�������̗p���ꂽ���v�̌Â��؋����݂̐퓬�@�ŁA�ȑf�����Y���e�Ղł�����������B
�@��평���ɂ͐��Y���̗e�Ղ����瑽�������Y����Ă���A���Z�p�I�ɂ��������e�ՂȎ�����h��C���Ŋ��A�A�W�A����ɂ���������Ă���B
�@�ȑf�ȍ��͌��ʓI�ɍ�����e���\�������ɂȂ���A��e�����ꍇ�ł����Q�͒Ⴍ�}���鎖���ł��A�������͂��Ȃ荂�������ƌ����Ă���B
�@�܂��A�����Ƃ��Ă͋��͂ȃG���W����ς�ł���A�h�C�c�鍑�R�퓬�@�ɑ��Ď�����x�A����ȊO�ɑ��Ă͗D���ɐ퓬���d�|���鎖���ł����B
�@�n���ȑ��݂Ȃ���������ɐ�ʂ�ςݏd�˂Ă������A�X�s�b�g�t�@�C�A���Y���i�ݐ������낤�悤�ɂȂ�ƁA�����ȑ�퓬�C���ȊO�ւ̓����������Ă������B
�@�Q�[���ł͏��Ղɐ퓬�@�A�㔼�ɑΐ�ԍU���@�Ƃ������r���[�Ȉʒu�Â��ő��݂��A���\�I�ɂ͒�߂̕]���ŃX�e�[�^�X�͂��Ȃ�Ⴍ�}�����Ă���B
�@�����Ȑ퓬�@�Ƃ��Ă͎g�����ɂȂ�Ȃ����x���ł���A�����ȂƂ���g���ǂ���ɔY�ދ@�̂ł͂��邪�AIID�^���Βn40mm�@�֖C�Ƃ����������𓋍ڂ��A�Α��b�Η͂͒��ˏオ��B
�@�����͂�₸��邪�w�ǂ̌^�͑����Y���\�ŁA�i���̓}�C�i�[�`�F���W��F�̏��とII��IID��IV�Ƒ����AIID����͎����I�ɑΐ�Ԑ�͂ŕK�v�ȂƂ��ɐ��Y������Ηǂ����낤�B
|
 |
���\�[�h�t�B�b�V���@�i�����@�F�͏�U���@�j
�@�ΐ�O�����ʂɐ��Y����A���̂܂ܑ��֓˓��A�h�C�c�鍑��̓r�X�}���N�����̎菕��������Ȃǃ��[���b�p�E�吼�m�ő劈���@�̂ł���B
�@���t�A�̂Ȃ���̍��g�݂ɕz����̍\���A�ݑ��ƌ������Ƃ���J�펞�ɂ͊��ɋ����������@�̂ƂȂ��Ă������A���L���p�r�Ɏg����ėp���Ƒf���ȑ��쐫�͍����]�����B
�@���̍��]���̗��R�Ƃ��ẮA���[���b�p�E�吼�m���ʂł͋@���E�͑���̋K�͂����K�͂Ŋ����Ȍ�킪���Ȃ��A���R�ȉ^�p���o����������ȑ傫�ȗ��R�ł���Ǝv����B
�@��풆���ɂ͐��\�̌��E�����p�@��ɂ��̍�������A�������珙�X�ɑނ��Ă��������A������ނ��������q�@�Ƃ��ċ@�������ɓ���AU�{�[�g���ȂǔC���ɏA���Ă���B
�@�����Ɋւ��Ă͈ӊO�ȂقǏ_��ŁA����^�ł͑ΐ����[�_�[�A���P�b�g�e�Ȃǂ����������܂łɂȂ��Ă���A��������������������ނ�����̊�����Ԃ������v���ł��������B
�@�S�ʓI�Ȑ��\�͒Ⴍ�A�G�ƌ݂��ɔF����������Ԃł̌��ł͕ېg����낤���@�̂ŁA���ۂɔ�Q�������������A�z�����ʁA�^�p�̎d���Ɍb�܂ꂽ�@�ł������ƌ����邾�낤�B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��琶�Y���\�ŁA�g�[�^���ł͒ᐫ�\�Ȃ��̂̍��G5/����2�A�ΐ��Η�50�A227lg���e�ł���Ȃ���Βn�Η͂���⍂�߁A���͉\�Ƃ����D�������B
�@�͂����茾���đ�Η͂̍�������ɍU�������قڑS�ł͊m��ł͂��邪�A�R�X�g�������A���e��3�i�܂��͋���1�j�Ǝg���̂ēI�ȑΒn�U���@�Ƃ��Ă͂܂��܂��ł���B
�@�������A�g���̂ĂŎg��������ɂ��㔼���Y�͕s�A�i����͒ᐫ�\�̃o���N�[�_�ł��邱�Ƃ���A�����Ɏg�����R�͂قƂ�ǖ����A�唼�̃v���[���[�ɂ͑��݉��l�̒Ⴂ�@���낤�B
|
 |
���o���N�[�_�@�i�����@�F�͏�U���@�j
�@�\�[�h�t�B�b�V���̋������ɔ����A���̒S����Ƃ��ĊJ�����ꂽ�@�ł��邪�A���X�̖�����������߂ɑO���ւ̓������x��ɒx�ꂽ�@�ł���B
�@���̑����͂Ȃ�Ƃ����P�ł��郌�x���̂��̂ł��������A�@�̋��x�̕s�����o�����Ƃɂ��⋭�A�����̌������Ȃǂ��甭�������d�ʂɊւ�����͍Ō�܂ʼn��P�ł��Ă��Ȃ��B
�@���ʁA�^�p�ł͕⋭���ꂽ���Ƃɂ���ē���ꂽ���S�ȋ@�͈̂��萫�������A�R�N�s�b�g�̎��E���ǍD�ł��������߁A�p�C���b�g�B����͂���قLj����]���ł͂Ȃ������悤���B
�@�����̋@�̂͏����C���ɓ�����A�����ɔC�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����p���ł͑傫�Ȗ��͌����Ȃ��������A�����Ζ����t�̉t�R��W���玖�̂������N�����Ă����B
�@�h�C�c�鍑�C�R�e���s�b�c���ʊ��ɍU�����A���x����Ō���^�����@�Ƃ��Ă��L���ł���A�s���_�ȓ_�A���_�ȓ_�A�o�������������@�̂ł��邾�낤�B
�@�����I�Ȑ��\�A���̂̌����猻��ɂ����Ă͕]���̗ǂ��Ȃ��A�������Ă��܂��Έ������ނ̗����@�ł͂��邪�A�����Ɍ����ŗE�҂ȋ@�ł������Ƃ�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[���ł͒��Ձ`�I�Ղɂ����ă\�[�h�t�B�b�V�����i���A���@�����ɂ�鑦���Y�Ŏg�������o����̂����A�����E�ΐ����o����������l���ɓ���Ă����݂͂������ł���B
�@���G�͈͍͂L���̂������^���e�̑Βn�Η͂͒Ⴍ�A�R�������Ȃ����ߐ퓬�p���͂����A����ɖh�䐫�\������߂ƁA�n�߂ɖ{�@���^�p���鉿�l�����邩�ǂ��������ɕ����ԁB
�@�ŏI�i���̂��ߐ��\�͑ł��~�߁A���킪��̍��t�@�C���ł͂��������s�v�ɋ߂��A�����������}�C�i�X�ʂ܂���Ǝ�Ő��@���g�����x�Ƃ����Ƃ��납�B
|
 |
���X�L���A�@�i�X�N�A�@�͏�U���@�F�}�~�������@�j
�@�C�M���X�鍑�R���̋}�~�������@�ł���A���ʓI�ɂ��������邨���Ȃ������Ƃ͂����`���I�ɑ����̐V�Z�p�����荞�܂�A�A���o�����X�ł͂��邪���̐��������߂��@�̂ł���B
�@�ߋ��A�퓬�@�Ƃ��čL���F������Ă������Ƃ���ᐫ�\�Ȑ퓬�@�ŋ}�~���������s�����Ƃ����]���ł��������A���ۂɂ͋}�~�������@�ɋ��\�͂�t�������Ƃ����������������낤�B
�@���������������D�ǂȊ͏�@�������Ȃ������C�M���X�C�R�ł́A�ǂ����Ă���@��ɂ���đ����̔C�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂ���A�{�@�̓��������̌��ʂ���Ǝv���Ă悢�B
�@���\�͂͂����茾���Ēᐫ�\�ŁA�{�����ڂ����͂��̃G���W������������Ȃ�������A�Ə��@���œK������Ă��Ȃ�������ƁA�s�^�ɉ��������s���ł��������͔ۂ߂Ȃ��B
�@�������Ȃ���A�ᐫ�\�ł��Œ���̐��\�͊m�ۂ���Ă���A�y�����@���x�Ȃ�ΐ퓬�����Ȃ��������玸�s��Ƃ��f���ł����A�h�C�c�鍑�C�R��C�^���A�C�R��ɕ��������B
�@��풆���ɂȂ�Ɖ^�p�Ɛ�p�ŃJ�o�[���Ă������\���������Ɍ��E�ɒB���A��Q�̑�������������ނ��Ă��������A�������̃C�M���X�C�R���x�����@�ł���ƕ]���ł���B
�@�Q�[���ł͒��Ղ��瑦���Y�œ��邱�Ƃ��\�Ȋ͏�}�~�������@�ł��邪�A�߂������炢�ɒ��ᐫ�\�ŁA�C�M���X�鍑�Ɏ��p�@�������Ȃ����߉^�p�����ɂ߂ĒႢ�B
�@���\�͂�Ju87���A���e�̓��ڐ���1�Ɛ퓬�p���́E�����\�͂͒������Ⴍ�A�ǂ��_�͍��G�͈͂��L�����炢�ƁA���͂⑶�ݎ��̂������߂ɋ߂��ƌ�����B
�@���Y����قǂ̉��l�͂قږ����A�i�����ǂȂ��̒P�̂ő��݂��邽�ߑ��ݎ��̂��Y�ꋎ��ꂪ�������A�ǂ������݂��炢�͖Y��Ȃ��ł��Ă���Ăق����ƐɎv���B
|
 |
���u���j���@�i�����@�F����U���@�j
�@���O�A�V���ɂĕx�����U�~�A�����u���X�g���Ђɔ��������������q�@�����^�Ƃ����A�ꕗ�ς�����������������y�����@�ł���B
�@�@�̂͑o���ł���͋����ɉ����đS���������̗p����A����ɓ����̍ŐV�v�v�z����������葍���I�Ȑ��\�͍����A�������̃O���W���G�[�^�[�퓬�@���������ł������B
�@����́A�R�▯�Ԋ�Ƃɂ��u���ƓI�E�����I�����l���Ɋ܂߂��J���v�ƈႢ�A�u������x����Ȏ����������Ė��m�ȕ�������������Ă����J���v�ł���䂦�̌��ʂł��낤�B
�@���낢��Ȍo�܂������ă��U�~�A�����猴�^���C�M���X�鍑��R�ɑ�����ƁA�e�X�g���ʂ����R�͖{�@��D�G�L�p�Ɣ��f���A�����܂��������E�ʎY����e�n�ɔz�����ꂽ�B
�@�{�@�͔�s�@�Ƃ��Ă͋ɂ߂č����\�ł����������������ȗ��q�@�ł��邽�߁A�R�p�Ɍ����Ȃ������������A���ɖh��ʂɗ�邱�Ƃ͒v���I�ő�평�������Q�͏�ɏo�Ă����B
�@����ł������O�̌y�����A���\�����������C�������Ȃ��Ă������A��풆���ɓ��邱��ɂ͐��\�I�ɂ����E���߂Â��A������@�Ƃ̌��ő�������ނ��Ă���B
�@�Q�[�����ł͏��Ղ��琶�Y�\�ȗ���U���@�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă���A���ɕ��}�Ȑ��\�ő��݊��͔������̂́A�R�X�g���A���G�͈�4�Ǝg���₷���ʂ�����B
�@���\�I�ɂ̓A�����J�R�̃~�b�`�F��������̉��������悤�Ȑ��\�ŁA���Ȃ��s���Ȃ��܂��ɖ}�f�Ƃ����Ƃ���ł���A�g�����g��Ȃ����̓v���[���[����ƌ������Ƃ��납�B
�@�i����̓��X�L�[�g�ň��肵�����\����������߂邪�A���X�L�[�g�͏I�Ց����Y���o���A���\�E�g��������l������Ƃ��̎����܂Ŗ{�@���^�p���邩�ǂ����Y�݂ǂ���ł���B
|
 |
�����X�L�[�g�@�i����U���@�j
�@�S�ؐ��̋@�̂������A�C�M���X�R�݂̂Ȃ炸�A���R�ɂ����đ听�������߂��C�M���X�R�̑o������U���@�ł���B
�@�{�@�͔��ɍ����؍H�Z�p�ɂ���Đ�������Ă���A���\�E���x�ɂ��Ă͂܂������s���͂Ȃ��������A�������łȂ����������R������͐������ւ̖Ҕ����E��R���������B
�@�������A������s�Ȃǂ��s����悤�ɂȂ�ƁA�퓬�@���݂́i�������͂���������j���x���R���Ɍ������A�\�͓I�ȋ^����̂��Đ���������Ă���B
�@�f�n�r�����h�Ђ̖ژ_���ǂ���A���\�E���x�͐܂莆���ŁA�����\�肳��Ă��������C���̂ق��A��Ԍ^�A��@�^�ȂLj�������ɑ����A��p�ȋ@�̂ł������ƌ����邾�낤�B
�@�܂��A���Ȗh�q�\�͂̍������{�@�̓����ł���A�������C���ɂ����Ă��������͔��ɒႭ�i���������������j�A�O�q�̓������l������ƁA�������\�͋ɂ߂č����ƌ�����B
�@�B��A�ؐ��ƌ������ŁA����Ƃ��Ă͍����������������ł���Ƃ�������Ȏ�_�����݂��邪�A�A�W�A���ʂ֓W�J���ꂽ�@�̈ȊO�͂���قǖ��ƂȂ�Ȃ������悤���B
�@�Q�[���ł͒��Ղ��߂���������œo�ꂵ�A�����Y�A�܂��̓u���j������̐i���œ��鎖���ł���B�i�{�@�̐i���E���ǂ͖����A��U���͔����̂݁j
�@�h�䐫�\�������ł��ꋭ�����ʁA�Η͂�������Ȃ����[�Ȋ����͂�����̂́A���펞�ɓ��������{�@�͓Ɠ��̑��݊�������A�����ɓ������Ă������Ă���鎖�������B
�@�Η͕s�������Ō���������p�r�ɂ͌����Ȃ����A�h��͂������S�苭�����킶��Ɛ�͂����p�r�ɂ͍œK���낤�B�i�����ɓ�������قǂ̐��\�ł��Ȃ����E�E�E�j
|

coffee break |
|
�`�����ɕ����Ȃ������R�p�@�f�ށA�؍ށA�z�`
�@����E���ł͂�����̕���������オ�����������i�݁A�ߋ��̕���͎��X�Ƒ�������ނ��Ă������B�R�p�@�̕���ł�����͓����ŁA�������P�t�@�Ƃ������d�l�����W���[�ƂȂ莟�X�Ƃ��̃^�C�v�����܂�Ă������B�����A�`������Ɍ����������Ȃ���A�z�A�؍ނȂǐ̂Ȃ���̑f�ނ������g��ꂽ���̂����݂����B�L���ȂƂ���ł̓\�r�G�g��Yak�n�퓬�@�͖؍ށi�\�r�G�g�͌��X�����f�ނ̋@�������j�A�C�M���X�鍑�̃n���P�[���͕z�E�؍ނ����p����Ă������A�A�����J��B-29�ł��ꕔ�̕��i�ɕz���肪�̗p����Ă����������B����E���ł͂܂��z�E�؍ނƂ������f�ނ��͂ꂽ�n�����H�Z�p���g����M�����̍������̂������B�����ĕz�E�؍ނ̎g�p�͋����̐ߖ�ɂ��Ȃ����B
�@���ł��S�ؐ��ł���C�M���X�鍑�̃��X�L�[�g�͂��܂�ɂ��L���ł���B����͐��\�E���������ɂ߂č��������������邪�A���̉e���ʼnғ����̗����Ă����Ƌ�����؍H���쏊����H����L���Ɋ������A�����ɍ������H�Z�p���������u�H�ƓI�ɂ��R���I�ɂ������I���L�Ӌ`�Ȃ��̂������v����ł���ƕM�҂͎v���B���X�L�[�g�̐����͑����ւ��e����^���A�؍ނɍēx���ڂ��W�߂�����قǂ��������i�Ⴆ�h�C�c�鍑�ł�Ta-154�Ȃǂ��������ꂽ�j�A�c�O�Ȃ��Ƃɂ����͌`�������Ă����\���Ⴉ������A�������Ȃ�������ƎU�X�ł������B���Ȃ݂ɑ���{�鍑�̌R�p�@�͂قƂ�ǂ������f�ނ�O��Ƃ���Ă������߁A��K�͂Ȗ؍ނ̍�������ؐ����͓�������悤�ł���B�i����ȋ@�⎑���������Ăǂ����悤���Ȃ��ꍇ�͕z�E�ؐ������ꂽ�������������悤�����B�j����E���ŌR�p�@�ɋ��������p�����悤�ɂȂ��Ă��A�z��؍ނ͏d�v�������̂��B
|
 |
���{�[�t�H�[�g�@�i����U���@�F�����@�j
�@���O��艈�x���E�����܂��͑ΐ���ړI�Ƃ��Čv�悳��A�u���j���̋@�̐v�𗬗p���č��ꂽ�����@�ŁA�C�M���X�鍑�R�����łȂ��I�[�X�g�����A�R�ł����C�Z���X���Y���ꂽ�B
�@�J���ɂ̓G���W���̖���Y���C���̖�肪�t���܂Ƃ������߁A�v��̔�����������������ɑO���ւ̔z���A�{�i�I�Ȑ퓬�ւ̎Q���͒x���A��평�����߂��Ă���̓o��ł������B
�@�����u���j���Ƃ�����펞�ɂ͊��ɋ����������@�̂ł��������߁A�����I�Ȑ��\�͗ǂ��Ƃ͌����Ȃ����̂ł��������A�����@�Ƃ��Ă̑����͏\���ŁA���̖ʂł͐ϋɓ�������Ă���B
�@��ɏ������悤�ɁA�{�@�͔�s�@�Ƃ��Ă̐��\�͍������̂ł͂Ȃ��A���A�����ʂł͂�������Ƌ@���E�����E�ΐ��������������Ă���A�Œ���̑����͎{����Ă����B
�@���̂��߁A�v��ǂ���u���x���E�����E�ΐ��v�ɐϋɓI�ɓ�������A�h�C�c�鍑�͑��ւ̍U���ɂ��Q�����Ă��邪�A���\�ʂ̌��O����D�c�U���ւ܂킳�ꂽ�ق������������悤�ł���B
�@�ᐫ�\�ȋ@�̂ł���Ȃ���������E�����ɔC���𐋍s�����{�@�́A��ʓI�ɂ͒�]���ł����Ă��C�M���X�鍑�R�ɂƂ��Ă͏d�v�ȋ@�ł������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Q�[�����ł͔�r�I���Ղ��瑦���Y���\�ȗ���U���@�ƂȂ��Ă���A�����ɂ���ė������\�ȋ@�̂ƂȂ��Ă���B�i�i���E���ǁA�ΐ��Η͖͂����j
�@�Q�[���ɂ����Ă������\�ł͂Ȃ����A�P�ɑS�ʓI�ɔ\�͂���߂Ǝj���ǂ���̌����ȋ@�̂ƂȂ��Ă���A�������ᐫ�\�ł��Ȃ������瓯�R�Ȃ�ł͂̒��r���[�����ڗ��B
�@�{�X�g���A���X�L�[�g�ƌ������炩�̈ꕪ��ɏG�ł�����U���@�����钆�A���r���[�Ȗ{�@���^�p���邩���Ȃ����̓v���[���[�̔��f�Ɉς˂��邾�낤�B
|
 |
���E�F�����g���@�i�����@�j
�@�r�b�J�[�Y�Ђ̔����@�ł���A���Ђ̑O�����@�A�E�F���Y���ɑ����đ北�\���Ƃ����Ɠ��̍\�������B
�@�北�\���Ƃ́A�����̐��i���g�j���Ă̂悤�ɑg�݁A���̏�ɕz��t������Ɏ�Ԃ̂�����H�@�����A�����ł͂���قǒ������H�@�ł͂Ȃ��B�i���W���[�ł��Ȃ����j
�@���̍H�@�Ő��Y���ꂽ�q��@�́A�S�������ɔ�d�ʂ��y���A��s�����E���x���҂����A�ɂ߂ď�������e�Ȃ�A�ђʂ��đ�j�Ɍq���邱�Ƃ����Ȃ��Ƃ������_������B
�@���ʁA���̎�Ԃ䂦�ɑ�ʐ��Y�ɂ͌������A���v�̌Â����狌�����͎v�������������i�݁A�V���ɍ����\�Ȕ����@���o�ꂵ�n�߂�ƁA�����ʼn^�p�����悤�ɂȂ����B
�@���Ԕ��������Ȃ��Ȃ��悤�Ȓᐫ�\�ł����Ă��A�^�p���\�E�g���S�n�͔��ɍ����A�퓬�ȊO�̔C���ɂ��g�p����A�C�M���X�R�̒��ł͌��O���1���@�ȏオ���Y����Ă���B
�@�Q�[���ł͏������琶�Y���\�ŁA���̒����U���@�������Ȃ��C�M���X�R�Ƃ��Ă͔����E�Βn�U���A�o���Ɏg����g������̗ǂ�����ɂȂ邾�낤�B
�@�@�̎��̂̐��\�͒Ⴍ�A�������C���ɏ]�m������Ƃ����܂���Q�͖c��オ�邪�A��������ł͏��Ղ���g���钷�����U���@�Ƃ��Ĕ��ɖ��͓I�ł���B
�@�i����̓n���t�@�N�X�ƂȂ�A��r�I�����i�����\�ȏ�ɐ��\����͊m���ł��邱�Ƃ���A����߂ɃX�g�b�N���Ă����Ă����͖����B
�@�����J�X�^�[������E�F�����g���n�͗v��Ȃ��Ƃ����l���������邪�A�����J�X�^�[�͐��\�̊��ɃR�X�g���������߁A�M�҂̓E�F�����g���n���������ق����������ƍl����B
|
 |
���n���t�@�N�X�@�i�����@�j
�@�E�F�����g���̌�p�Ƃ��ĊJ������A�����J�X�^�[�ƕ���ŃC�M���X�R���\����d�����@�ƂȂ����@�̂ł���B
�@�����̐v�ł͑o���@�ł��������̂́A���\�s������4���@�ւƕύX�A����ɍו��̕s�s���Ȃǂɂ��J���͎v���悤�ɐi�܂��A�������Y�̖��ł̐������ł������B
�@����������s�s���͂܂�ɑ��݂��Ă������A�o�[�W�������d�˂邲�ƂɓK�ɖ��͉��P����A�ŏI�I�ɂ͔ėp���̍����@�̂Ɏd�オ���Ă���B
�@�{�@�͕��}�œ��M���ׂ��_�͌����Ȃ����A���Y�E�ێ炵�₷���v���Ȃ���Ă���A��ʐ��Y�����₷���A��n�Ŏ���Q���Z���ԂŏC�����\�ł������ƌ����B
�@���}�ł��邪�䂦�ɒ�����������_�����Ȃ��A�����C�M���X�A�M�ȊO�̐��J���ʼn^�p����Ă��鎖����A���ۂ̉^�p�ɂ����Ă͈�ʓI�ȕ]�������\�͍͂����Ǝv����B
�@�ΐ��E�A���E����E�d�q��C���Ȃǂɂ���������A���ʂ��������t���邠����A����������Ɩ����������J�X�^�[��������̏�͍L�������̂�������Ȃ��B
�@�Q�[�����ł̓����J�X�^�[�Ƃ̑o�������@�̂悤�Ȉ����ŁA��r�I�����ɃE�F�����g�����i���A�܂��͎��@������͑����Y�Ŏ�ɓ���B�i�i���͂����őł��~�߁B�j
�@��͂ɖR�����C�M���X�R�̒��ŁA�i�����̃E�F�����g����傫�����鐫�\�E���ڗʂ͗�����������ł���A�����J�X�^�[�ƕ���ő���͂ɑ����������\�ƂȂ��Ă���B
�@��^���e�̓��ڂ͂��Ȃ����̂́A���R�X�g�̃����J�X�^�[�ɔ�ׂ�����̓R�X�g���}�����Ă���A�ǖʂɂ���Ďg�������鎖�ŌR����̐ߖ�ɂ����т����낤�B
|
|
�������J�X�^�[�@�i�����@�j
�@�}���`�F�X�^�[�����@�̓G���W��������Ȑv�ł��������ߐM�������Ⴍ�A����p�C���b�g����̕s�]�͂����܂����A�C�M���X�鍑�R�͑��}�ȑΉ����K�v�ł������B
�@���̃G���W�����͎v���Ă��������傫���A�A�u���ł͍��{�I�ȉ��ǂ��}���A�@�̊g���A�G���W���@��ύX�A�o����4���ɕύX����Ȃǐv�ɑ傫�ȕύX���s��ꂽ�̂ł���B
�@����ɂ���Ċ��������}���`�F�X�^�[�����@�u���v�������{�@�A�����J�X�^�[�ł���A�{���ꂽ���ǂɂ���ă}���`�F�X�^�[�����@�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂ̍����\�@�ƂȂ����B
�@�{�@�́A���N���X�̔����@�Ƃ��Ă͂�⏬�Ԃ�ȋ@�̂Ȃ���4���Ȃ�ł͂̈��肵�����\�������AB-29��������ʂ̔��e���ڂ��\�ƌ������ɗD�G�Ȕ����@�ł���B
�@����ɉ��ǂ��ꂽ�@�͑Ί͔C���ɂ�����A�_���o�X�^�[�A�g�[���{�[�C�A�O�����h�X�����ȂǗl�X�ȓ���/��^���e��ύڂ��A�h�C�c�鍑�R�̏d�v�{�݂�j�������B
�@�����l�i�̋@�̂ł͂��������A�����C���ȊO�Ɏg���鈟��������A�܂��A���\�ʁA���ڗʁA�^�p�ʂŗD��Ă������Ƃ����ォ�Ȃ蒷���ԉ^�p���Ă��������������B
�@�Q�[���ł͑S�q��@���ō��̑Βn�Ί͍U���͂��ւ�u5t���e�v�𓋍ڂł���@�Ƃ��ēo�ꂵ�A�i���A���ǂȂ��̑����Y�œ������鎖���\�ł���B�i��r�I�������瑦���Y�\�j
�@���j�b�g�R�X�g�͍�����5t���e�̍U���͂͂�������������Ă����͓I�ł���A��U�ƂȂ�䂦�̔�Q���C�ɂ��Ȃ���ΉΗ͖ʂł͔��ɗ��������A��p�ɕ��������炵�Ă���邾�낤�B
�@��퓬�͋��ł��邽�ߏo������萧���ʼn^�p���������A���풆�ł���Q�����ł����Ƃ������G���قڈꔭ�Ŕr������ȂǁA�ʔ����g�����͂��邩������Ȃ��B
|
|
���n�E�j�u�@�iUFO�j
�@��������Ƃ���������Ă����̉~�ՁB
�@�ӂ��Ƌ߂Â��Ă͓G������̂����Ղ�ɂ��ċ����Ă����Ƃ����B
�@��s���錴���͂��Ƃ��A���̑��݂̈����ł���B
|
|
|
|
| �@�@ |
���[���h�A�h�o���X�h��헪�`�|�S�̐����`�@�Z�K�T�^�[��
�@���ꂪ�Ȃ���͂��܂�Ȃ��B
|
| �@�@ |
���[���h�A�h�o���X�h��헪�`���FILE�`�@�Z�K�T�^�[��
�@�P�̂ł��V�ׂ�A���ʂȃX�^���_�[�h�}�b�v�A����Ȃ��\�r�G�g�L�����y�[���A�j���ɂ������Ȃ���Ή��x�ł��J��Ԃ��V�ׂ鉼�z�L�����y�[���������B
�@���t�@�C���͍D���ł͂Ȃ��Ƃ����l���������낤���A�o���l�̏��Ȃ�����{�鍑�^�C�v�𑀂��͖̂{�\�t�g�łȂ��Ƃł��Ȃ��B
�@�|�S�̐����ł��ꂾ���̋������ւ��킪�A���\�̒������ꂽ�S�\�r�G�g�R���A�����ꒃ�Ȑݒ�̃X�^���_�[�h�}�b�v���A�|�S�̐����ł͖��킦�Ȃ��A����ȐV�N��������B
�@�܂��A���z�L�����y�[���͏���������������x��邭�A�I�����ɂ�肠����x�i�R�ߒ����ς�邽�߁A���܂��i�߂�|�S�̐��������i���E���ǂ��y���߂邾�낤�B
�@���Ȃ݂ɁA�܂������o���l�̂Ȃ����{�R�́A�t���[�}�b�v�A�t�H�[�g���X�ȂǂŖ��킦��B
|
| �@�@ |
���[���h�A�h�o���X�h��헪~���t�@�C�� �����K�C�h �@�P�s�{
�@�U���{����1�B
|
| �@�@ |
���[���h�A�h�o���X�h��헪 �|�S�̐핗�\���E�V�������݃}�j���A���@�P�s�{
�@�U���{����2�B
�@�t�@�~�ɂ̖{�Ȃ̂ŁA���܂���҂��Ă͂����Ȃ��B
|
| �@�@ |
���[���h�A�h�o���X�h��헪�|�S�̐핗�R���v���[�g�t�@�C���@�P�s�{
�@�U���{����3�B
�@�g�����玁�ɂ��C���X�g�t�������A�ȒP�ȃ}�b�v����E�i���\�A�Q�[���i�s�̕���\������B
�@�����ȂƂ���A���ꂾ������Α��͂���Ȃ���������Ȃ��B
|
| �@�@ |
THE �����`���̌������`�@(PS2 FPS���A�N�V����)
�@�l�i�̊���ɗV�ׂ�v�f�������A���V�їp�̕�������킠��B
�@��Փx���ʂ邭�A�C�y�ɗV�ׂ�_���ǂ��B
�@�킩��l�ɂ͂킩��ł��낤���A�M�҂��n�߂ėV�Ƃ��́u���������L���m���v�ł������B
|
| �@�@ |
THE �Ō�̓��{���`���������y�D�ҍ��`�@(PS2�@FPS���A�N�V����)
�@��L�AThe �����Ɠ����悤�Ȃ��̂��Ǝv�����̂����A���Ȃ��Փx�������B
�@���쐫�A�J�������[�N�������A���l�����ł͂Ȃ����A�X�����̂悤�Ȗ��t���Ŋ����Ί����قǎv���悤�ɐi�ށB
�@�ς�������̂��v���C�������Ƃ����l�������B
�@�M�҂͈ꉞ�A�V�яI����Ă���B
|
| �@�@ |
SEGA AGES �A�h�o���X�h��헪�@�h�C�c�d�����@(PS2)
�@���͂�}�j�A����SLG�̑㖼���ƂȂ����MD�ŃA�h�o���X�h��헪��PS2�ڐA�łł���B�i���Ȃ�̉�������j
�@���܂�̃o�O�̍����Ɉ�x�C���ł��o���ꂽ���A����ł�MD�łɔ�ׂďo���邱�Ƃ����Ȃ����Ă���A���Ƀ}�b�v�G�f�B�^�������̂��v���I���낤�B
�@�������Ȃ���APS2�̏������x�������v�l���Ԃ�MD�łɔ�ׂċ��낵�������A���M�҂̗V���o�ł̓��[�`�����ύX����Ă���悤�ŁA���ꂾ���͎�V�N���B
�@�����ȂƂ���A�T�E���h�A�~���[�W�b�N�A�v�l���Ԃ����O���[�h�A�b�v���Ă���ȊO��MD�ł�S�ė��p�ł悩�����Ǝv���̂����E�E�E�A�J���w�̍l�����悭�킩��Ȃ��\�t�g�ł͂���B
�@�M�҂��ő���ۂ݂Ȃ���u���@��@�́@���@���v�ƂԂ₢�Ă��܂������ł͐ԃ��x���A�C���ł͐��x���ł���B
�@�ԃ��x���Ȃ�Ό������\�Ȃ̂ŁA���[�J�[�ɖ₢���킹��ׂ��ł���B
|
| �@�@ |
Call of Duty: World at War (�A���� �k��)
�@FPS�Q�[���B
�@�����m����̐퓬���y���߂�B
�@�Ƃ�����ُ�Ȃقǂ̎�֒e����ь�������A�S�z�u�̌Œ�y�@�֏e�A�҂�������P�͂��邪�A��Փx���K�x�Ŕ�r�I�y���߂�B
|
| �@�@ |
Medal of Honor 10th Anniversary Bundle (�A����)
�@FPS�Q�[���B
�@���_���E�I�u�E�I�i�[�̃G�A�E�{�[�����͂��߁A����܂ł̃A���C�h�A�T���g�A�p�V�t�B�b�N�A�T���g����������Ă���B
�@���C���̓G�A�E�{�[���ɂȂ邾�낤�B
�@�G�A�E�{�[���̓V�i���I���[�h�̃{�����[�����Z�߂����A�`�F�b�N�|�C���g�������A��y�ɗV�Ԃ̂ɂ��傤�ǂ������낤�B
�@���O�̂Ƃ���A�V�i���I�Q�[���J�n���͊�{�I�ɗ����P�ł̍~������n�܂邽�߁A�ʏ��FPS�Ƃ͈ꖡ������퓬�ւ̓������̌��ł���B
|
| �@�@ |
�r�W���A���K�C�h WW2��ԁi1�j�d����
�@����ɋ���������A���̂悤�Ȗ{�����Ă݂�̂��悢���낤�B
|
| �@�@ |
�r�W���A���K�C�h WWII ���(2)�������
�@����ɋ���������A���̂悤�Ȗ{�����Ă݂�̂��悢���낤�B
|
| �@�@ |
����ł��A���{�l�́u�푈�v��I�� �����z�q
�@�푈�Ɋւ��鏑�ЁA����1�B
|
|
|
|
| �@�@ |
�q�g���[�@�Ŋ���12���ԁ@�X�^���_�[�h�E�G�f�B�V�����@DVD
�@��햖���̕��͋C�͂悭�ł��Ă���B
�@�q�g���[�̐l�����\�����ǍD�ŁA�u���̂悤�Ȑl�Ȃ̂��v�ƃC���[�W�����ނ̂ɗǂ����낤�B
|
| �@�@ |
��݂��������E���@�J���[�����ꂽ�����t�B�����@Blu-ray BOX(3���g)
�@�f�������I���l�͂���Ǝv����B |
|
|